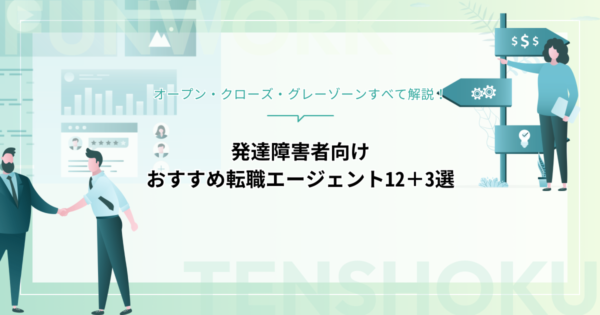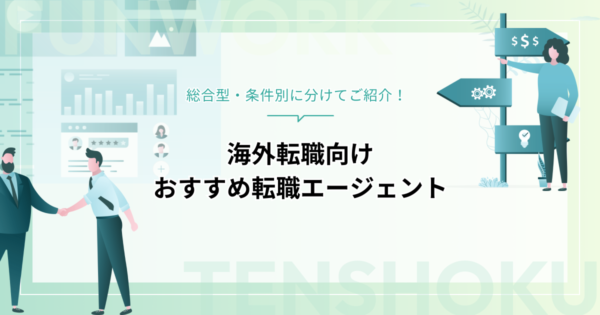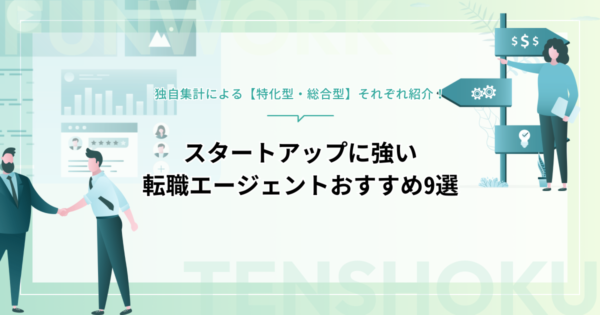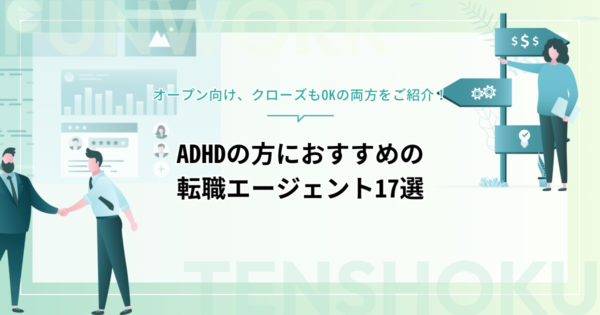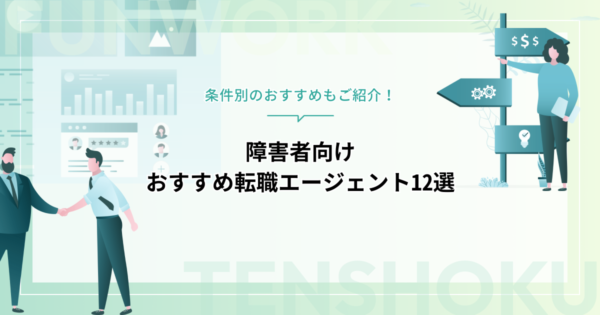適応障害の方が転職したり仕事に復帰したりするために仕事を探すとき、役に立つのが転職エージェントです。しかし自分の特性などを考えた場合、どのエージェントを利用したらよいかわからないことがあるかもしれません。
この記事では、適応障害の方におすすめの転職エージェントを解説します。障害者/障がい者特化型のエージェントと一般就労でも利用できるエージェントの両方を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
なおこれ以降、「障害」単体の表記は「障がい(障害)」、そのほか別の単語とつながっている場合は慣例などを参考に使い分けします。
Contents
- 1 適応障害のある方の転職におすすめ特化型転職エージェント10選
- 1.1 LITALICO仕事ナビは定番で求人も多く使いやすい
- 1.2 dodaチャレンジは幅広い求人を扱っておりサポートにも配慮あり
- 1.3 ランスタッドチャレンジドは職歴があってよい条件希望の人におすすめ
- 1.4 atGPエージェントはスカウトサービスもあり
- 1.5 かべなし求人ナビ(旧:デイゴー求人ナビ)は就労移行支援や就労継続支援も確認できる
- 1.6 DIエージェントは希望に合わせて求人を新規開拓してくれる
- 1.7 エージェント・サーナは業界トップクラスの求人数で非公開求人が85%
- 1.8 LHH転職エージェント Social Partnersはステップアップ転職や年収アップに強みあり
- 1.9 アビリティスタッフィングは精神障害者に特化しておりフォローも手厚い
- 1.10 マイナビパートナーズ紹介は特例子会社ならではのアドバイスを企業・求職者に提供
- 2 手帳なしでもありでも利用しやすい適応障害の方向け総合型転職エージェント5選
- 3 適応障害の方向け転職エージェント選びのポイント
- 4 オープン就労とクローズ就労のメリット・デメリット
- 5 適応障害は転職エージェントに言うべき?
- 6 総合型・特化型転職エージェントの違い
- 7 転職エージェント・転職サイトを有効活用するポイント
- 8 適応障害の方が転職活動をする際の注意点
- 9 適応障害の方が転職を成功させる方法
- 10 適応障害で採用されるための応募書類・面接のポイント
- 11 適応障害とは?改めて確認
- 12 適応障害の方に向いている仕事の特徴
- 13 適応障害の方に向いていない仕事の特徴
- 14 適応障害の人が働きやすくなる配慮
- 15 障害者/障がい者転職で採用される人の特徴
- 16 転職エージェント利用の流れ
- 17 適応障害の方が転職活動でしてはいけないこと
- 18 転職にはまだ早い場合の選択肢
- 19 適応障害の人が転職する際によくあるQ&A
- 20 転職エージェントを活用して転職を成功させよう
適応障害のある方の転職におすすめ特化型転職エージェント10選

まず、適応障害のある方が転職する際におすすめの特化型転職エージェントを紹介します。以下の10のサービスです。
- LITALICO仕事ナビ
- dodaチャレンジ
- ランスタッドチャレンジド
- atGPエージェント
- かべなし求人ナビ(旧:デイゴー求人ナビ)
- DIエージェント
- エージェント・サーナ
- LHH転職エージェント Social Partners
- アビリティスタッフィング
- マイナビパートナーズ紹介
いずれも障がい(障害)のあることをオープンにして利用することができます。では、1つずつ見ていきましょう。
LITALICO仕事ナビは定番で求人も多く使いやすい

「LITARICO仕事ナビ」は、就労移行支援事務所も運営しているリタリコによる転職エージェントです。
障がい(障害)のある方向けの転職エージェントとしては定番です。サイトの作りも、障がい(障害)のある方が自分に合わせた検索がしやすいようになっています。
そのほか就労移行支援施設や就労継続支援A型/B型の施設の検索もできるため、すぐに就労するのではない場合にも利用できます。コラムによる情報発信も充実しており、情報収集にも役立つでしょう。
- LITARICO仕事ナビのおすすめポイント
- 障がい(障害)のある方が自分に合わせた検索がしやすいサイト
- すぐに就労するのではない場合にも利用できる
- コラムによる情報発信が充実している
基本データ
| LITARICO仕事ナビ | |
|---|---|
| 公開求人数 | 3,609件(2025年7月14日現在) |
| 提供サービス | 書類添削、面接対策 |
| 拠点 | 東京 |
| URL | https://snabi.jp/ |
口コミ・評判
リタリコというサイトを登録してみるといいかもね
実際、適応障害でしんどかった時にお世話になりましたので(引用元:X)
私のいまの、障害者雇用の就職先は、実はリタリコさんのエージェントさん経由なのだ(引用元:X)
リタリコ仕事ナビと電話した
障害者雇用の週20時間以上の壁が😢
私の希望勤務日数と時間じゃあ紹介するものないって言われた😔(引用元:X)
dodaチャレンジは幅広い求人を扱っておりサポートにも配慮あり
「dodaチャレンジ」は、転職エージェント「doda」の障害者/障がい者特化型のサービスです。人材サービス最大手の1つパーソルグループによる運営です。
障害者/障がい者枠のハイキャリア向けの求人も扱っており、求人の幅が広いのが特長です。大手企業や正社員の求人も多数保有しています。
そのほか個別のサポートが充実。障害者/障がい者採用の専門的な知識や情報を持った専任のキャリアアドバイザーが在籍しており、パーソナリティも考慮した提案が受けられます。
- dodaチャレンジのおすすめポイント
- 障害者/障がい者枠のハイキャリア向け求人を扱っている
- 大手企業や正社員の求人も多数保有
- 専門的な知識や情報を持った専任のキャリアアドバイザーが在籍
基本データ
| dodaチャレンジ | |
|---|---|
| 公開求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | 書類添削、模擬面接、企業との調整・交渉代行、入社後フォロー |
| 拠点 | 東京・大阪・名古屋 |
| URL | https://doda.jp/challenge/promo/shutoken01.html |
口コミ・評判
私dodaチャレンジで特例子会社の正社員雇用にありつけました。14社くらい紹介してくれて書類選考で5社通って最終的に2社決まりました。(引用元:X)
私はdodaチャレンジを使ってキャリアアドバイザーとすり合わせしながら転職をしました(引用元:X)
DODAチャレンジは多分だけど身体障害者しか応募取ってないんじゃ…相互さんでDODAチャレンジで紹介されてたの1人しか知らん精神(引用元:X)
ランスタッドチャレンジドは職歴があってよい条件希望の人におすすめ

「ランスタッドチャレンジド」は、外資系の人材サービス会社ランスタッドによる障害者/障がい者の方向け求人をまとめたページです。
健常者向けと遜色ない条件の求人も多くあり、給与にこだわりがある方におすすめです。ただし正社員の職歴がないとサポートが受けられない場合もあるなど、その分やや応募する際の条件も厳しめとなっています。障害者/障がい者雇用枠を探しているなら、ほかのエージェントと併用しましょう。
一都三県と大阪では精神保健福祉士の支援が受けられるのが大きな特長です。
- ランスタッドチャレンジドのおすすめポイント
- 健常者向けと遜色ない条件の求人が多くある
- 給与にこだわりがある方におすすめ
- 一都三県と大阪では精神保健福祉士の支援が受けられる
基本データ
| ランスタッドチャレンジド | |
|---|---|
| 公開求人数 | 561件(2025年7月14日現在) |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| 拠点 | 北海道・山形県・宮城県・福島県・栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都・新潟県・静岡県・愛知県・三重県・大阪府・京都府・兵庫県・広島県・香川県・愛媛県・福岡県・宮崎県・熊本県・鹿児島県 |
| URL | https://www.randstad.co.jp/challenged/ |
口コミ・評判
てんかん持ちだけどオープンにして障害者雇用枠で就職してめちゃくちゃ天職だったから多分企業選びが悪いか運がないか別の問題があるか
なお私も新卒時はしこたま落とされて、色々あってから最終的にランスタッドの障害者雇用部門に斡旋してもらった
マジであの時の担当者さんに感謝してる(引用元:X)
ランスタッドの障害者向けエージェント、大阪も精神・発達に対応してる。今まで首都圏だけだったんだよね、すごい。(引用元:X)
健常者に近い障害者を求めてる印象。条件もそんなに悪くはない。障害者にとっては現実的ではない印象、私は、そう思いました。地域も限られているし。(引用元:X)
atGPエージェントはスカウトサービスもあり
「atGP」は定番転職サービスの1つで、就労移行支援事業など障がい(障害)のある方向けの就労サービスを提供する株式会社ゼネラルパートナーズによる運営です。
転職サイトとして利用できるほか、エージェントサービスも提供しておりさまざまなサポートが受けられます。さらに2種類のスカウトサービスがあり、「プラチナスカウト」は面接が確約のスカウトです。
管理部門に強いハイクラス求人を扱う「atGPハイクラス」もあります。
- atGPエージェントのおすすめポイント
- 転職サイトとして利用できたりエージェントサービスの提供もある
- 2種類のスカウトサービスがある
- ラチナスカウトは面接が確約されている
基本データ
| atGPエージェント | |
|---|---|
| 公開求人数 | 1,381件(2025年7月14日現在) |
| 提供サービス | 面接日程調整、志望動機や自己PRのアドバイス、模擬面接、面接後の振り返り、入社日調整、退職相談 |
| 拠点 | 東京・大阪・名古屋 |
| URL | https://www.atgp.jp/ |
口コミ・評判
atGPは割と親切で対応も良かった(引用元:X)
他にも色々な転職エージェントがあるけど、私はatGPがオススメだと思う。逐一連絡してくれるし、分からない事はすぐ答えてくれるし、書類の添削や作成、面接の練習などもしてくれる。次もしまた転職活動しないといけないとなったら私はここを使うと思う。あと求人数も多かったように感じた。(引用元:X)
atGP、書類全然通らないやん笑
障害者雇用無理なのでは(引用元:X)
かべなし求人ナビ(旧:デイゴー求人ナビ)は就労移行支援や就労継続支援も確認できる
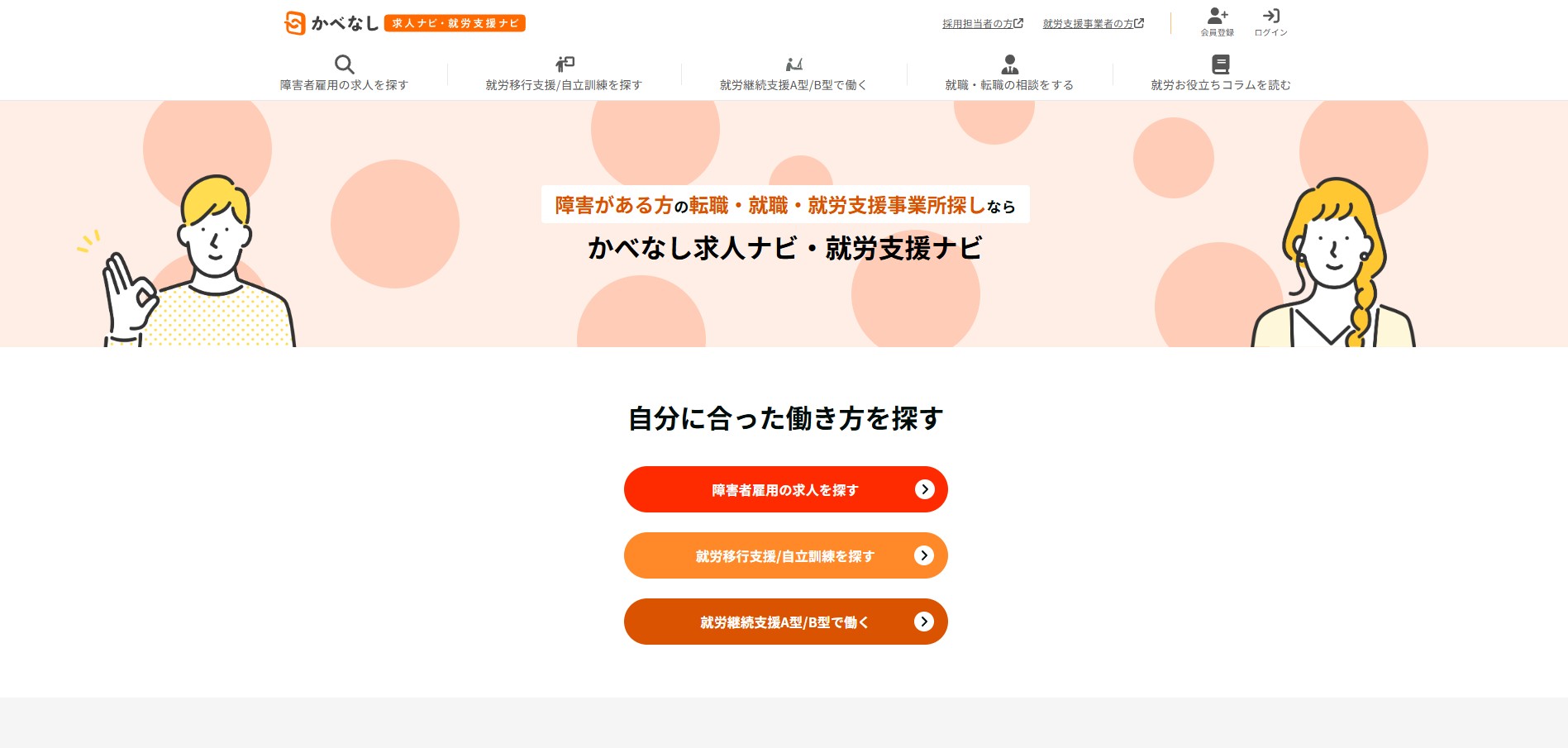
「かべなし求人ナビ(旧:デイゴー求人ナビ)」は、介護・医療系の人材サービスを展開する株式会社エス・エム・エスが運営する障害者/障がい者向けの転職支援サービスです。
障害者/障がい者枠での転職向け求人のほか、就労移行支援施設や就労継続支援A型・B型も調べることが可能です。転職以外の選択肢も比較したい人に適していると言えるでしょう。
求人検索と応募では、キャリアプランナーに相談することができます。案件は東京中心ですが、全国に対応。地方在住で求人が見つからなかった場合も、定期的にチェックするとよいでしょう。
- かべなし求人ナビ(旧:デイゴー求人ナビ)のおすすめポイント
- 就労移行支援施設や就労継続支援A型・B型も調べることが可能
- 求人検索と応募では、キャリアプランナーに相談可能
- 案件は東京中心だが、全国に対応
基本データ
| かべなし求人ナビ(旧:デイゴー求人ナビ) | |
|---|---|
| 公開求人数 | 290件(2025年7月14日現在) |
| 提供サービス | キャリアプランナー相談 |
| 拠点 | 東京 |
| URL | https://dei-go.com/ |
口コミ・評判
他のエージェントと比較すると始めたてのサービスで手厚くサポートをしてくれるのではないかと思い登録しました。 実際、担当の方のLINEを用いた密な連絡や書類添削の早さもあり安心して転職活動を行うことができました。 その結果、初めての障害者雇用枠でしたが、希望の条件で内定をもらうことができて満足です。(引用元:キャリズム)
身体的な障害があり、転職活動に不安でしたが、キャリアプランナーの方の返信ペースが早く気軽に連絡できたのが良かったです。 希望した条件に合った求人を紹介してくださいました。(引用元:キャリズム)
障害者雇用でのエージェントでデイゴー求人ナビは絶対使わない方が良い。希望していない案件しか紹介してくれない(引用元:X)
DIエージェントは希望に合わせて求人を新規開拓してくれる

「DIエージェント」は、障害者/障がい者雇用支援・教育事業を行う株式会社D&Iによる障害者/障がい者特化型の転職支援サービスです。
ヒアリングした希望に合わせて、求人を新規に開拓してくれるのが最大の特徴です。提案数が少ないと言われることもありますが、マッチングがていねいなため数が絞られることが理由です。収入アップの事例はもちろん、配慮してもらえる環境への転職の事例もあります。
また、面接対策に力を入れている点も特徴の1つです。
- DIエージェントのおすすめポイント
- ヒアリングした希望に合わせて、求人を新規に開拓してくれる
- マッチングが丁寧
- 面接対策に力を入れている
基本データ
| DIエージェント | |
|---|---|
| 公開求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | 書類作成サポート、面接対策、求人提案、入社日調整 |
| 拠点 | 東京 |
| URL | https://di-agent.dandi.co.jp/ |
口コミ・評判
障害者雇用を求めてDIエージェントに登録したら、予想の数倍以上の規模の会社からの求人が送られてきてビビる……40のオッサン障害者に社保完備でねんしう400万のきうじんて……(引用元:X)
DIエージェント○
→求人事務系多くてありがたかった
ちゃんと応募と選考されてた(引用元:X)
障害者雇用のDIエージェントさんから「今紹介できる求人ないや」のメールが来ちゃった。
私の職歴、カスなのかなぁ。やっぱり身体の人が優先なのかな。(引用元:X)
エージェント・サーナは業界トップクラスの求人数で非公開求人が85%

「エージェント・サーナ」は、障害者/障がい者採用支援30年以上となる株式会社イフによる障害者/障がい者専門の転職エージェントです。
求人数が業界トップクラスで、非公開求人も多数。全案件の約85%を占めています。選択肢が多いのが大きなメリットです。なお対応エリアは関東・東海・関西となっています。
またサービスもマッチングがていねいで、入社後のギャップを抑えることにも成功。短期離職率が0.5%ときわめて低い水準を実現しています。
- エージェント・サーナのおすすめポイント
- 求人数が業界トップクラス
- 全案件の約85%が非公開求人
- マッチングが丁寧で短期離職率は0.5%
基本データ
| エージェント・サーナ | |
|---|---|
| 公開求人数 | 1,432件(2025年7月14日現在) |
| 提供サービス | 就労条件の調整、面談対策、入社後のフォロー |
| 拠点 | 東京 |
| URL | https://www.agent-sana.com/ |
口コミ・評判
エージェントサーナさん、しっかりしてる😄こんな私に4社も紹介してくれた。ありがとうございます😊どれも大手ばかりで、私には敷居が高いかな😅(引用元:X)
ネットで探してエージェントサーナって会社に登録して条件に合うところ紹介して頂きました。何社か応募した中で(給与がいいとこ)実力主義であると記載があったので、内定頂いてた中で選択しました。(引用元:X)
糞エージェントサーナが勤務地の少なさもさることながら障害内容身体ばかみたいに細分化して精神一括りっておかしいやろがボケカス(引用元:X)
LHH転職エージェント Social Partnersはステップアップ転職や年収アップに強みあり

「LHH転職エージェント Social Partners」は、障害者/障がい者採用の専門的な知識を持つコンサルタントによる転職支援サービスです。世界的な人材サービス大手アデコグループが提供しています。
障害者/障がい者支援専門のコンサルタントが在籍、適切なサポートを提供。またもともと障害者/障がい者枠以外の人材サービスのため、ステップアップの転職支援に強みがあります。年代問わず、精神障害の方の年収アップの事例も豊富です。
- LHH転職エージェント Social Partnersのおすすめポイント
- 障害者/障がい者支援専門のコンサルタントが在籍
- ステップアップの転職支援に強みがある
- 精神障害の方の年収アップの事例も豊富
基本データ
| LHH転職エージェント Social Partners | |
|---|---|
| 公開求人数 | 417件(2025年7月14日現在) |
| 提供サービス | 求人提案、応募に関するアドバイス、面接日程の調整、企業との調整 |
| URL | https://jp.lhh.com/occupation/socialpartners |
口コミ・評判
障害者雇用の就職/転職活動ではあまり話題に上ることはないですが、私は転職にあたってSocial Partnersを使いました。アデコグループ自体が外資系だからなのか、外資系企業への転職に強い印象。コンサルタントの方には大変お世話になりました。(引用元:X)
書類選考が通ったときは、応募した企業の面接の想定質問を教えてもらえます。実際に面接を受けた際も想定から大きなずれを感じなかったので面接も戸惑いはありませんでした。(引用元:うつ病経験者の日記)
障害者雇用の転職エージェントLHHの初回面談、まさかの10分で終了。「30〜60分の面談」って事前説明やったのに。しかも、こっちが話してる途中で通話切られて、最後の挨拶もなかった(引用元:X)
アビリティスタッフィングは精神障害者に特化しておりフォローも手厚い

「アビリティスタッフィング」は、 リクルートグループが運営する障害者/障がい者向け人材紹介事業です。
精神障害者/障がい者の方向けのサービスで、求人の95%が精神障害者/障がい者向け案件となっています。今のところ対応エリアは首都圏なので、東京周辺で仕事を探している精神障がい(障害)の方にぴったりです。
求人への応募は、紹介のほか直接応募も可能。さらにフォローが手厚く、定着率が高いのも特徴です。入社後も精神保健福祉士等の資格をもった専門家から、定期的に面談などのサポートを受けることができます。
- アビリティスタッフィングのおすすめポイント
- 求人の95%が精神障害者/障がい者向け案件
- 求人への応募は、紹介のほか直接応募も可能
- フォローが手厚く、定着率が高い
基本データ
| アビリティスタッフィング | |
|---|---|
| 公開求人数 | 275件(2025年7月14日現在) |
| 提供サービス | 求人照会、入社後のフォロー |
| 拠点 | 東京 |
| URL | https://ability.r-staffing.co.jp/ |
口コミ・評判
私はリクルートのアビリティスタッフィングを利用しました
今の会社に入社するきっかけにもなりましたが10年近く前のことです
担当してくれた方がとても良い方だったので実際の企業面接前にトレーニングしてくれたり色々お世話になりました(引用元:X)
私はハローワークで探してたけど見つからず、リクルートのアビリティスタッフィングに登録したら面接会から就職までこぎつけました。(引用元:X)
アビリティスタッフィング…25社書類出して全滅。同じ求人ばかり紹介。書類添削なし。(引用元:X)
マイナビパートナーズ紹介は特例子会社ならではのアドバイスを企業・求職者に提供
「マイナビパートナーズ紹介」は、マイナビグループの特例子会社である株式会社マイナビパートナーズによる障害者/障がい者に特化した求人紹介サービスです。
障がい(障害)に詳しい専門カウンセラーがサポート。運営元が特例子会社のため、企業へのアピールのポイントなどにも精通しており的確なサポートが得られます。
また企業が障害者/障がい者を受け入れる際のノウハウも蓄積。企業にアドバイスすることも可能で、求人にも働きやすさが期待できます。イベントの実施や企業のインターンシップ情報の提供も行っています。
- マイナビパートナーズ紹介のおすすめポイント
- 障がい(障害)に詳しい専門カウンセラーがサポート
- 企業へのアピールのポイントなどにも精通している
- イベントの実施や企業のインターンシップ情報の提供を行っている
基本データ
| マイナビパートナーズ紹介 | |
|---|---|
| 公開求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | 書類添削、面接対策、面接の日程調整、入社日の調整、定着支援 |
| URL | https://mpt-shoukai.mynavi.jp/ |
口コミ・評判
マイナビパートナーさんはちゃんと紹介してくれるから良い子のみんなはdodaチャレンジじゃなくてマイナビパートナーを使おうね(引用元:X)
マイナビパートナーズ⋯首都圏、関西圏、名古屋という限定。事務職が多かった印象。ただ、求人数が少なめ。マイナビの安心感があるのは、頼れる。(引用元:X)
マイナビパートナーズに登録してて、とっくに忘れてたんだけど、さっき「あなたの経歴では紹介できる求人はありません」って連絡来た😂 だったらわざわざ連絡してこなくていいよ…(引用元:X)
手帳なしでもありでも利用しやすい適応障害の方向け総合型転職エージェント5選

続いて、手帳がなくてもあっても適応障害の方が利用しやすい総合型の転職エージェントについてまとめます。以下の5つのサービスがあります。
- リクルートエージェント
- dodaエージェント
- マイナビAGENT
- パソナキャリア
- キャリアスタート
上記のサービスは、クローズ就労で利用するのにとくに向いています。またケースバイケースにはなりますが、オープン就労でも利用できることも少なくありません。
【まずはチェック!!】求人数の多い大手転職サービスが人気!おすすめの求人数比較表!
大手転職サービスの取り扱い求人件数を独自調査。転職サービスの専任担当者が最新の取り扱い求人情報を確認し、求人数比較表にまとめています。転職活動にあたってはエージェントやサイトを積極的に活用しましょう。まずは一通りサービスを体験してみて自分にあったサービスを見つけることをおすすめします。比較表はこちら。
右にスクロールできます
| おすすめ | リクルートエージェント | doda | マイナビAGENT | リクナビNEXT | パソナキャリア | ビズリーチ | リクルートダイレクトスカウト | マイナビ転職 | エン転職 | JACリクルートメント | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特色 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | 全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス・女性向け | ハイクラス全年代・業界 | ハイクラス・全年代 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス | 全業界・首都圏 |
| 求人数 | 619,020件 | 253,658件 | 非公開 | 1,008,000件以上 | 49,483件 | 172,146件 | 534,042件 | 非公開 | 99,695件 | 22,272件 | 2,525件 |
| 求人の豊富さ | |||||||||||
| ポイント | 非公開求人も多数 | エージェント・サイト両方の利用が可能 | 地方の求人も充実 | 企業からのオファーあり | オファーも受けられる | 2種類のスカウトあり | 登録するとスカウトが多数届く | スカウトサービスあり | 利用者の満足度が高い | コンサルタントのサポートが手厚い | とくにエンジニア、20代、女性の求人に強み |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
2025年9月9日調査:各転職エージェントの取り扱い求人件数・各転職サイトの掲載求人数
リクルートエージェントは圧倒的な求人数でチャンスが広がる
「リクルートエージェント」は、求人数を豊富に持つ転職エージェントです。求人数、安定したサービス品質でまずは登録して損はないエージェントです。
とにかくほかの追随を許さない圧倒的な求人数を誇ります。営業・技術系を中心にあらゆる業種・職種をカバー。地方の求人も多く、拠点も各地にあります。地方で転職活動中の人にとっても大きなメリットとなるでしょう。
選択肢を増やせるため、希望に合う求人に出会える可能性が高まります。
- リクルートエージェントのおすすめポイント
- ほかの追随を許さない圧倒的な求人数を誇る
- 営業・技術系を中心にあらゆる業種・職種をカバー
- 地方の求人が多く、拠点も各地にある
基本データ
| リクルートエージェント | |
|---|---|
| 公開求人数 | 581,492件(2025年7月14日現在) |
| 提供サービス | エージェントサービス、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供 |
| 拠点 | 東京・北海道・宮城・宇都宮・さいたま・千葉・横浜・金沢・新潟・長野・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡 |
| URL | https://www.r-agent.com/ |
口コミ・評判
前職を辞めた理由を説明すると「それは大変でしたね」と親身になって話をきいてくれ嬉しかったです。このエージェント会社の良し悪しは担当者によると思うので、はじめから避けない方がいいと思いました。(引用元:みん評)
担当してくれたエージェントさんはすごく親切な方でした。エージェント代理で日程調整や書類提出の対応をしてくださるサポート事務局の方も丁寧です。リクルートに限らず、合う合わないや当たり外れはどうしてもあると思います。(引用元:みん評)
精神疾患について理解がない人はいますよね。私はリクルートエージェントの人と転職面談をしたときに「適応障害があと何日で治るのか、お医者さんに聞いてきてください。」と言われました。それが分かったらこんなに苦労しないのに。(引用元:X)
dodaはエージェント/サイト一体型で自分でも応募が可能
「doda」は、人材紹介・転職支援を行う大手「パーソルキャリア」が運営する総合型転職サイトです。エージェントサービスも利用できる点が人気の理由の1つになっています。
業界最大級の求人数で、非公開求人が多いのもメリットです。またサイト/エージェント一体型なので、サポートを受けながらの応募も自力での応募も両方が可能です。
エージェントサービスのキャリアアドバイザーは専任。パーソナリティをより深く理解したうえでのサポートが期待できます。クローズ就労でも安心して一任できるでしょう。
- dodaのおすすめポイント
- 業界最大級の求人数
- サイト/エージェント一体型
- キャリアアドバイザーは専任で求職者に合ったサポートが期待できる
基本データ
| doda | |
|---|---|
| 公開求人数 | 250,356件(2025年7月14日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、年収査定、合格診断、レジュメビルダー、「自己PR」発掘診断、転職タイプ診断、はたらく女性のためのモヤモヤ解消診断、オンライン仕事力診断 |
| 拠点 | 東京・横浜・札幌・仙台・静岡・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・広島・福岡・鹿児島 |
| URL | https://doda.jp/consultant/ |
口コミ・評判
私が職選びや面接や転職後のことで抱える不安や疑問にも一つ一つ答えて下さり、大変心強かったのが印象的でした。レスポンスに関しては、まれに時間がかかることもありましたが、全体的に満足しています。(引用元:みん評)
非常に親身になって話を聞いてくれて、面談の感想や今後の悩みなども素直にお話することができました。求人も他の転職エージェントからは紹介されない求人を多く紹介してくれました。(引用元:みん評)
当時は適応障害で焦りとかあったからしゃーないとは言えもうちょい考えなあかんかったな
dodaのエージェントクソ過ぎるわ(引用元:X)
マイナビAGENTは20代・30代の求人に強みあり
「マイナビAGENT」は、さまざまな転職サイトを運営している株式会社マイナビによる転職エージェントです。きめ細かいサポートが受けられると評価されています。
とくに20代・30代の求人を多く扱っており、その年代ならおすすめです。拠点も全国にあり、地方在住で仕事を探している場合も多くの選択肢の中から選ぶことができるでしょう。働きやすそうな求人が見つかるかもしれません。サポートがきめ細かい点もクローズ就労で安心できるポイントです。
- マイナビAGENTのおすすめポイント
- 20代・30代の求人を多く扱っている
- 拠点が全国にある
- サポートがきめ細かい
基本データ
| マイナビAGENT | |
|---|---|
| 公開求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| URL | https://mynavi-agent.jp/ |
口コミ・評判
業界職種のことや未経験について、書類作成、面接対策、選考先との折衝、退職と入社後に向けたアドバイス等、全体的に丁寧に支援していただきました。特にこちらの目線に立って都合を合わせていただいたり、アドバイスをしてくださる担当者でしたので、とても良い担当者でした。(引用元:Google Map)
転職活動の進め方やポイントなど担当の方がわかりやすく教えてくださり、丁寧にサポートしてくれてました。面接対策などもしっかりできた為、満足のいく転職活動ができました。(引用元:Google Map)
マイナビエージェントさん偉そうにCMやってるけど、転職ときに前職で適応障害で治療経験ありますって素直に話したら1社しか紹介しない上にそれ落ちて以降一切紹介無かったけど大丈夫そ?(引用元:X)
パソナキャリアは希望と提案のマッチング度が高くサポートも充実

「パソナキャリア」は、人材派遣会社の株式会社パソナによる転職エージェントです。ハイクラス転職に強みがあるエージェントですが、適応障害の方も安心して利用できます。
ていねいなヒアリングによるマッチング力とサポート体制が同社の長所。希望をはっきり伝えればしっかり対応してくれるでしょう。それは実績としても現れており、オリコン顧客満足度調査で4年連続No1を獲得するなど、利用者の満足度が高いのが特長です。
女性の転職にも強みがあるので、女性の方はまず相談してみるとよいでしょう。
- パソナキャリアのおすすめポイント
- 丁寧なヒアリングをしてくれる
- マッチング力やサポート体制に強みがある
- オリコン顧客満足度調査で4年連続No.1
基本データ
| パソナキャリア | |
|---|---|
| 公開求人数 | 公開求人6,785件(2025年7月14日現在) |
| 提供サービス | エージェントサービス、スカウトサービス |
| 拠点 | 東京・大阪・名古屋・横浜・広島・福岡 |
| URL | https://www.pasonacareer.jp/ |
口コミ・評判
私の場合は親身に話を聞いてくる方だったので自分の要望とかも結構ストレートに伝えて、結果的に希望する業界で転職することができ、感謝してます。(引用元:Google Map)
他のエージェントにも登録していて、紹介先のラインナップにはそこまで違いがないとは思いましたが、対応の早さ、丁寧さが圧倒的に良かったです。面接のアドバイスも助かりました。(引用元:Google Map)
ここを使う意味はありません。自分で求人を探して応募するのと何ら変わらないからです。(引用元:Google Map)
キャリアスタートは第二新卒・既卒特化型で内定率・定着率が高い
「キャリアスタート」は、若手のキャリア形成を応援する第二新卒・既卒専用の転職エージェントです。
面接や書類作成のサポートを提供しているので、準備したうえで安心して本番に臨めます。そのため内定率は80%以上。さらにマッチングの精度も高く、転職してからの定着率は90%以上と高い水準です。利用できる年齢が限られるのと拠点が少ないですが、都市部で仕事を探している第二新卒・既卒の方ならぴったりです。
そのほかYouTubeやコラム記事を通じて、就職・転職に関する情報発信も行っています。
- キャリアスタートのおすすめポイント
- 面接や書類作成のサポートを提供
- 内定率は80%以上
- マッチングの精度が高く、転職後の定着率は90%以上
基本データ
| キャリアスタート | |
|---|---|
| 公開求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | 面接トレーニング、書類作成サポート |
| 拠点 | 東京・大阪 |
| URL | https://careerstart.co.jp/ |
口コミ・評判
失敗もありましたが、キャリアサポーターの方と伴走して転職活動が進められたことで、本当に大きな喜びや心強さがありました。その結果、一番に希望していた会社への内定がかないました。(引用元:Google Map)
我ながら厳しい条件で仕事を探していたのですが、他社では「紹介できる企業がない」「書類で落ちた」と言われ、そこで担当者とのやり取りが途絶える中、1番親身に熱血に関わってくれたのがキャリアスタートでした。(引用元:Google Map)
最初は丁寧に対応してくださったのですが、通院があると言った数日後の電話で「企業は探したけど、通院してるから、もし〇〇さんに何かあったら企業側が保証できないとかなんとかで対応できないから断られた。マイナビとか見て自力で探してください」と言われました。(引用元:Google Map)
適応障害の方向け転職エージェント選びのポイント

適応障害の方向けの転職エージェントを選ぶ際、エージェントに関して確認しておくべきポイントをまとめます。以下の点が挙げられます。
- 適応障害の方向け転職エージェント選びのポイント
-
- 求人の数が多い
- 職場の雰囲気をを知っている
- サポートが充実している
上記の3点は、障害者/障がい者特化型のエージェントも一般就労向けの総合型も共通の内容です。順に見ていきましょう。
求人の数が多い
まず、求人の数が多いかどうかチェックしましょう。求人の数が多いと選択肢が増えるためです。
障害者/障がい者の方に合う求人がそもそも少ないため、母数が多いほうがよい求人に出会える確率を高めることができます。そのためとくに数が少なくなりがちな特化型の場合は確認しましょう。特化型の場合、障がい(障害)の種類によって応募できる求人が決まっている場合もあります。たとえば精神障害特化型などです。適応障害に対応している求人数をチェックしてみてください。ただし特化型は無関係な求人がふくまれていないため、効率よく探せるメリットもあります。
もちろんクローズ就労で総合型のエージェントを見る場合も同様です。
職場の雰囲気をを知っている
また、職場の雰囲気を把握しているエージェントかどうかもチェックしましょう。担当者が教えてくれるか、掲載されている求人内容の文面から伝わってくるかなどが見るべき点です。
職場の雰囲気を事前に知ることで、残業が多い、コミュニケーションの風通しが悪いなど適応障害の方に向かない職場を避けることができます。安心して働き続けるためには、応募する前に職場の雰囲気を知っておくと安心できるでしょう。
とくに一般就労向けの総合型エージェントを
利用するときは要確認です。
サポートが充実している
転職活動におけるサポートが充実しているかどうかもポイントです。手厚いサポートが受けられると、障がい(障害)をカバーすることが可能になるためです。
書類の添削や面接対策がしっかりしていれば、特性や希望条件をどのように伝えたらよいかアドバイスがもらえます。突破率が高まるのはもちろん、メンタル面でも不安解消にも大きく役立つでしょう。
加えて特化型エージェントならば、専門的な知識に基づくサポートも期待できます。経験によりノウハウも蓄積されていることが期待できるので、安心度がより高まると言えます。
オープン就労とクローズ就労のメリット・デメリット

続いては、障がい(障害)を公表して就労するオープン就労と公表しないクローズ就労、それぞれのメリット・デメリットについてまとめます。
オープン/クローズのどちらにするかで、選択するべき転職エージェントも変わってきます。譲れない条件を明確にすることで、どちらのメリットを享受してどちらのデメリットを避けるかが決まります。
また両方の種類のエージェントを併用する場合も、それぞれの特徴を理解しておくことが転職活用に役立つでしょう。
では、順に見ていきます。
オープン就労のメリット
オープン就労の場合、障がい(障害)があることを認識されている状態で就労できるのが大きなメリットとなります。そのため、より具体的には以下のような対応が期待できます。
- 不向きな仕事を紹介されずに済む
- 配慮が受けられる
- 環境が整備されている
転職活動中は、適応障害の方に向かない仕事は除外して提案してもらえます。
さらに就労してからも、配慮や整備された環境により、不安を軽減したり症状の再発を予防したりすることが期待できます。その結果仕事がしやすくなり、長く働き続けられる可能性が高まるでしょう。
オープン就労のデメリット
ただしオープン就労にもデメリットがあります。
たとえば一般に、選択肢となる職種が限られます。軽作業や単純作業などの割合が高くなるため、必ずしも希望している職種の仕事が見つかるとは限りません。
また作業内容がシンプルなことが多いせいで、収入が低くなりやすいと言えます。さらに関連してキャリア形成が難しくなる場合もあります。
将来的な収入アップやキャリア形成を意識するなら、
徐々にステップアップしていくことが必要になるでしょう。
クローズ就労のメリット
クローズ就労では、オープン就労でデメリットとなる点が解消されます。
まずは、クローズ就労で応募する一般就労の求人は障碍者枠の求人に比べて圧倒的に数が多くあります。そのため選択肢が多くなり、希望に合う仕事が探しやすくなるほか決まりやすくなるとも言えます。
さらにオープン就労の障害者/障がい者枠の求人に比べ、収入も高くなります。そのため経済的な面では生活を安定させやすくなるでしょう。
クローズ就労のデメリット
しかしクローズ就労の場合は、オープン就労にあるメリットを享受できない点がデメリットとなります。
具体的には、就労中の配慮を受けることができません。そのため残業が多かったり仕事量を調節してもらえなかったりして、ストレスを感じるリスクがあります。さらに障がい(障害)を理由に休んだり免除を受けたりすることができないため、仕事の内容や進め方で負担感があるかもしれません。
そのほかにも、人間関係や物理的な面で職場の環境が合わないといった場合もあるでしょう。
ただし少し配慮してもらえれば勤務可能な場合は、配慮してほしいことについて「苦手なことがある」といった表現で上司や人事にだけ話しておくセミクローズという選択肢があります。
適応障害は転職エージェントに言うべき?
適応障害の場合、その事実を転職エージェントに言うべきなのでしょうか。企業に伝えるオープン就労の場合は当然言うことになりますが、企業に伝えないクローズ衆望の場合は悩むかもしれません。ここでは以下の側面からエージェントに伝えるべきかどうか考えます。
- 言うメリット・デメリット
- 言わないメリット・デメリット
- 休職した場合は?
順に見ていきましょう。
言うメリット・デメリット
障害者/障がい者枠、オープン就労を目指すなら当然エージェントにも言うことになります。障がい(障害)があると伝えることの最大のメリットは、転職活動中も入社後も配慮が受けられることです。エージェントも障がい(障害)の症状や程度に合わせた対応をしてくれます。
デメリットとしては、仕事が限られることが挙げられるでしょう。障害者-障がい者枠の求人はまだまだ少ないのが現状です。そのためさらに希望の条件があれば、求人数もますます少なくなります。そのぶん競争も激しくなるでしょう。
言わないメリット・デメリット
クローズ就労の場合は、エージェントにも言わないことをおすすめします。エージェントには話して企業には話さないという選択は、事実上ないと考えた方がよいでしょう。
エージェントだけに伝えておけば、クローズでも働きやすそうな求人を紹介してもらえるのでは?と期待する方がいるかもしれません。しかし現実問題として、その可能性は非常に低いと言えます。むしろサポートしてもらえなくなるというデメリットのリスクが高まります。
そのため言わない方が企業の選択肢が多くなり、メリットも大きいということになります。その場合、もちろん転職活動中も転職後も配慮は受けられません。その点はデメリットですが、クローズの場合はやむを得ないと言えるでしょう。
休職した場合は?
休職していた場合にその事実を伝えるべきかどうかはケースバイケースです。
オープン就労や障害者特化型エージェントの場合は伝えた方がよいでしょう。それを踏まえたうえでどう対処すべきかアドバイスが受けられます。
クローズの場合は伝えてしまうと理由を聞かれることとなるため、言わない方が得策です。法的な義務もありません。
ただし3か月以上の休職期間があると、入社後にバレる可能性があります。提出した源泉徴収票や住民税の納税額から、勤務していた機関が短いと気づかれるケースです。
総合型・特化型転職エージェントの違い
ここで、総合型の転職エージェントと特化型の転職エージェントの違いを確認しておきましょう。オープン就労・クローズ就労のどちらにするかで利用するべきエージェントも変わってくるためです。
両者のメリット・デメリットを理解して、使い分けるか組み合わせるかすることが必要です。なお、基本的にエージェントは複数利用します。両者を組み合わせる場合もそれぞれの特徴を理解しておくと役立つでしょう。
総合型転職エージェントとは
総合型の転職エージェントとは、一般的な転職で広く使われるエージェントの一種で職種や年齢層など限定せず幅広い求人を扱うエージェントです。求人数が多いと大規模になりやすいため、大手のエージェントが大半を占めています。
クローズ就労の場合は総合型への登録は必須です。ただし一部の大手エージェントは障害者枠の求人を保有しています。そのため、オープン就労でも総合型を利用することが可能です。
総合型転職エージェントのメリット・デメリット
総合型転職エージェントのメリットとデメリットを見ていきましょう。
メリットとしては、以下の点が挙げられます。
- 求人の数が多い
- 扱っている職種や業種も幅広い
- 障害者特化型に比べると求人の条件がよい
多くの条件のよい求人の中から選ぶことができ、選択肢が多いのがメリットです。
対して、デメリットとして以下の点が挙げられます。
- 転職活動で専門的なサポートが得られない
- 入社したあと配慮が得られない
条件がよい求人が多い代わりに、あらゆる面で障害への理解がないことが前提となります。クローズ就労はもちろん、オープン就労で一般企業に就職した場合もじゅうぶんな配慮が得られるとは限りません。もちろん障害者枠の場合は問題ありません。
特化型転職エージェントとは
特化型の転職エージェントとは、年齢や職種など条件を限定して転職サポートを行う転職エージェントです。障害者/障がい者特化型の転職エージェントも多くあります。
障害者/障がい者特化型では、障害者/障がい者枠や特例子会社、障害者/障がい者雇用に理解のある企業の求人を提案してもらえます。エージェントの規模は会社によってさまざまですが、大手の人材サービスが提供する特化型エージェントもあります。
効率よく障害者/障がい者向け求人を探せるため、オープン就労なら特化型の利用は必須だと言えるでしょう。
特化型転職エージェントのメリット・デメリット
特化型転職エージェントのメリットとデメリットも確認しましょう。ここでは障害者/障がい者特化型の転職エージェントに限定して解説します。
メリットは以下の点です。
- 転職活動中に障害者/障がい者専門のサポートが受けられる
- 配慮してもらえる企業に入社できる
転職活動においても入社後も障がい(障害)に配慮してもらえるのが最大のメリットです。
逆にデメリットとしては以下の点が挙げられます。
- 求人の数が少ない
- 総合型に比べると条件が劣る
求人数が少ないこともあり、特化型であっても利用を事実上断られることもあるのが現実です。また配慮が受けられるぶん給与など条件が劣るのが一般的です。ただし一部にはハイクラス求人を扱う障害者特化型のエージェントもあります。
転職エージェント・転職サイトを有効活用するポイント
続いて、転職エージェントや転職サイトを有効活用する際のポイントについてまとめます。以下の点が挙げられます。
- 複数のエージェントを併用する
- 相性の悪い担当者は交代してもらう
- 経歴・スキルは正確に伝える
- サポートをフルに活用する
これらは障害者/障がい者特化型でも一般向けの総合型でも同じです。順に見ていきましょう。
複数のエージェントを併用する
まず、転職エージェントは複数のサービスを併用しましょう。エージェントはそれぞれ得意・不得意があります。複数のエージェントを組み合わせることで、それぞれの短所をカバーしつつ長所を活用することができるようになります。とくに初めは多めに登録して、相性の良いところに絞り込んでいくのがおすすめです。
なお、もちろん転職エージェントと転職サイトを併用するのも有効です。転職サイトだけで転職活動する場合も、複数のサイトに登録しましょう。確認できる求人の数を増やすことができます。
相性の悪い担当者は交代してもらう
担当のアドバイザーと相性が悪いと感じたら、別の担当者に後退してもらいましょう。担当者は代えてもらうことができます。それまでの担当者に悪いのでは?と感じるかもしれませんが、転職活動は自分の生活がかかっていることです。遠慮する必要はありません。
ただし、担当者の対応が悪いと感じたとしても担当者個人のせいではないこともあるので注意が必要です。応募できる求人がないと言われたとしても、タイミングによってはありえます。担当者のせいとは限りません。あるいはなかなか書類選考に通らないとしても、応募者数が多いなど担当者以外に理由があることは少なくありません。
経歴・スキルは正確に伝える
また、担当のアドバイザーに経歴やスキルを伝えるときは正確に伝えましょう。
よいところを紹介してもらいたいと思っても、虚偽の説明は厳禁です。担当者との信頼感を大きく損ねるほか、経歴詐称が発覚した場合はエージェント利用を断られる場合もあります。また仮に入社にこぎつけたとしても、実力以上の職場で求められるレベルが高すぎると結局続けることができません。
正直に話したうえで、どのようにアピールしたらよいか相談するのが最良の策だと言えるでしょう。
サポートをフルに利用する
転職エージェントでは、さまざまなサポートを提供しています。エージェントの各種サポートをフルに利用することで、転職活動に大きなプラスとなります。具体的には、求人紹介、書類添削、面接対策、企業との条件の交渉などが挙げられます。
自分に合う求人に出会えるまで、可能な限り紹介してもらいましょう。ただし障がい者/障害者枠の求人は少ないため、すぐには紹介してもらえず長い目で見なければならない可能性もあります。
書類の添削や面接対策をしてもらうことで、応募先の事情に合わせたアピールが可能になります。担当者は、募集の背景や企業の社風、求める人物像などを把握していることが多いためです。
また企業との交渉も個人では難しいものですが、エージェントに任せることでよりよい条件に整えてくれる可能性があります。
適応障害の方が転職活動をする際の注意点

次に、適応障害の方が転職活動をする際に注意すべき点についてまとめます。以下の点が挙げられます。
- 転職活動をする際の注意点
-
- 体調を優先して無理をしない
- 発症した原因を特定する
- 希望条件に優先順位をつける
- 応募企業の環境や制度を確認する
- 適応障害に不向きな仕事は避ける
1つずつ見ていきましょう。
体調を優先して無理をしない
収入面などで不安を感じたとしても、まずは体調を優先して無理をしないことが非常に重要です。まだ不安定な状態で就労しても、結局続けられず退職するといったことになりかねません。それだけでなく、結果的に回復が長引くリスクも高まります。
家庭の事情やそれまでの勤務状況などによっても変わりますが、傷病手当や失業手当、生活保護などお金をどうにかする方法はいくつかあります。
まずは体調を整えることを第一に考え、
就労は医師の許可が出てからにしましょう。
発症した原因を特定する
適応障害を発症した場合、はっきりした原因があります。原因を特定することで、似た仕事内容や職場環境を避けるなど対処することができるようになります。対処すれば、再発防止や軽減も可能です。
安心して職探しができるようになるほか、就労後も継続・定着できる可能性が高まります。さまざまな面でプラスに働くので、具体的な転職活動を始める前に原因を特定しておきましょう。
医師の診断を受けることで特定してもらえます。その際、復帰するときの条件を診断書に書いてもらうのも良い方法です。
希望条件に優先順位をつける
さらに希望条件に優先順位をつけることも重要です。条件の優先順位をつけて優先順位が低い条件は妥協することが、現実的な対処として求められます。
オープン就労、障害者/障がい者枠を希望する場合、そもそも求人が少ないのが実情です。クローズ就労でも、適応障害に合う環境の整っている求人は見つけづらい可能性があります。あれもこれもと条件を付けていると、仕事が見つからないということになりかねません。
自分にとって大きなストレス源は避けつつ、妥協できる範囲を探りましょう。
応募企業の環境や制度を確認する
さらに、応募企業の職場環境や制度を確認することも大切です。
具体的には、人間関係などの環境はどうか、
メンタルヘルスに関する制度が整っているかなどを調べましょう。
エージェントの担当者に尋ねる、求人情報を読み込む、口コミを参考にする、面接で質問するといった方法があります。
メンタルヘルスに取り組んでいる会社なら、制度を整備したり社風に反映されたりするはずです。働きやすさに直結することなので、事前に確認しましょう。
適応障害に不向きな仕事は避ける
また仕事を探す時点で、適応障害のある方には向かない仕事は避けるようにしましょう。一言で言えば、ストレスの負荷が大きい仕事は避けた方がよいと言えます。
具体的には、責任が大きい仕事です。たとえばチームをまとめる管理職や命を預かる医師などが該当します。そのほかノルマの厳しい営業職もストレスを感じやすいでしょう。クレーム対応の担当者なども、気持ちの切り替えが苦手な人には不向きです。
意味がわかりづらい横文字の職種名にも注意しましょう。たとえば「ビジネスサポーター」など、事実上は営業職で、顧客の問題を聞き出したうえで問題を解決できる商品を提案して買ってもらう仕事であったりする可能性があります。
適応障害の方が転職を成功させる方法
続いて、適応障害の方が転職を成功させる方法について解説します。以下の点が挙げられます。
- 主治医やカウンセラーに相談する
- 障害者/障がい者特化型の転職エージェントを利用する
- ハローワークの障害者/障がい者専用窓口で相談する
- 深く自己分析をする
- 妥協できない希望条件を明確にする
1つずつ見ていきましょう。
主治医やカウンセラーに相談する
まず、転職活動を始める前に主治医やカウンセラーに相談することが必須です。
専門的な知識のある人に、客観的に見て現在の状態で転職できるかアドバイスをもらいましょう。適応障害の場合、精神状態が安定していないと現実問題として転職できません。入社までこぎつけたとしても、働き続けられるかどうかは別問題です。
転職できる状態になっていたとしても、どんな配慮が必要かも知っておく必要があります。自己判断はせず、まずは専門家に相談しましょう。
障害者/障がい者特化型の転職エージェントを利用する
また障害者/障がい者特化型の転職エージェントを利用することも成功のポイントです。状態にもよりますが、特化型のエージェントで障害者/障がい者雇用に理解のある職場を探した方が再発のリスクを格段に抑えられるためです。すでに述べたように、入社までの転職活動でも障がい(障害)に理解があるサポートを受けられます。
特化型の求人では給与などの条件面で満足できない場合もあるでしょう。そのような場合も、時間をかけてステップアップしていくことで徐々に改善するという方法があります。その方が現実的だと言えるでしょう。
ただし特化型だけ利用するべきということではありません。総合型も組み合わせて利用することでチャンスを増やすことができます。
ハローワークの障害者/障がい者専用窓口で相談する
ハローワークには障害者/障がい者専用窓口があり、相談すると就職支援が受けられます。
障がい(障害)のある方の転職は健常者の転職より制限も多いため、利用できるサポートはできるだけ利用しましょう。ハローワークでは職業紹介のほか、就職説明会などの情報提供も行っています。ハローワークはさまざまな都市にあるので利用するのもラクでしょう。
深く自己分析をする
さらにすでに述べたことともかかわりますが、深く自己分析をして自分への理解を深めることが非常に重要です。再発を防ぐためには、自分が発症した原因を特定することが不可欠なためです。自分の障がい(障害)について分析する必要があります。
そのほか自分の強みや弱みを理解することで、自分に適した職場選びが可能になります。自分の性格を分析して理解することも大切です。
さらに自分のスキルや経験なども棚卸しましょう。転職活動において、仕事選びや応募時の自己PR作成などに不可欠です。
妥協できない希望条件を明確にする
自己分析の結果をもとに、妥協できない希望条件を明確にしておきましょう。障がい(障害)の再発を防ぎ、安心して働き続けるためにとても大切なステップだからです。
希望する条件を思いつく限りリストアップして、その中で妥協できない条件を選びます。優先したい順に並べ替えて、どこまでは妥協できないか考えると整理しやすいでしょう。
適応障害で採用されるための応募書類・面接のポイント
続いて、適応障害の方が採用されるための応募書類・面接のポイントについてまとめます。以下の点が挙げられます。
- 安定して出勤できることを伝える
- 自分の障害を正確に説明する
- 基本的なビジネスマナーを守る
なお、上記はオープン就労の場合です。順に見ていきましょう。
安定して出勤できることを伝える
まず、安定して出勤できることをはっきりとわかりやすく伝えることが大切です。安定して働けるかどうかは企業が最も重視するポイントのためです。
安定して勤務できる根拠をピックアップして、企業にとって安心材料になるようにわかりやすく伝えましょう。たとえば、以下の例が挙げられます。
- 過去の勤務実績:「前職は〇年勤務していた」「週5日フルタイムで勤務できている」
- 現在の体調管理:「規則正しい生活を心がけている」「1日7時間以上眠っている」
- 医師の診断:「医師からは転職活動してよいと言われている」
企業側の不安を取り除くのに役立ちます。
自分の障がい(障害)を正確に説明する
また自分の障がい(障害)を正確に説明しましょう。説明できるよう事前に準備することが大切です。振り返りや主治医のカウンセリングなどが必要になるでしょう。
自分が自分の障がい(障害)を理解していることは企業にとって安心感となります。企業にとっても、応募者がどのような人でどのような状態なのか理解できるためです。正確に説明することで、企業の側としては以下のような点がイメージしやすくなります。
- 実際に採用したときに何をしてもらうか
- どのような配慮をすればよいか
このように、採用した場合をより具体的に考えるのに役立ちます。
基本的なビジネスマナーを守る
また、社会人として基本的なビジネスマナーを守ることも必須です。とくに面接では意識しましょう。
ビジネスマナーは障がい(障害)とは無関係です。基本的なマナーが守れるかは、職場になじめるかを企業側がイメージするときに重要となります。ビジネスマナーを守れるなら、採用した場合に周囲とうまくやっていけそうだと想像できます。逆に守れないと、トラブルが起こりそうだと判断されてしまうでしょう。
具体的には、あいさつ、身だしなみ、話し方や姿勢などが挙げられます。
適応障害とは?改めて確認
ここで、適応障害とはどのような障がい(障害)なのか確認しておきましょう。以下の側面からまとめます。
- 適応障害とは
- 適応障害の症状
- 職場不適応を見分ける方法
- 適応障害は転職すれば治る?
順に見ていきましょう。
適応障害とは
適応障害とは、ストレスが原因となってメンタルや行動に悪影響が及び健康な生活が送れていない状態を指します。はっきりした原因により起こる点も特徴です。そのためストレスの原因から遠ざかると、徐々に症状が改善されます。
原因となるストレスは、個人レベルから災害などのような社会にかかわるレベルまでさまざまです。もちろん仕事上のストレスによって発病することもあります。わかりやすい例ではハラスメントや人間関係、業務量やノルマのプレッシャーなどです。それ以外が原因になることもあります。
ただし残念ながら完治するとは限りません。再発リスクもあるため、長期的に対処することが必要です。またうつ病に至る確率も高いため、早めに対処することが求められます。”
適応障害の症状
適応障害の症状は、精神面・身体面・行動面に現れます。
- 精神面の症状:意力の低下、意欲減退、不安やイライラなど
- 身体面の症状:不眠、胸の圧迫感、息苦しさ、動悸、吐き気など
- 行動面の症状:無断欠勤、遅刻、暴飲暴食、暴力的・衝動的な行動など
当てはまるものが複数ある場合は医師の診察を受けましょう。
職場不適応を見分ける方法
職場不適応とは職場に対してストレスを感じる状態で、そのストレスが精神・身体・行動に影響すると適応障害となります。つまり職場不適応は適応障害の原因です。以下のようなサインや自覚症状がある場合は、職場不適応の可能性があります。
- 出勤したいができない
- 週末になると不調が改善される
- 遅刻や早退が増える
- 有休の利用や欠勤が増える
- 仕事上の責任感が乏しくなる
上記のほかにもいろいろな現れ方をする場合があります。やはり違和感を感じたら医師の診察を受けることをおすすめします。
適応障害は転職すれば治る?
適応障害の原因が職場にあった場合は、転職することで症状が解消されます。しかし原因が職場ではなく、家庭、職場以外の人間関係、通勤の環境や住環境などにある場合は転職しても改善しません。
またいったん症状が解消したとしても、再発のリスクがあります。気を抜かず注意・対処を継続することが大切です。
適応障害の方に向いている仕事の特徴
続いて、適応障害の方に向いている仕事の特徴についてまとめます。以下の特徴が挙げられます。
- 休みが取りやすい
- 時間の制約が少ない
- 異動や転勤が少ない
適応障害の原因はストレスです。そのため適応障害の方にはストレスを感じにくい職場が向いているということになります。ストレスを感じにくいということをより具体的に表現したのが上記の特徴です。それぞれについて見ていきましょう。
休みが取りやすい
まず、いざというときに休みがとりやすい仕事です。症状が悪化して休息が必要なときや急遽医者に行かなくてはならない場合なども、休みが取れると安心です。休みが取りやすいと思えるだけでも、メンタル面の不安を減らすことにつながるでしょう。
求人をチェックするときや面接では、有給休暇取得の実績や取得率などを確認します。いくつかの企業をチェックすることで、取りやすいかどうかイメージしやすくなるでしょう。
休みがとりやすい職種の例
休みの取りやすさは、職種よりも企業風土や職場ごとの環境などで決まる傾向があります。そのため求人ごとに確認するのがおすすめです。そのほかフリーランスも自分で休みの日を決めやすいので、休みがとりやすいと言えるでしょう。
時間の制約が少ない
また時間の制約が少ない仕事も適応障害の方に向いています。自分のペースを守りやすく、落ち着いた気持ちで仕事に取り組めるためです。
スケジュールを自分で決められる、周りの事情で突発的な業務が入ったりしないといった仕事だと安心です。よりわかりやすい例では、リモートワークやフレックスタイムなどを導入している職場が挙げられます。
時間の制約が少ない職種の例
時間の制約が少ない職種としては、リモートワークがしやすい仕事が多く該当します。とくにIT系の仕事が挙げられます。たとえばライター、デザイナー、プログラマー、エンジニアなどです。
ただしこれらの職種はチームで業務を進める面もあります。適応障害の人はチームでの仕事が苦手なので、注意することも必要です。しかし突発的なことが起こらない限り、働く場所はもちろん時間帯も自由なケースが少なくありません。そのほか職種ではありませんが、フリーランスも時間の融通が利きやすい働き方です。
異動や転勤が少ない
また異動や転勤が少ない仕事も適応障害の人に向いています。新しい環境はストレスになりやすく、同じ場所で働き続けられる方がストレスを感じにくいためです。
異動は仕事の内容も変わることが多く、その意味でも不安を感じやすいでしょう。転勤は出勤のルートや時間も変わるため、慣れるまでしばらくは落ち着かない気分になりがちです。またどちらも人間関係や仕事の進め方などが新しくなるため、その点でも不安になりやすくなります。
異動や転勤が少なければ、新しい環境に適応するのが苦手な人も安心して働けるでしょう。
異動や転勤が比較的少ない職種の例
異動や転勤が比較的少ない職種としては、IT系、公務員などがあります。どちらも転勤になることがあまりありません。また専門性の高い職種であれば、異動による業務内容の変更も起こりづらいと言えます。
そのほか企業の規模が小さいと転勤はありません。またリモートワークの仕事は、そもそも転勤という概念がないとも言えます。ただし小さい企業やリモートワークの仕事はそのほかの要素も確認しておきましょう。たとえばオーナー社長がワンマンでハラスメント体質だったという可能性もゼロではありません。
適応障害の方に向いていない仕事の特徴
次に、反対に適応障害の方に抜いていない仕事の特徴を確認しましょう。以下の特徴が挙げられます。
- プレッシャーを感じやすい
- 業務が変則的になりやすい
- 連携して業務を進める
いずれもストレスの原因となる特徴です。1つずつ解説します。
プレッシャーを感じやすい
まず、プレッシャーを感じやすい仕事です。プレッシャーはストレスの大きな原因になるため、適応障害の方は避けるべきです。仕事の内容や職場の環境でプレッシャーがありそうだと感じたら、その求人はやめておいた方がリスク回避になります。
より具体的には、ノルマがきつい、ミスが致命的になる、リーダーなど管理する仕事であるなどと言い換えることができるでしょう。
プレッシャーを感じやすい職種の例
プレッシャーの種類別に職種を見てみましょう。ノルマがきつい可能性があるのは営業職です。ただしフルコミッションなどノルマがない場合は、逆に働きやすいかもしれません。
ミスが致命的になる代表的な例は医療関係です。また致命的というほどではありませんが、プログラマー・エンジニアなども業務に厳密さが求められます。
リーダーのポジションとしては管理職です。そのほかクレーム対応もプレッシャーを感じやすい職種です。
業務が変則的になりやすい
業務が変則的になりやすい仕事も適応障害の方には向いていません。定型的な作業のような安心感がなく、ストレスや焦りを感じやすいためです。より具体的には、臨機応変さが求められる、突発的な業務が発生する、時間を自分でコントロールできないといった仕事が挙げられます。
また仕事をコントロールしづらいと、長時間労働になりやすくなるケースもあります。そのような面も適応障害の方にとってマイナスです。
業務が変則的になりやすい職種の例
業務が変則的になりやすい職種の例を、パターン別に見てみましょう。臨機応変な対応が求められるタイプとしては、介護、保育士、教員などの職種が挙げられます。いずれも、相手がこちらの言うことを聞いてくれなかったりして、自分が相手に合わせる必要が出てくる可能性がある仕事です。
突発的な業務が発生するタイプとしては、接客業が挙げられます。やはり相手の都合でいろいろなことが起こり、その場その場で対応しなければならなくなることがあります。より具体的な例としては、飲食店やホテルのスタッフなどです。
連携して業務を進める
チームで連携して業務を勧める仕事も、適応障害の人にはあまり向いていません。自分のペースで仕事ができなくなったり、次の工程の担当者がいると焦ってしまったりしてストレスになりうるためです。
また適応障害の場合、そもそも人づきあいが苦手で対人関係の距離感をうまく保てないケースもあります。そのようなケースでは、仕事の内容以前に相手がいること自体がストレスになってしまうかもしれません。
連携して業務を進める職種の例
連携して業務を進める職種の例としては、医療関係、介護系、システム開発、飲食店などが挙げられます。いずれもチームとして仕事を行い、1人ひとりがチームの一員として分担された業務を担当します。
そのほか、一般に適応障害の人に向いているとされるライン作業も、自分の作業が滞ると次の作業の担当者に影響します。職場の雰囲気や相手の性格によっては急かされることもあり、必ずしも安心して作業できるとは限りません。
適応障害の人が働きやすくなる配慮
次に、適応障害の人が働きやすくなる配慮について解説します。以下の点が挙げられます。
- 業務量や業務内容を調整する
- 窓口やカウンセラーに相談できる環境を整える
- 物理的・人的な社内環境を整備する
- 共感・傾聴する姿勢で接する
- 強制や圧力を用いない
- プライバシーの侵害を避ける
上記のような配慮が受けられる職場なら安定して続けられる可能性が高まります。職場選びの参考にしてみてください。
では、順に解説していきます。
業務量や業務内容を調整する
まず、業務の量や内容を調整することです。多すぎる量の仕事、苦手な仕事はストレスになり症状の悪化につながるリスクがあります。仕事の量・内容を調整する配慮により、ストレスの危険が減り働きやすくなるでしょう。
具体的なカバーの方法には、業務をほかの社員と分担する、締め切りを遅らせるなどが挙げられます。
仕事を選ぶ際は、負担にならない体制が整っているかどうか確認してみましょう。
窓口やカウンセラーに相談できる環境を整える
窓口やカウンセラーに相談できる環境を整えることも、適応障害の方が働きやすくなる配慮です。産業医やカウンセラーに相談できると安心感が増し、続けやすくなるためです。
仮に不調になった場合も、相談できる場所があれば早期に発見することができます。悪化する前に適切な対処ができるので、その意味でも働きやすくなると言えるでしょう。
あるいは主治医の診察が受けられるような臨機応変な対応もプラスです。具体的には、不調のときに早退・遅刻が許される環境です。
求人をチェックする際は相談できる環境があるかどうか確認するとよいでしょう。
物理的・人的な社内環境を整備する
また、社内の環境が整備されていることも働きやすさにつながります。このときの「環境」には、物理的・人的の両面の環境がふくまれます。
物理的な社内環境の例としては、照明や机の配置などが挙げられます。細かいことのように感じるかもしれません。しかし物理的環境が整っていると、集中しやすさがアップします。
人的環境については、転職の場合は社内の異動と異なり苦手な人を遠ざけるような配慮は不要でしょう。職場の人間関係ができあがっているわけでないためです。とはいえ、傾聴ができる人を担当にするなどの配慮が考えられます。
面接や会社見学など実際に職場を訪問する機会があったら、環境も確認しましょう。
共感・傾聴する姿勢で接する
仕組みというより接し方についてですが、共感・傾聴する姿勢も適応障害の方にとって働きやすい雰囲気を作ります。適応障害の方の場合、まず評価や判断をする前にしっかり受け止めてほしいと感じているケースが多くあります。共感・傾聴は安心感を与えます。しっかり聞くことが大切です。
職場では、話したいことがあるときには相談に乗る、とふだんから伝えることが受け入れられているという安心感につながります。
強制や圧力を用いない
何かを強制したり圧力をかけたりして行動を促すようなことがあると、働きづらくなってしまいます。これは適応障害の方に限らないことでしょう。強制・圧力をしない配慮が必要です。強制・圧力はストレスとなるためです。その結果症状が再発したり悪化したりすると、周囲にとってもむしろ負担が大きくなりかねません。企業側にもリスクとなるのです。
強制や圧力の例には、障害を早く治すよう促したりすることもふくまれます。仕事上の内容に限りません。
事前にエージェントの担当者に職場の雰囲気や上司のタイプなどを確認しておきましょう。
プライバシーの侵害を避ける
またプライバシーを侵害しないようにすることも、適応障害の人にとって働きやすくなる配慮の1つです。健康状態や家庭の環境などをしつこく聞き出すようなことは、ストレスの原因になるためです。
この点を事前に確認するのは難しいですが、過去に障害者/障がい者雇用の実績があれば配慮できる体制が作られていると考えられるでしょう。
企業側には、サポートに必要な情報以上は無理に聞き出さないことが求められます。よかれと思って聞いたことや軽い気持ちで質問したことが、相手にとってはストレスになるケースもあるためです。注意が必要です。
障害者/障がい者転職で採用される人の特徴
続いて、障害者/障がい者雇用で採用される人の特徴についてまとめます。何度も述べているように、障害者/障がい者枠の求人は数が少なく、大変狭き門となっています。採用される人の特徴を知ることで、採用されるために注意すべき点の参考になるでしょう。以下の点が挙げられます。
- 安定して働ける根拠がある
- 自分の障害を説明できる
- 自分にできることとできないことを理解している
- スキル・実績など採用するメリットがある
- 謙虚さ・素直さがある
1つずつ解説します。
安定して働ける根拠がある
まず安定して働ける根拠がある人です。言い換えると、続けて勤務できそうな人と言えるでしょう。
企業は採用に費用をかけているためコストを回収する必要があります。また将来的な人員計画に基づき採用の計画を立てます。いずれも安定して働き続けてくれることが前提です。そのため安定して働けるかどうかは、採用する際に優先度の高い事項だと言えるでしょう。以下のような根拠を示せると採用されやすくなります。
- 過去の職歴の勤務実績(勤務していた期間、勤務時間)
- 休職期間や休養していた期間が短い
- 現在の健康状態と体調管理
このように、続けられそうという根拠を示すことができると、企業側の安心感が高まります。その結果採用される可能性もアップするでしょう。
自分の障がい(障害)を説明できる
また自分の障がい(障害)害を説明できることも採用される人に共通する点だと言えます。障がい(障害)の種類・症状を客観的に理解していることとなり、自分で自分を把握している証拠となります。企業の側では、落ち着き・冷静さがあると評価するでしょう。
また業務にどんな影響があるか、どんな配慮でカバーできるかも説明できると、企業は採用した場合をイメージしやすくなります。より具体的に方針を立てることも可能になるでしょう。
自分にできることとできないことを理解している
さらに自分にできることとできないことを理解していることも、採用される人に共通の特徴です。
できることとできないことを説明してもらえると、任せられる業務、ほかの人に割り振る業務が明確になります。企業にとっては具体的な方針を立てることが可能です。どんなことができるかは採用するメリットにもつながるため、採用をより具体的に検討してもらえる可能性が高まります。
採用された場合はできることを中心に任されることが期待でき、安定的に業務を進めることができるでしょう。
スキル・実績など採用するメリットがある
スキル・実績など採用するメリットがあることは大きなポイントとなります。
企業にとって障害者/障がい者雇用は義務でもあるため、その意味では採用すること自体に意味があるとも言えますが、業務上で貢献してくれる人が優先されるのも事実です。
活躍できるスキルがある人は採用されやすいと言えます。アピールできる実績があるかどうか確認するとよいでしょう。
現時点でスキルがなくても、勉強中のことがあれば姿勢も含めてアピールになります。採用してもらうためにも入社後に自信を持って働くためにも、スキル習得に努めましょう。
謙虚さ・素直さがある
謙虚さ・素直さがあることも採用されるポイントです。自分の考え方ややり方に固執せず、新しい環境でも周囲に合わせて仕事に取り組める証明でもあるためです。企業が一方的に配慮するだけでなく、障害があっても環境に溶け込む努力をしてくれるだろうと期待もできます。
新しいことを学ぶ意欲、指示されたことを行動に移す力などがあると採用されやすいでしょう。新しい環境でも、ミスを防いだり業務をスムーズに進めたりできるためです。具体的なエピソードなどがあればぜひ自己PRに活用しましょう。
転職エージェント利用の流れ
次に、転職エージェント利用の流れを解説します。一般的には次の流れです。
- 登録
- カウンセリング
- 求人紹介・応募
- 書類添削・面接対策
- 面接
- 内定
- 退職・入社
順に見ていきましょう。
1. 登録
登録は、公式ホームページから行います。ホームページ内に入力フォームや登録ページへのリンクがあるのがふつうです。
入力事項を入力していくだけなので登録そのものは難しくありません。ただし経歴を入力する必要があるため、学歴や職歴の年号や内容をあらかじめ確認しておくとスムーズです。またすでに述べたように、経歴は正しく伝えなくてはなりません。虚偽の内容は厳禁です。
2. カウンセリング
登録が済むと、エージェント側から連絡がありカウンセリングが行われます。現在の状態やこれまでの職歴、希望する条件などについて質問されるので正直に答えましょう。職務経歴書や履歴書も用意しておくとスムーズです。
オープン就労ならここで障害のことも正確に伝えます。説明できるようにまとめておくと、伝え漏れを防ぐことができます。すでに述べた通り、クローズ就労の場合は障害のことを伝える必要はありません。
カウンセリングは対面のほかオンラインや電話で行うこともあります。
3. 求人紹介・応募
カウンセリングが終わると、話した内容に応じて求人を紹介してもらえます。疑問点があれば質問して、詳細をよく理解してからよいと思えるかどうか判断することが大切です。よいと思える求人があったら応募しましょう。紹介されたからといって応募しなければならないわけではありません。
なお、タイミングによっては適した求人がないこともありえます。わずかな数しか紹介してらえない場合があるほか、そもそも紹介が受けられない可能性もあるので理解しておきましょう。
4. 書類添削・面接対策
応募・選考に当たっては、サポートが受けられます。具体的には書類の添削や面接対策です。
応募書類となる職務経歴書・履歴書などは添削してもらえます。とくに障害者/障がい者特化型のエージェントであれば、自己PRや希望する条件、休職期間や空白期間の上手な伝え方など、専門的なアドバイスがもらえて非常に有益です。
面接対策は模擬面接などを行ったうえでアドバイスしてもらえることが一般的です。面接対策も効果的な自己PRの表現や表情・話し方などの面で、適切かつ役立つアドバイスが受けられます。特化型エージェントなら面接対策でもより専門的な意見が得られます。
5. 面接
書類選考に通過すると面接へと進みます。日程の調整もエージェントが代行してくれます。またエージェントによっては、面接に同席してくれる場合もあります。面接のあとにフィードバックしてくれるエージェントも少なくありません。
6. 内定
面接にパスするといよいよ内定です。面接の回数は企業によって異なります。内定した場合は、条件の交渉や入社日の調整を代行してくれます。
なお、もちろん内定が出たからと言って必ず入社しなくてはならないわけではありません。面接で実際に社内の様子を見たら気になることがあった、といったケースもあるでしょう。複数の企業から内定をもらう場合があるかもしれません。自分にとって最善と思える選択をしましょう。
7. 退職・入社
在職だった場合は退職です。可能な限り、円満な退職を目指しましょう。必要な場合は、エージェントがスムーズに退職するアドバイスをしてくれます。
また入社して終わりとは限りません。とくに障害者/障がい者特化型の場合、入社してからも相談に乗ってくれるエージェントも少なくありません。総合型でも対応しているエージェントがあります。
適応障害の方が転職活動でしてはいけないこと
続いて、適応障害の方が転職活動でしてはいけないことを確認します。以下の事項が挙げられます。
- 自己判断で転職活動を進めてしまう
- 企業選びで妥協してしまう
- 適応障害の理解が足りていない
1つずつ見ていきましょう。
自己判断で転職活動を進めてしまう
まず、自己判断で転職活動を進めてしまうのはやめましょう。まだ働ける状態でないのに働けると思ってしまったり、転職活動で客観的な判断ができなくなり焦ってしまったりする可能性があるためです。
すでに述べたように、始めるときはまず主治医やカウンセラーに確認しましょう。転職活動もエージェント利用が安心です。客観的・専門的なアドバイスが受けられるためです。
企業選びで妥協してしまう
早く仕事を見つけたいからと、企業選びで妥協してしまうのもNG行為です。妥協してしまうと障がい(障害)が再発してしまう可能性があるためです。再発を防ぐには、原因となることを避ける必要があります。すでに述べたように、再発を避けるために必要となる条件を明確にしておき、その条件については妥協しないことが大切です。
なかなか仕事が決まらなかったりして焦ると妥協しがちです。気を付けなくてはなりません。その意味でも、第三者の客観的なアドバイスを受けながら転職活動を進めるのがおすすめです。
適応障害の理解が足りていない
また適応障害の理解を深めておかなくてはなりません。再発防止には自己理解が非常に重要となるためです。何を避けるべきか、何ならしても大丈夫かを自覚することが必要です。自分の障がい(障害)の原因や症状の内容・程度を把握するようにしましょう。リスクを避けるのに役立ちます。
また自分の障がい(障害)の理解を深めることは、応募書類や面接などで自己PRをしたり自分の希望を伝えたりするときなどにも有益です。
転職にはまだ早い場合の選択肢
症状が安定していないなど、転職にはまだ早い場合にはどのような選択肢があるのか解説します。主に次の3つがあると言えるでしょう。
- とにかくまず休む
- 就労移行支援を利用する
- 就労継続支援を利用する
1つずつ見ていきます。
とにかくまず休む
症状が不安定な場合は、まずはしっかり休みを取ることが大切です。会社に籍を残したまま休職するパターンと、退職した状態で休むパターンとがあります。どちらを選ぶかは状況によるでしょう。
休む場合は、ただ会社に行かないというだけでは不十分です。余裕が出てきたら、ストレスの原因を深く掘り下げること、自分に変えるべき点はないか考えることが大切です。再発を防ぐために役立ちます。
休んでいる間は、生活費をどう工面するかが大きな問題となるでしょう。休職する場合、条件を満たせば傷病手当などが利用できます。退職している場合もハローワークに相談してみましょう。失業保険など、利用できる制度があれば教えてもらえます。
就労継続支援を利用する
就労継続支援を利用する方法もあります。就労継続支援とは、障がい(障害)のある方に軽作業などの働く場を提供しつつ仕事・日常生活に必要な訓練を実施する福祉サービスです。次に解説する就労移行支援と比べると、障がい(障害)・症状が重い人向けです。
就労継続支援にはA型・B型があり、A型の方が軽い人向け、A型の利用が難しい人はB型となっています。給与・工賃という名目の違いはありますが、A型・B型ともに収入が得られるのが特徴です。ただし一般的な就労に比べると金額は低くなっており、就労継続支援の収入だけで生活するのは事実上かなり難しいでしょう。とくにB型は自由度が高く配慮してもらえるぶん、得られる金額には限りがあります。
就労移行支援を利用する
就労移行支援を利用する方法は、安定してきて就労できる状態になりつつある人向けだと言えます。就労移行支援は、障がい(障害)のある人に就職・転職に向けた訓練を行う福祉サービスです。訓練の内容は事業所により異なります。人気の事務系のスキルはもちろん、Web制作のようなクリエイティブ系のスキル習得ができるところまでさまざまです。
事業所では作業を行いますが、あくまで訓練であり労働ではないため基本的に収入は得られません。その点がデメリットに感じる方もいるでしょう。収入については、自分の場合は失業保険や何らかの給付金などを利用できないか、就労移行支援の担当者に相談することをおすすめします。
2年までという期間の制限がある点も覚えておきましょう。
適応障害の人が転職する際によくあるQ&A
最後に、適応障害の人が転職する際によく感じる疑問と回答をまとめます。
適応障害の転職は難しい?
障がい(障害)のある方の転職は難しいのが実状です。適応障害も同様です。
率直なところ、身体・精神・知的の障がい(障害)のうち、身体以外の2つはさらに難しいと言えます。配慮ができる余裕のある職場が限られており、求人自体少ないためです。
できればしっかり休養を取ってから一般就労を目指す方が、選択肢を増やすことができます。障害者/障がい者枠を希望する場合は、すでに述べたようにスキル向上など自分の努力が必要です。
適応障害は転職で不利になる?
適応障害が転職で不利になるかどうかはケースバイケースです。
原因がはっきりしており対処すれば症状も大幅に改善されるため、その意味では問題は少ないと言えます。また近年はうつなどの人も増えており、障がい(障害)に理解が広まっている側面もあります。これらの理由により、不利になるリスクが少なくなりつつあります。
ただしここまでに解説してきたように、障害者の方向けの求人はまだまだ少ないのが現状です。そのため1件に対する応募者が多く、症状が軽い人が選ばれる可能性が高くなります。症状の重さによっては不利になることも現実的には起こりうるでしょう。
適応障害で転職したらバレる?
適応障害で転職しても、手続きなどの過程でバレることはありません。自分から言うほか、仕事に何らかの支障が出るとバレる可能性はあります。
また休職期間がある場合、長さによってはすでに解説したように企業に気づかれる可能性はあります。提出した源泉徴収票や住民税の金額により、勤務期間が短いことに気づかれるケースです。
自分から伝える義務はありませんが、面接などで質問されたのにウソをついた場合は問題視されるリスクがあります。
「適応障害が転職で治った」は本当?
「適応障害が転職で治った」という話を聞くことがありますが、これもケースバイケースです。
適応障害はストレスが原因のため、仕事にストレス源がありそれが転職で解消されれば治るでしょう。ただし仕事以外に原因がある場合は治りません。よって原因を特定することが非常に大切です。
またすでに述べたように、治ったように見えても再発リスクがあります。気を抜かず、継続して対処することが不可欠です。
適応障害で転職を繰り返す場合はどうすればいい?
適応障害の場合、根本的な解決を目指さない限り再発する可能性があります。根本的な解決ができていない場合、転職を繰り返すリスクもあります。
原因となったストレス源を明確にすることがとにかく大切です。適応障害ははっきりした原因があるため、原因を特定して対処することで再発するリスクを減らすことができます。
また、なぜ発症するまでに至ったのかの原因も明確にしましょう。専門家によるカウンセリングが有効です。原因を特定する過程で、自分と向き合う必要が出てくる場合もあります。
退職・転職をすでに繰り返している場合、今後の連続を防ぐためには、まずは復職できるよう休養をしっかり取ることが大切です。その際はやはり自分に変えられる点がないか考えることが重要になります。そのうえで自分に合う職場を見つけることで退職・転職の連続を断ち切りましょう。
転職後すぐ適応障害になってしまったら?
転職後すぐに適応障害になってしまったら、まず上司や人事に相談しましょう。休職・異動など、どのような対処が可能か検討してもらいます。
その際、原因を特定しておくことが対処に役立ちます。そのためにも医師の診察を受けて原因を突き止めましょう。
企業側に問題があり改善が見込めない場合は、退職・転職を視野に入れるのもやむを得ないでしょう。
障害者/障がい者雇用では給与は低くなる?
障害者/障がい者雇用は一般的な雇用より給与が低くなるのが現実です。
障害者/障がい者雇用には以下のような配慮・特徴があることが理由です。
- 勤務日数や1日の勤務時間が短縮されている
- 仕事内容が単純作業だったりする
- 雇用形態が非正規雇用のことがある
なお「障害者雇用促進法」によって、障害者/障がい者の給与の差別は禁止されています。そのため仕事内容や勤務日数などの条件が同じであれば、障がい(障害)を理由に給与を低くされることはありません。
適応障害で転職の繰り返しを防ぐには?
適応障害の方が転職の繰り返しを防ぐには、原因となったストレスを明確にすることが何よりも大切です。
ストレスのもととなった要素・状況と同じ/似た要素がない職場を選びましょう。同じ状況を避けることでストレスを感じるリスクが下がります。その結果その職場で仕事を続けやすくなるでしょう。
さらに自分の側も、なぜそれをストレスに感じたのか考えてみることが大切です。パワハラなど自分に一切非がないケースもありますが、受け取り方が違えば避けられたケースも存在します。もちろんそのケースも自分に非があるとは言えません。しかし感じ方を変えることができれば、さらに再発のリスクを下げることが可能です。
適応障害は労災になる?
適応障害も、基準を満たせば労災になります。基準としては、以下の点が挙げられます。
- 発病前のおおむね6か月の間に業務による強い心理負担があった
- 業務以外の原因で発病したのではない
上記2つの条件を満たしていれば、労災となります。企業によっては労災にすることを避けようとするかもしれません。しかし労災認定されれば休業補償が受けられるなどのメリットもあります。復職したい場合はいづらくなる可能性もあるかもしれませんが、自分にとってよりよい選択をするようにしましょう。
転職エージェントを活用して転職を成功させよう

適応障害で転職をしようという場合、サポートしてくれる転職エージェントは転職成功に近づくことができる頼もしい存在です。ただし本文でも述べた通り、まずは自分の体調が最優先です。不安定な状態の間は転職活動はしないようにして、回復してから転職活動を始めましょう。
その際は、エージェントに頼れるところは頼りつつ、納得のいく転職のために自分でも積極的に活動していきましょう。この記事をぜひ参考にしてください。応援しています。

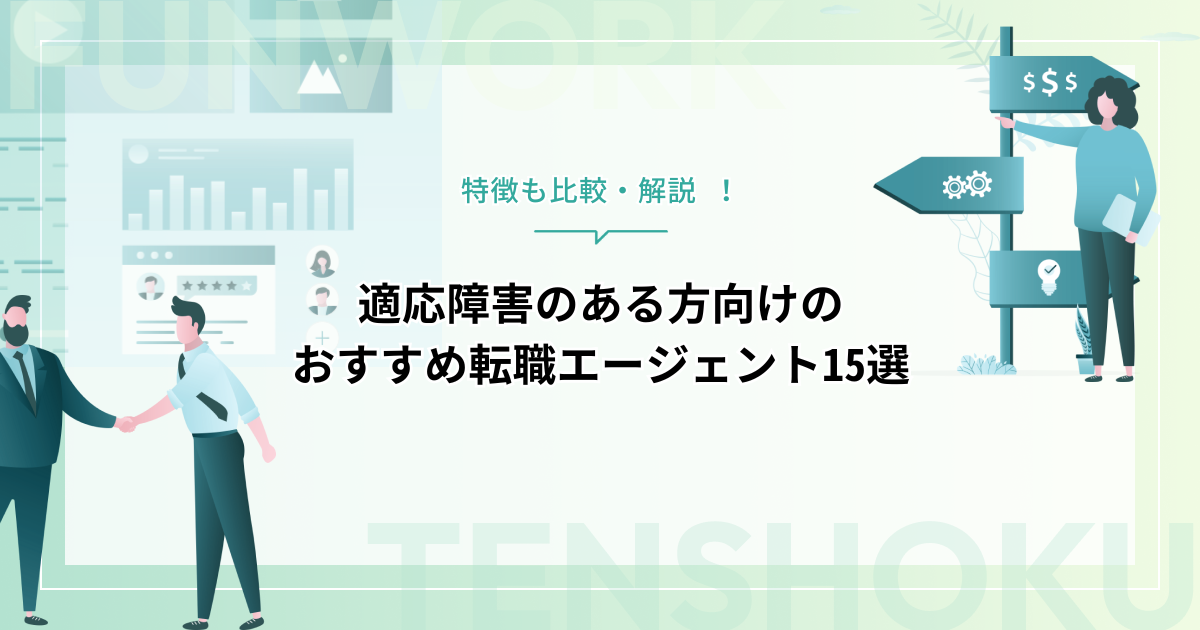

エージェント.png)