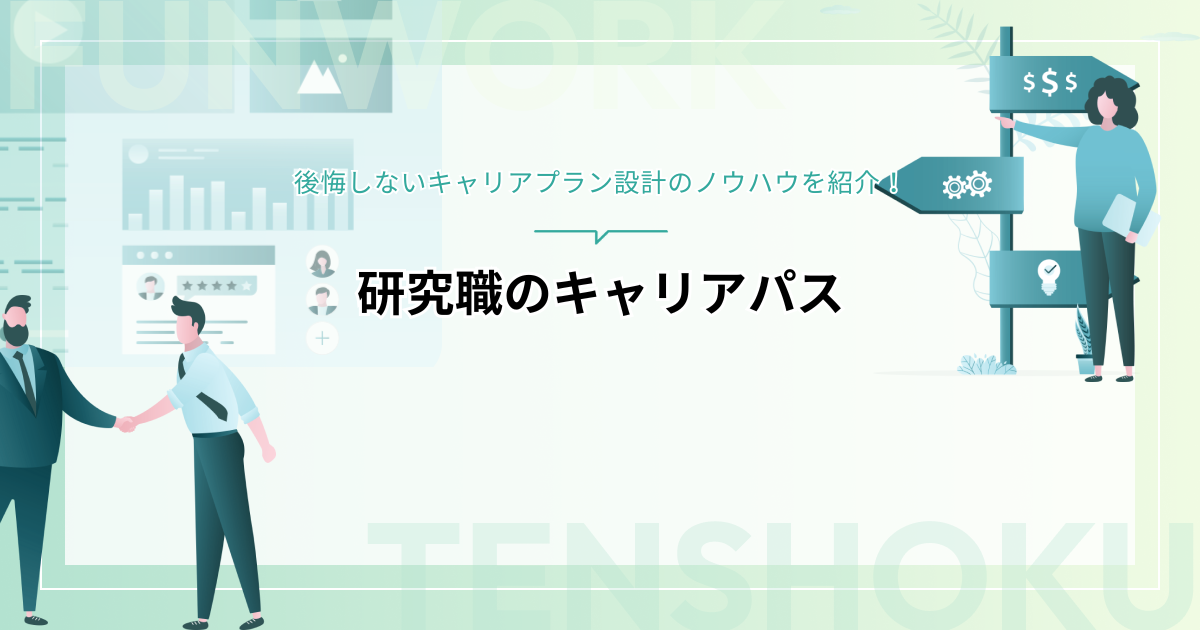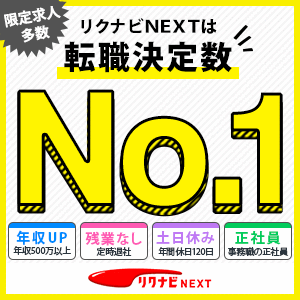- この記事でわかること
- 研究職には大学や企業、医療など多様な分野がある
- 研究職のキャリアパス成功には基礎スキルや発信スキルが必要
- 研究職キャリアプランで後悔しないための設計ノウハウ3つを解説
- 研究職からのキャリアチェンジは管理職や知的財産部門への異動などがある
- 研究者としての将来性と転職市場動向を解説
- 研究職のキャリアパスを目指して転職!転職サービス上位6選 【1,382人に聞いた転職サービス利用状況】
研究職のキャリアパスは、アカデミアから企業まで幅広い選択肢が用意されています。研究者として成長するためには、専門性の向上だけでなく、戦略的なキャリアプラン設計が重要です。
この記事では、研究職のキャリアパスの種類や必要なスキル、キャリアアップの方法について詳しく解説します。
研究職への転職を考えている方も、すでに研究職として働いている方も、後悔しないキャリアプランのためのヒントがきっと見つかるはずです!
【まずはチェック!!】求人数の多い大手転職サービスが人気!おすすめの求人数比較表!
大手転職サービスの取り扱い求人件数を独自調査。転職サービスの専任担当者が最新の取り扱い求人情報を確認し、求人数比較表にまとめています。転職活動にあたってはエージェントやサイトを積極的に活用しましょう。まずは一通りサービスを体験してみて自分にあったサービスを見つけることをおすすめします。比較表はこちら。
右にスクロールできます
| おすすめ | リクルートエージェント | doda | マイナビAGENT | リクナビNEXT | パソナキャリア | ビズリーチ | リクルートダイレクトスカウト | マイナビ転職 | エン転職 | JACリクルートメント | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特色 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | 全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス・女性向け | ハイクラス全年代・業界 | ハイクラス・全年代 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス | 全業界・首都圏 |
| 求人数 | 605,771件 | 250,676件 | 非公開 | 1,184,000件以上 | 48,766件 | 166,803件 | 516,157件 | 非公開 | 105,190件 | 22,064件 | 2,587件 |
| 求人の豊富さ | |||||||||||
| ポイント | 非公開求人も多数 | エージェント・サイト両方の利用が可能 | 地方の求人も充実 | 企業からのオファーあり | オファーも受けられる | 2種類のスカウトあり | 登録するとスカウトが多数届く | スカウトサービスあり | 利用者の満足度が高い | コンサルタントのサポートが手厚い | とくにエンジニア、20代、女性の求人に強み |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
2025年8月9日調査:各転職エージェントの取り扱い求人件数・各転職サイトの掲載求人数
Contents
研究職のキャリアパスを理解しよう

研究職のキャリアパスは、専門性と経験を積み重ねることで様々な可能性が広がります。研究職には大学や研究機関、企業など、活躍できる場所が多くあり、それぞれの特徴や求められる役割、待遇も異なります。
まずは研究職の全体像を把握することから始めましょう。
- 研究職の種類と特徴
- 研究職の役割と責任
- 研究職の年収相場
それでは順に見ていきましょう。
研究職の種類と特徴
研究職は大きく分けて、アカデミックな研究職と企業の研究職に分類されます。
| 研究職の種類 | 特徴 |
|---|---|
| アカデミックな研究職 |
|
| 企業の研究職 |
|
アカデミックな研究職には、大学教員や国立研究機関の研究員などがあり、より基礎的な研究に重点を置く傾向があります。一方、企業の研究職は製品開発や技術革新に直結する応用研究が中心となります。
また研究分野によっても特徴が異なり、理学系、工学系、医学系、農学系などの自然科学分野から、人文科学、社会科学まで幅広い領域があります。それぞれの分野で求められる専門知識や研究手法は異なりますが、科学的な思考方法や研究プロセスには共通点も多くあります。
特に近年は学際的な研究も増えており、複数の分野を横断する研究者も増加しています。このような多様な選択肢の中から、自身の興味や適性に合った研究分野を選択することが、充実したキャリアパスを築く第一歩となります。
研究職の役割と責任
研究職の主な役割は、新しい知見や技術を生み出し、学術や産業の発展に貢献することです。
具体的には、研究テーマの設定から実験計画の立案、データ収集と分析、結果の考察と論文執筆まで、研究プロセス全体をマネジメントする責任があります。
また研究費の獲得や研究チームの指導、外部機関との共同研究の推進なども重要な責務です。特にシニアクラスの研究者は、若手研究者の育成や研究室の運営など、マネジメント面での役割も担います。研究成果は論文や学会発表を通じて公表され、その質と量は研究者としての評価に直結します。
さらに近年は、研究成果の社会実装や産学連携、知的財産の管理なども
求められるようになっており、研究者の役割は多様化しています。
このように研究職には大きな責任が伴いますが、その分やりがいも大きい職種といえます。
研究職の年収相場
研究職の年収は、所属機関や経験年数、実績によって大きく異なります。
国立大学の助教クラスでは年収400万円~500万円程度からスタートし、准教授で600万円~700万円、教授では800万円~1,000万円以上となることが一般的です。
企業の研究職では、大手企業の場合、修士卒で年収350万円~400万円程度からスタートし、経験を積むことで500万円~700万円程度まで上昇します。博士号取得者は初任給から30万円~50万円程度上乗せされることが多く、管理職クラスになると1,000万円以上の年収も珍しくありません。
また研究実績や特許取得による報奨金、外部資金の獲得など、基本給以外の収入機会もあります。ただしこれらの金額はあくまでも目安です。研究機関の規模や業績、地域による差も大きいため、キャリアプランを立てる際は様々な要素を考慮する必要があります。
研究職のキャリアパス【分野別】

研究職のキャリアパスは、所属する機関や分野によって特徴が異なります。それぞれの分野での具体的なキャリアの歩み方を理解することで、自分に合った道筋を見つけることができます。
ここでは主要な研究分野別の研究職のキャリアパスについて解説します。
- 大学・研究機関での研究職キャリアパス
- 企業の研究開発職のキャリアパス
- 医療分野の研究職キャリアパス
それでは順に見ていきましょう。
大学・研究機関での研究職キャリアパス
大学や研究機関での研究職キャリアパスは、一般的に助教や研究員からスタートし、准教授、教授へと段階的にステップアップしていきます。博士号取得後、ポスドクとして研究経験を積むケースも多く、この期間に研究実績を重ねることが重要です。
昇進には論文数や被引用数、外部資金の獲得実績などが重視されます。また教育面での実績も重要で、学生の指導力や講義の質も評価対象となります。任期付きのポジションが多いため、常勤職を獲得するための競争は激しいものの、安定したポジションを得られれば、自身の興味に基づいた研究を長期的に進めることができます。
さらに海外の研究機関との交流も活発で、
国際的なキャリアを築くチャンスも豊富です。
研究者としての専門性を極めながら、アカデミアでの確固たる地位を築いていくことができます。
企業の研究開発職のキャリアパス
企業の研究開発職では、入社後まず研究員として実務経験を積み、その後主任研究員やグループリーダーへと昇進していきます。研究成果は直接的に製品開発や技術革新につながるため、より実用的な視点での研究が求められます。
キャリアパスとしては、研究専門職として技術を極める道と、研究マネジメント職として組織を統括する道の2つが一般的です。専門職では主席研究員やフェローなどの上級職を目指し、マネジメント職では研究部長や技術担当役員などを目指します。
また企業では、研究成果の事業化や特許取得なども重要な評価対象となります。市場ニーズや開発コスト、スケジュールなども考慮しながら研究を進める必要があり、ビジネス感覚も求められます。
医療分野の研究職キャリアパス
医療分野の研究職は、基礎研究から臨床研究まで幅広い領域があり、医師として臨床経験を積みながら研究を進めるケースも多くあります。大学病院や研究所、製薬企業など、活躍の場も多様です。
このキャリアパスには、基礎研究者として新しい治療法や医薬品の開発を目指す道、臨床研究者として実際の治療現場でのエビデンス構築を行う道などがあります。また医工連携やバイオインフォマティクスなど、他分野との融合研究も増えており、より専門的な知識とスキルが求められます。
特に医療分野では、研究成果が直接人々の健康や生命に関わるため、高い倫理観と責任感が必要です。
また薬事規制や臨床試験の手順など、
専門的な知識も必要となり、継続的な学習が欠かせません。
研究者のキャリアアップ戦略

研究者がキャリアアップし目標とするキャリアパスを実現するためには、計画的なスキルアップと実績の積み重ねが不可欠です。
ここでは、研究者としての成長に必要な要素と、具体的な戦略について解説します。効果的なキャリアアップを実現するためのポイントを押さえていきましょう。
- 昇進ステップと必要条件
- 論文実績の重要性
- 研究予算の獲得方法
それでは順に見ていきましょう。
昇進ステップと必要条件
研究職の昇進には、研究実績や経験年数に加え、マネジメント能力や組織への貢献度など様々な要素が評価されます。
アカデミアでは、助教から准教授、教授へと昇進する際、査読付き論文の本数や被引用数、外部資金の獲得実績などが重視されます。
企業の研究職では、研究成果の事業化への貢献や特許取得数、プロジェクトマネジメントの実績なども重要な評価基準となります。また、後進の指導育成能力や、他部門との連携力なども昇進の要件となることが多いです。
各ステップでの昇進には、それぞれ必要な資格や条件があり、計画的な準備が重要です。特に博士号の取得は、上級職への昇進において重要な要件となることが多く、早い段階での取得を検討する必要があります。
論文実績の重要性
研究者としての評価において、論文実績は最も重要な指標の一つです。
特にインパクトファクターの高い国際ジャーナルでの論文掲載は、研究者としての信頼性と専門性を証明する重要な実績となります。
論文は単なる数だけでなく、その質も重要で、被引用数や掲載ジャーナルの評価も考慮されます。また筆頭著者としての論文や、国際共著論文なども、より高い評価につながります。定期的な論文投稿を心がけ、着実に実績を積み重ねていくことが大切です。
さらに学会発表や研究会での報告など、
研究成果の発信機会も積極的に活用すべきです。
これらの活動は、研究コミュニティでの認知度を高め、共同研究などの新たな機会につながることもあります。
研究予算の獲得方法
研究を継続的に進めるためには、十分な研究予算の確保が不可欠です。科研費をはじめとする競争的資金の獲得は、研究者としての評価にも直結する重要な実績となります。
研究費の獲得には、魅力的な研究提案書の作成が重要です。研究の独自性や社会的意義、期待される成果を明確に示し、実現可能性の高い研究計画を立案する必要があります。また過去の研究実績や、研究チームの体制なども重要な審査対象となります。
民間企業との共同研究や受託研究なども、研究費獲得の重要な手段です。産学連携を通じて、より実用的な研究にも取り組むことができ、研究の幅を広げることにもつながります。研究費の申請は計画的に行い、複数の資金源を確保することが望ましいです。
研究者に求められるスキルと資格

研究職のキャリアパスを歩むには、専門的な研究スキルだけでなく、幅広い能力が必要とされます。
ここでは、研究者として成功するために必要なスキルと、キャリアの幅を広げるために有効な資格について詳しく解説します。
- 研究職に必要な基礎スキル
- 研究成果を発信するためのスキル
- キャリアアップに役立つ資格
それでは順に見ていきましょう。
研究職に必要な基礎スキル
研究職の基礎となるスキルは、専門分野における深い知識と研究手法の習得です。
文献調査から実験計画の立案、データ分析まで、研究プロセス全体を適切に遂行できる能力が求められます。特に統計解析やプログラミングなどのデータ処理スキルは、現代の研究において必須となっています。
また問題発見能力と解決能力も重要です。研究テーマの設定から仮説の構築、検証方法の確立まで、論理的な思考プロセスを展開できることが必要です。さらに予期せぬ実験結果や技術的な課題に直面した際の対応力も、研究を成功に導く重要な要素となります。
チームでの研究活動も増えており、プロジェクトマネジメントやチームワークのスキルも欠かせません。研究計画の進捗管理や、共同研究者との効果的な協力関係の構築など、組織的な研究活動を推進できる能力が求められています。
- 研究者に必要な基礎スキルはコレ!
-
- 文献調査能力
- 実験計画能力
- 自己管理能力
- データ分析能力
- 問題発見・解決能力
- チームワーク能力
研究成果を発信するためのスキル
研究者のキャリアを成功させるためには、研究成果を効果的に発信するスキルも欠かせません。
論文執筆能力は最も基本的なスキルで、研究内容を論理的かつ説得力のある形で文章化する能力が必要です。英語での論文執筆も必須となっており、アカデミックライティングの技術を磨くことが重要です。
プレゼンテーション能力も不可欠です。学会発表や研究会での報告、外部との折衝など、様々な場面で研究内容を分かりやすく説明する機会があります。視覚的な資料の作成能力や、質疑応答での対応力も含めて、総合的なプレゼンテーションスキルが求められます。
また、近年ではSNSやウェブサイトを通じた研究成果の発信も増えており、一般向けのコミュニケーション能力も重要性を増しています。専門家以外にも研究の意義や成果を分かりやすく伝える能力が求められています。
- 研究者に必要な情報発信スキルはコレ!
-
- 論文執筆能力
- 英語力
- プレゼンテーションスキル
- コミュニケーション能力
キャリアアップに役立つ資格
研究職のキャリアアップにおいて、各種資格の取得は大きな強みとなります。
まず研究に直結する専門資格として、分野ごとの技術士や専門医、臨床検査技師などの資格があります。これらは専門性の証明となり、より高度な研究活動への参画機会を広げます。
語学資格も重要で、特にTOEICやIELTSなどの英語資格は、国際的な研究活動において必須となっています。また、知的財産管理技能検定や中小企業診断士など、研究成果の活用や事業化に関連する資格も、キャリアの選択肢を広げる上で有効です。
データサイエンスや統計解析の資格も注目されており、統計検定やデータサイエンティスト検定などの取得も推奨されます。これらの資格は、研究活動の質を高めるだけでなく、将来的なキャリアチェンジの際にも活かすことができます。
- 研究者におすすめの資格はコレ!
-
- 専門分野に特化した資格(臨床検査技師、臨床工学技士、薬剤師など)
- 英語資格(TOEIC、IELTSなど)
- 特許に関する資格(知的財産管理技能検定など)
- 統計に関する資格(統計検定、データサイエンティスト検定など)
後悔しない!研究職キャリアプラン設計のノウハウ3つ

研究職のキャリアパスを成功に導くには、慎重な計画と的確な判断が必要です。
ここでは、後悔しないキャリアプランを設計するための3つの重要なノウハウを紹介します。
- 研究職キャリアプラン設計のノウハウ3つ
-
- 自分に合ったキャリアパスの見つけ方
- 研究分野の選び方と専門性の築き方
- キャリアの分岐点での意思決定方法
それでは順に見ていきましょう。
自分に合ったキャリアパスの見つけ方
研究職のキャリアパスを選択する際は、自身の興味や適性を深く理解することが重要です。
まずはこれまでの研究経験や学習過程で特に興味を持った分野や、得意とする研究手法を振り返ってみましょう。また、基礎研究と応用研究のどちらに魅力を感じるか、チーム研究と個人研究のどちらが合っているかなども、重要な判断材料となります。
メンターや先輩研究者との対話も、キャリアパスを見つける上で有効です。その分野で実際に活躍している研究者の経験談を聞くことで、より具体的なキャリアイメージを描くことができます。またインターンシップや共同研究プロジェクトへの参加を通じて、様々な研究環境を体験することも推奨されます。
さらに長期的なキャリアビジョンを持つことも重要です。
10年後、20年後にどのような研究者になりたいのか、具体的な目標を設定することで、
そこに向けた効果的なキャリアパスを見つけることができます。
研究分野の選び方と専門性の築き方
研究分野を選択する際は、その分野の将来性と自身の興味のバランスを考慮することが重要です。
注目を集めている研究分野であっても、自身の情熱が持続しなければ長期的な成功は難しいでしょう。一方で、興味だけでなく、その分野での研究資金の獲得しやすさや就職機会の豊富さなども考慮に入れる必要があります。
専門性を築く過程では、段階的なアプローチが効果的です。基礎的な研究手法やツールの習得から始め、徐々により高度な技術や知識を積み重ねていきます。また関連分野の知識も広く学ぶことで、独自の研究アプローチを確立することができます。
継続的な学習と実践も重要です。学会への参加や論文の執筆、共同研究プロジェクトへの参画など、様々な機会を通じて専門性を深化させていきましょう。研究コミュニティでの活動を通じて、同分野の研究者とのネットワークを構築することも大切です。
キャリアの分岐点での意思決定方法
研究職のキャリアパスには、以下のように様々な分岐点が存在し、重要な決断を迫られる機会が多くあります。
- アカデミアと企業のどちらを選ぶか
- 専門研究職とマネジメント職のどちらを目指すか
- 海外で研究するかどうか など
これらの決断を行う際は、客観的な情報収集と冷静な分析が必要です。それぞれの選択肢のメリット・デメリットを整理し、自身のキャリアゴールとの整合性を確認します。
また女性研究者に多いのがワークライフバランスついての懸念です。キャリアプランを考える際には、将来的な家族の状況や生活環境の変化なども考慮に入れ、総合的な判断を行うことが重要です。
意思決定の際は、一時的な状況だけでなく、長期的な視点を持つことが何よりも大切です。必要に応じて、経験豊富な研究者やキャリアアドバイザーに相談することも推奨されます。
また決断後も柔軟な姿勢を保ち、
必要に応じて軌道修正を行っていきましょう!
研究職から広がる未来!キャリアチェンジの選択肢

研究職での経験は、様々な分野でのキャリアチェンジにつながる可能性を秘めています。研究で培った専門知識や分析力、問題解決能力は、転職しても多くの職種で高く評価されます。
ここでは、研究者が選択できる代表的なキャリアチェンジの可能性について解説します。
- 管理職への転向
- 知的財産部門への異動
- コンサルタントへの転身
それでは順に見ていきましょう。
管理職への転向
まず1つ目に、研究職からのキャリアチェンジの選択肢として管理職への転向があります。
研究部門の管理職は、研究者としての経験を活かしながら、組織全体の研究戦略の立案や運営に携わる役割です。研究部門の統括、研究予算の管理、研究チームの育成など、より広い視点での研究活動のマネジメントを担当します。
このキャリアパスを選ぶ場合は、研究の専門知識に加えて、組織運営やリーダーシップのスキルの習得をキャリアプランに組み込む必要があります。
研究部門の管理職は、複数の研究プロジェクトを同時に進行させる必要があり、プロジェクトマネジメントの能力も求められます。また経営層との折衝や他部門との連携も重要な業務となるため、コミュニケーション能力とビジネス感覚の向上も必要です。
このキャリアパスは、研究の現場を理解しながら、より戦略的な立場で研究活動に関わることができる点が魅力です。特に大規模な研究機関や企業では、管理職としてのキャリアアップの機会が豊富にあります。
知的財産部門への異動
2つ目のキャリアチェンジとして、知的財産部門への異動もキャリアの幅を広げるのに役立ちます。
知的財産部門では、研究成果の権利化や特許管理、技術移転など、研究成果の保護と活用に関する業務を担当します。研究者としての専門知識を活かしながら、法務的な視点も加えて研究成果の価値を最大化する役割を果たします。特許戦略の立案や、知的財産のポートフォリオ管理なども重要な業務となります。
このキャリアパスでは、特許法や知的財産権に関する知識の習得が必要です。弁理士資格の取得も、キャリアアップの重要なステップとなります。
また研究者と法務部門の橋渡し役として、両者の言語を理解し、
適切なコミュニケーションを図る能力も求められます。
知的財産部門は、研究開発の成果を社会実装につなげる重要な役割を担っており、研究者としての経験を活かしながら、新たな専門性を身につけることができる魅力的なキャリアパスです。
コンサルタントへの転身
3つ目に紹介するのは、研究者からコンサルタントへの転職です。専門分野での深い知識と分析力を活かし、企業や研究機関に対して技術的なアドバイスや戦略的な提言を行います。
研究職の経験を活かして、技術コンサルタントやリサーチコンサルタントとして独立するキャリアパスは大きな決断が必要ですが、魅力もたくさんあります。
このキャリアパスは、より自由度の高い働き方を実現できる点が大きなメリットです。また研究者としての専門性を活かしながら、より幅広い分野で活躍できる可能性が広がります。
一方で継続的な案件獲得や顧客管理など、ビジネス面でのスキルも求められます。コンサルタントとして成功するには、技術的な専門性に加えて、クライアントのニーズを理解し、適切なソリューションを提案できる能力が必要です。またプレゼンテーション能力やビジネス感覚も重要となります。
特定の業界や技術分野に特化したスペシャリストとして、独自の市場価値を確立することが重要です。
さらに10年後へ!研究職のセカンドキャリア選択

研究者としての経験とスキルは、長期的なキャリア展開において大きな強みとなります。
ここでは、研究職で培った専門性を活かした、10年後、20年後を見据えたセカンドキャリアの選択肢について解説します。これらの選択肢は、より自由度の高い働き方や新たな挑戦の機会になります。
- 大学教員としての道
- ベンチャー企業の立ち上げ
- 研究アドバイザーとしての独立
それでは順に見ていきましょう。
大学教員としての道
研究職のセカンドキャリアとして、大学教員への転身は魅力的な選択肢の一つです。
企業や研究機関での実務経験は、実践的な知識として教育現場で高く評価されます。特に専門的な研究経験は、大学院での研究指導や産学連携プロジェクトの推進において重要な資産となります。
大学教員としては、研究活動に加えて教育者としての役割も担います。講義やゼミの運営、学生の指導など、次世代の研究者や専門家の育成に携わることができます。また、より自由度の高い研究テーマの設定や長期的な研究計画の立案が可能となります。
ただし、教育経験や教育に対する熱意も重要な要素となります。また競争の激しい分野では、
十分な研究実績と教育能力の証明が求められます。
計画的な準備と実績作りが、このキャリアパスの成功につながります。
ベンチャー企業の立ち上げ
研究成果を実用化し、自身の技術やアイデアを活かしてベンチャー企業を立ち上げることも、魅力的なセカンドキャリアの選択肢です。
特に最先端の研究分野では、革新的な技術やサービスを市場に提供する機会が豊富にあります。
起業のためには、技術的な専門性に加えてビジネスプランの策定や資金調達、チーム構築など、経営者としてのスキルも必要となります。また市場調査やマーケティング、財務管理など、ビジネス面での知識も重要です。
ただし起業には相応のリスクも伴います。十分な事業計画の策定と慎重な準備期間が必要です。また研究開発型ベンチャーでは、特許戦略や技術移転なども重要な検討事項となります。
研究アドバイザーとしての独立
豊富な研究経験を活かして、研究アドバイザーとして独立するキャリアパスも考えられます。
企業や研究機関に対して、研究戦略の立案や技術評価、研究プロジェクトの指導など、専門的な知見に基づくアドバイスを提供します。
このキャリアパスでは、幅広い技術動向の把握と、実践的な研究マネジメントの経験が重要となります。
また、クライアントとの信頼関係構築や
ネットワーク作りも成功の鍵となります。
より柔軟な働き方が実現できる一方で、継続的な案件獲得や専門性の維持・向上が求められます。また独立したコンサルタントとしての活動には、ビジネススキルや自己管理能力も必要です。
研究者としての将来性と転職市場動向

研究職の将来性は、技術革新やグローバル化の進展により、ますます高まっています。
この章では研究職の需要予測と今後の研究環境の変化、そして転職市場での研究職の立ち位置について解説します。長期的なキャリアプランを立てる上で参考にしてくださいね。
- 研究職の需要予測
- 今後の研究環境の変化
- 転職市場での研究職の将来的な立ち位置
それでは順に見ていきましょう。
研究職の需要予測
研究職の需要は、特にAIや再生医療、環境技術など、最先端の技術分野で高まっています。
企業の研究開発投資は増加傾向にあり、特に高度な専門性を持つ研究者への需要は今後も続くと予測されています。
また産学連携の活発化や国際共同研究の増加により、グローバルに活躍できる研究者への需要も拡大しています。特に複数の専門分野を横断するような学際的な研究者は、より多くの機会を得られる可能性があります。
ただし、分野によって需要の偏りも存在します。市場動向や技術トレンドを常に把握し、必要に応じて専門性の方向性を柔軟に調整することも重要です。
今後の研究環境の変化
研究環境は、デジタル化やグローバル化の進展により、大きく変化しています。AIや機械学習の活用、オープンサイエンスの普及など、研究手法や情報共有の方法も進化しています。またリモートワークの普及により、研究活動の場所や時間の制約も少なくなっています。
一方で、研究資金の獲得競争は激化しており、より実用的で社会的インパクトの高い研究が求められる傾向にあります。また研究倫理や情報セキュリティへの要求も高まっており、これらへの適切な対応も必要となっています。
このような環境変化に適応し、新しい研究スタイルを確立できる研究者が、
今後より多くの機会を得られると予想されます。
転職市場での研究職の将来的な立ち位置
研究職の転職市場における価値は、技術革新とグローバル化の進展により今後さらに高まると予測されています。
特にAIや再生医療、環境技術など、新興分野での研究経験を持つ人材は、ますます重要な存在となるでしょう。企業が研究開発投資を増加させる中、高度な専門性を持つ研究者への需要は継続的に拡大すると考えられています。
また研究者に求められるスキルセットも進化しています。従来の専門分野における深い知識や研究実績に加えて、デジタルリテラシーやデータサイエンスのスキル、そして複数の専門分野を横断できる学際的な視点も重視されるようになってきました。このような複合的なスキルを持つ研究者は、将来的により多くの転職機会を得られる可能性があります。
さらに産学連携の活発化により、アカデミアと企業の垣根が低くなっていることも、研究職の転職市場に大きな影響を与えています。研究者が自身のキャリアステージに応じて、柔軟に活躍の場を選択できる環境が整いつつあります。
このトレンドは今後も続くと予想され、
研究職の転職市場はより流動的で機会に満ちたものになっていくでしょう。
研究職のキャリアパスに関するよくある質問

最後に研究職のキャリアに関する代表的な質問と回答をご紹介します。
- 研究職のキャリアパスは大学教授以外にもありますか?
- 研究職でキャリアアップするためには何をすればいいですか?
- 研究職のキャリアパスを始めるには海外経験が必要ですか?
- 企業の研究職と大学での研究職のキャリアパスの違いは何ですか?
ひとつずつ見ていきましょう。
研究職のキャリアパスは大学教授以外にもありますか?
研究職のキャリアパスは、大学教授以外にも多様な選択肢があります。
企業の研究開発部門、国立研究機関、公的研究所など、様々な場所で研究者として活躍することができます。また研究部門の管理職や知的財産部門、技術コンサルタントなど、研究経験を活かした関連職種への転向も可能です。
特に近年は、ベンチャー企業での研究開発やフリーランスの研究者として独立するケースも増えています。また産学連携コーディネーターや科学技術政策の立案者など、研究と社会をつなぐ役割も注目されています。
重要なのは、自身の興味や適性に合った進路を選択することです。様々な可能性を探りながら、最適なキャリアパスを見つけることができます。
研究職でキャリアアップするためには何をすればいいですか?
研究職でのキャリアアップには、主に以下の取り組みが効果的です。
まず質の高い研究成果を継続的に出すことが基本となります。論文発表や学会発表、特許取得など、具体的な実績を積み重ねることが重要です。
また外部資金の獲得や共同研究プロジェクトの推進など、研究活動の幅を広げることも必要です。語学力やデータ分析スキルなど、現代の研究に必要な能力の向上も欠かせません。
さらに後進の指導やチームマネジメントの経験を積むことも、キャリアアップの重要な要素となります。
継続的な学習と自己啓発、そしてネットワークの構築が、
着実なキャリアアップにつながります。
研究職のキャリアパスを始めるには海外経験が必要ですか?
海外経験は必須ではありませんが、グローバル化が進む研究分野ではアドバンテージとなります。
海外での研究経験は、国際的な研究ネットワークの構築や異なる研究文化への理解を深める貴重な機会となります。
ただし海外経験の必要性は分野や目指すキャリアパスによって異なります。国内を中心に活動する場合は、必ずしも長期の海外経験は必要ありません。短期の国際会議への参加やオンラインでの国際共同研究なども、グローバルな経験を積む方法として有効です。
重要なのは、自身のキャリアゴールに合わせて適切なタイミングと方法で海外経験を積むことです。
企業の研究職と大学での研究職のキャリアパスの違いは何ですか?
企業と大学では、研究の目的や評価基準に大きな違いがあります。
企業の研究職では、事業化や製品開発につながる実用的な研究が重視され、より短期的な成果が求められます。一方、大学では基礎研究や長期的な視点での研究が可能で、論文発表などの学術的成果が重視されます。
キャリアパスの面では、企業では研究専門職とマネジメント職の2つの道があり、
比較的早い段階でどちらかを選択する必要があります。
大学では教育と研究を両立させながら、助教から准教授、教授へと段階的にキャリアアップしていきます。
また給与体系や雇用の安定性、研究の自由度なども異なります。自身の価値観や目標に合わせて、適切な進路を選択することが重要です。
みんなが使っている転職サービス上位6選 【1,382人に聞いた転職サービス利用状況】
実際に登録したことのある転職サービスについてアンケートをとりました。アンケート結果として、みんなが使っている転職サービスの上位6サービスは以下です。
- 1位|リクルートエージェント(821人)
- 2位|doda(564人)
- 3位|リクナビNEXT(389人)
- 4位|マイナビAGENT(312人)
- 5位|ビズリーチ(288人)
- 6位|エン転職(282人)
※転職サービスの利用アンケート(クラウドワークス) 回答数:1,382 / 集計期間:2024年09月19日~10月03日
1位|リクルートエージェント(利用回答数:821人) 圧倒的な求人数
「リクルートエージェント」は、求人数、安定したサービス品質で、まずは登録が必須のエージェントです。
まず何と言っても求人数が多いことがおすすめの理由として挙げられます。転職成功の実績も多く、優れているのは求人の数だけではありません。業界に精通したアドバイザーが在籍しているので、ぴったりの求人を見つけ出してくれます。求人やサービスの質・量ともにトップクラスで転職エージェントとしては定番・王道のサービスです。
営業・技術系を中心にあらゆる業種・職種をカバー。総合型ながら条件ごとに特化したページもあり、使いやすいのも人気の理由です。
- リクルートエージェントのおすすめポイント
- 求人数が圧倒的に多い
- 業界に精通したアドバイザーが在籍
- 条件ごとに特化したページがあり使いやすい
基本データ
| リクルートエージェント | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人474,685件/非公開求人399,542件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | エージェントサービス、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供 |
| 拠点 | 東京・北海道・宮城・宇都宮・さいたま・千葉・横浜・金沢・新潟・長野・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡 |
| URL | https://www.r-agent.com/ |
2位|doda(利用回答数:564人) エージェント/サイトの一体型で自分でも応募が可能
「doda」は、人材紹介・転職支援を行う大手「パーソルキャリア」が運営する総合型転職サイトです。エージェントサービスも利用できる点が人気の理由の1つになっています。
dodaも求人数が多く、非公開求人も条件が良いものが多いのが大きなポイントです。
また転職サイトと転職エージェントの一体型で、使い方の自由度が高いのもおすすめポイント。エージェントサービスでは専任のキャリアアドバイザーがサポートしてくれます。なお企業との対応は採用プロジェクト担当が行い、求職者と企業とでそれぞれ別のプロフェッショナルが対応します。
- dodaのおすすめポイント
- 非公開求人も好条件多数
- 転職サイトと転職エージェントの一体型で自由度が高い
- 専任のキャリアアドバイザーがサポート、企業は別のプロフェッショナルが対応
基本データ
| doda | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人262,342件/非公開求人31.049件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、年収査定、合格診断、レジュメビルダー、「自己PR」発掘診断、転職タイプ診断、はたらく女性のためのモヤモヤ解消診断、オンライン仕事力診断 |
| 拠点 | 東京・横浜・札幌・仙台・静岡・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・広島・福岡・鹿児島 |
| URL | https://doda.jp/consultant/ |
3位|リクナビNEXT(利用回答数:389人) 求人サイト群の中でも最大級の求人数と使いやすさ
「リクナビNEXT」は大定番の転職サイトで、サイトの見やすさや使いやすさにも定評があります。
エージェントなしの狭義の転職サイトの中では、求人数はトップクラス。新規の求人も多く、定期的にチェックすることで希望に合う求人に出会える可能性が高まります。
ツールが便利でサイトが使いやすいのも特長です。たとえば「気になるリスト」を使うと、気になる企業や後でゆっくりチェックしたい企業をリスト化できるほか、気になるに追加した企業から面接のオファーが来る可能性があります。
そのほか、公開求人・非公開求人の企業からオファーがもらえる「オファーを待つ」、自己分析ツール「グッドポイント診断」などがあります。
- リクナビNEXTのおすすめポイント
- サイトが見やすく使いやすい
- 狭義の転職サイトでは最大級の求人数
- 多くの人が利用している定番の転職サイト
基本データ
| リクナビNEXT | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人824,000件以上(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | オファー、気になるリスト、グッドポイント診断 |
| URL | https://next.rikunabi.com/ |
4位|マイナビAGENT(利用回答数:312人) 20代・30代の求人に強い
「マイナビAGENT」は、さまざまな転職サイトを運営している株式会社マイナビによる転職エージェントです。きめ細かいサポートが受けられると評価されています。
とくに20代・30代の求人が多いので、その世代の人にはおすすめです。また全国に拠点があり地方の求人も充実しているので、大都市圏以外で探している人にもぴったりです。
履歴書や職務経歴書のサポートも充実、初めての転職でも安心して利用できます。IT、営業など業種・職種別のサービスもあります。自分が探している業種と一致するならより探しやすくなるでしょう。
- マイナビAGENTのおすすめポイント
- 20代・30代の求人が多い
- 地方の求人も充実
- 履歴書や職務経歴書のサポートもあり安心
基本データ
| マイナビAGENT | |
|---|---|
| 公開求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| 拠点 | 拠点情報はこちらをご確認ください |
| URL | https://mynavi-agent.jp/ |
5位|ビズリーチ(利用回答数:288人) ハイクラス向けで企業からスカウトが受けられる
「ビズリーチ」は、ハイクラス求人が多いのが特徴の転職サイトです。厳密にはスカウト型のサイトで、エージェントではありません。登録するとヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられます。
最大の特長は、ハイクラス求人が多いことです。年収1,000万円以上の求人が1/3以上を占めています。一定以上の経験やスキルがある人が転職活動するのに役立つサービスです。
もう1つの大きな特徴として、登録するだけでヘッドハンターや企業からスカウトが届く点があります。以前は「スカウト」と「プラチナスカウト」の2種がありましたが、今は「プラチナスカウト」に一本化されています。プラチナスカウト経由での採用は全体の約70%。採用される可能性が高く、スカウトが届いたら大きなチャンスです。実際、企業からスカウトが届いた場合は書類選考が免除されます。
基本的にヘッドハンターはアドバイスをしませんが、場合によってはアドバイスをもらえることもあります。無料プランと有料プランがあり、有料プランは制限なく求人に応募できます。
- ビズリーチのおすすめポイント
- ヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられるハイクラス向けサイト
- 企業からプラチナスカウトが来た場合は即面接が可能
- 有料プランなら制限なく求人に応募できる
基本データ
| ビズリーチ | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人138,081件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、有料プラン(プレミアムステージ) |
| 拠点 | 東京・大阪・名古屋・福岡・静岡・広島 |
| URL | https://www.bizreach.jp/ |
6位|エン転職(利用回答数:282人) サイトが使いやすく情報も充実、利用者の満足度が高い

「エン転職」は、人材サービス大手の一つエン・ジャパン株式会社による転職サイトです。エージェントサービスも利用できます。
オリコン顧客満足度調査の転職サイト部門で、2018年から2024年まで7年連続で総合満足度No.1となっています。サイトの使いやすさは定評があり、自力で検索・応募するのに適したサービスです。口コミなどの情報も充実しており、企業間の比較検討もしやすくなっています。
さらに転職サイトのほか転職エージェントとしても利用することができ、非公開求人も多数保有しています。大手ですが最大手ほどでない規模で、きめ細かいサポートを受けることが可能。また女性向けのページのほか、ミドルや若手ハイキャリアなどに特化した関連サイトもあります。
- エン転職のおすすめポイント
- 2018年から2024年まで7年連続で総合満足度No.1
- サイトが使いやすいほか情報も充実
- 非公開求人も多数保有
基本データ
| エン転職 | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人152,678件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| URL | https://employment.en-japan.com/ |
さいごに

この記事では、研究職のキャリアパスの全体像から、具体的なキャリアアップの方法、さらには将来を見据えたキャリアチェンジの可能性まで詳しく解説してきました。
研究職は専門性の高い職種ですが、その経験とスキルは様々な分野で活かすことができます。
特に重要なのは、早い段階から自身の興味や適性を見極め、長期的な視点でキャリアプランを設計することです。また継続的なスキルアップと実績作りを通じて、着実にキャリアを築いていくことが目標達成への近道となります。
研究職のキャリアパスには、多様な可能性が秘められています。この記事で紹介した情報を参考に、あなたらしいキャリアプランを見つけ、充実したキャリアを築いてください!