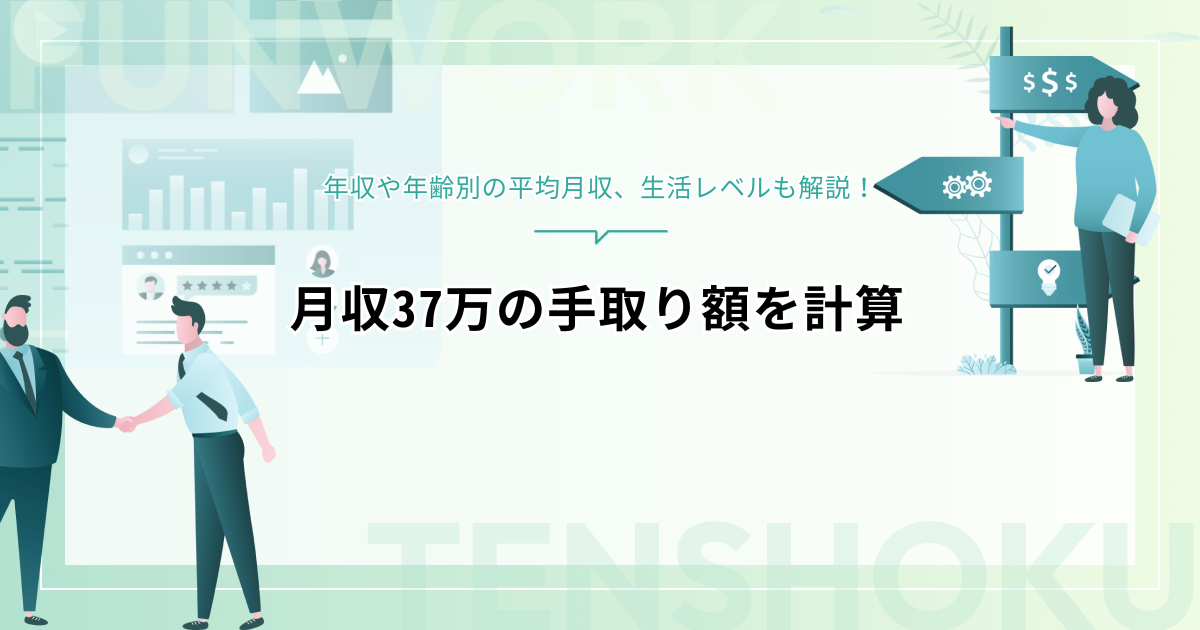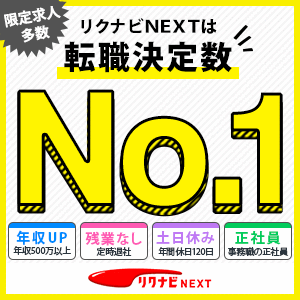月収37万円の手取り額や年収、生活レベルがどのくらいになるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、月収37万円の手取り額の計算方法や控除内訳、年収換算、年齢別や男女別の平均月収との比較、生活レベルを詳しく解説します。
また、月収37万円からのキャリアアップのポイントまでご紹介しますので、現在の生活設計や今後のキャリア設計にぜひお役立てください!
【まずはチェック!!】求人数の多い大手転職サービスが人気!おすすめの求人数比較表!
大手転職サービスの取り扱い求人件数を独自調査。転職サービスの専任担当者が最新の取り扱い求人情報を確認し、求人数比較表にまとめています。転職活動にあたってはエージェントやサイトを積極的に活用しましょう。まずは一通りサービスを体験してみて自分にあったサービスを見つけることをおすすめします。比較表はこちら。
右にスクロールできます
| おすすめ | リクルートエージェント | doda | マイナビAGENT | リクナビNEXT | パソナキャリア | ビズリーチ | リクルートダイレクトスカウト | マイナビ転職 | エン転職 | JACリクルートメント | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特色 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | 全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス・女性向け | ハイクラス全年代・業界 | ハイクラス・全年代 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス | 全業界・首都圏 |
| 求人数 | 605,771件 | 250,676件 | 非公開 | 1,184,000件以上 | 48,766件 | 166,803件 | 516,157件 | 非公開 | 105,190件 | 22,064件 | 2,587件 |
| 求人の豊富さ | |||||||||||
| ポイント | 非公開求人も多数 | エージェント・サイト両方の利用が可能 | 地方の求人も充実 | 企業からのオファーあり | オファーも受けられる | 2種類のスカウトあり | 登録するとスカウトが多数届く | スカウトサービスあり | 利用者の満足度が高い | コンサルタントのサポートが手厚い | とくにエンジニア、20代、女性の求人に強み |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
2025年8月9日調査:各転職エージェントの取り扱い求人件数・各転職サイトの掲載求人数
Contents
月収37万の手取りは約30.5万円!計算方法と控除内訳

月収37万円からは様々な税金や社会保険料が差し引かれ、実際の手取り額は約30.5万円となります。しかし、これは独身の場合の金額であり、配偶者がいる場合は若干異なります。
ここでは、月収37万の手取り額の計算に影響する要素や控除の内訳について詳しく見ていきましょう。
- 月収37万円の手取り額の計算方法
- 独身の場合の月収37万円の手取り額と控除内訳
- 配偶者ありの場合の月収37万円の手取り額と控除内訳
それでは順に見ていきましょう。
月収37万円の手取り額の計算方法
月収37万円の手取り額を計算するには、額面から税金や社会保険料などの控除額を差し引く必要があります。
主な控除項目は
- 所得税
- 住民税
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
です。
これらの控除額は個人の状況によって異なり、配偶者や扶養家族の有無、住んでいる地域、加入している健康保険の種類などによって変動します。また、会社の福利厚生制度や各種手当の有無も手取り額に影響します。
一般的に月収37万円の場合、控除される金額は約6.5万円程度となり、手取り額は約30.5万円前後になると考えられます。
独身の場合の月収37万円の手取り額と控除内訳
独身者の場合、月収37万円からの控除内訳は一般的に次のようになります。
【月収37万の手取り額計算】
<独身の場合>
| 月収(額面) | 37万円 |
| 所得税 | 9,650円 |
| 健康保険料 | 18,962円 |
| 厚生年金 | 34,770円 |
| 雇用保険 | 2,220円 |
| 控除合計額 | 65,602円 |
| 手取り額 | 304,398円 |
※出典:ファンジョブ|【2025年度対応】手取り計算|月給シミュレーション
ただし、これはあくまで一般的な例であり、勤務先の社会保険の種類や地域によって多少の違いがあります。また住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、年度によって変動することがあります。
配偶者ありの場合の月収37万円の手取り額と控除内訳
配偶者がいる場合、月収37万円からの控除内訳は独身者と比べて若干異なります。所得税が約7,350円と独身者より低くなります。これは配偶者控除や配偶者特別控除の適用があるためです。
一方、社会保険料は独身者とほぼ同じです。結果として、控除額合計は約63,302円となり、手取り額は約306,698円(約30.7万円)となります。
【月収37万の手取り額計算】
<配偶者ありの場合>
| 月収(額面) | 37万円 |
| 所得税 | 7,350円 |
| 健康保険料 | 18,962円 |
| 厚生年金 | 34,770円 |
| 雇用保険 | 2,220円 |
| 控除合計額 | 63,302円 |
| 手取り額 | 306,698円 |
※出典:ファンジョブ|【2025年度対応】手取り計算|月給シミュレーション
ただし、配偶者の収入状況によっては、さらに控除額が変わることもあります。特に配偶者の年収が103万円以下の場合は、配偶者控除の恩恵を最大限に受けられるため、手取り額が若干増えることになります。
月収37万円の年収はいくら?業種別の平均年収との比較

月収37万円を年収に換算すると、約444万円となります(ボーナスなしの場合)。
この年収は、日本の平均年収と比較するとどのような位置づけになるのでしょうか。ここでは業種別の平均年収と比較しながら詳しく見ていきましょう。
- 月収37万円の額面年収は約444万円(ボーナスなしの場合)
- 月収37万円でボーナスありの年収シミュレーション
- 業種別の平均年収・平均賞与と月収37万円の比較
それでは順に見ていきましょう。
月収37万円の額面年収は約444万円(ボーナスなしの場合)
月収37万円の場合、ボーナスなしで単純計算すると、年収は約444万円(37万円×12ヶ月)になります。
この年収は、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、全国平均の年収460万円とほぼ同等の水準です。
全国の平均年収460万円のうち71万円は賞与額であり、月収ベースにすると
平均32万円のため、月収37万円は平均以上と捉えることもできます。
月収37万円でボーナスありの年収シミュレーション
月収37万円でボーナスがある場合、年収はさらに増加します。一般的に日本企業では、ボーナスは年間で月収の3〜5ヶ月分が支給されることが多いです。
つまり月収37万円の年収は、以下のようにシミュレーションできます。
- ボーナスが3ヶ月分なら年収約555万円(444万円+111万円)
- ボーナスが5ヶ月分なら年収約629万円(444万円+185万円)
業種によってはさらに多くのボーナスが支給される場合もあります。たとえば、金融業や保険業では平均で約149万円の賞与が支給されています(国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」より)。
業種別の平均年収・平均賞与と月収37万円の比較
月収37万円(年収約444万円〜約629万円)を業種別の平均年収と比較してみましょう。
国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、電気・ガス・熱供給・水道業(平均年収775万円)、情報通信業(平均年収649万円)、金融業・保険業(平均年収652万円)といった業種では、月収37万円の年収は平均を下回ります。
一方、医療・福祉(平均年収404万円)、卸売業・小売業(平均年収387万円)、サービス業(平均年収378万円)などの業種では、月収37万円は平均を上回る水準となります。
賞与についても業種による差が大きく、金融業・保険業では平均149万円、電気・ガス・熱供給・水道業では平均139万円の賞与がある一方、宿泊業・飲食サービス業では平均16万円にとどまります。
そのため、キャリア選択の際には、基本給だけでなくボーナスを含めた年収全体を考慮することが重要です。
【業種別の平均月収(額面)】
| 業種 | 月給 (給料・手当) |
年収 | うち賞与 |
|---|---|---|---|
| 全体平均 | 32万円 | 460万円 | 71万円 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 53万円 | 775万円 | 139万円 |
| 情報通信業 | 44万円 | 649万円 | 120万円 |
| 金融業、保険業 | 42万円 | 652万円 | 149万円 |
| 建設業 | 39万円 | 548万円 | 81万円 |
| 学術研究、専門・技術サービス業、教育・学習支援業 | 38万円 | 551万円 | 100万円 |
| 製造業 | 36万円 | 533万円 | 103万円 |
| 複合サービス業 | 35万円 | 535万円 | 117万円 |
| 運輸業、郵便業 | 34万円 | 473万円 | 63万円 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 34万円 | 469万円 | 63万円 |
| 医療、福祉 | 29万円 | 404万円 | 52万円 |
| 卸売業、小売業 | 28万円 | 387万円 | 54万円 |
| サービス業 | 28万円 | 378万円 | 43万円 |
| 農林水産・鉱業 | 24万円 | 333万円 | 44万円 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 21万円 | 264万円 | 16万円 |
※出典:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」の「(第 13 図)業種別の平均給与」より
※月給は「給料・手当 ÷ 12ヶ月」で算出
※正社員以外を含む
月収37万円は少ない?年齢別・男女別の平均月収と比較

月収37万円が多いのか少ないのかは、年齢や性別によって評価が大きく変わります。
ここでは、年齢別・男女別の平均月収と比較しながら、月収37万円の位置づけを詳しく解説します。
- 月収37万円の年収偏差値は50.2
- 年齢別(20代・30代・40代・50代)に見る月収37万円の評価
- 月収37万円の女性はすごい?男女別の平均月収の格差
それでは順に見ていきましょう。
月収37万円の年収偏差値は50.2
月収37万円(年収約444万円)の年収偏差値は、全体で50.2とほぼ平均的な水準です。これは日本の労働者全体の中で、ちょうど真ん中あたりに位置することを意味します。
しかし、学歴別に見ると評価が変わります。高卒の場合の年収偏差値は56.5と平均よりも高く評価される一方、大卒では43.8とやや低めに評価されます。
また企業規模別では、中小企業では51.2と平均よりやや高く評価されます。年齢別に見ると、35歳の場合、この偏差値は全体の中でちょうど平均的な位置にあります。
つまり月収37万円の評価は、比較する集団によって大きく変わり、
一概に「多い」「少ない」とは言えないことがわかります。
【月収37万円の年収偏差値】
| 月収額面 | 37万円 | |
| 年収額面 | 444万円 | |
| 年収偏差値 | 総合 | 50.2 |
| 高卒 | 56.5 | |
| 大卒 | 43.8 | |
| 中小企業 | 51.2 | |
※出典:年収偏差値チェッカー
※35歳の場合
年齢別(20代・30代・40代・50代)に見る月収37万円の評価
年齢別に月収37万円を評価すると、
- 20代: かなり高い水準
- 30代: 平均以上の水準
- 40代: 平均並みかやや下回る
- 50代: 平均を下回る
と言えます。
厚生労働省の統計によると、20代の平均月収は、20〜24歳で約23.3万円、25〜29歳で約26.7万円であり、月収37万円はかなり高い水準です。
30代では、30〜34歳の平均が約29.9万円、35〜39歳の平均が約32.9万円であり、月収37万円は平均を上回ります。
40代になると、40〜44歳の平均が約35.1万円、45〜49歳の平均が約37.3万円となり、月収37万円は平均並みかやや下回る水準です。
50代では平均月収が40万円を超えるケースも多く、月収37万円は平均を下回ります。このように月収37万円の評価は年齢によって大きく異なり、若いほど高く評価されます。
【年代別・男女別の平均月収】
| 年齢層 | 賃金 | ||
|---|---|---|---|
| 男女計 | 男性 | 女性 | |
| 全体 | 330,400円 | 363,100円 | 275,300円 |
| ~19 | 199,300円 | 203,600円 | 191,300円 |
| 20~24 | 232,500円 | 234,200円 | 230,600円 |
| 25~29 | 267,200円 | 274,700円 | 258,100円 |
| 30~34 | 299,500円 | 316,300円 | 271,600円 |
| 35~39 | 328,700円 | 352,300円 | 284,300円 |
| 40~44 | 351,400円 | 385,500円 | 288,400円 |
| 45~49 | 372,700円 | 416,000円 | 298,000円 |
| 50~54 | 380,400円 | 428,200円 | 295,400円 |
| 55~59 | 392,000円 | 444,100円 | 294,000円 |
| 60~64 | 317,700円 | 344,700円 | 259,900円 |
| 65~69 | 275,500円 | 294,300円 | 234,000円 |
※出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」の「第2表 性、年齢階級別賃金、対前年増減率及び年齢階級間賃金格差」より
月収37万円の女性はすごい?男女別の平均月収の格差
月収37万円の評価は、性別によっても大きく異なります。先述の厚生労働省の統計データを見ると、女性の全年齢の平均月収は約27.5万円であり、月収37万円はこれを大きく上回る水準です。
年齢別に見ても、女性の平均月収は30代で約27〜28万円、40代で約29万円前後であり、月収37万円はかなり高い水準と言えます。
一方、男性の全年齢の平均月収は約36.3万円であり、月収37万円はほぼ平均的な水準です。さらに年齢別に見ていくと、30代までの男性では平均以上、40代男性ではほぼ平均と同じであることがわかります。
このように、女性の場合は月収37万円が非常に高い水準であるのに対し、
男性では平均的な水準と評価が分かれます。
男女間の賃金格差が依然として大きいことがわかります。
【参考】月収別手取りの目安早見表
月収別に手取り額の目安がわかる早見表を作成しました。参考にしてみてください。
| 額面 | 手取り |
| 13万円 | 11万円 |
| 14万円 | 12万円 |
| 15万円 | 13万円 |
| 16万円 | 13万円 |
| 17万円 | 14万円 |
| 18万円 | 15万円 |
| 19万円 | 16万円 |
| 20万円 | 17万円 |
| 21万円 | 17万円 |
| 22万円 | 18万円 |
| 23万円 | 19万円 |
| 24万円 | 20万円 |
| 25万円 | 21万円 |
| 26万円 | 22万円 |
| 27万円 | 22万円 |
| 28万円 | 23万円 |
| 29万円 | 24万円 |
| 30万円 | 25万円 |
| 31万円 | 26万円 |
| 32万円 | 27万円 |
| 33万円 | 27万円 |
| 34万円 | 28万円 |
| 35万円 | 29万円 |
| 36万円 | 30万円 |
| 37万円 | 30万円 |
| 38万円 | 31万円 |
| 39万円 | 32万円 |
| 40万円 | 33万円 |
| 45万円 | 37万円 |
| 50万円 | 41万円 |
| 60万円 | 48万円 |
| 70万円 | 55万円 |
| 80万円 | 63万円 |
| 90万円 | 71万円 |
| 100万円 | 78万円 |
※出典:ファンジョブ|【2025年度対応】手取り計算|月給シミュレーション
※配偶者なし・40歳未満の場合
月収37万円の生活レベルはどのくらい?世帯構成別に検証

月収37万円の手取りで、実際にどのような生活ができるのでしょうか。単身、夫婦、子育て世帯など、世帯構成別に生活水準を検証します。また、この収入で可能な貯金額についても見ていきましょう。
- 月収37万円の手取りでの一人暮らしの生活水準
- 月収37万円の手取りでの夫婦二人世帯の家計モデル
- 月収37万円の手取りでの子育て世帯(4人家族)の生活レベル
- 月収37万円の手取りで可能な貯金額のシミュレーション
それでは順に見ていきましょう。
月収37万円の手取りでの一人暮らしの生活水準
月収37万円の手取り約30.5万円で一人暮らしをする場合、比較的余裕のある生活が可能です。
月収37万円の一人暮らしの標準的な支出例として、
- 家賃8〜10万円(都市部の場合)
- 食費5万円
- 水道光熱費1.5万円
- 通信費1万円
- 交通費2万円
- 娯楽費3万円
などがあります。これらの基本的な生活費を合計しても20〜22.5万円程度であり、手取りとの差額8〜10.5万円を貯金や投資、趣味などに充てることができます。
都市部では家賃が高いものの、地方であれば家賃が5〜7万円程度に抑えられるため、さらに余裕が生まれます。
月収37万円(手取り約30.5万円)であれば、一般的な趣味や月数回の外食を楽しみながらも、毎月一定額の貯金が可能な生活レベルと言えるでしょう。
月収37万円の手取りでの夫婦二人世帯の家計モデル
月収37万円(手取り約30.5万円)が世帯の唯一の収入である夫婦二人世帯の場合、やりくりは少し厳しくなります。
月収37万円の標準的な支出例は次のようになります。
- 家賃10万円(都市部の場合)
- 食費7万円
- 水道光熱費2万円
- 通信費1.5万円
- 交通費3万円
- 保険料2万円
これらの基本的な生活費を合計すると25.5万円程度となり、手取りとの差額は5万円程度となります。この金額を貯金や娯楽費に充てることになりますが、予期せぬ出費や将来のための貯蓄を考えると、やや余裕が少ない状況です。
ただし、共働きが一般的な現代では配偶者も収入を得ているケースが多く、
その場合は家計の余裕度が大きく向上します。
たとえば配偶者が月10万円程度の収入があれば、世帯の可処分所得は40万円程度となり、かなり余裕のある生活が可能になります。
月収37万円の手取りでの子育て世帯(4人家族)の生活レベル
月収37万円(手取り約30.5万円)が唯一の収入である4人家族(夫婦と子ども2人)の場合、かなり厳しい家計状況となります。
月収37万円の4人家族の標準的な支出例は、
- 家賃12万円(都市部の場合)
- 食費10万円
- 水道光熱費2.5万円
- 通信費1.5万円
- 教育費5万円(公立学校の場合)
- 保険料2万円
などがあります。これらの基本的な生活費を合計すると33万円程度となり、手取り額を超えてしまいます。そのため、家賃をより安い地域に抑えたり、食費や娯楽費を削減したりする必要があるでしょう。
また、子どもの年齢によっては児童手当などの公的支援を受けられますが、それでも余裕のある生活は難しいといえます。
このような世帯では、配偶者のパートタイム収入などにより家計を支えることが重要となります。たとえば共働きで世帯収入が50万円前後になれば、より安定した生活が可能になるでしょう。
月収37万円の手取りで可能な貯金額のシミュレーション
月収37万円(手取り約30.5万円)での貯金可能額は、世帯構成や生活スタイルによって大きく異なります。
一人暮らしの場合、基本的な生活費が20〜22.5万円程度であれば、毎月8〜10.5万円程度の貯金が可能です。これを1年間続けると、年間96〜126万円の貯蓄となります。
夫婦二人世帯で月収37万円が唯一の収入の場合、毎月の貯金可能額は5万円程度となり、年間60万円程度の貯蓄となります。子育て世帯(4人家族)では、月収37万円のみでは貯金が難しく、配偶者の収入や公的支援が必要です。
貯金を増やすための方法としては、
- 固定費(特に家賃)の見直し
- 食費の削減(自炊の増加など)
- 不要なサブスクリプションの解約
などが効果的です。また、月収37万円の手取りから毎月一定額を自動的に貯蓄口座に振り替える「先取り貯金」も効果的な方法です。
- 月収37万円の生活レベルのまとめ
-
- 一人暮らし:かなり余裕がある(月8〜10万円の貯蓄可能)
- 夫婦二人世帯:やや余裕がある(月5万円程度の貯蓄可能)
- 子育て世帯(4人家族):かなり厳しい(配偶者の収入有無がポイント)
月収37万円の手取りで住める家賃と住まいの選択肢

月収37万円の手取りで、どの程度の家賃や住宅ローンを組むことができるのでしょうか。
ここでは、地域による違いや適正な家賃の目安、住宅ローンの限度額について詳しく解説します。
- 都道府県別の平均月収から見る月収37万円の住居選択の地域差
- 月収37万円の手取りで適正な家賃の目安
- 月収37万円で組める住宅ローンの限度額
それでは順に見ていきましょう。
都道府県別の平均月収から見る月収37万円の住居選択の地域差
月収37万円は地域によって評価が大きく異なります。
厚生労働省の統計データによると、東京都の平均月収は約36.9万円、神奈川県は約35.0万円であり、月収37万円はこれらの都市部ではほぼ平均的な水準です。一方、地方では平均月収が25〜30万円程度のため、月収37万円はかなり高い水準となります。
この収入差は住居費に大きく影響し、同じ月収37万円でも住める物件の広さや質が地域によって大きく異なります。
たとえば東京都心では家賃10万円の物件は1LDK程度が一般的ですが、地方都市では同じ家賃で2LDK〜3LDKの広い物件に住むことができます。また、大阪府(平均月収34.0万円)や愛知県(平均月収32.2万円)などの大都市でも、東京ほどではありませんが住居費が高めです。
このように月収37万円で選べる住居の選択肢は地域によって大きく異なります。
【都道府県別の平均年収・平均月収】
| 都道府県 | 平均年収 | 平均月収(所定内給与額) | 都道府県 | 平均年収 | 平均月収(所定内給与額) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国平均 | 472.9万円 | 31.8万円 | 三重県 | 455.3万円 | 30.5万円 |
| 北海道 | 422.4万円 | 28.9万円 | 滋賀県 | 455.5万円 | 30.3万円 |
| 青森県 | 357.4万円 | 25.0万円 | 京都府 | 470.0万円 | 31.6万円 |
| 岩手県 | 379.6万円 | 26.0万円 | 大阪府 | 510.3万円 | 34.0万円 |
| 宮城県 | 419.5万円 | 28.9万円 | 兵庫県 | 477.3万円 | 31.7万円 |
| 秋田県 | 381.6万円 | 26.1万円 | 奈良県 | 437.2万円 | 30.2万円 |
| 山形県 | 372.3万円 | 25.6万円 | 和歌山県 | 438.6万円 | 29.8万円 |
| 福島県 | 406.7万円 | 27.9万円 | 鳥取県 | 368.9万円 | 25.8万円 |
| 茨城県 | 465.5万円 | 31.2万円 | 島根県 | 395.8万円 | 26.9万円 |
| 栃木県 | 496.3万円 | 32.3万円 | 岡山県 | 430.4万円 | 29.1万円 |
| 群馬県 | 435.9万円 | 29.7万円 | 広島県 | 444.3万円 | 29.7万円 |
| 埼玉県 | 460.9万円 | 31.7万円 | 山口県 | 433.8万円 | 29.0万円 |
| 千葉県 | 453.0万円 | 31.0万円 | 徳島県 | 396.6万円 | 27.1万円 |
| 東京都 | 546.5万円 | 36.9万円 | 香川県 | 410.5万円 | 27.9万円 |
| 神奈川県 | 530.5万円 | 35.0万円 | 愛媛県 | 411.3万円 | 28.0万円 |
| 新潟県 | 396.7万円 | 27.0万円 | 高知県 | 399.7万円 | 27.3万円 |
| 富山県 | 437.2万円 | 29.4万円 | 福岡県 | 437.7万円 | 29.7万円 |
| 石川県 | 432.3万円 | 29.0万円 | 佐賀県 | 395.8万円 | 26.9万円 |
| 福井県 | 420.7万円 | 28.5万円 | 長崎県 | 376.2万円 | 25.7万円 |
| 山梨県 | 437.4万円 | 29.2万円 | 熊本県 | 394.1万円 | 26.9万円 |
| 長野県 | 428.7万円 | 28.8万円 | 大分県 | 399.9万円 | 27.1万円 |
| 岐阜県 | 435.9万円 | 29.2万円 | 宮崎県 | 368.0万円 | 25.4万円 |
| 静岡県 | 461.0万円 | 30.5万円 | 鹿児島県 | 389.5万円 | 26.8万円 |
| 愛知県 | 490.0万円 | 32.2万円 | 沖縄県 | 368.3万円 | 26.5万円 |
※出典:厚生労働省の2023年(令和5年) 賃金構造基本統計調査 をもとに算出
※平均年収は、「所定内給与額×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額」により算出(所定内給与額は各種手当を除く)
※短時間労働者(パートタイム労働者)を除く
月収37万円の手取りで適正な家賃の目安
月収37万円(手取り約30.5万円)での適正な家賃は、一般的に手取り収入の30%以内とされています。つまり、約9.2万円が上限の目安となります。ただし、世帯構成や他の支出によってこの割合は変動します。
単身者の場合、家賃に上限いっぱいの9万円前後を使うことも可能ですが、夫婦や家族がいる場合は、他の生活費とのバランスを考慮する必要があります。また、手取りの25%(約7.6万円)程度に抑えることで、より余裕のある家計運営が可能になります。
都市部では家賃相場が高いため、通勤時間とのトレードオフを考慮する必要があります。駅から徒歩15分以上の物件や、築年数が経過した物件を選ぶことで、家賃を抑えることができます。
また、地方では同じ予算でより広い物件を選べるため、テレワークが可能な職種であれば、地方移住も選択肢の一つとなるでしょう。
- 月収37万円で住める家賃の目安
-
- 手取りの30%の場合:約9.2万円
- 手取りの25%の場合:約7.6万円
月収37万円で組める住宅ローンの限度額
月収37万円の場合、住宅ローンの借入可能額は一般的に年収の7〜8倍程度とされています。
月収37万円の年収は約444万円(ボーナスなしの場合)ですので、約3,100万円〜3,550万円が借入可能額の目安となります。ただし、審査では他の借入状況や勤続年数、職業の安定性なども考慮されるため、実際の借入可能額は個人によって異なります。
返済負担率(年収に対する年間返済額の割合)は一般的に35%以下が望ましいとされており、月収37万円の場合、月々の返済額は約13万円以下が目安となります。
たとえば金利1%、35年返済で計算すると、約3,700万円程度の借入が可能です。ただし、将来の金利上昇リスクや収入減少リスクを考慮すると、余裕を持った計画が重要です。
特に子育て世帯では教育費などの将来的な支出増加も考慮し、住宅ローンの返済計画を立てる必要があります。
月収37万円からのキャリアアップ戦略

月収37万円は平均的な収入水準ですが、さらに収入を増やすためのキャリアアップ戦略について解説します。
どのような職種や業界が高収入につながるのか、また転職で年収アップを目指すためのコツを見ていきましょう。
- 月収37万円以上が期待できる主な職種と業界
- 月収37万円の人の年齢層とキャリアステージ
- 転職で月収37万円から年収アップを目指す3つのコツ
それでは順に解説します。
月収37万円以上が期待できる主な職種と業界
月収37万円以上の収入が期待できる職種や業界は多数あります。
特に高収入が期待できる業界としては、
- IT・通信業界(平均月収44万円)
- 金融業・保険業(平均月収42万円)
- 電気・ガス・熱供給・水道業(平均月収53万円)
などが挙げられます。
また高収入の傾向にある職種は、次のとおりです。
- データサイエンティストやAIエンジニアなどのIT専門職
- 投資銀行業務やファンドマネージャーなどの金融専門職
- コンサルタント
- 営業職(法人営業や技術営業)
このほか、近年ではデジタルマーケティングやUXデザイナーなどの新しい職種も注目されています。
ただし、これからキャリアチェンジを考える場合は、年収だけでなく、業界の将来性や自分の適性も考慮することが長期的なキャリアを築く上で大切です。
月収37万円の人の年齢層とキャリアステージ
月収37万円の収入がどのような年齢層やキャリアステージで一般的かを見てみましょう。
先述の厚生労働省の統計データによると、月収37万円に最も近い平均月収は45〜49歳の女性(約29.8万円)や35〜39歳の男女計(約32.9万円)です。
つまり、キャリアステージとしては中堅社員から管理職(係長〜課長クラス)が多いと考えられます。
特に大企業では30代後半で係長、40代前半で課長に昇進することが一般的であり、役職手当などが加わって月収37万円に達するケースが多いです。専門職では経験年数5〜10年程度で同水準の収入に達することが多いでしょう。
転職で月収37万円から年収アップを目指す!3つのポイント
月収37万円からさらに年収アップを目指す場合、転職は効果的な手段の一つです。
月収37万円から転職成功するための3つのポイントをご紹介します。
- 市場価値の高いスキルを磨く
- 年収の高い業界や成長産業への転職を狙う
- 専門性を高める
まず1つ目のスキルアップですが、特にデータ分析能力やプログラミングスキル、語学力(特に英語)などは、多くの業界で重宝されます。資格取得も効果的で、ITであればAWS認定資格、金融であればFP資格やCFA資格などが有利です。
2つ目の転職先の選択については、IT業界、金融業界、コンサルティングなどが平均年収が高い傾向にあります。また同じ業界内でも、大手企業や外資系企業は給与水準が高いことが多いです。
3つ目は、専門性を高めることです。ジェネラリストよりもスペシャリストの方が、年齢の上昇とともに高収入を得られる傾向があります。
この3つのポイントを押さえた上で、転職エージェントを上手く活用し、
市場価値と自己評価のギャップを把握して転職活動を効率的に進めましょう。
みんなが使っている転職サービス上位6選 【1,382人に聞いた転職サービス利用状況】
実際に登録したことのある転職サービスについてアンケートをとりました。アンケート結果として、みんなが使っている転職サービスの上位6サービスは以下です。
- 1位|リクルートエージェント(821人)
- 2位|doda(564人)
- 3位|リクナビNEXT(389人)
- 4位|マイナビAGENT(312人)
- 5位|ビズリーチ(288人)
- 6位|エン転職(282人)
※転職サービスの利用アンケート(クラウドワークス) 回答数:1,382 / 集計期間:2024年09月19日~10月03日
1位|リクルートエージェント(利用回答数:821人) 圧倒的な求人数
「リクルートエージェント」は、求人数、安定したサービス品質で、まずは登録が必須のエージェントです。
まず何と言っても求人数が多いことがおすすめの理由として挙げられます。転職成功の実績も多く、優れているのは求人の数だけではありません。業界に精通したアドバイザーが在籍しているので、ぴったりの求人を見つけ出してくれます。求人やサービスの質・量ともにトップクラスで転職エージェントとしては定番・王道のサービスです。
営業・技術系を中心にあらゆる業種・職種をカバー。総合型ながら条件ごとに特化したページもあり、使いやすいのも人気の理由です。
- リクルートエージェントのおすすめポイント
- 求人数が圧倒的に多い
- 業界に精通したアドバイザーが在籍
- 条件ごとに特化したページがあり使いやすい
基本データ
| リクルートエージェント | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人474,685件/非公開求人399,542件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | エージェントサービス、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供 |
| 拠点 | 東京・北海道・宮城・宇都宮・さいたま・千葉・横浜・金沢・新潟・長野・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡 |
| URL | https://www.r-agent.com/ |
2位|doda(利用回答数:564人) エージェント/サイトの一体型で自分でも応募が可能
「doda」は、人材紹介・転職支援を行う大手「パーソルキャリア」が運営する総合型転職サイトです。エージェントサービスも利用できる点が人気の理由の1つになっています。
dodaも求人数が多く、非公開求人も条件が良いものが多いのが大きなポイントです。
また転職サイトと転職エージェントの一体型で、使い方の自由度が高いのもおすすめポイント。エージェントサービスでは専任のキャリアアドバイザーがサポートしてくれます。なお企業との対応は採用プロジェクト担当が行い、求職者と企業とでそれぞれ別のプロフェッショナルが対応します。
- dodaのおすすめポイント
- 非公開求人も好条件多数
- 転職サイトと転職エージェントの一体型で自由度が高い
- 専任のキャリアアドバイザーがサポート、企業は別のプロフェッショナルが対応
基本データ
| doda | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人262,342件/非公開求人31.049件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、年収査定、合格診断、レジュメビルダー、「自己PR」発掘診断、転職タイプ診断、はたらく女性のためのモヤモヤ解消診断、オンライン仕事力診断 |
| 拠点 | 東京・横浜・札幌・仙台・静岡・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・広島・福岡・鹿児島 |
| URL | https://doda.jp/consultant/ |
3位|リクナビNEXT(利用回答数:389人) 求人サイト群の中でも最大級の求人数と使いやすさ
「リクナビNEXT」は大定番の転職サイトで、サイトの見やすさや使いやすさにも定評があります。
エージェントなしの狭義の転職サイトの中では、求人数はトップクラス。新規の求人も多く、定期的にチェックすることで希望に合う求人に出会える可能性が高まります。
ツールが便利でサイトが使いやすいのも特長です。たとえば「気になるリスト」を使うと、気になる企業や後でゆっくりチェックしたい企業をリスト化できるほか、気になるに追加した企業から面接のオファーが来る可能性があります。
そのほか、公開求人・非公開求人の企業からオファーがもらえる「オファーを待つ」、自己分析ツール「グッドポイント診断」などがあります。
- リクナビNEXTのおすすめポイント
- サイトが見やすく使いやすい
- 狭義の転職サイトでは最大級の求人数
- 多くの人が利用している定番の転職サイト
基本データ
| リクナビNEXT | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人824,000件以上(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | オファー、気になるリスト、グッドポイント診断 |
| URL | https://next.rikunabi.com/ |
4位|マイナビAGENT(利用回答数:312人) 20代・30代の求人に強い
「マイナビAGENT」は、さまざまな転職サイトを運営している株式会社マイナビによる転職エージェントです。きめ細かいサポートが受けられると評価されています。
とくに20代・30代の求人が多いので、その世代の人にはおすすめです。また全国に拠点があり地方の求人も充実しているので、大都市圏以外で探している人にもぴったりです。
履歴書や職務経歴書のサポートも充実、初めての転職でも安心して利用できます。IT、営業など業種・職種別のサービスもあります。自分が探している業種と一致するならより探しやすくなるでしょう。
- マイナビAGENTのおすすめポイント
- 20代・30代の求人が多い
- 地方の求人も充実
- 履歴書や職務経歴書のサポートもあり安心
基本データ
| マイナビAGENT | |
|---|---|
| 公開求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| 拠点 | 拠点情報はこちらをご確認ください |
| URL | https://mynavi-agent.jp/ |
5位|ビズリーチ(利用回答数:288人) ハイクラス向けで企業からスカウトが受けられる
「ビズリーチ」は、ハイクラス求人が多いのが特徴の転職サイトです。厳密にはスカウト型のサイトで、エージェントではありません。登録するとヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられます。
最大の特長は、ハイクラス求人が多いことです。年収1,000万円以上の求人が1/3以上を占めています。一定以上の経験やスキルがある人が転職活動するのに役立つサービスです。
もう1つの大きな特徴として、登録するだけでヘッドハンターや企業からスカウトが届く点があります。以前は「スカウト」と「プラチナスカウト」の2種がありましたが、今は「プラチナスカウト」に一本化されています。プラチナスカウト経由での採用は全体の約70%。採用される可能性が高く、スカウトが届いたら大きなチャンスです。実際、企業からスカウトが届いた場合は書類選考が免除されます。
基本的にヘッドハンターはアドバイスをしませんが、場合によってはアドバイスをもらえることもあります。無料プランと有料プランがあり、有料プランは制限なく求人に応募できます。
- ビズリーチのおすすめポイント
- ヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられるハイクラス向けサイト
- 企業からプラチナスカウトが来た場合は即面接が可能
- 有料プランなら制限なく求人に応募できる
基本データ
| ビズリーチ | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人138,081件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、有料プラン(プレミアムステージ) |
| 拠点 | 東京・大阪・名古屋・福岡・静岡・広島 |
| URL | https://www.bizreach.jp/ |
6位|エン転職(利用回答数:282人) サイトが使いやすく情報も充実、利用者の満足度が高い

「エン転職」は、人材サービス大手の一つエン・ジャパン株式会社による転職サイトです。エージェントサービスも利用できます。
オリコン顧客満足度調査の転職サイト部門で、2018年から2024年まで7年連続で総合満足度No.1となっています。サイトの使いやすさは定評があり、自力で検索・応募するのに適したサービスです。口コミなどの情報も充実しており、企業間の比較検討もしやすくなっています。
さらに転職サイトのほか転職エージェントとしても利用することができ、非公開求人も多数保有しています。大手ですが最大手ほどでない規模で、きめ細かいサポートを受けることが可能。また女性向けのページのほか、ミドルや若手ハイキャリアなどに特化した関連サイトもあります。
- エン転職のおすすめポイント
- 2018年から2024年まで7年連続で総合満足度No.1
- サイトが使いやすいほか情報も充実
- 非公開求人も多数保有
基本データ
| エン転職 | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人152,678件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| URL | https://employment.en-japan.com/ |
まとめ

この記事では、月収37万円の手取り額や年収換算、平均収入との比較、生活レベルなどについて詳しく解説しました。
月収37万円の手取りは約30.5万円で、年収は約444万円(ボーナスなし)〜約629万円(ボーナスあり)となります。この月収37万円という収入レベルは、年齢や性別、業界によって評価が大きく異なり、20代では高収入、40代では平均的な水準です。
月収37万円の手取りでは、一人暮らしなら余裕のある生活レベルになりますが、子育て世帯では厳しい状況といえます。
月収37万円から収入アップを目指すなら、スキルアップや成長産業への転職が効果的です。自分の状況に合わせて、適切な家計管理と将来設計を行いましょう。