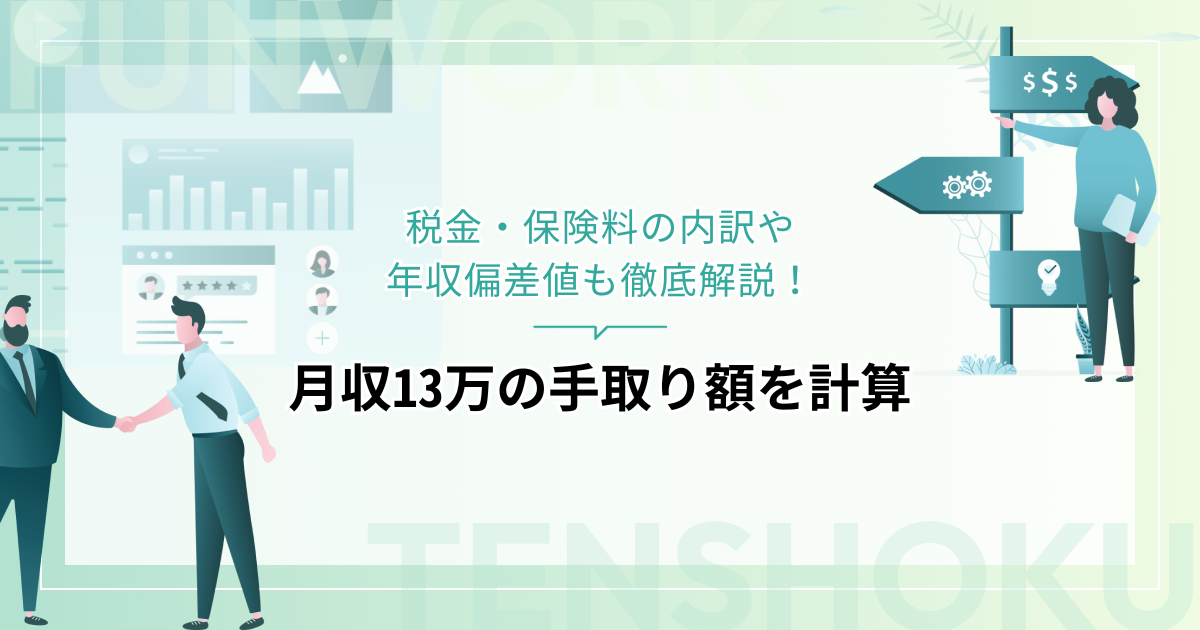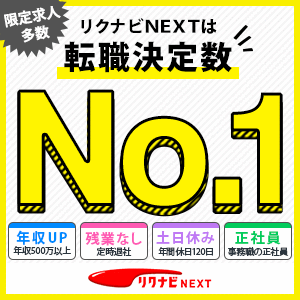月収13万円の手取り額がどれくらいになるのか、気になるところですよね。
まず結論からいうと、月収13万円の手取りは約11万円となり、約2万円が税金や社会保険料などで差し引かれます。
この記事では、月収13万円の手取り額の計算方法や税金・社会保険料の内訳、年収偏差値など、あなたの収入の位置づけを多角的に解説します。
また、月収13万円での生活プランや収入アップの方法まで幅広くカバーしているので、今後のキャリアプランや家計管理にぜひお役立てください!
【まずはチェック!!】求人数の多い大手転職サービスが人気!おすすめの求人数比較表!
大手転職サービスの取り扱い求人件数を独自調査。転職サービスの専任担当者が最新の取り扱い求人情報を確認し、求人数比較表にまとめています。転職活動にあたってはエージェントやサイトを積極的に活用しましょう。まずは一通りサービスを体験してみて自分にあったサービスを見つけることをおすすめします。比較表はこちら。
右にスクロールできます
| おすすめ | リクルートエージェント | doda | マイナビAGENT | リクナビNEXT | パソナキャリア | ビズリーチ | リクルートダイレクトスカウト | マイナビ転職 | エン転職 | JACリクルートメント | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特色 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | 全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス・女性向け | ハイクラス全年代・業界 | ハイクラス・全年代 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス | 全業界・首都圏 |
| 求人数 | 619,020件 | 253,658件 | 非公開 | 1,008,000件以上 | 49,483件 | 172,146件 | 534,042件 | 非公開 | 99,695件 | 22,272件 | 2,525件 |
| 求人の豊富さ | |||||||||||
| ポイント | 非公開求人も多数 | エージェント・サイト両方の利用が可能 | 地方の求人も充実 | 企業からのオファーあり | オファーも受けられる | 2種類のスカウトあり | 登録するとスカウトが多数届く | スカウトサービスあり | 利用者の満足度が高い | コンサルタントのサポートが手厚い | とくにエンジニア、20代、女性の求人に強み |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
2025年9月9日調査:各転職エージェントの取り扱い求人件数・各転職サイトの掲載求人数
Contents
月収13万円の手取りは約11万円!年収(額面)は156万円

【月収13万円の手取り額・年収の目安】
| 月収(額面) | 13万円 |
|---|---|
| 手取り額 | 約11万円 |
| 年収(額面) | 156万円 |
※出典:ファンジョブ|【2025年度対応】手取り計算|月給シミュレーション
月収13万円の手取り額は約11万円が目安ですが、手取り額はさまざまな要因によって変動します。
まずは、月収13万円の手取り額の目安と手取り額が変動する要素について見ていきましょう。
- 月収13万円の手取り額の目安
- 雇用形態別の月収13万円の手取り額の違い
- 【参考】額面と手取り額の違い
それでは順に解説します。
月収13万円の手取り額の目安
月収13万円の手取り額は約11万円で、具体的には
- 独身の場合:約10万9,000円
- 配偶者がいる場合:約11万300円
となります。つまり月収13万円から差し引かれる金額は約2万円で、これには所得税や社会保険料などが含まれています。
さらに手取り額は
- 雇用形態
- 家族構成
- 住んでいる地域
によっても変動するため、一概には言えません。
たとえばパートやアルバイトで社会保険に加入していない場合は、控除額が少なくなり手取り額は増えます。
月収13万円は決して高くはありませんが、税金面では低所得者への配慮もあり、控除率は比較的低めになっています。
雇用形態別の月収13万円の手取り額の違い
月収13万円の手取り額は、雇用形態によって大きく異なります。
- 正社員の場合
- 社会保険料が会社と折半で支払われるため、約11万円程度の手取りとなります。
- パートやアルバイトの場合
- 週20時間未満の勤務であれば、社会保険に加入する必要がないため(控除は所得税のみ)、手取り額は約12万5,000円程度まで上がります。
※ただし、20時間以上働く場合や従業員101人以上の企業で働く場合は、パートでも社会保険への加入が必要です。
月収13万円で手取り額を最大化したい場合は、社会保険の加入条件をよく確認し、働き方を調整するのも一つの方法でしょう。
【参考】額面と手取り額の違い
- 額面給与とは?
- 雇用契約で定められた基本給に各種手当を加えた金額で、いわゆる「総支給額」のことです。
- 手取り額とは?
- 額面給与から税金や社会保険料などを差し引いた、実際に銀行口座に振り込まれる金額です。
生活設計をする際には、額面ではなく手取り額をベースに考えることが重要です。特に住居費や生活費の計画を立てる場合、月収13万円の手取り約11万円を基準に予算を組んでみましょう。
月収13万円の手取り額の計算方法は?税金と社会保険料の内訳
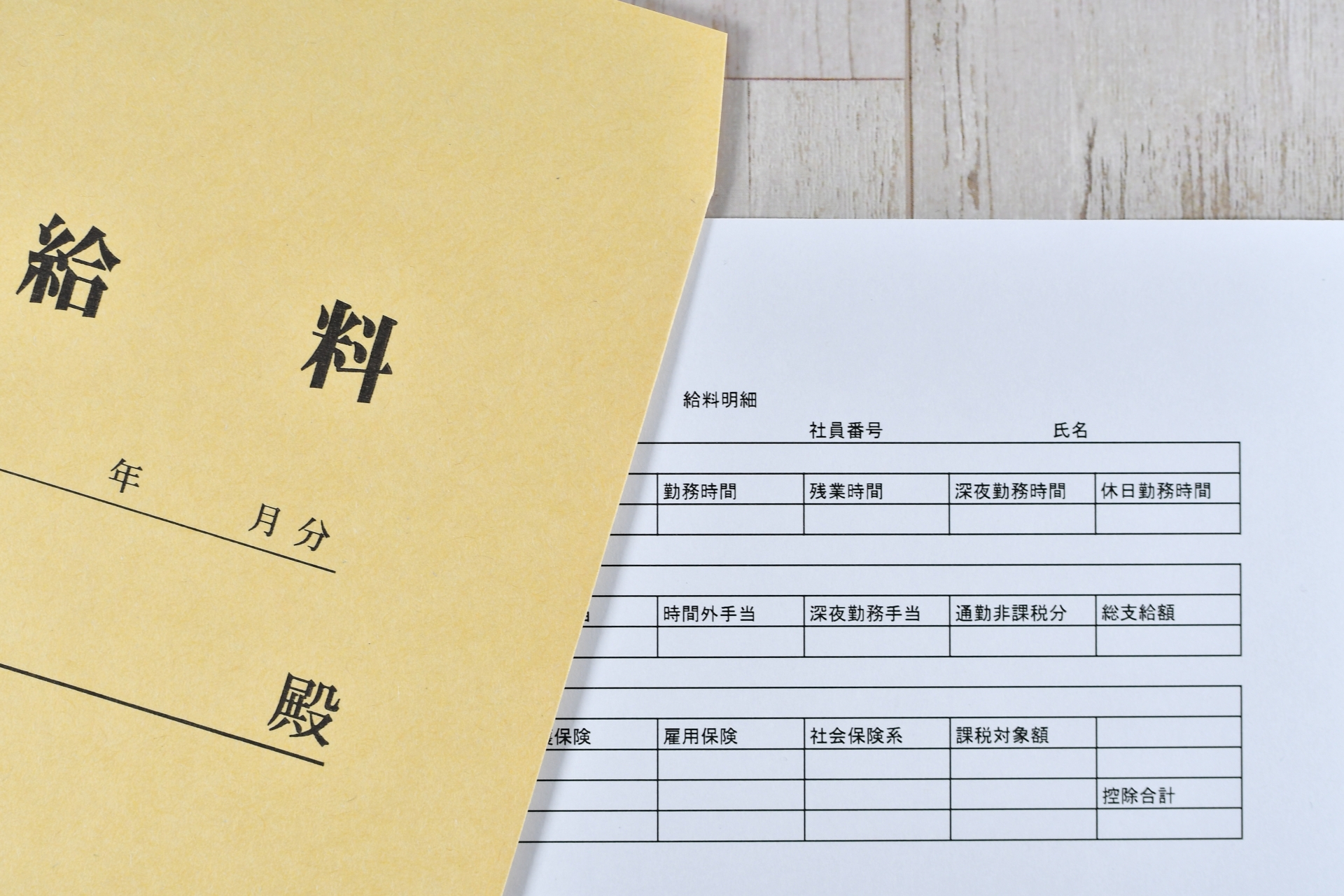
続いて、月収13万円から手取り額がどのような計算で算出されるのか、また税金や社会保険料がどれくらい差し引かれるのかを詳しく解説していきます。
- 月収13万円から引かれる税金と社会保険料の内訳
- 月収13万円の国民健康保険料の計算方法
- 月収13万円の社会保険料(健康保険料・厚生年金)の計算方法
- 月収13万円の所得税・住民税の計算方法
- 月収13万円で厚生年金はいくらもらえる?
それでは順に見てみましょう。
月収13万円から引かれる税金と社会保険料の内訳
月収13万円から手取り額を計算する場合、差し引かれる税金と社会保険料には
- 所得税
- 住民税
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
などがあります。
【月収13万の手取り額計算】
<独身の場合>
| 月収(額面) | 13万円 |
|---|---|
| 控除合計額 | 20,968円 |
| 所得税 | 1,240円 |
| 健康保険料 | 6,687円 |
| 厚生年金 | 12,261円 |
| 雇用保険 | 780円 |
| 手取り額 | 109,032円 |
<配偶者ありの場合>
| 月収(額面) | 13万円 |
|---|---|
| 控除合計額 | 19,728円 |
| 所得税 | 0円 |
| 健康保険料 | 6,687円 |
| 厚生年金 | 12,261円 |
| 雇用保険 | 780円 |
| 手取り額 | 110,272円 |
※出典:ファンジョブ|【2025年度対応】手取り計算|月給シミュレーション
このように独身の場合、合計約2万1,000円が差し引かれます。
配偶者がいる場合は配偶者控除が適用され、所得税が0円になることもあります。
月収13万円の手取り計算では、社会保険料が最も大きな割合を占めており、特に厚生年金保険料が全体の約60%を占めています。
こうした控除は負担が大きいと感じられるかもしれませんが、将来の社会保障の原資となるため、重要な支出といえるでしょう。
月収13万円の国民健康保険料の計算方法
月収13万円で自営業やフリーランスとして働く場合、国民健康保険に加入することになります。月収13万円の手取りを考える場合、国民健康保険料は大きな支出の一つです。
- 月収13万円の国民健康保険料の計算方法
- 国民健康保険料は住んでいる自治体によって異なりますが、年収156万円(月収13万円×12ヶ月)をベースに計算されます。一般的に年収の7〜10%程度が保険料となるため、年間で約11万〜16万円、月々で約9,000〜13,000円程度の負担となるでしょう。
ただし、収入が少ない場合は保険料の減額制度もあります。月収13万円のケースでは軽減措置が適用される可能性もあるため、自治体の窓口で相談してみることをおすすめします。
月収13万円の社会保険料(健康保険料・厚生年金)の計算方法
月収13万円の会社員の場合は、支払う社会保険料が健康保険料と厚生年金保険料に分かれます。
- 月収13万円の社会保険料(健康保険料・厚生年金)の計算方法
- 健康保険料は標準報酬月額(この場合13万円)に保険料率(約10%)を掛けた金額の半額で、約6,687円です。厚生年金保険料は標準報酬月額に保険料率(約18.8%)を掛けた金額の半額で、約12,261円となります。
月収13万円の手取り額を計算すると、これらの社会保険料だけで約19,000円が差し引かれることになります。ただし、これらの保険料は会社と折半で支払うため、実際は半額の負担で済むのがメリットです。
月収13万円の所得税・住民税の計算方法
月収13万円の場合の所得税は、年収から給与所得控除や基礎控除などを差し引いた課税所得に税率を掛けて計算します。
- 月収13万円の所得税・住民税の計算方法
- 月収13万円(年収156万円)の場合、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を差し引くと、課税所得は53万円となります。これに所得税率5%を掛けると、年間の所得税は約26,500円、月々では約2,200円です。
ただし、実際には配偶者控除や扶養控除などが適用されることもあり、独身の場合の月々の所得税は約1,240円となります。住民税も同様に計算され、翌年度に課税されます。
月収13万円の手取り計算では、所得税の負担は比較的軽く、社会保険料より小さい割合を占めています。
月収13万円で厚生年金はいくらもらえる?
月収13万円で40年間働き続けた場合、将来もらえる厚生年金の目安を計算してみましょう。
- 月収13万円で厚生年金はいくらもらえる?
- 厚生年金は標準報酬月額(この場合13万円)と加入期間に応じて決まります。月収13万円で40年間加入した場合、年金額は月々約5.5万円程度と試算されます。これに国民年金(満額で月約6.5万円)を加えると、合計で月約12万円の年金を受け取れる見込みです。
月収13万円の手取りと将来の年金額を比較すると、年金額が手取り額に近い水準になることがわかります。ただし、これはあくまで現行制度での試算であり、将来の年金制度改革によって変動する可能性があることには注意が必要です。
月収13万円は低い?平均月収と年収偏差値から見る位置づけ
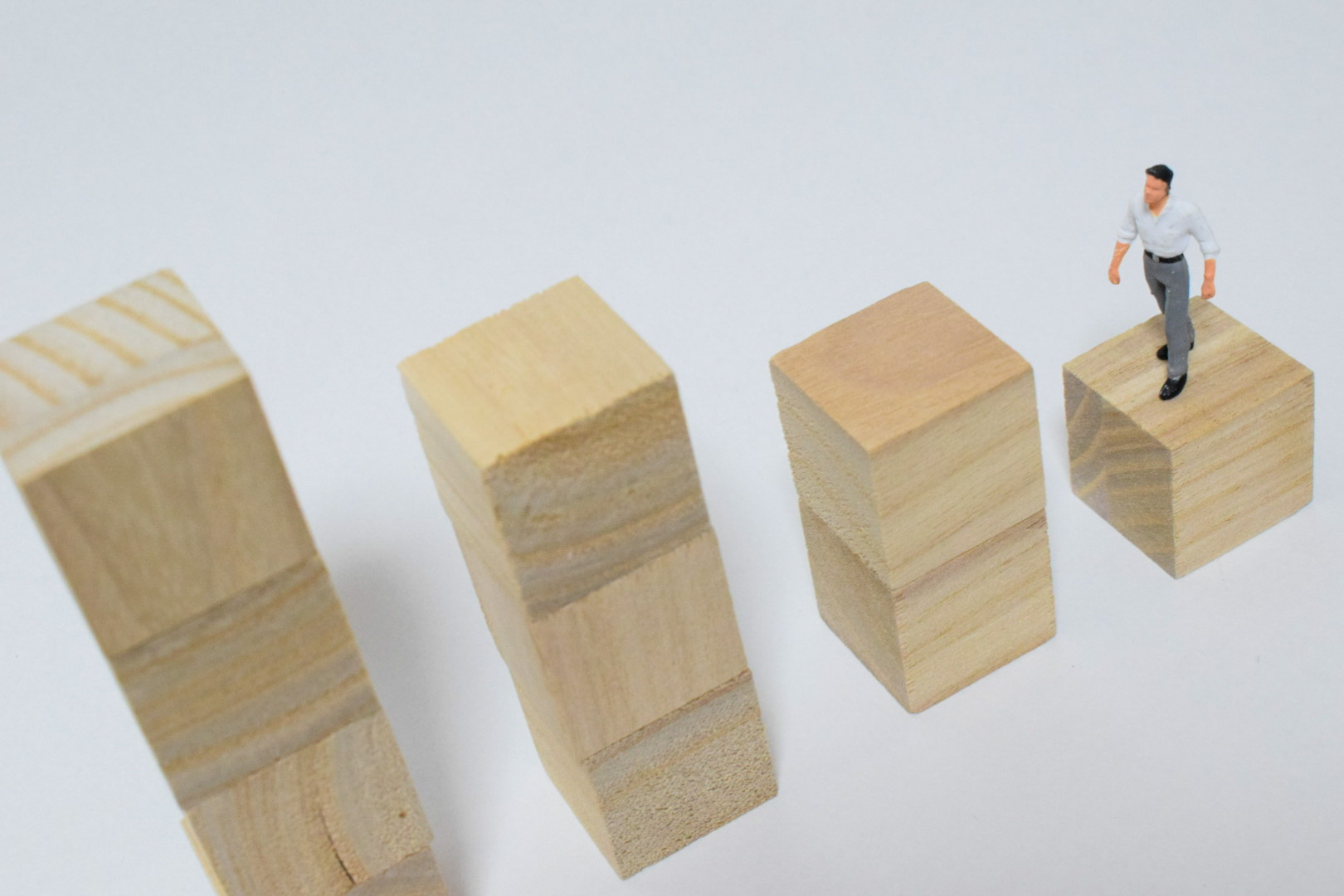
月収13万円は全国平均と比べるとどのくらいの水準なのでしょうか。
年齢や性別、業種別の平均と比較することで、自分の給与の位置づけを客観的に把握することができます。
- 年代別・男女別の平均月収との比較
- 業種別に見る月収13万円の傾向
- 月収13万円の年収偏差値(25歳の場合)
それでは順に見ていきましょう。
年代別・男女別の平均月収との比較
月収13万円が平均と比べてどの程度なのか、年代別・男女別に比較してみましょう。
【年代別・男女別の平均月収】
| 年齢層 | 賃金 | ||
|---|---|---|---|
| 男女計 | 男性 | 女性 | |
| 全体 | 330,400円 | 363,100円 | 275,300円 |
| ~19 | 199,300円 | 203,600円 | 191,300円 |
| 20~24 | 232,500円 | 234,200円 | 230,600円 |
| 25~29 | 267,200円 | 274,700円 | 258,100円 |
| 30~34 | 299,500円 | 316,300円 | 271,600円 |
| 35~39 | 328,700円 | 352,300円 | 284,300円 |
| 40~44 | 351,400円 | 385,500円 | 288,400円 |
| 45~49 | 372,700円 | 416,000円 | 298,000円 |
| 50~54 | 380,400円 | 428,200円 | 295,400円 |
| 55~59 | 392,000円 | 444,100円 | 294,000円 |
| 60~64 | 317,700円 | 344,700円 | 259,900円 |
| 65~69 | 275,500円 | 294,300円 | 234,000円 |
※出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」の「第2表 性、年齢階級別賃金、対前年増減率及び年齢階級間賃金格差」より
厚生労働省の令和6年賃金構造基本統計調査によると、全年齢・全性別の平均月収は約33万円で、月収13万円はこの半分以下の水準となります。10代の平均月収は約19.9万円、20代前半は約23.2万円であり、月収13万円はこれらの年代でも平均を下回っています。
また男性の平均月収は約36.3万円、女性は約27.5万円であり、月収13万円は女性の平均と比較しても低い水準といえます。
特に30代以上の平均月収とは大きな差があり、30代前半で約30万円、40代前半で約35万円となっており、月収13万円との差は歴然としています。
業種別に見る月収13万円の傾向
月収13万円はどのような業種に多いのでしょうか。
国税庁の令和5年民間給与実態統計調査によると、全業種の平均月給は約32万円ですが、業種によって大きな差があります。
【業種別の平均月収(額面)】
| 業種 | 月給 (給料・手当) |
年収 | うち賞与 |
|---|---|---|---|
| 全体平均 | 32万円 | 460万円 | 71万円 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 53万円 | 775万円 | 139万円 |
| 情報通信業 | 44万円 | 649万円 | 120万円 |
| 金融業、保険業 | 42万円 | 652万円 | 149万円 |
| 建設業 | 39万円 | 548万円 | 81万円 |
| 学術研究、専門・技術サービス業、教育・学習支援業 | 38万円 | 551万円 | 100万円 |
| 製造業 | 36万円 | 533万円 | 103万円 |
| 複合サービス業 | 35万円 | 535万円 | 117万円 |
| 運輸業、郵便業 | 34万円 | 473万円 | 63万円 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 34万円 | 469万円 | 63万円 |
| 医療、福祉 | 29万円 | 404万円 | 52万円 |
| 卸売業、小売業 | 28万円 | 387万円 | 54万円 |
| サービス業 | 28万円 | 378万円 | 43万円 |
| 農林水産・鉱業 | 24万円 | 333万円 | 44万円 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 21万円 | 264万円 | 16万円 |
※出典:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」の「(第 13 図)業種別の平均給与」より
※月給は「給料・手当 ÷ 12ヶ月」で算出
※正社員以外を含む
月収13万円に近い水準の業種としては、宿泊業・飲食サービス業の平均月給約21万円が挙げられます。また、農林水産・鉱業の約24万円も比較的近い水準です。
一方、電気・ガス・熱供給・水道業の平均月給は約53万円、金融業・保険業は約42万円と高水準です。月収13万円で働く場合、業種によっては平均よりもかなり低い位置にいることを認識し、スキルアップや転職を検討する材料にするとよいでしょう。
月収13万円の年収偏差値(25歳の場合)
月収13万円(年収156万円)の年収偏差値を見てみましょう。
【月収13万円の年収偏差値】※25歳の場合
| 月収額面 | 13万円 | |
|---|---|---|
| 年収額面 | 156万円 | |
| 年収偏差値 | 総合 | 27.0 |
| 高卒 | 24.3 | |
| 大卒 | 27.3 | |
| 中小企業 | 27.7 | |
※出典:年収偏差値チェッカー
年収偏差値は、25歳の場合、総合で27.0と平均(偏差値50)を大きく下回っています。
学歴別では高卒で24.3、大卒で27.3となっており、どの学歴でも平均より低い水準です。企業規模別では中小企業で27.7となっています。
年収偏差値が30を下回るということは、同年代の方と比較して収入が下位25%以下に位置することを意味します。
月収13万円の手取りは約11万円ですが、この収入水準は25歳としては決して高くないことがわかります。キャリアアップや収入増加を目指すなら、スキルアップや資格取得、転職などを検討する余地があるといえるでしょう。
【参考】月収別手取りの目安早見表
月収別に手取り額の目安がわかる早見表を作成しました。参考にしてみてください。
| 額面 | 手取り |
|---|---|
| 13万円 | 11万円 |
| 14万円 | 12万円 |
| 15万円 | 13万円 |
| 16万円 | 13万円 |
| 17万円 | 14万円 |
| 18万円 | 15万円 |
| 19万円 | 16万円 |
| 20万円 | 17万円 |
| 21万円 | 17万円 |
| 22万円 | 18万円 |
| 23万円 | 19万円 |
| 24万円 | 20万円 |
| 25万円 | 21万円 |
| 26万円 | 22万円 |
| 27万円 | 22万円 |
| 28万円 | 23万円 |
| 29万円 | 24万円 |
| 30万円 | 25万円 |
| 31万円 | 26万円 |
| 32万円 | 27万円 |
| 33万円 | 27万円 |
| 34万円 | 28万円 |
| 35万円 | 29万円 |
| 36万円 | 30万円 |
| 37万円 | 30万円 |
| 38万円 | 31万円 |
| 39万円 | 32万円 |
| 40万円 | 33万円 |
| 45万円 | 37万円 |
| 50万円 | 41万円 |
| 60万円 | 48万円 |
| 70万円 | 55万円 |
| 80万円 | 63万円 |
| 90万円 | 71万円 |
| 100万円 | 78万円 |
※出典:ファンジョブ|【2025年度対応】手取り計算|月給シミュレーション
※配偶者なし・40歳未満の場合
月収13万円のパートの働き方

月収13万円をパートタイマーとして稼ぐ場合、どのくらいの勤務時間が必要なのか、社会保険や扶養控除との関係はどうなるのかなど、具体的な働き方について解説します。
- パートで月収13万円を稼ぐための必要勤務時間
- 月収13万円のパート勤務と社会保険の関係
- パートで月収13万円を超えるとどうなる?扶養控除の壁
- 月収13万円のパートから正社員への転換のメリット
それでは順に見ていきましょう。
パートで月収13万円を稼ぐための必要勤務時間
月収13万円のパート勤務を実現するためには、時給と勤務時間のバランスが重要です。
月収13万円を得るためには、時給1,000円の場合は月130時間の勤務が必要です。週5日勤務であれば、1日約6時間の勤務となります。
時給1,200円なら月約108時間(1日約5時間)、時給1,500円なら月約87時間(1日約4時間)の勤務で月収13万円に達します。
月収13万円の手取りは約11万円ですが、社会保険に加入しない場合はより多くの手取りになる可能性があります。ただし、勤務時間が長くなると社会保険への加入が必要になる点には注意が必要です。
家庭と両立しながら月収13万円を目指す場合は、時給の高い仕事を選ぶことがポイントです。
月収13万円のパート勤務と社会保険の関係
月収13万円のパート勤務と社会保険の関係は重要なポイントです。
月収13万円でパート勤務をする場合、週の労働時間と事業所の規模によって社会保険の加入義務が変わります。
月収13万円の手取りを最大化したい場合、社会保険料(約19,000円程度)の負担を避けるため、週の勤務時間を調整することも一つの選択肢です。ただし、将来の年金受給額に影響するため、長期的な視点での判断が必要です。
パートで月収13万円を超えるとどうなる?扶養控除の壁
パートで働く方、特に配偶者の扶養に入っている方にとって、月収13万円は重要な分岐点になります。
配偶者控除の適用を受けるためには、年収103万円以下(月収約8.6万円以下)という条件があります。月収13万円(年収156万円)では、この基準を超えるため、配偶者の税金が増える可能性があります。
また、社会保険の扶養の場合は年収130万円(月収約10.8万円)が基準となり、月収13万円ではこの壁も超えてしまいます。
つまり月収13万円の手取りを得ると、自分で国民健康保険と国民年金を支払う必要が生じ、実質的な手取り額が減少することがあります。ただし、収入増による手取り減少は一時的なものであり、収入をさらに増やすことで、「解決できる壁」であることを理解しておきましょう。
月収13万円のパートから正社員への転換のメリット
月収13万円のパート勤務から正社員へ転換するメリットは大きいです。
- パート勤務から正社員へ転換するメリット
-
- 基本給が上昇する
- 賞与や各種手当が支給される可能性がある
- 雇用の安定性が高まる
- 昇給やキャリアアップの機会が増える
- 社会保険料の負担が軽減される
- 住宅ローンなどの審査において有利
現在の職場でパートから正社員への転換制度がある場合、積極的に検討してみる価値はあります。
月収13万円(手取り11万円)でのライフスタイルと生活設計

月収13万円で手取り約11万円という収入では、どのような生活レベルになるのでしょうか。
ここでは、一人暮らしの場合の家計モデルや可能な貯蓄プラン、住居費の目安などを解説します。
- 月収13万円の一人暮らしの家計簿モデル
- 月収13万円で可能な貯蓄プラン
- 月収13万円で賄える家賃の目安
それでは順に見ていきましょう。
月収13万円の一人暮らしの家計簿モデル
月収13万円で手取り約11万円の一人暮らしの場合、次のような家計簿モデルが考えられます。
【月収13万円の生活費内訳シミュレーション】
| 生活費 | 金額 |
|---|---|
| 家賃 | 30,000円 |
| 食費 | 25,000円 |
| 光熱費・通信費 | 15,000円 |
| 雑費(日用品等) | 5,000円 |
| 交通費・医療費・娯楽費 | 25,000円 |
| 貯金 | 10,000円 |
| 合計 | 110,000円 |
月収13万円の手取り約11万円から基本的な生活費を差し引くと、残りは約10,000円となり、これが貯蓄に回せる金額です。
ただし、この家計簿モデルは非常に節約した生活を前提としており、特に住居費は都市部では実現が難しい水準です。地方や郊外であれば可能性はありますが、都市部では家計の見直しやさらなる収入アップが必要でしょう。
月収13万円で可能な貯蓄プラン
月収13万円の手取り約11万円で、どの程度の貯蓄が可能でしょうか。
先述の家計モデルでは月約10,000円の貯蓄が可能ですが、これを最大化するためのプランを考えてみましょう。
月収13万円の手取りで厳しい家計の中でも、このように少額から貯蓄や積立投資を始めることで将来の安心につながります。
月収13万円で賄える家賃の目安
月収13万円の手取り約11万円で適正な家賃は、どのくらいでしょうか。
一般的に住居費は手取り収入の30%以内が理想とされています。月収13万円の手取り約11万円の場合、住居費の上限は約3万3,000円となります。
都市部では家賃だけでこの金額を超えてしまうことが多いため、郊外や地方都市の物件を検討するか、シェアハウスやルームシェアなどの選択肢も考慮する必要があるでしょう。
また、住居費には家賃以外にも水道光熱費や通信費などの固定費がかかることを忘れてはいけません。
- Point!
- 月収13万円で一人暮らしをする場合、住居費を抑えることが家計管理の最重要ポイントです。会社の家賃補助や寮制度がある場合は積極的に活用したり、初期費用を抑えられる物件を選ぶことも大切です。
月収13万円(手取り11万円)でも生活を充実させるポイント

月収13万円(手取り約11万円)という限られた収入でも、生活の質を高め満足度を上げるための4つのポイントをご紹介します。
- 支出の見直しと予算管理
- 賢い貯蓄と投資
- 収入を増やす工夫
- 生活に満足感をもたらすマインドセット
それでは順に見ていきましょう。
ポイント① 支出の見直しと予算管理
月収13万円の手取り約11万円で生活するためには、効率的な支出管理が欠かせません。
特に「固定費の最適化」と「変動費の計画的な使用」この2つのポイントを意識することで、限られた収入でも効率的な生活が可能になるでしょう。
具体的には、
- 携帯電話 → 格安SIMに切り替える
- サブスクリプションサービス → 本当に必要なものだけに絞る
- 食費 → 自炊をメインにして外食を減らす
といった取り組みにより、固定費と変動費の節約が可能です。
また予算管理には家計簿アプリを活用し、カテゴリー別に予算を設定して支出を可視化すると効果的です。月収13万円の手取りが11万円という厳しい家計でも、このような小さな節約の積み重ねが大きな違いを生みます。
ポイント② 賢い貯蓄と投資
月収13万円の手取り約11万円という収入でも、少額から始める貯蓄や投資は将来的な資産形成に大きな意味があります。
まずは生活防衛資金として、3ヶ月分の生活費(約33万円)を目標に積み立てることから始めます。
その後、長期的な資産形成として、つみたてNISAやiDeCoなどの制度を活用することを検討してみましょう。月々5,000円からでも始められるこれらの制度は、税制優遇もあり効率的な資産形成が可能です。
月収13万円の手取りでは大きな金額は難しいかもしれませんが、少額でも長期的・継続的に積み立てることで、複利の効果が期待できます。特に若いうちから始めることで、時間の力を最大限に活用することができるでしょう。
ポイント③ 収入を増やす工夫
月収13万円の手取り約11万円で生活するなら、支出の見直しと並行して収入を増やす工夫も大切です。
本業での収入アップを目指すなら、資格取得やスキルアップが効果的です。業界や職種によって有利な資格は異なりますが、取得によって数万円の月収アップが期待できるものもあります。
また、空いた時間を活用した副業も検討価値があり、月に数万円の追加収入を得ることも可能です。
- 在宅でできるWebライティングやデータ入力
- 休日を利用したアルバイト など
月収13万円の手取りに副業収入が加われば、生活の幅が広がります。
ただし、会社の副業規定やタイムマネジメントには十分な注意が必要です。無理のない範囲で収入増加を目指しましょう。
ポイント④ 生活に満足感をもたらすマインドセット
月収13万円の手取り約11万円という収入でも、充実した生活を送るためには前向きなマインドセットが重要です。
まず「お金をかけずに楽しむ方法」を意識的に探してみましょう。お金をかけずに充実した時間を過ごす方法は意外と多くあります。
- 地域の無料イベント
- 自然を楽しむアウトドア活動
- 図書館の活用 など
また「人と比べること」は不満の源になりがちです。SNSでの他者との比較ではなく、自分自身の成長や小さな幸せに目を向けることで満足度が高まります。
月収13万円の手取りという経済状況は一時的なものと捉え、今できる最善を尽くしながら将来のキャリアアップや収入増加に向けた計画を立てる前向きな姿勢が、現在の生活の質を高めることにもつながるでしょう。
月収13万円(手取り11万円)から収入アップを目指す方法

先述の月収13万円から手取り収入を増やす工夫について、さらに掘り下げて解説します。
- 月収13万円から収入アップする方法
-
- いまの仕事の収入を増やす
- 副業で収入を得る
- 転職して給与アップを目指す
それでは順に見ていきましょう。
いまの仕事の収入を増やす
月収13万円の手取り約11万円から現在の職場で収入アップを目指す方法はいくつかあります。
まず、昇給交渉は効果的な手段の一つです。自分の業績や貢献を具体的な数字で示しながら、適切なタイミングで上司に相談してみましょう。
また、資格取得やスキルアップも昇給につながります。業界に関連する資格や技能を習得することで、会社内での評価が上がり、給与アップの根拠となります。
さらに部署異動や職種転換を検討するのも一つの方法です。より専門性の高い部署や収益部門への異動によって、収入アップの可能性が広がります。
月収13万円の手取りでは生活が厳しいと感じる場合、まずは現在の職場で可能な収入アップの方法を積極的に模索してみることをおすすめします。
副業で収入を得る
月収13万円の手取り約11万円では十分な生活ができない場合、副業で収入を補うことも効果的な選択肢です。
副業を始める際は、まず自分のスキルを棚卸しして、活かせる分野を探しましょう。
- たとえば
- デザインやプログラミングのスキルがあれば、クラウドソーシングサイトで案件を受注することができます。
また、趣味や特技を活かした副業も人気です。
- たとえば
- 写真が好きならストックフォト販売など、好きなことで収入を得られる可能性があります。
オンラインでの活動も増えており、在宅で完結する副業の選択肢も広がっています。
月収13万円の手取りに月3〜5万円の副収入が加われば、生活の余裕が生まれるでしょう。
短時間・短期間のアルバイトを探すなら、土日のみの接客業や季節性の高い仕事などもおすすめです。
ただし副業を始める際には、以下の点に注意しましょう。
- 本業に支障が出ない範囲で行う
- 会社の就業規則(副業禁止など)を確認する
- 確定申告が必要になる場合がある
転職して給与アップを目指す
月収13万円の手取り約11万円では生活が厳しい場合、転職による収入アップも選択肢の一つです。
転職で成功するためには、まず市場価値の高いスキルを身につけることが重要です。以下のような専門知識は多くの業界で需要があります。
- IT関連スキル
- マーケティング
- 経理・財務 など
また、転職活動では転職エージェントの活用がおすすめです。プロの目線からキャリアプランのアドバイスを受けられるだけでなく、非公開求人の紹介も受けられます。月収13万円から20万円以上への年収アップを実現した事例も少なくありません。
転職先としては、成長産業や人手不足の業界を狙うと良いでしょう。以下のような業界は比較的給与水準が高く、未経験者の採用にも積極的です。
- IT・Web業界
- 介護・医療分野
- 物流業界 など
月収13万円の手取りからの大幅な収入アップを実現するためには、自己分析と市場分析を丁寧に行い、計画的な転職活動を進めることが成功の鍵となります。
みんなが使っている転職サービス上位6選 【1,382人に聞いた転職サービス利用状況】
実際に登録したことのある転職サービスについてアンケートをとりました。アンケート結果として、みんなが使っている転職サービスの上位6サービスは以下です。
- 1位|リクルートエージェント(821人)
- 2位|doda(564人)
- 3位|リクナビNEXT(389人)
- 4位|マイナビAGENT(312人)
- 5位|ビズリーチ(288人)
- 6位|エン転職(282人)
※転職サービスの利用アンケート(クラウドワークス) 回答数:1,382 / 集計期間:2024年09月19日~10月03日
1位|リクルートエージェント(利用回答数:821人) 圧倒的な求人数
「リクルートエージェント」は、求人数、安定したサービス品質で、まずは登録が必須のエージェントです。
まず何と言っても求人数が多いことがおすすめの理由として挙げられます。転職成功の実績も多く、優れているのは求人の数だけではありません。業界に精通したアドバイザーが在籍しているので、ぴったりの求人を見つけ出してくれます。求人やサービスの質・量ともにトップクラスで転職エージェントとしては定番・王道のサービスです。
営業・技術系を中心にあらゆる業種・職種をカバー。総合型ながら条件ごとに特化したページもあり、使いやすいのも人気の理由です。
- リクルートエージェントのおすすめポイント
- 求人数が圧倒的に多い
- 業界に精通したアドバイザーが在籍
- 条件ごとに特化したページがあり使いやすい
基本データ
| リクルートエージェント | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人474,685件/非公開求人399,542件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | エージェントサービス、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供 |
| 拠点 | 東京・北海道・宮城・宇都宮・さいたま・千葉・横浜・金沢・新潟・長野・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡 |
| URL | https://www.r-agent.com/ |
2位|doda(利用回答数:564人) エージェント/サイトの一体型で自分でも応募が可能
「doda」は、人材紹介・転職支援を行う大手「パーソルキャリア」が運営する総合型転職サイトです。エージェントサービスも利用できる点が人気の理由の1つになっています。
dodaも求人数が多く、非公開求人も条件が良いものが多いのが大きなポイントです。
また転職サイトと転職エージェントの一体型で、使い方の自由度が高いのもおすすめポイント。エージェントサービスでは専任のキャリアアドバイザーがサポートしてくれます。なお企業との対応は採用プロジェクト担当が行い、求職者と企業とでそれぞれ別のプロフェッショナルが対応します。
- dodaのおすすめポイント
- 非公開求人も好条件多数
- 転職サイトと転職エージェントの一体型で自由度が高い
- 専任のキャリアアドバイザーがサポート、企業は別のプロフェッショナルが対応
基本データ
| doda | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人262,342件/非公開求人31.049件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、年収査定、合格診断、レジュメビルダー、「自己PR」発掘診断、転職タイプ診断、はたらく女性のためのモヤモヤ解消診断、オンライン仕事力診断 |
| 拠点 | 東京・横浜・札幌・仙台・静岡・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・広島・福岡・鹿児島 |
| URL | https://doda.jp/consultant/ |
3位|リクナビNEXT(利用回答数:389人) 求人サイト群の中でも最大級の求人数と使いやすさ
「リクナビNEXT」は大定番の転職サイトで、サイトの見やすさや使いやすさにも定評があります。
エージェントなしの狭義の転職サイトの中では、求人数はトップクラス。新規の求人も多く、定期的にチェックすることで希望に合う求人に出会える可能性が高まります。
ツールが便利でサイトが使いやすいのも特長です。たとえば「気になるリスト」を使うと、気になる企業や後でゆっくりチェックしたい企業をリスト化できるほか、気になるに追加した企業から面接のオファーが来る可能性があります。
そのほか、公開求人・非公開求人の企業からオファーがもらえる「オファーを待つ」、自己分析ツール「グッドポイント診断」などがあります。
- リクナビNEXTのおすすめポイント
- サイトが見やすく使いやすい
- 狭義の転職サイトでは最大級の求人数
- 多くの人が利用している定番の転職サイト
基本データ
| リクナビNEXT | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人824,000件以上(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | オファー、気になるリスト、グッドポイント診断 |
| URL | https://next.rikunabi.com/ |
4位|マイナビAGENT(利用回答数:312人) 20代・30代の求人に強い
「マイナビAGENT」は、さまざまな転職サイトを運営している株式会社マイナビによる転職エージェントです。きめ細かいサポートが受けられると評価されています。
とくに20代・30代の求人が多いので、その世代の人にはおすすめです。また全国に拠点があり地方の求人も充実しているので、大都市圏以外で探している人にもぴったりです。
履歴書や職務経歴書のサポートも充実、初めての転職でも安心して利用できます。IT、営業など業種・職種別のサービスもあります。自分が探している業種と一致するならより探しやすくなるでしょう。
- マイナビAGENTのおすすめポイント
- 20代・30代の求人が多い
- 地方の求人も充実
- 履歴書や職務経歴書のサポートもあり安心
基本データ
| マイナビAGENT | |
|---|---|
| 公開求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| 拠点 | 拠点情報はこちらをご確認ください |
| URL | https://mynavi-agent.jp/ |
5位|ビズリーチ(利用回答数:288人) ハイクラス向けで企業からスカウトが受けられる
「ビズリーチ」は、ハイクラス求人が多いのが特徴の転職サイトです。厳密にはスカウト型のサイトで、エージェントではありません。登録するとヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられます。
最大の特長は、ハイクラス求人が多いことです。年収1,000万円以上の求人が1/3以上を占めています。一定以上の経験やスキルがある人が転職活動するのに役立つサービスです。
もう1つの大きな特徴として、登録するだけでヘッドハンターや企業からスカウトが届く点があります。以前は「スカウト」と「プラチナスカウト」の2種がありましたが、今は「プラチナスカウト」に一本化されています。プラチナスカウト経由での採用は全体の約70%。採用される可能性が高く、スカウトが届いたら大きなチャンスです。実際、企業からスカウトが届いた場合は書類選考が免除されます。
基本的にヘッドハンターはアドバイスをしませんが、場合によってはアドバイスをもらえることもあります。無料プランと有料プランがあり、有料プランは制限なく求人に応募できます。
- ビズリーチのおすすめポイント
- ヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられるハイクラス向けサイト
- 企業からプラチナスカウトが来た場合は即面接が可能
- 有料プランなら制限なく求人に応募できる
基本データ
| ビズリーチ | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人138,081件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、有料プラン(プレミアムステージ) |
| 拠点 | 東京・大阪・名古屋・福岡・静岡・広島 |
| URL | https://www.bizreach.jp/ |
6位|エン転職(利用回答数:282人) サイトが使いやすく情報も充実、利用者の満足度が高い

「エン転職」は、人材サービス大手の一つエン・ジャパン株式会社による転職サイトです。エージェントサービスも利用できます。
オリコン顧客満足度調査の転職サイト部門で、2018年から2024年まで7年連続で総合満足度No.1となっています。サイトの使いやすさは定評があり、自力で検索・応募するのに適したサービスです。口コミなどの情報も充実しており、企業間の比較検討もしやすくなっています。
さらに転職サイトのほか転職エージェントとしても利用することができ、非公開求人も多数保有しています。大手ですが最大手ほどでない規模で、きめ細かいサポートを受けることが可能。また女性向けのページのほか、ミドルや若手ハイキャリアなどに特化した関連サイトもあります。
- エン転職のおすすめポイント
- 2018年から2024年まで7年連続で総合満足度No.1
- サイトが使いやすいほか情報も充実
- 非公開求人も多数保有
基本データ
| エン転職 | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人152,678件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| URL | https://employment.en-japan.com/ |
まとめ

この記事では、月収13万円の手取り額を詳しく解説しました。
また月収13万円の手取り額の計算について、独身・既婚での違い、雇用形態による変動、そして税金・社会保険料の内訳までを具体的にご紹介しました。
月収13万円を全国平均や同年代と比較することで、どの程度の位置にあるのか、年収偏差値からも客観的に把握できたことでしょう。
月収13万円、手取り約11万円は決して余裕のある収入ではありませんが、この限られた収入の中でも生活を充実させることは可能です。また将来的な収入アップを目指すための具体的な方法として、昇給交渉やスキルアップ、転職、副業などの選択肢も検討してみましょう。
この記事を参考に、今後の生活設計やキャリアプランをより具体的に描いてみてください!