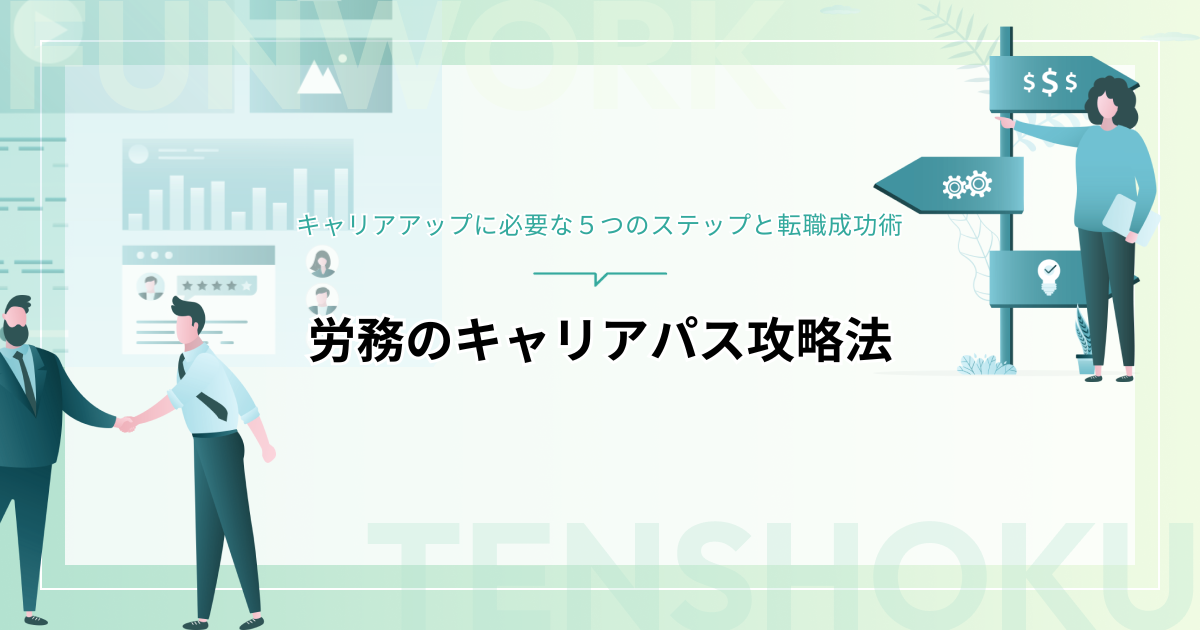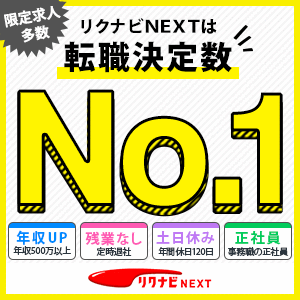- この記事でわかること
- 労務のキャリアパス事例:新卒入社組から他職種からのキャリアチェンジ事例も紹介
- 労務でのキャリアパスに向いている人の特徴3選を紹介
- 労務職に求められるスキルと資格を解説
- 労務でキャリアアップするための5つのステップ、基礎スキルの習得から始めよう
- キャリアプランや面接での例文を具体例で紹介
- 労務のキャリアパスを目指すなら!転職サービス上位6選 【1,382人に聞いた転職サービス利用状況】
労務でのキャリアパスに迷っていませんか?この記事では、労務職のキャリアアップに必要な5つのステップと、転職成功のためのポイントを詳しく解説しています。
労務職は、企業の人材マネジメントの要として今後ますます重要性が高まる職種です。労務職を極めるためには、具体的なキャリアパスや必要なスキル、資格取得のタイミングなど、転職前に知っておくべきことは数多くあります。
未経験から労務へのキャリアチェンジ転職を考えている方も、より上位のポジションを目指している方も、ぜひ最後まで読んで参考にしてください!
【まずはチェック!!】求人数の多い大手転職サービスが人気!おすすめの求人数比較表!
大手転職サービスの取り扱い求人件数を独自調査。転職サービスの専任担当者が最新の取り扱い求人情報を確認し、求人数比較表にまとめています。転職活動にあたってはエージェントやサイトを積極的に活用しましょう。まずは一通りサービスを体験してみて自分にあったサービスを見つけることをおすすめします。比較表はこちら。
右にスクロールできます
| おすすめ | リクルートエージェント | doda | マイナビAGENT | リクナビNEXT | パソナキャリア | ビズリーチ | リクルートダイレクトスカウト | マイナビ転職 | エン転職 | JACリクルートメント | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特色 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | 全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス・女性向け | ハイクラス全年代・業界 | ハイクラス・全年代 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス | 全業界・首都圏 |
| 求人数 | 629,925件 | 253,718件 | 非公開 | 1,093,000件以上 | 49,570件 | 172,146件 | 548,725件 | 非公開 | 97,835件 | 22,339件 | 2,523件 |
| 求人の豊富さ | |||||||||||
| ポイント | 非公開求人も多数 | エージェント・サイト両方の利用が可能 | 地方の求人も充実 | 企業からのオファーあり | オファーも受けられる | 2種類のスカウトあり | 登録するとスカウトが多数届く | スカウトサービスあり | 利用者の満足度が高い | コンサルタントのサポートが手厚い | とくにエンジニア、20代、女性の求人に強み |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
2025年9月20日調査:各転職エージェントの取り扱い求人件数・各転職サイトの掲載求人数
Contents
労務のキャリアパス概要

労務職のキャリアパスは、人事労務の専門性を活かしながら着実にステップアップできる魅力的な道筋です。企業の人材マネジメントの要となるポジションだからこそ、将来性も期待できる職種といえるでしょう。
この章では、新卒での入社から管理職までの一般的なキャリアの流れや、労務職としての役割の重要性について詳しく解説します。
- 労務とは?その役割と重要性
- キャリアパスの全体像
- 一般的なステップアップの流れ
それでは順に見ていきましょう。
労務とは?その役割と重要性
労務職は、企業における人材マネジメントの要として重要な役割を担っています。労務の主な仕事内容は、従業員の労働条件の管理や、給与計算、社会保険の手続きなど多岐にわたります。近年では働き方改革への対応や、労働関連法規の改正に伴うコンプライアンス対応なども重要な責務となっています。
企業にとって人材は最も重要な経営資源の一つです。そのため、労務職は単なる事務作業を行うだけでなく経営戦略を支える重要なポジションとして認識されています。
労務は従業員が安心して働ける環境を整備し、
生産性の向上に貢献することで企業の持続的な成長を支えているのです。
キャリアパスの全体像
労務職のキャリアパスは、通常、実務担当者からスタートしチームリーダー、マネージャー、人事労務部長といった具合にステップアップしていきます。
キャリアの初期段階では、給与計算や社会保険手続きなどの基本的な実務スキルを習得します。その後、労働法規や人事制度の設計など、より専門的な知識を身につけていきます。
また企業規模や業界によって求められる専門性は異なりますが、一般的に5年程度の経験を積むと、後進の指導や人事制度の企画立案にも携わるようになります。
10年以上のキャリアを積むと、経営層との折衝や人事戦略の立案など、より広い視野での業務が求められるようになります。
一般的なステップアップの流れ
入社後3年程度は、給与計算や各種手続きなどの実務作業を通じて基礎を固める時期です。この間に社会保険労務士の資格取得を目指す人も多くいます。その後、チームリーダーとして実務の取りまとめを担当し部下の教育も行うようになります。
経験を積むにつれて、労務関連の企画業務や制度設計にも携わるようになります。
入社後7〜10年程度でマネージャー職に就き、
部署全体のマネジメントを任されるケースが一般的です。
さらにキャリアを重ねると、人事労務部門の責任者として、経営層との連携を図りながら、会社全体の人事戦略の立案・実行を担うようになります。
労務のキャリアパスの具体例

労務職のキャリアパスは、新卒入社と転職組で異なる特徴があります。また企業規模によっても求められる役割や昇進スピードが変わってきます。
ここでは、実際の事例を基に様々なキャリアパスの可能性について解説していきます。
- 新卒入社組のキャリアパス事例
- 他職種からキャリアチェンジ転職組のキャリアパス事例
- 企業規模別のキャリアパスの違い
それでは順に見ていきましょう。
新卒入社組のキャリアパス事例
新卒入社の場合、計画的なキャリア形成が可能です。入社1〜2年目は給与計算や勤怠管理などの基本業務を担当し、3年目以降は社会保険関連の業務も任されるようになります。
5年目頃には実務のリーダーとして後輩の指導も行うようになり、
この頃までに社会保険労務士の資格取得を目指す人が多いでしょう。
7年目以降はチームリーダーとして、より責任のある立場で業務を遂行します。10年目前後でマネージャーに昇進し部門全体のマネジメントや人事制度の企画立案に携わるようになります。
このように、段階的にスキルと責任を積み上げていくことで着実なキャリアアップが実現できます。
他職種からキャリアチェンジ転職組のキャリアパス事例
他職種からキャリアチェンジする転職の場合、これまでの経験を活かしながら労務の専門性を身につけていきます。
たとえば営業職からの転職者は、コミュニケーション能力を活かして従業員との関係構築がスムーズにできるケースが多いです。経理職からの転職者は、数字への強みを活かして給与計算や労務コストの分析で即戦力となれます。
転職後は、まず労務の基礎知識の習得に3〜6ヶ月程度を要しますが、前職での経験を活かせる部分も多いため、1年程度で一通りの業務をこなせるようになります。
その後は、社会保険労務士の資格取得などを通じて専門性を高め、3年程度で中堅社員として活躍できるようになります。
企業規模別のキャリアパスの違い
大手企業では、専門性の高い業務に特化できる一方、昇進には時間がかかる傾向があります。たとえば給与計算チーム、労務管理チーム、制度企画チームなど、職務が細分化されており、各分野での専門性を高めやすい環境です。
- NOTE
- ただしマネージャー職への昇進には通常10年以上の経験が必要です。
一方、中小企業では、より幅広い業務を担当することになります。給与計算から労務管理、採用活動まで、人事労務全般を一気通貫で経験できます。そのため、総合的なスキルを身につけやすく、比較的早期の段階でマネジメント職に就けるチャンスがあります。ただし専門的な知識やスキルは自己啓発で補う必要があります。
労務でのキャリアパスに向いている人は?

続いて、労務職に向いている人の特徴や必要なスキル、また向いていないと感じる人への対策についても詳しく解説していきます。
- 労務職に向いている人
-
- 労務職に求められる適性と性格
-
- 労務職に必要なスキルと知識
-
- 向いていない人の特徴と対策
それでは順に見ていきましょう。
労務職に求められる適性と性格
労務職に向いている人の特徴として、まず「誠実さ」と「正確性」が挙げられます。給与計算や社会保険の手続きなど、ミスが許されない業務が多いためです。
また従業員からの相談対応も多いため、
「聞き上手」で「共感力」のある人も労務職との相性が良いでしょう。
さらに法改正への対応や制度変更など、常に新しい知識を吸収する必要があるため、「好奇心旺盛」で「学習意欲の高い」性格も重要です。また時には従業員と会社の間に立って調整を行う必要があるため、「バランス感覚」のある人も労務職に適していると言えます。
労務職に求められるスキルと知識
労務職に求められるスキルは、大きく「実務スキル」と「対人スキル」に分けられます。
実務スキルとしては、労働法規の理解や給与計算の知識、ExcelなどのPC操作スキルが必須です。また人事システムの操作や各種書類の作成能力も重要になります。
対人スキルとしては、コミュニケーション能力が最も重要です。従業員からの相談対応や、経営層への提案、社外の専門家との折衝など、様々な場面でコミュニケーション力が試されます。
また問題解決力やプレゼンテーション能力も、キャリアの発展に伴って必要性が増していきます。
向いていない人の特徴と対策
細かい作業が苦手な人や、数字に苦手意識がある人は、労務職に向いていないと感じるかもしれません。また人との関わりを避けたい人や、ストレス耐性の低い人も、労務職での活躍は難しいかもしれません。
しかしこれらの特徴は、適切な対策を取ることで克服可能です。
たとえばチェックリストを活用して作業の正確性を高めたり、
給与計算ソフトの操作に慣れることで数字への苦手意識を克服したりできます。
またコミュニケーションスキルは研修や実践を通じて向上させることができます。大切なのは、自己の課題を認識し改善に向けて継続的に努力することです。
労務でのキャリアパスに必須のスキル

労務職で成功するためには、実務能力に加えて、高度なコミュニケーション能力や問題解決能力が不可欠です。特に管理職へのキャリアアップを目指す場合、これらの能力は重要な評価ポイントとなります。
ここでは、労務職で求められる3つの重要な能力について詳しく解説していきます。
- 労務職で求められる3つの必須スキル
-
- コミュニケーション能力
-
- 法律・制度の理解力
-
- 問題解決能力とリーダーシップ
それでは順に見ていきましょう。
コミュニケーション能力
労務職では、様々な立場の人々と関わる機会が多いため、高いコミュニケーション能力が求められます。従業員からの相談対応では、相手の話をしっかりと聴き、適切なアドバイスを提供する必要があります。また経営層への報告や提案では、簡潔かつ論理的な説明が求められます。
特に重要なのは、「傾聴力」と「説明力」です。従業員の悩みや要望をしっかりと受け止め、それを制度や規則の範囲内で解決に導く能力が必要です。
また複雑な制度改定や規則変更を、わかりやすく説明する力も重要です。社内外の関係者との良好な関係構築も、スムーズな業務遂行には欠かせません。
法律・制度の理解力
労務職では、労働法規や社会保険制度など、多岐にわたる法律や制度の理解が必要です。これらは頻繁に改正されるため、常に最新の情報をキャッチアップする必要があります。また法改正が自社の制度にどのような影響を与えるかを分析し適切な対応を取ることも求められます。
- NOTE
- 実務では、労働基準法、労働契約法、社会保険関連法規などの基本的な法律を理解することはもちろん、各種助成金制度や税制についても知識が必要です。
さらに自社の就業規則や人事制度を熟知しそれらを適切に運用・改定できる能力も重要です。
問題解決能力とリーダーシップ
労務の現場では、日々様々な問題や課題が発生します。これらに対して、適切な解決策を見出し実行に移す能力が求められます。また部下や後輩の育成、チームのマネジメントなど、リーダーシップを発揮する場面も多くなります。
問題解決では、課題の本質を見極め、関係者の利害関係を調整しながら、最適な解決策を導き出す必要があります。また施策の実行においては、チームメンバーの協力を得ながら、計画的に進めていく能力が重要です。
さらに予防的な対応として、潜在的なリスクを把握し事前に対策を講じる視点も求められます。
労務でのキャリアパス形成に必要な資格

労務職でキャリアアップする上で、専門資格の取得は重要なステップとなります。資格は専門知識の証明になるだけでなく実務能力の向上にも直結します。
ここでは、労務職に関連する資格について、その重要性や取得のタイミングを詳しく解説します。
- 労務職に必須の資格
- キャリアアップに有利な資格
- 取得推奨時期と学習方法
それでは順に見ていきましょう。
労務職に必須の資格
労務職において最も重要な資格は「社会保険労務士」です。この資格は、労働および社会保険に関する法律・実務の専門家として認められる国家資格です。
企業内での昇進や転職時の評価においても、
大きなアドバンテージとなります。
また給与計算実務能力検定も、実務スキルを証明する上で重要な資格です。
特に中堅以上のポジションを目指す場合、社会保険労務士資格は事実上必須と言えます。この資格を持っていることで専門的な知識と実務能力の両面で高い評価を得ることができます。また社内での発言力も増し、より重要な案件を任されるようになります。
キャリアアップに有利な資格
社会保険労務士以外にも、キャリアアップに役立つ資格がいくつかあります。
たとえば「衛生管理者」は従業員の安全衛生管理に関する資格で、特に製造業では重宝されます。また「ファイナンシャル・プランナー」は、福利厚生制度の設計や従業員への金融教育を行う際に役立ちます。
さらに「キャリアコンサルタント」の資格も注目されています。従業員のキャリア開発支援や、メンタルヘルスケアの観点からも有用です。「人事労務検定」や「ビジネス法務検定」なども、実務能力の向上や専門性のアピールに効果的です。
取得推奨時期と学習方法
資格取得は、キャリアステージに応じて計画的に進めることが重要です。
入社1〜3年目では、給与計算実務能力検定などの実務に直結する資格から取得を始めるのが一般的です。その後、3〜5年目で社会保険労務士の受験に着手し、できるだけ早期の合格を目指します。
学習方法としては、通信講座や専門学校での講座受講が一般的です。
最近では、オンライン学習プラットフォームも充実してきており、
仕事と両立しやすい環境が整っています。
また職場の先輩や同僚と勉強会を組織するなど、モチベーションを維持する工夫も効果的です。
労務でキャリアアップするための5つのステップ

労務職のキャリアパスを確実に歩むためには、段階的なスキルアップと経験の蓄積が重要です。
ここでは、労務でキャリアアップするための5つのステップについて、それぞれの段階で必要な取り組みと目標を詳しく解説します。
- キャリアアップするための5つのステップ
-
- 基礎スキルの習得
-
- 資格取得による専門性の向上
-
- 実務経験の蓄積
-
- マネジメント能力の開発
-
- 戦略的思考力の醸成
それでは順に見ていきましょう。
ステップ1|基礎スキルの習得
入社から3年程度は、労務実務の基礎固めに注力する期間です。
給与計算や社会保険の手続き、勤怠管理など、日常的な実務作業を確実に行えるようになることが目標です。この時期は特にミスを恐れずに積極的に実務を経験することが重要です。
また社内システムの操作方法や書類作成のルールなど、会社特有の業務プロセスもしっかりと習得します。先輩社員への質問や、マニュアルの確認を通じて、基本的な業務フローを体得していきましょう。
ステップ2|資格取得による専門性の向上
基礎スキルを身につけた後は、社会保険労務士などの専門資格の取得を目指します。
資格取得の過程で得られる体系的な知識は、実務の質を高めることにもつながります。また資格保有者として、より責任のある業務を任されるようになります。
資格取得には計画的な学習が欠かせません。日々の業務と並行して学習時間を確保するため、スケジュール管理を徹底することが重要です。
また学習グループへの参加や、オンライン講座の活用など、
効率的な学習方法を選択しましょう。
ステップ3|実務経験の蓄積
実務経験を通じて、法律や制度の知識を実践的なスキルへと昇華させていきます。
特に従業員からの相談対応や、労務トラブルの解決など、実際のケースに携わることで応用力と判断力が養われます。
この段階では、できるだけ多様な案件を経験することが重要です。給与制度の改定プロジェクトや、就業規則の見直しなど、様々な業務に積極的に関わることで総合的な実務能力を高めることができます。
ステップ4|マネジメント能力の開発
キャリアの中期段階では、チームリーダーやマネージャーとしての役割を担うことになります。この時期は、個人の実務能力に加えてチームマネジメントのスキルが求められます。部下の育成や業務の配分、進捗管理など、マネジメントの基本を習得します。
また他部門との調整や、経営層への報告・提案など、より広い視野での業務遂行が必要になります。コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力の向上にも、意識的に取り組むことが大切です。
ステップ5|戦略的思考力の醸成
キャリアの集大成として、経営戦略を理解しそれに基づいた人事労務戦略を立案・実行できる能力を身につけます。企業の経営課題を把握し人事労務の観点からソリューションを提案できる存在を目指します。
この段階では、業界動向や他社の取り組みにも目を向け、広い視野で施策を検討することが重要です。またデジタル化やグローバル化など、新しい潮流への対応も求められます。常に学び続ける姿勢を持ち、変化する環境に適応していく必要があります。
このように、5つのステップを着実に積み上げることで労務のプロフェッショナルとしてのキャリアを築くことができます。
各ステップで求められるスキルと知識を意識的に習得し、
計画的にキャリアを形成していくことが成功への近道となります。
労務職の転職成功術① キャリアプランの例文

労務職への転職では、明確なキャリアプランの提示が求められます。特に面接時には、自身の経験と将来のビジョンを説得力のある形で伝える必要があります。
ここでは、労務のキャリアプランの作成方法と具体的な例文を紹介します。
- 労務のキャリアプランの書き方
- 労務のキャリアプラン例文
- 労務のキャリアプランNG例文
それでは順に見ていきましょう。
労務のキャリアプランの書き方
キャリアプランは、短期目標(1〜3年)、中期目標(3〜5年)、長期目標(5〜10年)の3段階で構成するのが効果的です。
各段階で、具体的なスキルアップ計画や資格取得計画を盛り込むことで実現可能性の高いプランとなります。また自身の強みや経験を活かせる点を明確に示すことも重要です。
特に重要なのは、企業の求める人材像と自身のキャリアプランを結びつけることです。たとえば「御社の〇〇という課題に対して、私の△△という経験を活かしながら、□□の専門性を身につけていきたい」といった具体的な展望を示すことで採用担当者の共感を得やすくなります。
労務のキャリアプラン例文
労務へキャリアチェンジする場合、キャリアプランには前職での経験を活かしつつ、労務職としての専門性をどう身につけていくかを具体的に示すことが重要です。
特に資格取得計画や数値目標を含めることで、本気度と実現可能性を印象付けることができます。
また、企業の課題解決にどう貢献できるかという視点も
忘れずに盛り込みましょう。
営業職からの転職例
経理職からの転職例
労務のキャリアプランNG例文
労務のキャリアプランを伝える際によく見られる失敗は、具体性の不足と企業視点の欠如です。「やってみたい」という興味だけの表現や、単なる地位や役職への言及は説得力に欠けます。
代わりに、具体的なスキルアップ計画とそれを企業でどう活かすかを示しましょう。
NG例1
改善例
NG例2
改善例
労務職の転職成功術② キャリアビジョンの面接での答え方<例文あり>

面接でよく聞かれる「労務のキャリアビジョン」の質問には、専門性の向上と組織への貢献をバランスよく語ることが大切です。
ここでは、面接官の意図を理解し、効果的なキャリアビジョンの回答方法を解説します。
- 面接官が知りたいポイント
- 面接でのキャリアビジョンの回答例文
- 印象的な答え方のコツ
それでは順に見ていきましょう。
面接官が知りたいポイント
面接官はキャリアプランの質問を通して、「あなたが当社でどこまで活躍できるか」を見極めたいと考えています。
つまり単なる経歴や志望動機の確認ではなく、応募者の将来性や組織への貢献意欲を総合的に判断する場面となります。したがって、以下のポイントを意識した回答を準備しましょう。
- 面接官が知りたいポイント
-
- 継続性
- 成長意欲
- 組織への貢献度
特に労務職は組織の中核を担う存在となるため、長期的なコミットメントが求められます。転職理由と将来のビジョンの一貫性も重視されます。「なぜ労務職を選んだのか」「どのように組織に貢献したいと考えているのか」という点について、説得力のある説明ができることが重要です。
面接でのキャリアビジョンの回答例文
面接で労務のキャリアビジョンを伝える際は、以下の要素を含めるようにします。
- 具体的な数値目標
- 時期、期限
- 習得したいスキル
- 組織への貢献方法
また自身の経験や強みを踏まえた実現可能性の高いビジョンを示すことで、説得力が増します。
一般的な回答例
経験者の回答例
印象的な答え方のコツ
キャリアビジョンを語る際は、「具体性」「実現可能性」「熱意」の3つが重要です。
時期や目標を明確に示しながら、そこに至るまでのプロセスも説明できると良いでしょう。
また自己の成長だけでなく組織への貢献を意識した内容にすることでより説得力が増します。
質問の意図を理解し回答の構成を「現在の状況」「短期目標」「長期目標」の順で組み立てると、論理的な説明が可能になります。また企業研究を十分に行い、その企業特有の課題や方針に触れることでより具体的な貢献イメージを示すことができます。
みんなが使っている転職サービス上位6選 【1,382人に聞いた転職サービス利用状況】
実際に登録したことのある転職サービスについてアンケートをとりました。アンケート結果として、みんなが使っている転職サービスの上位6サービスは以下です。
- 1位|リクルートエージェント(821人)
- 2位|doda(564人)
- 3位|リクナビNEXT(389人)
- 4位|マイナビAGENT(312人)
- 5位|ビズリーチ(288人)
- 6位|エン転職(282人)
※転職サービスの利用アンケート(クラウドワークス) 回答数:1,382 / 集計期間:2024年09月19日~10月03日
1位|リクルートエージェント(利用回答数:821人) 圧倒的な求人数
「リクルートエージェント」は、求人数、安定したサービス品質で、まずは登録が必須のエージェントです。
まず何と言っても求人数が多いことがおすすめの理由として挙げられます。転職成功の実績も多く、優れているのは求人の数だけではありません。業界に精通したアドバイザーが在籍しているので、ぴったりの求人を見つけ出してくれます。求人やサービスの質・量ともにトップクラスで転職エージェントとしては定番・王道のサービスです。
営業・技術系を中心にあらゆる業種・職種をカバー。総合型ながら条件ごとに特化したページもあり、使いやすいのも人気の理由です。
- リクルートエージェントのおすすめポイント
- 求人数が圧倒的に多い
- 業界に精通したアドバイザーが在籍
- 条件ごとに特化したページがあり使いやすい
基本データ
| リクルートエージェント | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人474,685件/非公開求人399,542件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | エージェントサービス、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供 |
| 拠点 | 東京・北海道・宮城・宇都宮・さいたま・千葉・横浜・金沢・新潟・長野・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡 |
| URL | https://www.r-agent.com/ |
2位|doda(利用回答数:564人) エージェント/サイトの一体型で自分でも応募が可能
「doda」は、人材紹介・転職支援を行う大手「パーソルキャリア」が運営する総合型転職サイトです。エージェントサービスも利用できる点が人気の理由の1つになっています。
dodaも求人数が多く、非公開求人も条件が良いものが多いのが大きなポイントです。
また転職サイトと転職エージェントの一体型で、使い方の自由度が高いのもおすすめポイント。エージェントサービスでは専任のキャリアアドバイザーがサポートしてくれます。なお企業との対応は採用プロジェクト担当が行い、求職者と企業とでそれぞれ別のプロフェッショナルが対応します。
- dodaのおすすめポイント
- 非公開求人も好条件多数
- 転職サイトと転職エージェントの一体型で自由度が高い
- 専任のキャリアアドバイザーがサポート、企業は別のプロフェッショナルが対応
基本データ
| doda | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人262,342件/非公開求人31.049件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、年収査定、合格診断、レジュメビルダー、「自己PR」発掘診断、転職タイプ診断、はたらく女性のためのモヤモヤ解消診断、オンライン仕事力診断 |
| 拠点 | 東京・横浜・札幌・仙台・静岡・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・広島・福岡・鹿児島 |
| URL | https://doda.jp/consultant/ |
3位|リクナビNEXT(利用回答数:389人) 求人サイト群の中でも最大級の求人数と使いやすさ
「リクナビNEXT」は大定番の転職サイトで、サイトの見やすさや使いやすさにも定評があります。
エージェントなしの狭義の転職サイトの中では、求人数はトップクラス。新規の求人も多く、定期的にチェックすることで希望に合う求人に出会える可能性が高まります。
ツールが便利でサイトが使いやすいのも特長です。たとえば「気になるリスト」を使うと、気になる企業や後でゆっくりチェックしたい企業をリスト化できるほか、気になるに追加した企業から面接のオファーが来る可能性があります。
そのほか、公開求人・非公開求人の企業からオファーがもらえる「オファーを待つ」、自己分析ツール「グッドポイント診断」などがあります。
- リクナビNEXTのおすすめポイント
- サイトが見やすく使いやすい
- 狭義の転職サイトでは最大級の求人数
- 多くの人が利用している定番の転職サイト
基本データ
| リクナビNEXT | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人824,000件以上(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | オファー、気になるリスト、グッドポイント診断 |
| URL | https://next.rikunabi.com/ |
4位|マイナビAGENT(利用回答数:312人) 20代・30代の求人に強い
「マイナビAGENT」は、さまざまな転職サイトを運営している株式会社マイナビによる転職エージェントです。きめ細かいサポートが受けられると評価されています。
とくに20代・30代の求人が多いので、その世代の人にはおすすめです。また全国に拠点があり地方の求人も充実しているので、大都市圏以外で探している人にもぴったりです。
履歴書や職務経歴書のサポートも充実、初めての転職でも安心して利用できます。IT、営業など業種・職種別のサービスもあります。自分が探している業種と一致するならより探しやすくなるでしょう。
- マイナビAGENTのおすすめポイント
- 20代・30代の求人が多い
- 地方の求人も充実
- 履歴書や職務経歴書のサポートもあり安心
基本データ
| マイナビAGENT | |
|---|---|
| 公開求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| 拠点 | 拠点情報はこちらをご確認ください |
| URL | https://mynavi-agent.jp/ |
5位|ビズリーチ(利用回答数:288人) ハイクラス向けで企業からスカウトが受けられる
「ビズリーチ」は、ハイクラス求人が多いのが特徴の転職サイトです。厳密にはスカウト型のサイトで、エージェントではありません。登録するとヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられます。
最大の特長は、ハイクラス求人が多いことです。年収1,000万円以上の求人が1/3以上を占めています。一定以上の経験やスキルがある人が転職活動するのに役立つサービスです。
もう1つの大きな特徴として、登録するだけでヘッドハンターや企業からスカウトが届く点があります。以前は「スカウト」と「プラチナスカウト」の2種がありましたが、今は「プラチナスカウト」に一本化されています。プラチナスカウト経由での採用は全体の約70%。採用される可能性が高く、スカウトが届いたら大きなチャンスです。実際、企業からスカウトが届いた場合は書類選考が免除されます。
基本的にヘッドハンターはアドバイスをしませんが、場合によってはアドバイスをもらえることもあります。無料プランと有料プランがあり、有料プランは制限なく求人に応募できます。
- ビズリーチのおすすめポイント
- ヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられるハイクラス向けサイト
- 企業からプラチナスカウトが来た場合は即面接が可能
- 有料プランなら制限なく求人に応募できる
基本データ
| ビズリーチ | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人138,081件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、有料プラン(プレミアムステージ) |
| 拠点 | 東京・大阪・名古屋・福岡・静岡・広島 |
| URL | https://www.bizreach.jp/ |
6位|エン転職(利用回答数:282人) サイトが使いやすく情報も充実、利用者の満足度が高い

「エン転職」は、人材サービス大手の一つエン・ジャパン株式会社による転職サイトです。エージェントサービスも利用できます。
オリコン顧客満足度調査の転職サイト部門で、2018年から2024年まで7年連続で総合満足度No.1となっています。サイトの使いやすさは定評があり、自力で検索・応募するのに適したサービスです。口コミなどの情報も充実しており、企業間の比較検討もしやすくなっています。
さらに転職サイトのほか転職エージェントとしても利用することができ、非公開求人も多数保有しています。大手ですが最大手ほどでない規模で、きめ細かいサポートを受けることが可能。また女性向けのページのほか、ミドルや若手ハイキャリアなどに特化した関連サイトもあります。
- エン転職のおすすめポイント
- 2018年から2024年まで7年連続で総合満足度No.1
- サイトが使いやすいほか情報も充実
- 非公開求人も多数保有
基本データ
| エン転職 | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人152,678件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| URL | https://employment.en-japan.com/ |
まとめ

この記事では、労務職のキャリアパスについて、基礎から応用まで詳しく解説してきました。労務でキャリアアップするための5つのステップをまとめると、以下のとおりです。
- 労務で成功するための5つのステップ
- ①基礎スキルの習得:入社後3年程度は、給与計算や社会保険手続きなど、基本的な実務スキルを確実に身につけます。
- ②資格取得による専門性の向上:社会保険労務士などの資格取得を通じて、専門知識を深めます。
- ③実務経験の蓄積:様々な案件に携わり、実践的なスキルと問題解決能力を養います。
- ④マネジメント能力の開発:チームリーダーやマネージャーとして、組織マネジメントのスキルを磨きます。
- ⑤戦略的思考力の醸成:経営視点を持ち、人事戦略の立案・実行ができる人材を目指します。
労務職の重要性は、今後ますます高まると予想されます。働き方改革の推進や多様な働き方への対応など、新たな課題が次々と登場しています。またデジタル化の進展により従来の実務作業は効率化され、より戦略的な業務にシフトしていくことが予想されます。
労務に携わる方は、このような変化に対応するため、デジタルリテラシーの向上や戦略的思考力の強化が求められます。また従業員のエンゲージメント向上や組織の持続的成長を支える役割も期待されています。
常に新しい知識とスキルを吸収し変化に対応できる柔軟性を持つことが、今後の労務職には不可欠です。