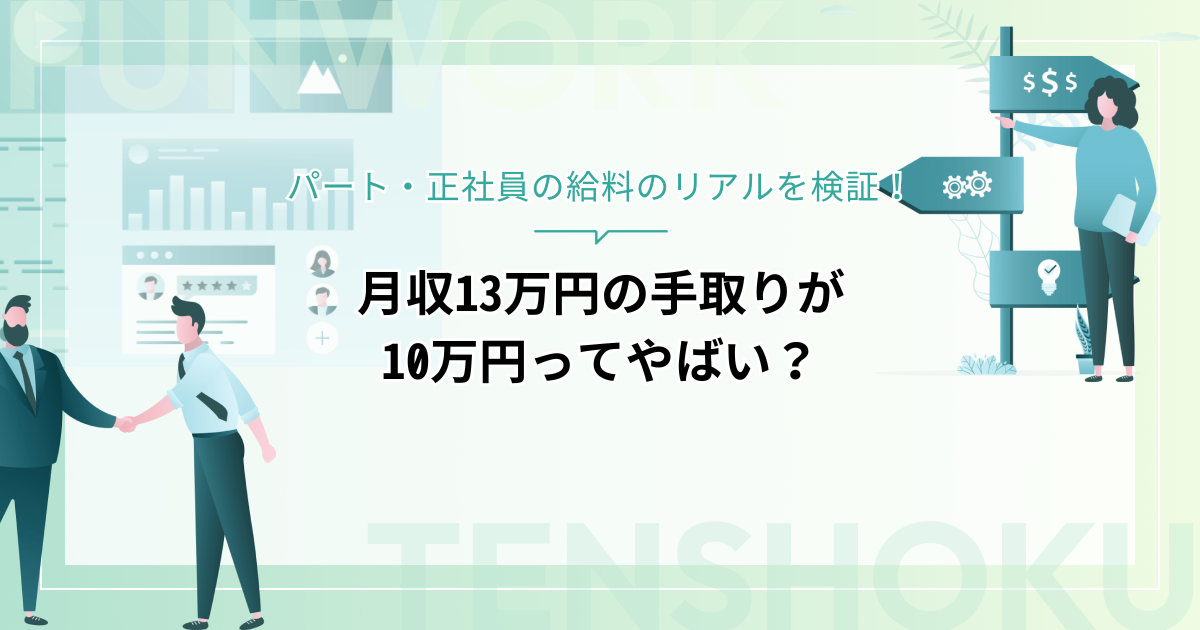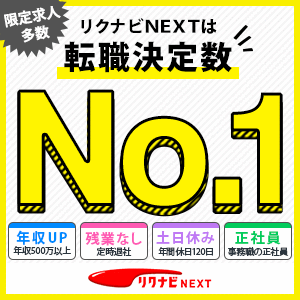- この記事でわかること
- 月収13万円の手取り額と実際の生活水準
- 手取り13万円での生活費シミュレーションと節約術
- パートと正社員の違い、どちらが得?手取り13万円から収入を増やす方法
- 社会保険・年金・老後資金の影響と対策
- 手取りを増やすなら転職もあり!みんなが使う転職サービス上位6選 【1,382人に聞いた転職サービス利用状況】
月収13万円の手取り額は約10万円です。これを聞いて、「月収13万円で手取り10万円って、やばい?生活できるの?」と思った方も多いのでは?
この記事ではそんな疑問にお答えします。社会保険や税金など、給料から引かれるものは一体どれくらい?一人暮らしでも生活できる?パートと正社員、どちらがお得?など、気になる疑問を徹底解説。
さらに手取り13万円の生活レベルや月々の貯金、投資、具体的な収入アップ方法までご紹介します!
【まずはチェック!!】求人数の多い大手転職サービスが人気!おすすめの求人数比較表!
大手転職サービスの取り扱い求人件数を独自調査。転職サービスの専任担当者が最新の取り扱い求人情報を確認し、求人数比較表にまとめています。転職活動にあたってはエージェントやサイトを積極的に活用しましょう。まずは一通りサービスを体験してみて自分にあったサービスを見つけることをおすすめします。比較表はこちら。
右にスクロールできます
| おすすめ | リクルートエージェント | doda | マイナビAGENT | リクナビNEXT | パソナキャリア | ビズリーチ | リクルートダイレクトスカウト | マイナビ転職 | エン転職 | JACリクルートメント | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特色 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | 全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス・女性向け | ハイクラス全年代・業界 | ハイクラス・全年代 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス | 全業界・首都圏 |
| 求人数 | 629,925件 | 253,718件 | 非公開 | 1,093,000件以上 | 49,570件 | 172,146件 | 548,725件 | 非公開 | 97,835件 | 22,339件 | 2,523件 |
| 求人の豊富さ | |||||||||||
| ポイント | 非公開求人も多数 | エージェント・サイト両方の利用が可能 | 地方の求人も充実 | 企業からのオファーあり | オファーも受けられる | 2種類のスカウトあり | 登録するとスカウトが多数届く | スカウトサービスあり | 利用者の満足度が高い | コンサルタントのサポートが手厚い | とくにエンジニア、20代、女性の求人に強み |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
2025年9月20日調査:各転職エージェントの取り扱い求人件数・各転職サイトの掲載求人数
Contents
月収13万円の手取りは約10万円!給料の額面と手取り額の違い
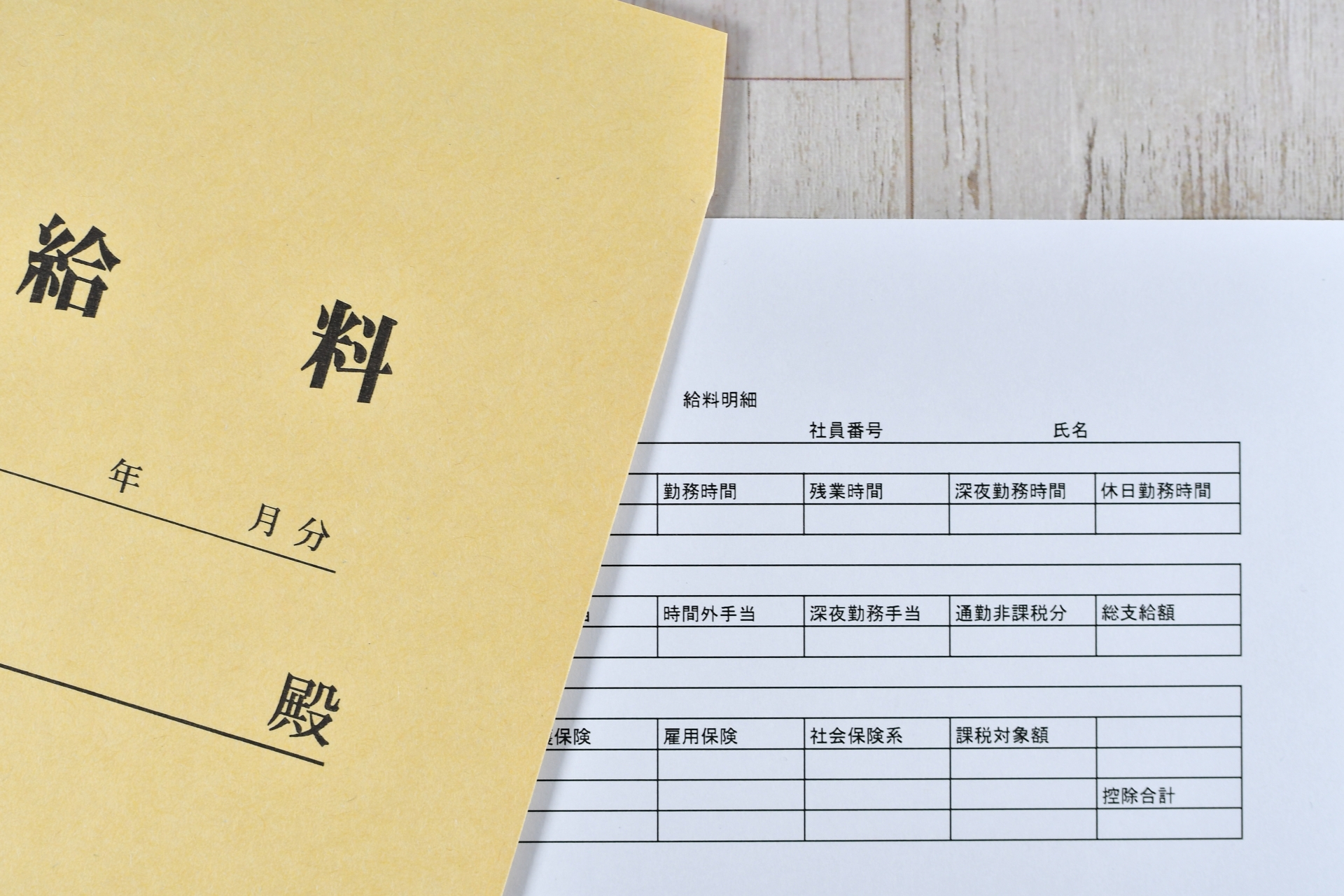
結論からいうと、月収(額面)13万円の手取りは、10万円前後になると考えられます。
実際、月収13万円の給与明細を見るとさまざまな項目が差し引かれており、月収(額面)と実際の手取り額には大きな差があることに気づくでしょう。そのため、月収13万円と手取り13万円では年収や生活水準が大きく異なるのです。
まず最初に、月収と手取りの違いや具体的な計算方法について詳しく解説します。
- 月収(額面)と手取りの違いとは
- 月収13万円の手取り計算方法
- 手取り13万円の月収は16万円~17万円
- 手取り13万円の年収は230万円~250万円
それでは順に見ていきましょう。
月収(額面)と手取りの違いとは
月収(額面)とは、会社があなたに支払う給与の総額のことを指します。一方、給料の手取りとは実際にあなたの口座に振り込まれる金額です。
両者の違いは、月収(給料)から差し引かれる各種控除額にあります。月収の主な控除項目には、次のようなものがあります。
① 社会保険料
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料 など
② 税金
- 所得税
- 住民税 など
これらの控除額は、雇用形態や年齢、扶養家族の有無などによって変動します。たとえば正社員の場合は社会保険料の負担が大きくなり、月収の20%~30%程度が控除されることも珍しくありません。
結果、「月収13万円の場合、手取りは10万円前後」になる可能性があるということです。
給与計算の際はこれらの控除を正しく理解し、実際に使える金額を把握することが家計管理の基本となります。
月収13万円の手取り計算方法
月収13万円からの手取り額を計算するには、まず控除額を正確に把握する必要があります。
社会保険料は給与の約15%程度で、健康保険料が月収の5%前後、厚生年金保険料が9%程度、雇用保険料が0.3%程度です。これに加えて所得税は課税所得に応じて計算され、住民税は前年の所得に基づいて決定されます。
<具体的な計算例>
| 月収13万円の控除額内訳 | |
|---|---|
| 健康保険料 | 約6,500円 |
| 厚生年金保険料 | 約11,700円 |
| 雇用保険料 | 約390円 |
| 所得税 | 約2,000円 |
| 住民税 | 約5,000円 |
これらを合計すると控除額は約25,590円となり、月収13万円の手取りは約104,410円となります。
手取り13万円の月収は16万円~17万円
ここまで月収13万円の手取りが約10万円になることを説明しましたが、それでは手取り13万円を実現するためには月収いくら必要なのでしょうか。
先ほど説明した各種控除を逆算すると、一般的な正社員の場合、手取り13万円は月収16万円から17万円程度となります。簡単にいうと、手取り13万円を得るには控除額(約3万円から4万円)を上乗せした金額が額面で必要となります。
ただし、この給料の金額は雇用形態や勤務先の条件などによって変動します。
たとえば社会保険に加入していないパート従業員の場合は、より少ない月収でも手取り13万円を実現できる可能性があります。反対に住民税が高額な地域に住んでいる場合などは、さらに高い月収が必要になることもあります。
手取り13万円の年収は230万円~250万円
手取り13万円(月収16万円)の場合、年収の目安は以下のように計算できます。
<手取り13万円の年収(目安)計算方法>
- 年収(手取り)= 13万円 × 12ヶ月 + 賞与(ボーナス) =約180万円~200万円
- 年収(額面)= 16万円 × 12ヶ月 + 賞与(ボーナス) =約230万円~250万円
月々の手取り13万円を12ヶ月分合計し、年2回の賞与を含めると、手取り年収は180万円から200万円程度になることが多いです。これを年収(額面)に換算すると、約230万円から250万円程度と試算されます。
ただし、この金額は会社の賞与制度や手当、生活環境(扶養家族の有無など)によって大きく変動する可能性があります。
月収13万円で手取り10万円の生活はやばい?生活レベルのリアル

月収13万円という給与水準について、実際の生活レベルや経済的な位置づけを客観的に見ていく必要があります。
この章では、全国平均との比較や年齢・業種による違い、そして実際の生活可能性について具体的に検証していきます。
- 月収13万円は全国平均と比べてどのレベルか
- 年齢別・業種別の平均月収との比較
- 一人暮らしで月収13万円は生活できるのか
それでは順に見ていきましょう。
月収13万円は全国平均と比べてどのレベルか
結論からいうと、月収13万円という水準は全国の給与データと比較して相対的に低い位置にあります。
厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると一般労働者の平均月収は約30万円であり、月収13万円はその半分以下となります。
またパートタイム労働者の平均時給は約1,200円で、月収に換算すると15万円程度となることから、パートタイム労働者の平均と比べても低めの水準といえます。
この収入レベルは、いわゆる貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)に近い水準となります。ただし、これは単身世帯の場合であり、世帯全体の収入としては配偶者の収入や他の収入源と合わせて考える必要があります。
また地域による生活費の違いも大きく、地方都市では13万円でもある程度の生活が可能な場合もあります。
- 月収13万は全国平均よりも低い!
-
- 一般労働者の平均月収:約30万円
- パートの平均月収:約15万円(平均時給 約1,200円から推計)
年齢別・業種別の平均月収との比較
月収13万円の位置づけは、年齢や業種によっても大きく異なります。
年齢別で見ると、新卒から20代前半の場合、月収13万円は決して珍しい額ではありません。特に小売業やサービス業などでは、初任給がこの水準に近い企業も少なくありません。
一方、30代以降になると月収13万円は平均を大きく下回る水準となります。
- 年齢別の平均月収
-
- 20代前半:約21万円
- 30代前半:約27万円
- 40代前半:約33万円
このように年齢が上がるにつれて差が開いていきます。
業種別では、特に飲食・サービス業や小売業などで比較的低い給与水準が多く見られます。一方、IT業界や製造業、金融業で月収13万円というと、非常に低い水準となります。
このように業種による給与格差は大きく、同じ月収13万円でもその評価は業界によって大きく異なります。
一人暮らしで月収13万円は生活できるのか
一人暮らしで月収13万円の場合、手取りは約10万円程度となるため、かなり苦しい家計運営といえます。
| 一人暮らしの生活費の内訳(例) | |
|---|---|
| 家賃 | 4~5万円 |
| 光熱費 | 1万円 |
| 食費 | 3万円 |
| 通信費 | 1万円 |
| 日用品費 | 5千円 |
| 交通費 | 1万円 |
このように基本的な生活費だけで既に11万円以上必要となり、手取り額を超過してしまいます。
さらに医療費や衣服費、交際費などの変動費や将来に向けた貯金までを考えると、月収13万円(手取り10万円)での一人暮らしは非常に厳しい状況といえます。特に都市部では家賃が高額になりがちなため、より一層の工夫や節約が必要となります。
このような状況では、副業や資格取得など何らかの収入アップ方法を考える必要があるでしょう。
手取り13万円ってやばい?実現できる生活水準を徹底検証

月収13万円で手取り10万円の生活はかなり厳しいということをお伝えしました。
しかし手取り額が13万円になると、適切な家計管理と支出計画によって、やりくりできる可能性が高くなります。特に一人暮らしの場合は、賢い支出管理が求められます。
この章では、手取り13万円で実現可能な生活レベルや家賃相場、貯金・投資の可能性について詳しく検証していきます。
- 13万円の手取りの支出シミュレーション
- 住める物件の家賃相場は4.5万円
- 13万円の手取りで貯金できる?節約術の工夫
- 13万円の手取りで投資できるのか
それでは順に見ていきましょう。
13万円の手取りの支出シミュレーション
手取り13万円での生活を考える際は、まず固定費と変動費を明確に区分し優先順位をつけた支出計画が必要です。一般的な支出シミュレーションでは、手取り13万円の場合は以下のような配分が推奨されます。
<手取り13万円の生活費:支出シミュレーション>
| 固定費(約8万円) | |
|---|---|
| 家賃・管理費 | 5万円 |
| 光熱費 | 1万円 |
| 通信費 | 8,000円 |
| 交通費 | 1万円 |
| 保険料 | 2,000円 |
| 変動費(約5万円) | |
|---|---|
| 食費 | 3万円 |
| 日用品費 | 5,000円 |
| 交際費 | 1万円 |
| 衣服費 | 5,000円 |
このシミュレーションを参考に、月々の支出を12万円に抑えることで1万円の貯金も可能です。ただし、これは標準的な目安であり、居住地域や生活スタイルによって大きく変動する可能性があります。
住める物件の家賃相場は4.5万円
手取り13万円の場合、家賃は手取りの35%程度である4.5万円が上限の目安となります。この予算で探せる物件は、地域によって大きく異なります。
たとえば東京23区では、築年数が古い物件や駅から徒歩15分以上の物件が中心となります。広さはワンルームや1Kで15㎡~20㎡程度が一般的です。一方、地方都市では同じ予算でより広い物件を借りることが可能です。
- 地域別の物件例
-
- 政令指定都市の郊外:1K~1DK(25㎡前後)
- 地方都市:1DK~2DK(30㎡以上)
地域別に手取り13万円で住まいを借りる場合、このような物件が選択肢として考えられます。ただし物件選びでは、通勤時間や通勤費とのバランスも考慮することが大切です。交通費を抑えられる物件であれば、その分家賃を高めに設定することも検討できます。
13万円の手取りで貯金できる?節約術の工夫
手取り13万円の一人暮らしで貯金する場合は、計画的な支出管理と工夫次第で可能です。
目標とする貯金額は月1万円~2万円程度が現実的です。これを実現するためには、以下のような具体的な対策が効果的です。具体的に、手取り13万円で毎月貯金するためのポイントは以下のとおりです。
① 固定費の見直し
- 格安SIMへの切り替え
- 光熱費の節約習慣化
- 安価なスーパーの活用
② 変動費の抑制
- 自炊の習慣化
- フリマアプリの活用
- ポイント還元の活用
上記以外にも、臨時収入(賞与など)の半分は必ず貯金に回すなど、明確なルールを設定することも重要です。ただし、あまりに厳しく節約しすぎると続けられなくなるため、適度に余裕を持った計画を立てることをおすすめします。
13万円の手取りで投資できるのか
手取り13万円という収入レベルでも、小規模な投資は可能です。
ただし、まずは生活費の確保と緊急時の備えとして3ヶ月分の生活費(約39万円)を貯金することが最優先です。その上で、月々の投資可能額を検討しましょう。具体的な投資のステップは、次のように考えられます。
- 投資を始める具体的なステップ
-
- 少額投資から始める(月3,000円~5,000円)
- つみたてNISAの活用
- インデックス投資信託の利用
特につみたてNISAは、少額から始められる上に非課税メリットがあり、投資初心者に適しています。
ただし、投資はあくまでも余裕資金で行うべきで、生活に支障をきたすような無理な投資は避けるべきです。月々の投資額は手取りの3~5%程度(4,000円~6,500円)を目安とすることをおすすめします。
月収13万円のパート vs 手取り13万円の正社員、どっちがお得?

続いて、月収13万円のパートと手取り13万円の正社員について、それぞれのメリット・デメリットを比較検討してみます。
パートと正社員では実際の待遇や福利厚生に大きな違いがあり、特に社会保険の加入条件や税金の控除方法が異なるため、実質的な収入にも差が生じます。
- パートと正社員の社会保険加入条件の違い
- 月収13万円のパートに対する税金・社会保険料
- 手取り13万円の正社員に対する税金・社会保険料
- パートのメリット・デメリット
- 正社員のメリット・デメリット
それでは順に見ていきましょう。
パートと正社員の社会保険加入条件の違い
パートタイマーと正社員では、まず社会保険の加入条件が大きく異なります。
正社員は原則として全員が社会保険に加入する必要がありますが、パートタイマーの場合は一定の条件を満たさない限り加入義務はありません。具体的には次の場合に社会保険への加入が必要となります。
- パートの社会保険加入条件
- 週の所定労働時間が20時間以上で、月額賃金が8.8万円以上、かつ勤務期間が1年以上見込まれる場合
つまり、パートは配偶者の扶養に入ることで社会保険料の負担を抑えることができますが、年収が130万円(月収にすると約10.8万円)を超えると配偶者の扶養から外れる可能性があるため、注意が必要なのです。
この境界線を意識した働き方が、パートで働く特徴の一つといえます。
月収13万円のパートに対する税金・社会保険料
月収13万円のパートタイマーの場合、通常、社会保険の加入条件に該当するため、給与からの控除額は以下のようになります。
<具体的な計算例:パートの場合>
| 月収13万円の控除額内訳 | |
|---|---|
| 健康保険料+厚生年金保険料 | 約18,000円 |
| 雇用保険料 | 約390円 |
| 所得税 | 約2,000円 |
| 住民税 | 約5,000円 |
※これらの控除額は勤務先の条件や地域によって変動します。
合計すると、控除額は約25,000円となります。
パートの場合、配偶者の扶養から外れることで世帯全体での収支にも影響が出る可能性があります。そのため、パートは世帯全体での収入と支出のバランスを考慮して、働き方を選択する必要があります。
手取り13万円の正社員に対する税金・社会保険料
手取り13万円の正社員の月収は、約16万円から17万円程度です。そのため社会保険料や税金などの控除額は、月収13万円のパートよりも多くなります。具体的には、次のような控除額になります。
<具体的な計算例:正社員の場合>
| 月収16万円~17万円の控除額内訳 | |
|---|---|
| 健康保険料 | 約8,000円 |
| 厚生年金保険料 | 約14,000円 |
| 雇用保険料 | 約480円 |
| 所得税 | 約3,000円 |
| 住民税 | 約6,000円 |
※これらの控除額は勤務先の条件や地域によって変動します。
これらを合計すると、控除額は約31,480円となります。
パートのメリット・デメリット
パートタイマーで働く最大のメリットは、勤務時間の融通が利きやすく、家庭との両立がしやすいことです。
また社会保険料の負担が少ない場合もあり、手取り額を効率的に確保できる可能性があります。特に配偶者の扶養内で働けるように月収や年収額を調整した場合は、税金や社会保険料の負担を最小限に抑えることができます。
一方でデメリットとしては、賞与や昇給が少ない、または無いことが多く、長期的な収入アップが期待しにくいことが挙げられます。雇用の安定性が正社員と比べて低く、福利厚生も限定的である場合が多いのもデメリットといえます。
さらに扶養内パートの場合は将来の年金受給額にも影響が出る可能性があるため、長期的なライフプランを考える際に注意が必要です。
- パートで働くメリット
-
- 勤務時間が柔軟で家庭と両立しやすい
- 社会保険料や税金の負担が少ない場合がある
- 税金や社会保険料の負担を抑えられる
- パートで働くデメリット
-
- 賞与や昇給が少なく収入が増えにくい
- 雇用の安定性や福利厚生が弱い
- 年金受給額にも影響が出る可能性あり
正社員のメリット・デメリット
正社員の最大のメリットは、雇用の安定性と充実した福利厚生です。
賞与や昇給の機会も定期的にあり、長期的な収入アップが期待できます。また、社会保険に加入することで将来の年金受給額も確保しやすくなります。さらにキャリアアップの機会も多く、スキルや経験を積むことでより良い待遇を得られる可能性が高まります。
デメリットとしては、労働時間が長くなりがちで残業や休日出勤が発生する可能性があることです。また転勤や配置転換がある場合もあり、生活環境の変更を強いられることもあります。さらに正社員の場合は社会保険料の負担も大きくなります。
- 正社員で働くメリット
-
- 雇用の安定性が高い
- 福利厚生が充実している
- 賞与や昇給の機会があり収入が増えやすい
- 将来の年金が確保しやすい
- キャリアアップやスキル向上の機会が多い
- 正社員で働くデメリット
-
- 労働時間が長くなりがち
- 残業や休日出勤がある場合がある
- 転勤や配置転換で生活環境が変わることがある
- 社会保険料の負担が大きい
月収13万円のパートから正社員になる方法

パートタイマーから正社員への転換は、長期的なキャリア形成において重要な転機となります。しかし月収13万円のパートから正社員になることは、収入面での変化だけでなく、働き方や責任、生活リズムなど様々な面での変化を伴います。
ここでは、月収13万円のパートから正社員への転換に向けたポイントを詳しく解説していきます。
- パートから正社員になるメリット・デメリット
- 正社員転換に必要な準備
- 企業の正社員登用制度の活用法
それでは順に見ていきましょう。
パートから正社員になるメリット・デメリット
パートタイマーから正社員への転換には、様々なメリットとデメリットが存在します。
月収13万円のパートから正社員になる場合、まず収入面では一時的に手取りが減少する可能性があります。これは社会保険料の負担が増えるためです。しかし、長期的に見れば、賞与や昇給により収入全体としては増加していく可能性が高くなります。
正社員になることの主なメリットとしては、雇用の安定性が高まることが挙げられます。また福利厚生の充実やキャリアアップの機会が増えることも大きな利点です。
さらに将来の年金受給額も増加するため、
老後の生活設計がより安定したものとなります。
一方でデメリットとしては、労働時間の増加や責任の重さ、転勤や配置転換の可能性など、生活スタイルの大きな変更を求められる可能性があります。これらのメリット・デメリットを十分に理解した上で、正社員への転換を検討してみましょう。
正社員になるために必要な準備
パートから正社員への転換を成功させるためには、計画的な準備が欠かせません。
まず業務スキルの向上が重要です。現在の月収13万円のパート業務で担当している仕事の範囲を広げ、より責任のある業務にチャレンジすることで、正社員としての適性をアピールすることができます。
正社員になるための一般的なステップは、次のとおりです。
① 基本的なビジネススキルの習得
- ビジネスマナーの徹底
- PCスキルの向上(特にExcelなど)
- 社内コミュニケーションの強化
② 業務知識の拡大
- 関連部署の業務理解
- 社内規定や制度の把握
- 業界知識の習得
③ 資格取得
- 職種に関連する資格
- ビジネス全般に関する資格
これらの準備を通じて、正社員として働くための適性を高めていくことが大切です。
企業の正社員登用制度の活用法
多くの企業では、パートタイマーを正社員に登用する制度を設けています。この制度を効果的に活用するためには、登用の条件や選考方法、試用期間の有無などについて、人事部門にまず確認することから始めましょう。
正社員登用制度の一般的な流れは、以下のとおりです。
① 上司との定期的な面談
- 正社員転換への意欲を伝える
- 必要なスキルや改善点の確認
- 具体的な目標設定
② 社内での評価向上
- 積極的な業務改善提案
- 後輩パートの指導・育成
- 部門を超えた協力体制の構築
③ 登用試験対策
- 筆記試験の準備
- 面接練習
- 志望動機の整理
月収13万円・手取り13万円からの収入アップ戦略

13万円から手取りや月収を増やすためには、計画的なアプローチが必要です。収入アップの方法には、次のような選択肢があります。
- 副業・ダブルワーク
- 資格取得
- 転職
それでは順に見ていきましょう。
① 副業・ダブルワークによる収入アップ
13万円の手取りで新たに副業を始める場合は、慎重に計画を立てる必要があります。
まず重要なのは、現在の勤務先の副業規定を確認することを忘れないようにしましょう。勤務先で副業が認められている場合、以下のような選択肢が考えられます。
- オンラインでできる副業はコレ!
-
- クラウドソーシング(ライティング、データ入力)
- オンラインレッスン(語学、趣味の指導)
- SNSやブログでの収益化
このようにオンラインでできる副業は時間や場所に縛られずに始められる利点があります。
- 実地での副業例
-
- 飲食店やコンビニでのシフト勤務
- 家事代行や清掃サービス
- 配送やデリバリー
これらの実地での副業は確実な収入が見込める一方で、本業との両立に際して体力的な負担を考慮する必要があります。本業に支障が出ない範囲で行うことが重要です。
また副業を始める際は、確定申告の必要性や社会保険、扶養への影響にも気をつけましょう。
② 資格取得による収入アップ
資格取得は、中長期的な収入アップの有効な戦略です。特に以下の資格は、手取り13万円からの収入アップに効果的です。
IT関連資格
- ITパスポート
- 基本情報技術者
これらは比較的短期間で取得できる資格の例です。IT企業への転職や社内でのキャリアアップに活用できます。
事務・経理系資格
- 日商簿記検定(2級程度)
- MOS(Microsoft Office Specialist)
これらは多くの企業で求められる基本スキルのため、将来、転職を考える場合にも有益です。
業種特化型資格
- 宅地建物取引士
- ファイナンシャルプランナー
- 介護福祉士
これらは特定の業界での専門性を高め、より高い収入を目指すのに役立ちます。業務に関連する資格を取得することで、キャリアアップが期待できます。
③ 転職による収入アップ
13万円の手取りや月収から収入を上げるためには、転職もひとつの方法です。
ただし転職活動は、段階的なステップアップが重要です。まず現在の業界での市場価値を高めることから始めましょう。
転職戦略① 準備段階(3~6ヶ月)
- 業界研究と市場調査
- スキルアップと資格取得
- 職務経歴書の作成
転職戦略② 転職活動段階(2~3ヶ月)
- 転職サイトへの登録
- 転職エージェントの活用
- 面接対策
転職戦略③ 条件交渉段階
- 現在の手取り13万円から20-30%アップが目標
- 福利厚生や賞与も含めた総合的な待遇交渉
- 転職後のキャリアパスの確認
転職先を選ぶ際は、単に給与だけでなく長期的なキャリア形成の可能性も重要な判断基準です。特に成長産業や安定性の高い業界を選ぶことで、将来的な収入アップの機会も広がります。
また効率的かつ効果的に転職活動を進めるためには、転職エージェントの活用がおすすめです。最新の市場動向について教えてもらえるだけでなく、面接対策や年収交渉のサポートを受けたり、今後のキャリア形成についても相談できます。
月収13万円・手取り13万円の社会保障と将来設計

月収13万円や手取り13万円で生活する場合、社会保障制度をしっかりと理解し活用することが将来の生活設計において重要です。
社会保険に加入することは一時的な負担増となりますが、長期的な視点では大きなメリットがあります。将来の安定した生活のために、社会保障制度と年金についてしっかり理解しておきましょう。
- 社会保険加入のメリット
- 国民年金の納付と将来の年金額
- 老後の生活設計における注意点
それでは順に見ていきましょう。
社会保険加入のメリット
社会保険料は、月収13万円(手取り約10万円)の場合と月収16~17万円(手取り13万円)の場合では以下のようになります。
| 社会保険料 | 月収13万円 (手取り10万円) |
月収16~17万円 (手取り13万円) |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 約6,500円 | 約8,000円 |
| 厚生年金保険料 | 約11,700円 | 約14,000円 |
| 雇用保険料 | 約390円 | 約480円 |
| 合計 | 約18,590円 | 約22,480円 |
どちらの場合も負担が大きいと感じるかもしれません。しかしこの制度は私たちの生活を様々な面でサポートしてくれる重要なセーフティーネットです。
健康保険は、予期せぬ病気やけがの際の経済的な負担を大きく軽減できます。また傷病手当金という制度により、病気やけがで働けなくなった場合でも、標準報酬日額の3分の2相当額が最長1年6ヶ月支給されます。
このような保障がないまま13万円という収入レベルを続けた場合、急な病気で収入が途絶えた際に生活が立ち行かなくなるリスクが高くなります。
さらに社会保険に加入していれば、出産育児一時金や育児休業給付金などライフイベントに関連した給付金も受けることができます。これらの制度は、限られた収入の中で将来の生活設計を考える上で非常に重要な支えとなります。
国民年金の納付と将来の年金額
令和6年度の国民年金保険料は月額16,980円ですが、13万円の手取りや月収の場合、国民年金保険料の納付は大きな負担に感じられるかもしれません。けれども、この納付は将来の年金受給額に直接影響するため、可能な限り継続することが重要です。
将来受け取れる年金額は、保険料の納付期間によって変わってきます。40年間満額で保険料を納付した場合、65歳からの老齢基礎年金は月額約6.5万円となります。
さらに厚生年金に加入している場合は、その分の年金も上乗せされます。
13万円の収入レベルでは、将来の年金受給額を最大化するための
戦略が特に重要となります。
老後の生活設計における注意点
13万円という収入レベルでの老後の生活設計では、特に計画的な準備が重要です。
一般的に老後の生活には月額20万円程度が必要といわれており、老齢基礎年金だけで賄うのは厳しいのが現実です。そのため、現役時代からの計画的な貯蓄や資産形成が不可欠となります。
老後設計は以下のポイントを意識しながら、限られた収入の中でも着実に将来への準備を進めていくことが重要です。
生活費の見直し
- 固定費の削減可能性の検討
- 将来の医療費の想定
- 趣味や娯楽費用の計画
資産形成の方法
- 長期的な積立投資の検討
- iDeCoやつみたてNISAの活用
- 預貯金と投資のバランス
健康管理の重要性
- 予防医療への投資
- 運動習慣の確立
- 定期的な健康診断の受診
13万円の手取り・月収に関するFAQ

月収13万円(手取り10万円)や手取り13万円について、よくある質問と回答をご紹介します。
- 月収13万円(手取り10万円)でクレジットカードは作れる?
- 月収13万円(手取り10万円)で老後資金は貯まる?
- 手取り13万円で車は持てる?
- 手取り13万円から投資を始めるには?
それでは順に見ていきましょう。
月収13万円(手取り10万円)でクレジットカードは作れる?
月収13万円でもクレジットカードの作成は可能です。ただし、審査の通りやすさや発行されるカードの種類には一定の制限があります。
この収入レベルでは、年会費無料の基本的なクレジットカードの取得が現実的な選択肢といえるでしょう。
申込みに際しては、勤続年数が1年以上の正社員であることが望ましいです。また他の借入がない状態で申し込むことで、審査に通りやすくなります。
月収13万円(手取り10万円)で老後資金は貯まる?
月収13万円という収入レベルでも、計画的な取り組みがあれば老後資金の積み立ては可能です。
ただし手取り額が限られているため、優先順位をつけた貯蓄計画が重要となります。まずは生活費と緊急時の備えを確保した上で、長期的な資産形成を考えていく必要があります。
老後資金の貯蓄において重要なポイントは、以下のとおりです。
- 支出の最適化
- 月収13万円の場合、まず固定費の見直しから始めます。特に、家賃や光熱費、通信費などの必要経費を最小限に抑えることで、貯蓄に回せる金額を確保します。食費や日用品費も、計画的な購入や節約術を活用することで、コストを抑えることができます。
- 段階的な積立計画
- 初めは月1万円程度からスタートし、徐々に積立額を増やしていく方法が現実的です。給与の上昇や臨時収入があった場合は、その一部を必ず貯蓄に回すルールを設定します。またiDeCoやつみたてNISAなどの税制優遇制度を活用することで、より効率的な資産形成が可能となります。
- 長期的な資産形成
- 若いうちから老後資金の積立を始めることで、複利効果を最大限に活用することができます。
手取り13万円で車は持てる?
手取り13万円での車の所有は、慎重な検討が必要です。車の維持費用は、購入費用以外にも多くの経費がかかります。
- 車にかかる月々の費用例
-
- 車両ローン:2~3万円(100万円の車を5年ローンで購入の場合)
- 自動車保険:1~1.5万円
- ガソリン代:1~1.5万円(月間走行距離により変動)
- 駐車場代:1~2万円(地域により大きく変動)
- 車検・メンテナンス費用の積立:1万円程度
これらを合計すると、月々6~9万円程度の費用が必要となります。13万円の手取り収入では、これらの費用を捻出するのはかなり厳しいといえます。
しかし車が必要不可欠な地域に住んでいる場合は、以下のような工夫で検討してみましょう。
- 車を持つために工夫できるポイントはコレ!
-
- 中古車の選択
初期費用を抑える。維持費の安い軽自動車を選ぶ。
- 保険の見直し
任意保険の補償内容の最適化。複数社の見積もり比較。安全運転による保険料割引を活用する。
- 駐車場費用の削減
安価な駐車場の利用。家族で複数台契約した場合の割引を活用する。
- 中古車の選択
手取り13万円から投資を始めるには?
手取り13万円からの投資は、リスクとリターンのバランスを慎重に考慮する必要があります。限られた収入の中から投資資金を捻出するため、まずは少額から始めることをおすすめします。
具体的な投資戦略として、以下のようなアプローチが考えられます。
- 投資初心者向けの基本戦略
- まずは月3,000円程度からつみたてNISAを活用し、低コストの投資信託への投資を始める方法があります。インデックスファンドは手数料が低めに抑えられているため、少額投資の開始時に適しています。
- 段階的な投資額の増額
- 生活費の見直しや収入の増加に応じて、徐々に投資額を増やしていくことを検討します。
ただし、投資は余裕資金で行うことが基本原則です。生活に支障をきたすような無理な投資は避け、長期的な視点で着実な資産形成を目指しましょう。
みんなが使っている転職サービス上位6選 【1,382人に聞いた転職サービス利用状況】
実際に登録したことのある転職サービスについてアンケートをとりました。アンケート結果として、みんなが使っている転職サービスの上位6サービスは以下です。
- 1位|リクルートエージェント(821人)
- 2位|doda(564人)
- 3位|リクナビNEXT(389人)
- 4位|マイナビAGENT(312人)
- 5位|ビズリーチ(288人)
- 6位|エン転職(282人)
※転職サービスの利用アンケート(クラウドワークス) 回答数:1,382 / 集計期間:2024年09月19日~10月03日
1位|リクルートエージェント(利用回答数:821人) 圧倒的な求人数
「リクルートエージェント」は、求人数、安定したサービス品質で、まずは登録が必須のエージェントです。
まず何と言っても求人数が多いことがおすすめの理由として挙げられます。転職成功の実績も多く、優れているのは求人の数だけではありません。業界に精通したアドバイザーが在籍しているので、ぴったりの求人を見つけ出してくれます。求人やサービスの質・量ともにトップクラスで転職エージェントとしては定番・王道のサービスです。
営業・技術系を中心にあらゆる業種・職種をカバー。総合型ながら条件ごとに特化したページもあり、使いやすいのも人気の理由です。
- リクルートエージェントのおすすめポイント
- 求人数が圧倒的に多い
- 業界に精通したアドバイザーが在籍
- 条件ごとに特化したページがあり使いやすい
基本データ
| リクルートエージェント | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人474,685件/非公開求人399,542件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | エージェントサービス、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供 |
| 拠点 | 東京・北海道・宮城・宇都宮・さいたま・千葉・横浜・金沢・新潟・長野・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡 |
| URL | https://www.r-agent.com/ |
2位|doda(利用回答数:564人) エージェント/サイトの一体型で自分でも応募が可能
「doda」は、人材紹介・転職支援を行う大手「パーソルキャリア」が運営する総合型転職サイトです。エージェントサービスも利用できる点が人気の理由の1つになっています。
dodaも求人数が多く、非公開求人も条件が良いものが多いのが大きなポイントです。
また転職サイトと転職エージェントの一体型で、使い方の自由度が高いのもおすすめポイント。エージェントサービスでは専任のキャリアアドバイザーがサポートしてくれます。なお企業との対応は採用プロジェクト担当が行い、求職者と企業とでそれぞれ別のプロフェッショナルが対応します。
- dodaのおすすめポイント
- 非公開求人も好条件多数
- 転職サイトと転職エージェントの一体型で自由度が高い
- 専任のキャリアアドバイザーがサポート、企業は別のプロフェッショナルが対応
基本データ
| doda | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人262,342件/非公開求人31.049件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、年収査定、合格診断、レジュメビルダー、「自己PR」発掘診断、転職タイプ診断、はたらく女性のためのモヤモヤ解消診断、オンライン仕事力診断 |
| 拠点 | 東京・横浜・札幌・仙台・静岡・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・広島・福岡・鹿児島 |
| URL | https://doda.jp/consultant/ |
3位|リクナビNEXT(利用回答数:389人) 求人サイト群の中でも最大級の求人数と使いやすさ
「リクナビNEXT」は大定番の転職サイトで、サイトの見やすさや使いやすさにも定評があります。
エージェントなしの狭義の転職サイトの中では、求人数はトップクラス。新規の求人も多く、定期的にチェックすることで希望に合う求人に出会える可能性が高まります。
ツールが便利でサイトが使いやすいのも特長です。たとえば「気になるリスト」を使うと、気になる企業や後でゆっくりチェックしたい企業をリスト化できるほか、気になるに追加した企業から面接のオファーが来る可能性があります。
そのほか、公開求人・非公開求人の企業からオファーがもらえる「オファーを待つ」、自己分析ツール「グッドポイント診断」などがあります。
- リクナビNEXTのおすすめポイント
- サイトが見やすく使いやすい
- 狭義の転職サイトでは最大級の求人数
- 多くの人が利用している定番の転職サイト
基本データ
| リクナビNEXT | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人824,000件以上(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | オファー、気になるリスト、グッドポイント診断 |
| URL | https://next.rikunabi.com/ |
4位|マイナビAGENT(利用回答数:312人) 20代・30代の求人に強い
「マイナビAGENT」は、さまざまな転職サイトを運営している株式会社マイナビによる転職エージェントです。きめ細かいサポートが受けられると評価されています。
とくに20代・30代の求人が多いので、その世代の人にはおすすめです。また全国に拠点があり地方の求人も充実しているので、大都市圏以外で探している人にもぴったりです。
履歴書や職務経歴書のサポートも充実、初めての転職でも安心して利用できます。IT、営業など業種・職種別のサービスもあります。自分が探している業種と一致するならより探しやすくなるでしょう。
- マイナビAGENTのおすすめポイント
- 20代・30代の求人が多い
- 地方の求人も充実
- 履歴書や職務経歴書のサポートもあり安心
基本データ
| マイナビAGENT | |
|---|---|
| 公開求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| 拠点 | 拠点情報はこちらをご確認ください |
| URL | https://mynavi-agent.jp/ |
5位|ビズリーチ(利用回答数:288人) ハイクラス向けで企業からスカウトが受けられる
「ビズリーチ」は、ハイクラス求人が多いのが特徴の転職サイトです。厳密にはスカウト型のサイトで、エージェントではありません。登録するとヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられます。
最大の特長は、ハイクラス求人が多いことです。年収1,000万円以上の求人が1/3以上を占めています。一定以上の経験やスキルがある人が転職活動するのに役立つサービスです。
もう1つの大きな特徴として、登録するだけでヘッドハンターや企業からスカウトが届く点があります。以前は「スカウト」と「プラチナスカウト」の2種がありましたが、今は「プラチナスカウト」に一本化されています。プラチナスカウト経由での採用は全体の約70%。採用される可能性が高く、スカウトが届いたら大きなチャンスです。実際、企業からスカウトが届いた場合は書類選考が免除されます。
基本的にヘッドハンターはアドバイスをしませんが、場合によってはアドバイスをもらえることもあります。無料プランと有料プランがあり、有料プランは制限なく求人に応募できます。
- ビズリーチのおすすめポイント
- ヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられるハイクラス向けサイト
- 企業からプラチナスカウトが来た場合は即面接が可能
- 有料プランなら制限なく求人に応募できる
基本データ
| ビズリーチ | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人138,081件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、有料プラン(プレミアムステージ) |
| 拠点 | 東京・大阪・名古屋・福岡・静岡・広島 |
| URL | https://www.bizreach.jp/ |
6位|エン転職(利用回答数:282人) サイトが使いやすく情報も充実、利用者の満足度が高い

「エン転職」は、人材サービス大手の一つエン・ジャパン株式会社による転職サイトです。エージェントサービスも利用できます。
オリコン顧客満足度調査の転職サイト部門で、2018年から2024年まで7年連続で総合満足度No.1となっています。サイトの使いやすさは定評があり、自力で検索・応募するのに適したサービスです。口コミなどの情報も充実しており、企業間の比較検討もしやすくなっています。
さらに転職サイトのほか転職エージェントとしても利用することができ、非公開求人も多数保有しています。大手ですが最大手ほどでない規模で、きめ細かいサポートを受けることが可能。また女性向けのページのほか、ミドルや若手ハイキャリアなどに特化した関連サイトもあります。
- エン転職のおすすめポイント
- 2018年から2024年まで7年連続で総合満足度No.1
- サイトが使いやすいほか情報も充実
- 非公開求人も多数保有
基本データ
| エン転職 | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人152,678件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| URL | https://employment.en-japan.com/ |
まとめ

13万円という手取りや月収は、確かに様々な課題や制約が存在します。しかし、適切な家計管理と将来を見据えた計画的な行動があれば、安定した生活基盤を築くことは可能です。
特に重要なのは、収入に見合った支出計画を立てて優先順位をつけた支出管理を行うことです。また社会保険制度をしっかりと活用し、将来の年金受給に向けた準備を整えることも大切です。
そして現在の収入に満足せず、資格取得やスキルアップを通じた収入増加を目指すことも重要です。転職や副業などの可能性も慎重に検討する価値があります。
13万円の手取りからでも、計画的な貯蓄と資産形成を始めることで、より安定した将来の生活基盤を築くことができます。まずは自身の生活スタイルと将来の目標を明確にし、それに向けた具体的な行動計画を立てることから始めてみませんか。