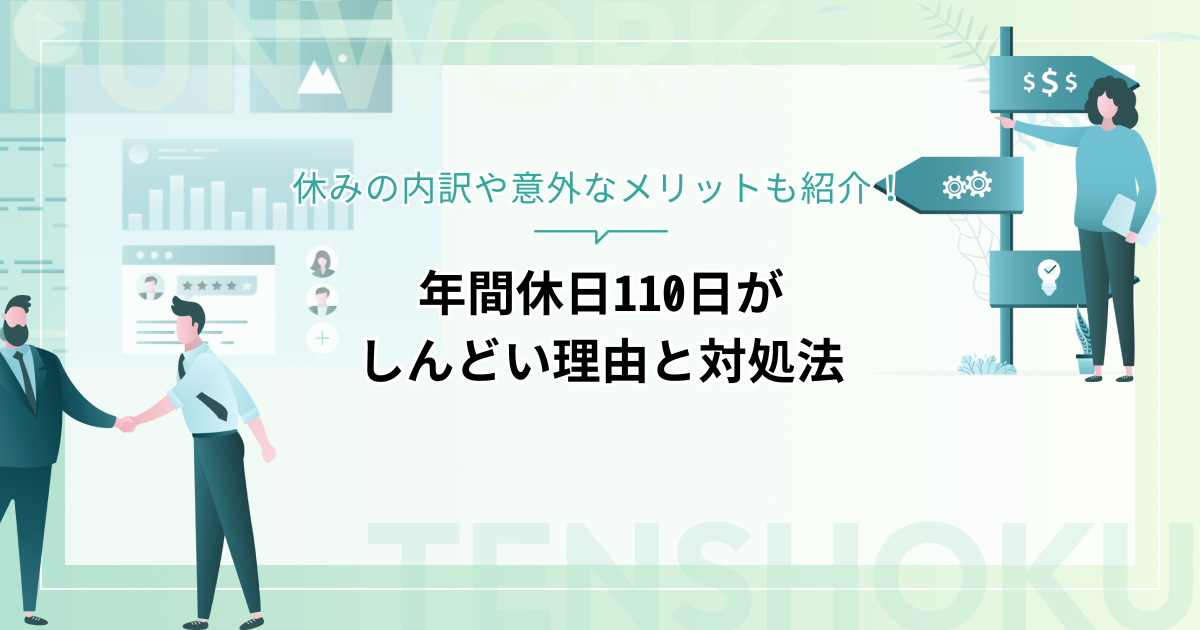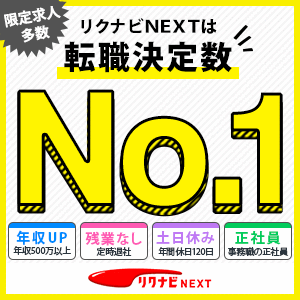- この記事でわかること
- 年間休日110日の実態とその内訳について
- 年間休日110日が少ないのか?業界別や企業規模別の比較
- 年間休日110日がしんどい理由とその対処法
- 休日を重視した転職活動のコツと、しんどいと感じた場合の改善策
- 年間休日110日の意外なメリットと充実させるための方法
- 自分に合った働き方が見つかる!おすすめ転職サービス上位6選 【1,382人に聞いた転職サービス利用状況】
「年間休日110日がしんどい」「年間休日110日は少ない」と感じることはありませんか?
実は年間休日110日という設定は全国平均とほぼ同等です。しかし多くの人が十分に休息が取れず、年間休日110日では足りないと感じています。
この記事では、年間休日110日がしんどいと感じる5つの理由や対処法、転職を含めた改善策、さらに年間休日110日の意外なメリットまで詳しく解説していきます。
少ない休みでも上手に活用する方法や改善策を知ることで、より充実した働き方を実現するヒントがきっと見つかるはずです!
【まずはチェック!!】求人数の多い大手転職サービスが人気!おすすめの求人数比較表!
大手転職サービスの取り扱い求人件数を独自調査。転職サービスの専任担当者が最新の取り扱い求人情報を確認し、求人数比較表にまとめています。転職活動にあたってはエージェントやサイトを積極的に活用しましょう。まずは一通りサービスを体験してみて自分にあったサービスを見つけることをおすすめします。比較表はこちら。
右にスクロールできます
| おすすめ | リクルートエージェント | doda | マイナビAGENT | リクナビNEXT | パソナキャリア | ビズリーチ | リクルートダイレクトスカウト | マイナビ転職 | エン転職 | JACリクルートメント | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特色 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | 全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス・女性向け | ハイクラス全年代・業界 | ハイクラス・全年代 | 全年代・全業界 | 全年代・全業界 | ハイクラス | 全業界・首都圏 |
| 求人数 | 605,771件 | 250,676件 | 非公開 | 1,184,000件以上 | 48,766件 | 166,803件 | 516,157件 | 非公開 | 105,190件 | 22,064件 | 2,587件 |
| 求人の豊富さ | |||||||||||
| ポイント | 非公開求人も多数 | エージェント・サイト両方の利用が可能 | 地方の求人も充実 | 企業からのオファーあり | オファーも受けられる | 2種類のスカウトあり | 登録するとスカウトが多数届く | スカウトサービスあり | 利用者の満足度が高い | コンサルタントのサポートが手厚い | とくにエンジニア、20代、女性の求人に強み |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
2025年8月9日調査:各転職エージェントの取り扱い求人件数・各転職サイトの掲載求人数
Contents
年間休日110日の内訳

年間休日110日という数字、実際の内訳はどのように休日が配分されているのでしょうか。
企業によって休日の設定方法は様々で、完全週休2日制を採用している場合や土曜出勤が一部含まれる場合など、その内訳は大きく異なります。
ここでは年間休日110日の一般的な内訳と、実際の運用について詳しく解説します。
- 年間休日110日の内訳:カレンダーどおりに土日祝日は休める?
- 年間休日110日に有給休暇10日を加えた場合の実態
- 年間休日110日は違法?大丈夫?
それでは順に見ていきましょう。
年間休日110日の内訳は?カレンダーどおりに土日祝日は休めるのか
年間休日110日の内訳は、企業によって様々な設定方法があります。
一般的な例として
- 完全週休2日制を採用している場合
- 土曜出勤が一部ある場合
の2つのパターンを見てみましょう。
年間休日110日で完全週休2日制のパターン=祝日出勤が多い
年間休日110日で完全週休2日制の場合は土曜日・日曜日が休みとなり、年間で104日程度の休日が確保されます。
残りの6日程度は祝日から充当することになりますが、これは通常の祝日日数(年間16日程度)よりも、かなり少ない日数です。つまり、年間休日110日で完全週休2日制というのは、多くの祝日が出勤日となっている可能性が高いということです。
年間休日110日で土曜出勤が一部あるパターン=まとまった休みが取りづらい
一方、土曜出勤が一部ある年間休日110日の場合は、毎月1〜2回の土曜日が出勤で、その分が祝日に休めるというかたちになります。たとえば年間の土曜出勤が24日程度となると、その分を祝日休みに充当できる可能性があります。
しかし土曜出勤があると、連続した休みが取りにくくなるというデメリットがあります。また土曜日が半日出勤という形態の企業もあり、まとまった休みがさらに取りづらいケースもあります。
年間休日110日に有給休暇10日を加えた場合の実態
続いて、年間休日110日に法定の年次有給休暇を加えた場合の実質的な休日数について見ていきましょう。
労働基準法では、6ヶ月継続して勤務し全労働日の8割以上を出勤した労働者に対して、最低10日の有給休暇を付与することが定められています。つまり、その有給休暇の日数を足すと年間120日休めるという計算になります。
しかし年間休日110日がしんどいと感じる場合、有給休暇を取得しても十分な休息が取れないと感じる人が少なくありません。
特に残業が多い職場では不規則な休日出勤や休日の待機などもあり、
実質的な休息時間が確保できないケースもあるからです。
また有給休暇の取得率も考慮する必要があります。
日本の有給休暇取得率は依然として高くありません。厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査概況」によれば、労働者1人あたりの平均取得率は62.1%(令和4年調査 58.3%)となっています。つまり有給休暇が10日あっても、実際は6日程度しか取得できていない現状があります。
年間休日110日は違法?大丈夫?
結論からいうと、年間休日110日は労働基準法上の最低基準を満たしているため、違法ではありません。労働基準法では、使用者は労働者に対して1週間に1日以上の休日を与えなければならないと定められています。これは年間換算すると最低52日の休日が必要となります。
したがって、年間休日110日という設定は、法定の最低基準を大きく上回っています。しかし法律上の基準を満たしているからといって、働く人にとって十分な休息が確保できているとは限りません。
特に残業が多い職場や精神的負荷の高い仕事の場合、年間休日110日ではワークライフバランスを保つのが難しいと感じる人も少なくありません。
また働き方改革の推進により、週休3日制など、より多くの休日を設定する企業も増えてきています。そのような中で、年間休日120日以上を設定する企業も増加傾向にあります。
年間休日110日は少ない?平均日数・業界別・企業規模別の比較

年間休日110日の内訳について詳しく見てきましたが、では年間休日110日を「しんどい」と感じるのは日数が少ないからでしょうか?
実際、年間休日110日が全国平均と比べてどのような位置づけなのか、詳しく見ていきましょう。
- 年間休日の平均日数は?
- 業界別の年間休日数の平均日数
- 大手企業と中小企業の年間休日数の差
それでは順に見ていきましょう。
年間休日の平均日数は?
厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、労働者1人あたりの平均年間休日は115.6日となっています。つまり年間休日110日という設定は、日本の平均的な水準とほぼ同等といえます。しかしこの数字は全業種の平均であり、実際には業界や企業規模によって大きな差があります。
特に近年は、働き方改革の推進により、
年間休日を120日以上に設定する企業も増加傾向にあります。
そのため、年間休日110日という休日数は、徐々に少ない側に位置づけられるようになってきています。
年間休日110日がしんどいと感じる背景には、このような休日数の増加トレンドも影響していると考えられます。特に若い世代を中心にワークライフバランスを重視する傾向が強まっており、休日の少なさが就職や転職の際の判断材料となるケースも増えています。
業界別の年間休日数の平均日数
業界によっても年間休日数には大きな差があります。厚生労働省の調査によると、情報通信業や金融業では年間休日が多い傾向にある一方、サービス業や小売業では比較的少ない傾向が見られます。
<業種別の平均年間休日総数>
| 産業分類 | 1企業平均年間休日数 |
|---|---|
| 情報通信業 | 118.8日 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 118.8日 |
| 金融業、保険業 | 118.4日 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 116.8日 |
| 製造業 | 111.4日 |
| 教育、学習支援業 | 112.7日 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 109.6日 |
| 医療、福祉 | 109.4日 |
| 複合サービス事業 | 110.4日 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 109.0日 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 104.6日 |
| 建設業 | 104.0日 |
| 卸売業、小売業 | 105.7日 |
| 運輸業、郵便業 | 100.3日 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 97.1日 |
※厚生労働省「平成30年就労条件総合調査」より
このような業界による差は、業務の特性や顧客対応の必要性、競争環境などが影響していると考えられます。特に年間休日110日がしんどいと感じる場合、同じ業界内でも休日の多い企業への転職を検討する選択肢もあります。
大手企業と中小企業の年間休日数の差
企業規模によっても、年間休日数には明確な差が見られます。厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」をもとに、企業規模別の年間休日数を見た場合、以下の調査結果になっています。
<企業規模別の平均年間休日総数>
| 企業規模(従業員数) | 1企業平均年間休日総数 |
|---|---|
| 1,000人以上 | 116.3日 |
| 300~999人 | 115.7日 |
| 100~299人 | 111.6日 |
| 30~99人 | 109.8日 |
※厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」より
一般的に、大手企業の方が中小企業よりも休日が多い傾向にあります。大企業では平均で年間休日が115日以上となっているのに対し、小規模な企業では、110日前後もしくはそれ以下というケースも少なくありません。
この背景には、人材確保の面での競争力や
業務効率化への投資余力の違いなどがあります。
大手企業では、優秀な人材を確保するために休日を含めた労働条件の改善に積極的な傾向があります。一方、中小企業では、人員や設備の制約から休日を増やすことが難しい状況にあることも多いのです。
年間休日110日がしんどいと感じる5つの理由
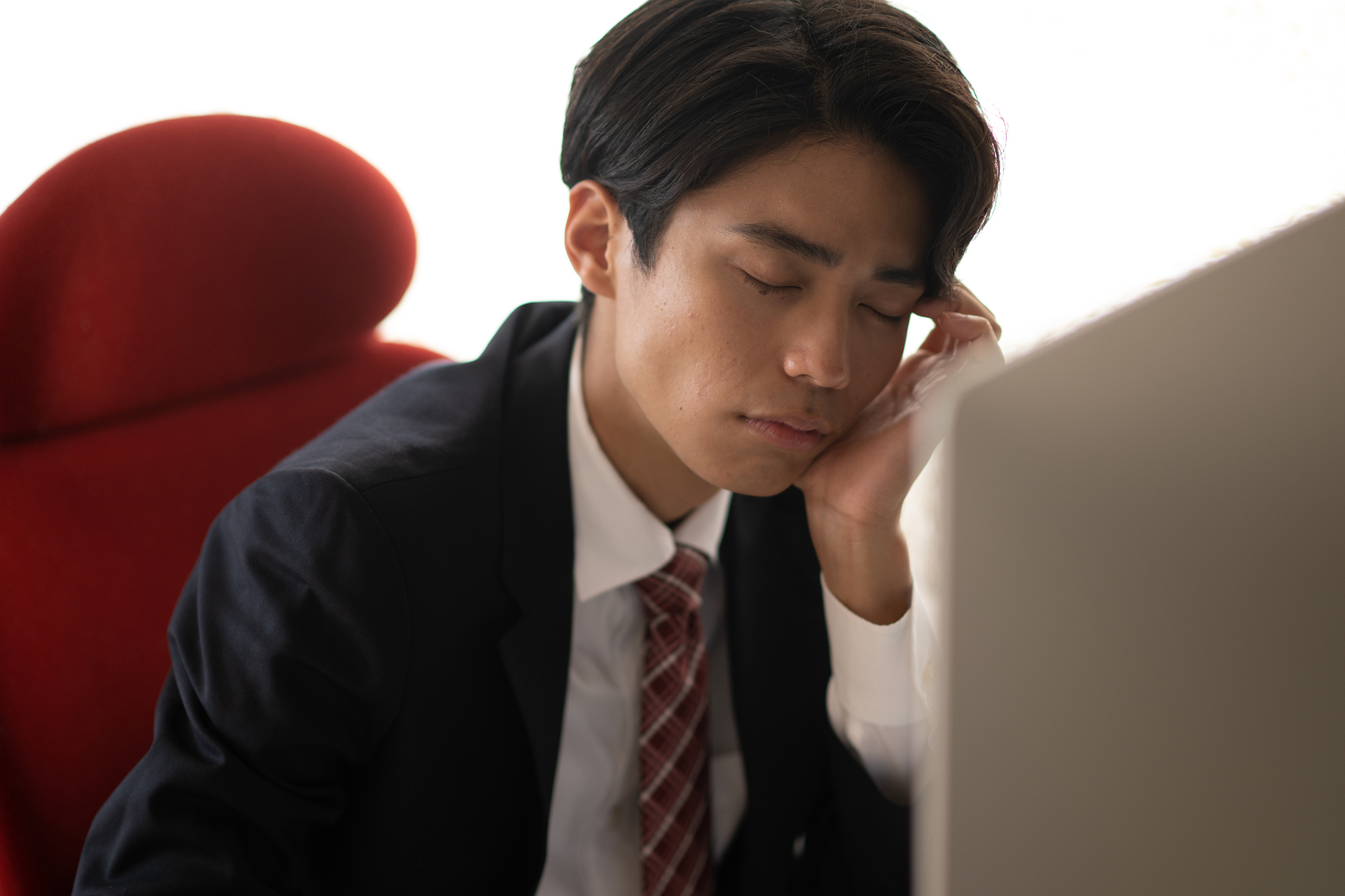
年間休日110日がしんどいと多くの人が感じるのはなぜでしょうか。
この理由として、単に日数の問題だけでなく、休日の質や仕事との関係など様々な要因が絡み合っていると考えられます。
ここでは、年間休日110日がしんどいと感じる主な理由を、以下の5つの観点から詳しく解説します。
- 長期休暇が取りづらい
- 土日で連休にならない
- 祝日が休みにならない
- 残業が多く週休2日制では疲れがとれない
- プライベート・家庭生活とのバランスが取りにくい
それでは順に見ていきましょう。
長期休暇が取りづらい
年間休日110日の企業では、長期休暇を取得することが難しい傾向にあります。これは、通常の土日以外の休日が限られているためです。
まとまった休暇を取るためには有給休暇を使う必要がありますが、業務の都合や人員配置の問題から、連続して休暇を取ることが難しいケースも多くあります。
特に夏季休暇やゴールデンウィーク、年末年始などの大型連休期間も、カレンダー通りの
休日の扱いとなることが多く、十分な休養期間を確保できないことがあります。
この結果、リフレッシュのための旅行や帰省なども計画が立てにくく、心身ともに疲労が蓄積しやすい状況となっています。
また長期休暇が取りづらい環境では、自己啓発や資格取得のための学習時間の確保も困難になります。その結果、キャリアアップの機会を制限することにもつながり、仕事のモチベーション低下の一因となることもあります。
土日で連休にならない
年間休日110日の場合、土日が必ずしも連続した休みとはならないケースが多く見られます。
特に土曜出勤が一部ある場合やシフト制を採用している職場では、週末であっても連続した休暇を取ることが難しい状況が発生します。
このような不規則な休日パターンは、生活リズムの乱れを引き起こす原因となります。特に土曜日が出勤となる場合、日曜日だけの休みでは十分な休養を取ることができず、疲労回復が追いつかない状況に陥りやすくなります。
このような状況が続くと精神的なストレスも蓄積しやすくなり、年間休日110日ではしんどいと感じるようになるのです。
祝日が休みにならない
年間休日110日の企業では、祝日が必ずしも休日とならないケースが多く見られます。
これは年間の休日数を調整するため、祝日を通常の営業日として扱うことが一般的だからです。その結果、他の多くの人が休みを楽しんでいる祝日も出勤しなければならず、精神的なストレスを感じる要因となっています。
また子どもの学校行事や地域の催し物など、祝日に開催されるイベントにも
参加しにくくなり、家庭生活や地域との関わりにも影響が出てきます。
特に大型連休期間中も出勤が必要となる場合は、旅行や帰省の計画が立てにくく、家族や友人との時間を持つ機会が制限されてしまいます。これらの要因が重なり、年間休日110日がしんどいと感じる大きな理由の一つとなっています。
残業が多く週休2日制では疲れがとれない
年間休日110日の企業は残業が多い傾向にあり、週休2日制だけでは十分な休息が取れないという問題が発生しています。
先述のとおり、年間休日数は企業規模が小さいほど少ない傾向があり、慢性的な人手不足や業務の効率化が進んでいない可能性が高いからです。そのような職場では平日の残業が常態化し、それによる疲労が週末までに回復しきれない状況が続きます。
また残業が多い環境では、帰宅時間が遅くなることで睡眠時間が削られたり、家事や育児の時間が確保できなくなったりすることも。その結果、休日は家事の遅れを取り戻すことに時間を取られ、本来の休養や余暇活動の時間が十分に確保できなくなってしまいます。
さらに精神的なストレスや身体的な疲労が蓄積することで、休日も十分な活力を持って過ごすことができず、ただ疲れを癒すだけの時間となってしまいがちです。このような状況が続くと、仕事へのモチベーションが低下したり、健康面での不調をきたしたりするリスクも高まります。
プライベート・家庭生活とのバランスが取りにくい
年間休日110日という環境では仕事とプライベートや家庭生活とのバランスを取ることが難しく、年間休日110日がしんどいと思う人が少なくありません。
特に育児や介護などの家庭責任を持つ社員にとって、
限られた休日で両立を図ることは大きな負担となります。
また友人との付き合いや趣味の活動、自己啓発のための学習など、個人の生活を充実させるための時間も制限されがちです。
特に休日が不規則な場合や祝日が出勤となる場合は、他の人々との予定を合わせることが難しく、社会的な活動や交流の機会が減少してしまう可能性があります。
このようなワークライフバランスの崩れは、長期的には仕事の生産性低下や心身の健康問題にもつながる可能性があり、年間休日110日のしんどさを増長する要因となっています。
年間休日110日がしんどいときの対処法 ~上手な休み方を考える~

年間休日110日の環境がしんどい場合、休日の使い方を工夫することで生活の充実度をアップできる可能性があります。
ここでは、限られた休日を効果的に活用するための具体的な方法や、休日の質を高めるためのテクニックについて解説していきます。
- 有給休暇の効果的な取得方法
- 連休を作るためのカレンダー活用術
- 休日と平日の時間管理のコツ
- 休日の質を高めるテクニック
それでは順に見ていきましょう。
有給休暇の効果的な取得方法
最初にお伝えしたとおり、有給休暇の取得率はあまり高くないのが現状です。しかし長期的にキャリアを続けることを考えると、休息時間を確保するために積極的に有給休暇を取ることが大切です。また戦略的に有給を取る計画を立てることで、より充実度を上げることができます。
たとえば祝日や週末と組み合わせて有給休暇を取得することで、連休を作ることが可能です。また繁忙期を避けて有給休暇を取得することで、休暇が取得しやすくなります。
計画性のある有給休暇の取得も重要です。年度初めに年間の有給休暇取得計画を立て、上司や同僚と事前に調整することで円滑な休暇取得が可能になります。
また忙しい職場や繁忙期には、半日単位での有給休暇取得も活用してみましょう。特に心身の疲労が蓄積する前に定期的に有給休暇を取得することで、年間休日110日という環境でもモチベーションやワークライフバランスを保つことができます。
連休を作るためのカレンダー活用術
限られた休日を最大限活用するために、年間カレンダーを効果的に活用することが重要です。祝日や会社の休日カレンダーを確認し、連休が取りやすい時期を早めに把握しておくことで、より効率的な休暇計画を立てることができます。
また業務の繁忙期と閑散期を把握し、
休暇を取得しやすい時期を事前に特定しておくことも大切です。
さらに同僚との休暇の重複を避けるため、部署内で休暇カレンダーを共有することも効果的です。
このような計画的なカレンダー活用により、年間を通じてバランスの取れた休暇取得が可能になります。
休日と平日の時間管理のコツ
休日を充実させるためには、平日の時間管理も重要です。
残業を減らし平日の夜の時間を確保することで、休日の疲労回復が促進できます。また平日の夜に軽い運動や趣味の時間を確保すると、休日のまとまった時間をより有意義に過ごすことができます。
また平日の家事や雑務を効率的に済ませる工夫も大事です。時短のための家電を揃えたり、食材(ミールキット)の宅配サービスを利用するのもひとつの方法です。
さらに時間管理アプリやタスク管理ツールを活用し、より効率的な仕事の仕方や生活リズムを作っていきましょう。このように日々の時間管理の工夫により、限られた休日をより効果的に活用することができるようになります。
休日の質を高めるテクニック
限られた休日をより充実させるためには、休日の過ごし方そのものを見直すことが重要です。単に休養を取るだけでなく、より積極的な活動を通じて充実感を得ることで、休日の質を高めることができます。
たとえば休日を「アクティブな時間」と「リラックスする時間」にバランスよく分けます。午前中に軽い運動や趣味の活動を行い、午後はゆっくりと休養を取るといった具合です。このメリハリのある過ごし方により、限られた休日でも充実感を得ることができます。
また休日を自己投資の時間として
活用することも効果的です。
キャリアアップのための学習や資格取得の勉強、健康維持のための運動など将来につながる活動を取り入れることで、休日の意義をより深めることができます。
さらに家族や友人との時間を大切にし、共有したい体験を計画的に実行することで、より思い出に残る休日を過ごすことができます。
年間休日110日がしんどいときの改善策 ~働き方を変える~

年間休日110日の環境でしんどさを感じる場合、働き方自体を見直すことも一つの選択肢です。
ここでは、より良い労働環境を実現するための具体的な改善策や、キャリアチェンジの可能性について解説していきます。
- 休日が多い部署に異動する
- 社内での働き方改革を提案する
- 年間休日が110日より多い企業に転職する
- フリーランスなど柔軟な働き方を検討する
それでは順に見ていきましょう。
休日が多い部署に異動する
同じ会社の中でも、部署によって実質的な休日数や働き方に違いがあることが多くあります。たとえば営業部門と管理部門では休日の取得パターンが異なったり、プロジェクト単位で働く部署では柔軟な休暇取得が可能だったりします。
このような状況を把握した上で、自分のスキルや経験を活かせる、かつ休日が多い部署への異動を検討することは、一つの有効な選択肢となります。人事部門との面談や上司との相談を通じて、より働きやすい部署への異動の可能性を探ることができます。
また、新規プロジェクトや新設部署など新しい働き方を試験的に導入している部門への異動も、より良い労働環境を実現する機会となる可能性があります。
社内での働き方改革を提案する
現在の部署内で、働き方改革を積極的に提案していくことも重要な改善策の一つです。
たとえばフレックスタイム制の導入や在宅勤務の拡大、業務の効率化による
実質的な休日増加など、具体的な改善案を提示することができます。
提案する際は、単に休日を増やすだけでなく、業務効率の向上や従業員のモチベーション向上、さらには企業の生産性向上につながる視点を含めることが重要です。
このような働きかけは、たとえ即座に大きな変化につながらなくても、徐々に職場環境を改善していくきっかけとなります。
年間休日が110日より多い企業に転職する
より良い労働環境を求めて、年間休日が多い企業への転職を検討することも一つの選択肢です。近年は年間休日120日以上を設定する企業が増加傾向にあり、特にIT業界やベンチャー企業では柔軟な休暇制度を導入している企業も多くあります。
転職を検討する際は、転職エージェントを活用することで詳細な企業情報や業界動向を効率よく把握することができ、より適切な転職先の選択が可能になります。
フリーランスなど柔軟な働き方を検討する
より柔軟な働き方を求めて、フリーランスやパラレルワーカーとしての働き方を検討することも可能です。
フリーランスとして働くことで、自身で仕事量や休日を調整することができ、より自由度の高い働き方を実現することができます。ただしフリーランスとして働く場合は、安定した収入の確保や社会保険の手続き、税務申告など、自己責任で対応する必要があります。
そのため十分な準備期間を設けて、副業や兼業から始めて徐々に移行していくなど、
リスクを最小限に抑えながら新しい働き方にチャレンジすることをおすすめします。
休日を重視した転職活動のポイント

年間休日110日がしんどいと感じている方が、より良い労働環境を求めて転職を検討する場合、どのような点に注意して転職活動を進めればよいのでしょうか。
ここでは、休日を重視した転職活動における具体的なポイントについて解説します。
- 年間休日数で会社を選ぶコツ
- 面接での休日に関する質問方法
- 転職エージェントの活用
それでは順に見ていきましょう。
年間休日数で会社を選ぶコツ
転職先を選ぶ際は、単純な年間休日数だけでなく、実質的な休暇の取りやすさを総合的に評価することが重要です。
求人票に記載された年間休日数に加えて、有給休暇の取得率や残業時間、フレックスタイム制度の有無なども重要な判断材料となります。転職サイトや企業の口コミサイトなどを活用して、実際の労働環境について詳しく調査しましょう。
さらに企業の成長性や将来性も考慮に入れることが大切です。
特に近年は働き方改革の影響で休日が増加傾向にある業界も多いため、将来的な動向も考慮に入れる必要があります。反対に休日が多くても企業の業績が不安定では、長期的なキャリア形成の観点からリスクとなる可能性があるので注意が必要です。
面接での休日に関する質問方法
面接で休日や労働時間について質問する際は、単に休日数を確認するだけでなく、より具体的な働き方について質問することが大切です。具体的な質問を通じて、入社後のミスマッチを防ぐことができます。
たとえば
- 繁忙期の休日出勤の頻度
- 休日の振替制度の運用実態
- 連休の取得しやすさ
といったかたちで実務的な観点からの質問が効果的です。
また「働き方改革への取り組み状況」「今後の休日増加の予定」などについても確認することで、企業の労働環境改善への姿勢を把握することができます。
質問する際は、単なる待遇面での関心ではなく、より効率的な働き方を目指したいという積極的な姿勢を示すことが重要です。
転職エージェントの活用
休日を重視した転職活動を効果的に進めるために、転職エージェントの活用は非常に有効です。
転職エージェントは、企業の休日制度や労働環境について詳しい情報を持っており、求人票には載っていない実態についても把握していることが多いです。
また転職エージェントを通じて、同業他社との比較や業界動向についての情報も得ることができます。
特に休日が多い企業や働き方改革に積極的な企業の紹介を依頼することで、
より効率的な転職活動が可能になります。
さらに面接対策や条件交渉においても、エージェントのサポートを受けることで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。
年間休日110日の意外なメリットとは

ここまで年間休日110日のしんどい部分について掘り下げてみてきましたが、見方を変えると、実はこの休日設定にも意外なメリットが存在します。
ここでは、年間休日110日の環境で働くことで得られる意外なメリットや、それを活かした働き方について解説していきます。
- 年間休日110日の意外なメリット
-
- メリハリのある働き方ができる
- 休日の過ごし方が計画的になる
- 質の高い休暇計画により満足度が上がる
- 仕事へのモチベーションを保てる
- 体力やストレス耐性が身につく
それでは順に見ていきましょう。
メリハリのある働き方ができる
年間休日110日の環境では、限られた休日を意識することで仕事とプライベートの切り替えが明確になるというメリットがあります。
休日が多すぎると仕事モードと休息モードの境界が曖昧になりがちですが、適度な休日数であることで、より意識的に仕事に集中し、休日をしっかりと休養に充てることができるためです。
また限られた時間をやりくりするため、自然と時間管理能力や業務の優先順位付けのスキルが向上します。これは長期的なキャリア形成においても重要なスキルとなり、将来的な仕事の効率化にもつながっていきます。
さらに休日が少ないからこそ、平日の仕事中により集中して取り組む意識が高まり、結果として業務効率が向上する効果も期待できます。
休日の過ごし方が計画的になる
休日が限られているからこそ、休日の使い方をより計画的に考えるようになるのもメリットのひとつです。
特にスキルアップや資格取得のための学習時間を確保する際に、計画的な時間配分が可能になります。
休日が多すぎると、かえってダラダラと過ごしてしまいがちですが、限られた休日であることで
より効果的な時間の使い方を考えるきっかけとなるのです。
また、限られた休日を有効活用するために家族や友人との予定も事前準備や調整をしっかり行うようになり、より充実した時間を過ごせるようになります。
質の高い休暇計画により満足度が上がる
年間休日110日という環境下では、休暇の質を高めることに意識が向きやすくなります。
限られた休日だからこそ、その一日一日をより大切に過ごそうという意識が自然と高まり、結果として休暇の満足度が向上する可能性があります。休暇の計画を立てる際も慎重に内容を吟味し、自分にとって本当に価値のある過ごし方を選択するようになります。
趣味の充実や自己啓発、家族との質の高い時間の確保など意識的な休暇の使い方を考えるようになることで、心身のリフレッシュ効果を高めることができます。
このような質を重視した休暇の過ごし方は、結果として仕事のパフォーマンス向上にもつながっていきます。
仕事へのモチベーションを保てる
年間休日110日という環境は、意外にも仕事へのモチベーション維持にプラスに働くことがあります。
休日が比較的少ないからこそ、「仕事の日」という意識が明確になり、その日は仕事に全力を注ぐという心構えが自然と身についていきます。また休日が多すぎると、かえって仕事モードへの切り替えが難しくなることもありますが、この休日数であれば適度な緊張感を保ちながら働くことができます。
休日と勤務日のリズムが一定であることで、心身の状態を安定させやすく仕事への集中力も維持しやすくなります。
体力やストレス耐性が身につく
年間休日110日という環境で働き続けることで、自然と体力やストレス耐性が向上していきます。
この休日数で働き続けるためには、効率的な体力の使い方や休息の取り方を工夫する必要があり、それが結果として心身の強さを育てることにつながります。
特に限られた休日を上手く活用して心身のリフレッシュを図る能力や、平日のストレスを適切にコントロールする力が自然と身につき、将来のキャリアにおいても大きな強みとなります。
このような環境で働く経験を積むことで、予期せぬ残業や突発的な業務にも
冷静に対応できる精神的な強さも養われていくと考えられます。
年間休日110日がしんどいと感じる人のよくある疑問と回答

年間休日110日の環境で働く人々から、よく寄せられる疑問や不安について、具体的な回答とアドバイスをまとめました。これらの情報は、現在の働き方に悩みを感じている方や、今後のキャリアプランを考える上での参考になるはずです。
- 年間休日120日の義務化はいつから?
- 年間休日110日の会社で働くときに気をつけることは?
- 年間休日110日、どうすればもっと充実できる?
それでは順に見ていきましょう。
年間休日120日の義務化はいつから?
年間休日120日の義務化については、2024年時点では具体的な法制化の予定はありません。
ただし、働き方改革の推進により多くの企業が自主的に休日を増やす傾向にあります。特に大手企業やIT業界では、年間休日120日以上を設定する企業が増加しています。
政府の「働き方改革実行計画」においても、労働時間の短縮や休日の確保が重要な課題として位置づけられていますが、まずは各企業の自主的な取り組みとして、休日増加の動きが広がっていくことが期待されています。
年間休日110日の会社で働くときに気をつけることは?
年間休日110日の企業で働く際は、まず有給休暇を計画的に取得することが重要です。
年度初めに年間の休暇計画を立て、
上司や同僚と調整しながら効果的な休暇取得を心がけましょう。
また残業時間の管理や業務の効率化にも注意を払い、限られた時間で最大限の成果を上げる工夫が必要です。
健康管理も重要なポイントです。休日が少ない環境では心身の疲労が蓄積しやすいため、日々の睡眠時間の確保や適度な運動、ストレス解消などを意識的に行うことが大切です。
また休日の過ごし方を工夫し、効果的なリフレッシュを心がけることも必要です。
年間休日110日、どうすればもっと充実できる?
年間休日110日の環境でも、以下のように働き方を工夫することで充実した生活を送ることができます。
- 平日の時間管理を見直す
- 効率的な業務遂行を心がける
- 残業を減らす
また休日の使い方を工夫することも重要です。家事や雑用を平日の帰宅後に済ませておくなど、休日を有効活用するための準備を整えることで、より充実した休日を過ごすことができます。
そして休みの日は、趣味や自己啓発、家族や友人との時間など、自分にとって価値のある活動を計画することで、休日の満足度も高めることができます。
さらに同僚との協力体制を築き、休暇を取得しやすい環境を整えることも大切です。
みんなが使っている転職サービス上位6選 【1,382人に聞いた転職サービス利用状況】
実際に登録したことのある転職サービスについてアンケートをとりました。アンケート結果として、みんなが使っている転職サービスの上位6サービスは以下です。
- 1位|リクルートエージェント(821人)
- 2位|doda(564人)
- 3位|リクナビNEXT(389人)
- 4位|マイナビAGENT(312人)
- 5位|ビズリーチ(288人)
- 6位|エン転職(282人)
※転職サービスの利用アンケート(クラウドワークス) 回答数:1,382 / 集計期間:2024年09月19日~10月03日
1位|リクルートエージェント(利用回答数:821人) 圧倒的な求人数
「リクルートエージェント」は、求人数、安定したサービス品質で、まずは登録が必須のエージェントです。
まず何と言っても求人数が多いことがおすすめの理由として挙げられます。転職成功の実績も多く、優れているのは求人の数だけではありません。業界に精通したアドバイザーが在籍しているので、ぴったりの求人を見つけ出してくれます。求人やサービスの質・量ともにトップクラスで転職エージェントとしては定番・王道のサービスです。
営業・技術系を中心にあらゆる業種・職種をカバー。総合型ながら条件ごとに特化したページもあり、使いやすいのも人気の理由です。
- リクルートエージェントのおすすめポイント
- 求人数が圧倒的に多い
- 業界に精通したアドバイザーが在籍
- 条件ごとに特化したページがあり使いやすい
基本データ
| リクルートエージェント | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人474,685件/非公開求人399,542件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | エージェントサービス、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供 |
| 拠点 | 東京・北海道・宮城・宇都宮・さいたま・千葉・横浜・金沢・新潟・長野・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡 |
| URL | https://www.r-agent.com/ |
2位|doda(利用回答数:564人) エージェント/サイトの一体型で自分でも応募が可能
「doda」は、人材紹介・転職支援を行う大手「パーソルキャリア」が運営する総合型転職サイトです。エージェントサービスも利用できる点が人気の理由の1つになっています。
dodaも求人数が多く、非公開求人も条件が良いものが多いのが大きなポイントです。
また転職サイトと転職エージェントの一体型で、使い方の自由度が高いのもおすすめポイント。エージェントサービスでは専任のキャリアアドバイザーがサポートしてくれます。なお企業との対応は採用プロジェクト担当が行い、求職者と企業とでそれぞれ別のプロフェッショナルが対応します。
- dodaのおすすめポイント
- 非公開求人も好条件多数
- 転職サイトと転職エージェントの一体型で自由度が高い
- 専任のキャリアアドバイザーがサポート、企業は別のプロフェッショナルが対応
基本データ
| doda | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人262,342件/非公開求人31.049件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、年収査定、合格診断、レジュメビルダー、「自己PR」発掘診断、転職タイプ診断、はたらく女性のためのモヤモヤ解消診断、オンライン仕事力診断 |
| 拠点 | 東京・横浜・札幌・仙台・静岡・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・広島・福岡・鹿児島 |
| URL | https://doda.jp/consultant/ |
3位|リクナビNEXT(利用回答数:389人) 求人サイト群の中でも最大級の求人数と使いやすさ
「リクナビNEXT」は大定番の転職サイトで、サイトの見やすさや使いやすさにも定評があります。
エージェントなしの狭義の転職サイトの中では、求人数はトップクラス。新規の求人も多く、定期的にチェックすることで希望に合う求人に出会える可能性が高まります。
ツールが便利でサイトが使いやすいのも特長です。たとえば「気になるリスト」を使うと、気になる企業や後でゆっくりチェックしたい企業をリスト化できるほか、気になるに追加した企業から面接のオファーが来る可能性があります。
そのほか、公開求人・非公開求人の企業からオファーがもらえる「オファーを待つ」、自己分析ツール「グッドポイント診断」などがあります。
- リクナビNEXTのおすすめポイント
- サイトが見やすく使いやすい
- 狭義の転職サイトでは最大級の求人数
- 多くの人が利用している定番の転職サイト
基本データ
| リクナビNEXT | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人824,000件以上(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | オファー、気になるリスト、グッドポイント診断 |
| URL | https://next.rikunabi.com/ |
4位|マイナビAGENT(利用回答数:312人) 20代・30代の求人に強い
「マイナビAGENT」は、さまざまな転職サイトを運営している株式会社マイナビによる転職エージェントです。きめ細かいサポートが受けられると評価されています。
とくに20代・30代の求人が多いので、その世代の人にはおすすめです。また全国に拠点があり地方の求人も充実しているので、大都市圏以外で探している人にもぴったりです。
履歴書や職務経歴書のサポートも充実、初めての転職でも安心して利用できます。IT、営業など業種・職種別のサービスもあります。自分が探している業種と一致するならより探しやすくなるでしょう。
- マイナビAGENTのおすすめポイント
- 20代・30代の求人が多い
- 地方の求人も充実
- 履歴書や職務経歴書のサポートもあり安心
基本データ
| マイナビAGENT | |
|---|---|
| 公開求人数 | 非公開 |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| 拠点 | 拠点情報はこちらをご確認ください |
| URL | https://mynavi-agent.jp/ |
5位|ビズリーチ(利用回答数:288人) ハイクラス向けで企業からスカウトが受けられる
「ビズリーチ」は、ハイクラス求人が多いのが特徴の転職サイトです。厳密にはスカウト型のサイトで、エージェントではありません。登録するとヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられます。
最大の特長は、ハイクラス求人が多いことです。年収1,000万円以上の求人が1/3以上を占めています。一定以上の経験やスキルがある人が転職活動するのに役立つサービスです。
もう1つの大きな特徴として、登録するだけでヘッドハンターや企業からスカウトが届く点があります。以前は「スカウト」と「プラチナスカウト」の2種がありましたが、今は「プラチナスカウト」に一本化されています。プラチナスカウト経由での採用は全体の約70%。採用される可能性が高く、スカウトが届いたら大きなチャンスです。実際、企業からスカウトが届いた場合は書類選考が免除されます。
基本的にヘッドハンターはアドバイスをしませんが、場合によってはアドバイスをもらえることもあります。無料プランと有料プランがあり、有料プランは制限なく求人に応募できます。
- ビズリーチのおすすめポイント
- ヘッドハンターや企業からのスカウトが受けられるハイクラス向けサイト
- 企業からプラチナスカウトが来た場合は即面接が可能
- 有料プランなら制限なく求人に応募できる
基本データ
| ビズリーチ | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人138,081件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | スカウトサービス、有料プラン(プレミアムステージ) |
| 拠点 | 東京・大阪・名古屋・福岡・静岡・広島 |
| URL | https://www.bizreach.jp/ |
6位|エン転職(利用回答数:282人) サイトが使いやすく情報も充実、利用者の満足度が高い

「エン転職」は、人材サービス大手の一つエン・ジャパン株式会社による転職サイトです。エージェントサービスも利用できます。
オリコン顧客満足度調査の転職サイト部門で、2018年から2024年まで7年連続で総合満足度No.1となっています。サイトの使いやすさは定評があり、自力で検索・応募するのに適したサービスです。口コミなどの情報も充実しており、企業間の比較検討もしやすくなっています。
さらに転職サイトのほか転職エージェントとしても利用することができ、非公開求人も多数保有しています。大手ですが最大手ほどでない規模で、きめ細かいサポートを受けることが可能。また女性向けのページのほか、ミドルや若手ハイキャリアなどに特化した関連サイトもあります。
- エン転職のおすすめポイント
- 2018年から2024年まで7年連続で総合満足度No.1
- サイトが使いやすいほか情報も充実
- 非公開求人も多数保有
基本データ
| エン転職 | |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人152,678件(2024年10月22日現在) |
| 提供サービス | エージェントサービス |
| URL | https://employment.en-japan.com/ |
さいごに

この記事では、年間休日110日の内訳から、年間休日110日がしんどいと感じる理由と対処法、さらに意外なメリットまで詳しく解説してきました。
年間休日110日という環境は、確かに多くの人にとって負担に感じられる要素を含んでいます。しかし働き方の工夫や休日の効果的な活用、さらには転職という選択肢も含めて、様々な改善の可能性が存在します。
重要なのは、自分自身のワークライフバランスや健康管理を第一に考え、より良い働き方を模索し続けることです。
この記事が、より充実した働き方を実現するためのヒントとなれば幸いです。