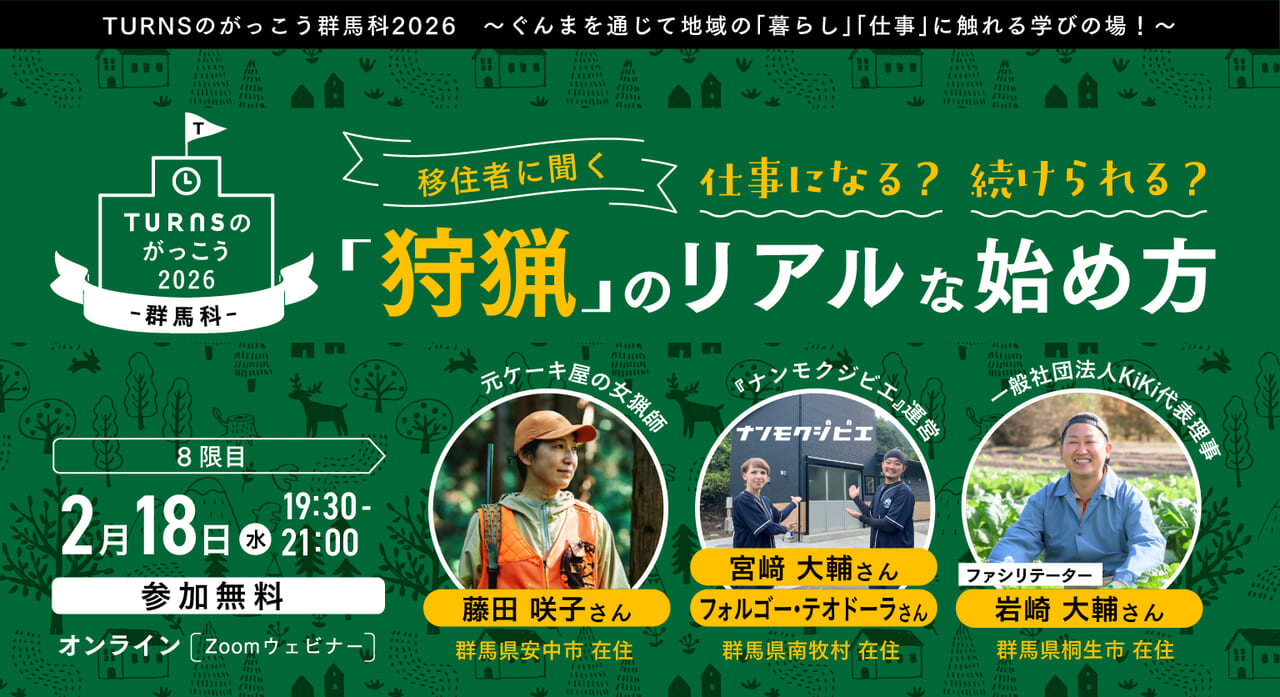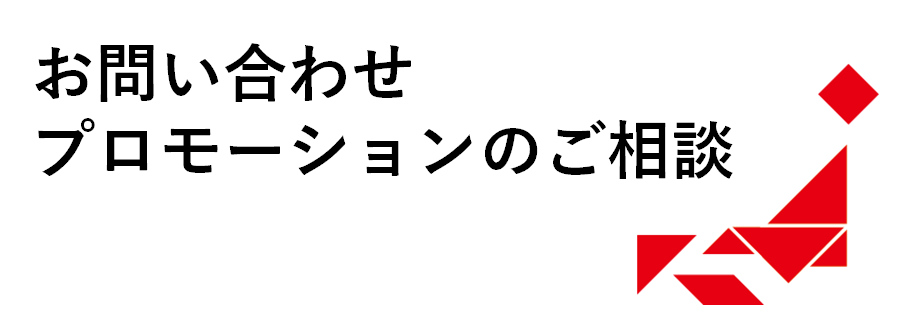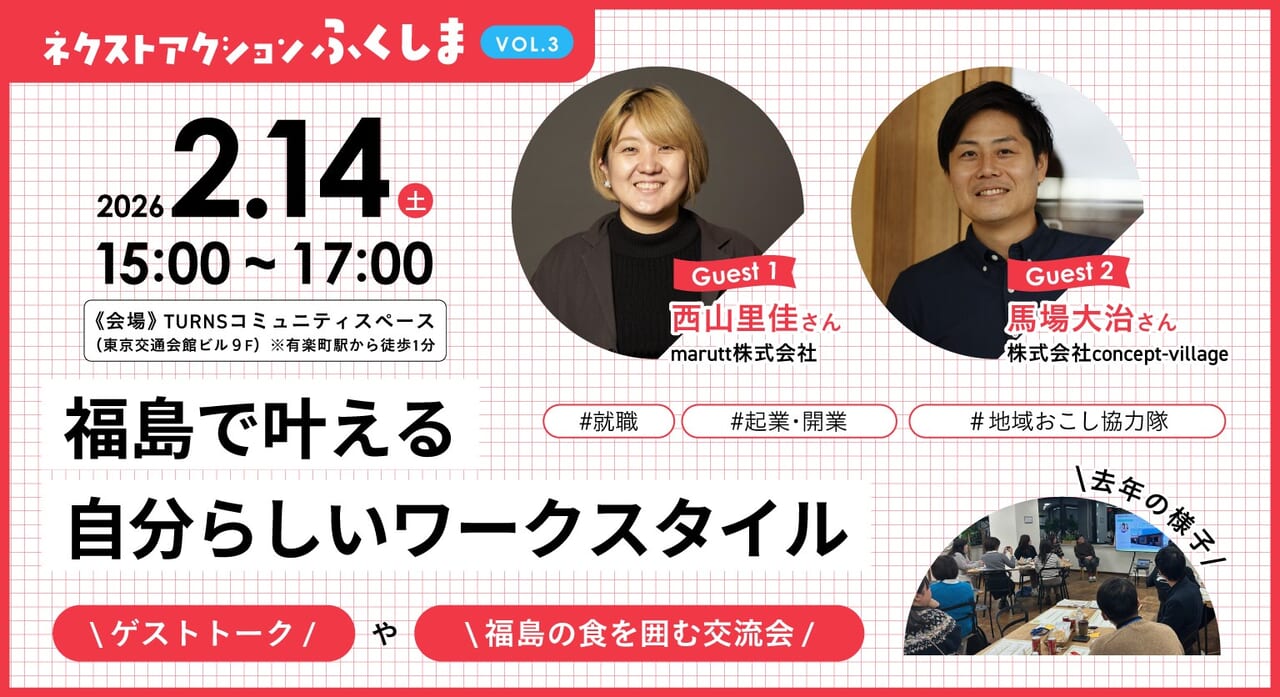すっかり一般化したかのように見える「地域おこし協力隊」。しかし、地域おこし協力隊制度設計の専門家、西塔大海さんのもとには、全国の隊員、受け入れ側からの相談が絶えることなく舞い込んできます。制度をよりよくしていくには、協力隊員志望者、現役協力隊員、そして受け入れ側それぞれが、問題を共有すること。TURNSで連載中の「誰も書かない地域おこし協力隊のトリセツ」では、毎回地域おこし協力隊の現場で起きている「困りごと」を挙げ、その解決策を西塔さんが解説しています。
西塔さんコメント
「地域おこし協力隊はローカルキャリアの入口としてすっかり定着しました。特に20~30代にとっては、当たり前の就職・転職先です。地域での存在感も増しています。地域づくりに関わる活動をしている人なら協力隊の知り合いが数人いるのではないでしょうか。
実際、毎年千数百人が新しく協力隊になり、全国で5000人が働いています。任期を終えた方を含めると1万人以上と言われています。
それだけ一般的な仕事になってきてもなお、「思っていた活動と違った」という隊員や、「応募者が集まらない」「期待していた成果が得られない」という職員や地域住民が後を断ちません。現場ではいったい何が起きているのでしょう? この連載では、今まで誰も書かなかった「協力隊制度」の取り扱いについて書いています」
第1回
「こんなはずじゃなかった」ミスマッチはどうして起こるのか
vol.48 2021年 10月号掲載
協力隊側の視点でミスマッチにならない自治体の選び方を解説。ミスマッチの構造の解析。
第2回
応募者が集まる募集の作り方 前編
vol.49 2021年 12月号掲載
自治体職員向けに、募集が集まらない理由と対策を紹介し、募集企画作成を徹底解説。
第3回
応募者が集まる募集の作り方 後編
vol.50 2022年 2月号掲載
自治体職員向けに、募集の人物像設定、ウリの作り方、募集の経費まで。vol.49の前編と合わせてどうぞ。
第4回
採用面接は、ミスマッチを防ぐ最後の砦
vol.51 2022年 4月号掲載
自治体職員向けに、採用基準の設定、絞り込み方、面接の準備、質問内容までを解説。志願者は読まないこと(笑)
第5回
「協力隊として上手くいく人が1年目に実践していること」
vol.52 2022年 6月号掲載
協力隊1年目の方向けに、初任者研修の内容です。報連相、信頼貯金、予算ルールなど初任者の必須知識。
第6回
「協力隊は起業すべき?任期終了後に向けて自分の仕事をつくる(考え方編)」
vol.53 2022年 8月号掲載
協力隊2〜3年目向けに、起業が推奨される本当の理由、就職と独立の組合せ方など。
第7回
「協力隊は起業すべき?任期終了後に向けて自分の仕事をつくる(実践編)」
vol.54 2022年 10月号掲載
任期終了後に、起業や就職という明確な答えが出ていないときでも役に立つ対処法。
第8回
「協力隊にはなぜ企画書が必要なのか」
vol.55 2022年 12月号掲載
協力隊向けに企画書の必要性と書き方、自分の企画が通らない時の対処法をご紹介。
第9回
「地域おこし協力隊の学び方」
vol.56 2023年 2月号掲載
「協力隊は独学するもの」? マニュアルのない地域おこし協力隊の学び方について。
第10回
フリーミッション型( FM)型協力隊の罠
vol.57 2023年 4月号掲載
〝自由〟こそがミスマッチを生む? 知っておくべき「フリーミッション型」の注意点。
第11回
地域おこし協力隊の聴く力
vol.58 2023年 6月号掲載
地域おこし協力隊に必要なコミュニケーション力の原点、「聴く力」について。
第12回
地域おこし協力隊の活動を支援する
vol.60 2023年 10月号掲載
隊員たちがスムーズに活動に取り組める支援のあり方とは?
第13回
「できそう×面白そう」で応募が集まる募集要項をつくる
vol.62 2024年 2月号掲載
数を増やし、ミスマッチを防ぐための、応募者視点の要項の作り方
第14回
地域おこし協力隊の可能性! 妄想アイデア集
vol.63 2024年 4月号掲載
西塔さんが提案する協力隊業務のアイディア集
第15回
地域おこし協力隊の物件探しはいつ?誰が?
vol.64 2024年 6月号掲載
住まいは受け入れ側、本人、誰が用意すべきか?
第16回
〝起業型〟地域おこし協力隊の現実的な募集企画を考える
vol.65 2024年 9月号掲載
「全部自分で考えて」と放り出されることもあるので要注意!
第17回
地域おこし協力隊推進要項の一部改正 運用のルールが変わります
vol.67 2025年 2月号掲載
改正で隊員の活動内容が対象外になってしまうことも起こりうる??
西塔大海 さいとうもとみ
1984年山形生まれ。地域おこし協力隊制度設計の専門家。2013年から福岡県上毛町で協力隊に。任期後も福岡を拠点に家族と暮らし続けている。協力隊を導入する自治体の募集支援、受入体制改善、活動支援を北海道から九州まで全国で行う。合作株式会社取締役。さとのば大学講師。愛犬の名前は村長。