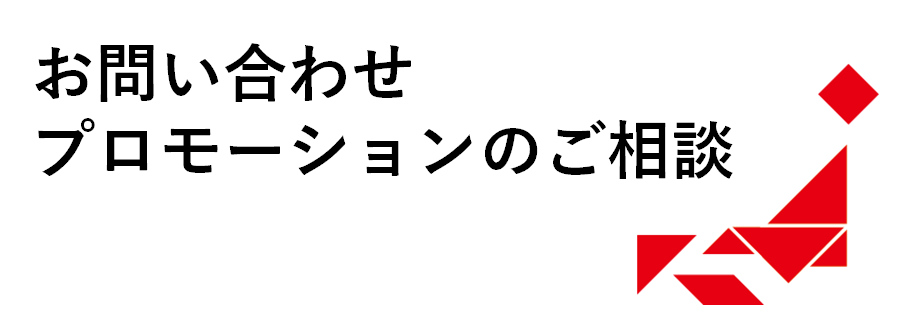山口市とTURNSは、企業と地域を結び、関係人口の創出に繋げるプロジェクトに取り組んでいます。
3年目を迎える今年は、「ローカルビジネスの視点で地域の未来を考える探究カレッジ」と題し、ローカルビジネスをよく知るゲストを講師に迎えて地域の発展のために何ができるのか、実践的なワークを交えて講義。
市内の事業者や起業家、大学生など異なるバックボーンを持つ参加者が集まり、新たな出会いや価値を共有する場として活発な交流も生まれました。
\ファシリテーター/

大森 愛さん(,too inc. )
三重大学教育学部音楽科卒業後、広告代理店の企画営業を経て、メーカー転職後は新規事業部にて商品開発からコンセプト立案、ブランディング、宣伝PRなど、開発から販売までに一貫して従事。その後、伝統工芸や地場産業のPRに特化した企業にて日本全国の職人や工房を訪ね歩き、それぞれの地域や工芸の歴史や文化、想いに耳を傾ける仕事に関わる。独立後は地域ブランディングを中心に「想いをカタチに」「朗々と暮らす」をモットーとしながら地域のブランディングや食に関わる事業に携わっている。
第1回(11/1):「人手不足の地域のおけるこれからの生存戦略」

第1回講師:坂口剛さん|野村総合研究所 未来創発センター エキスパート研究員/東京
ローカルの大局を知り、地域に必要な力を学ぶ
初回は、ローカルの大局を学ぶ回。講師の坂口さんは地域共創を専門に扱うスペシャリストで、さまざまなローカルの事業者と密に接し、事情に精通しています。講義は「地域に必要な人材育成」と「設定すべきターゲット」の二軸で行われ、コロナ禍で売り上げを伸ばした事業者の例を挙げて解説。ローカルで生き残るために必要な「主体性」「創造性」「機能補完」「スピード感」のうち、すぐに実践することが難しい「創造性」を意識するため、既存の商品から新たな商品やサービスを考えるワークを行いました。

「みかん」をテーマにしたチームからは「房単位で売る」「すっぱいみかんを、〝悲しい時に食べるみかん〟として売り出す」などのアイデアが。山口市阿知須地域の伝統的な漬物である「寒漬」をテーマにしたチームからは「個食タイプにして都会のサラリーマンに訴求する」というアイデアが。同じものでも視点をずらす場所によってオリジナリティが生まれることを学んだ参加者からは「まさに今、自分が必要としているもの。可能性が広がった」との声が上がり、坂口さんは「新たに市場を作るマーケットアウトにぜひ挑戦してほしい」と、講義を締めました。
第2 回(11/15):「ローカル企業が全国で輝く商品づくりに取り組むための差別化戦略」
同じ事業者の事例から自身の強み・弱みに気づく

第2回講師:加瀬宏行さん|株式会社セガワ 代表取締役/千葉
第二回では、地域で活躍する事業者として、千葉県旭市で落花生ブランド「Bocchi」を手がける「株式会社セガワ」の加瀬さんをお招きしました。
「間に人を挟むと商品の価値は一部しか伝わらない」と、自ら営業先に通う。アイデアはすぐに商品化し、自社のマルシェや店舗でテストマーケティングを行う。スピード感を持ってトライ&エラーを繰り返す加瀬さんの姿に「悩む前に真似からでもはじめたい」と、背中を押された参加者たち。

その後のワークでは、自身の今を振り返り、強みと課題を分析。「次世代に地域の食文化を繋いでいきたい」とすでに動き始めている事業者に対しては「もう未来が見えていますね」と賛辞を送り、「同じ生産者としてこれからの農業の未来をどう考えているか」の問いには、「農業がなくなることはないが、楽しいものにしたい。人を巻き込む力が必要」と答えた加瀬さん。講義の最初に「同じ事業者として、教えるのではなく学び合いたい」と話していたとおり、立場を同じくする者同士の対話がそこにはありました。
講義のあとには、「Bocchi」の落花生や参加者が開発したジュース、食品を持ち寄り、交流会を開催。互いの商品について新たな視点を共有したり、協力できる部分はないか話し合ったりと活発な交流が行われ、さっそく「スピード感」を意識して実践する姿が印象的でした。
第3回(12/4):「伝えるから伝わるへ~魅力や個性の可視化~」
伝えるべき人に伝わるスキルを磨く

第3~4回講師:岡山史興さん|,too inc.代表取締役/富山
三回目の講義では、富山県舟橋村を拠点に活動する岡山さんから「伝え方」を学びました。長崎県で生まれ育ち、当たり前に「平和」に関する活動に携わってきた岡山さん。しかし、関東の大学に進学すると、まわりの人たちにとって「平和」はそれほど身近な話題ではないことを知ります。そして、より多くの人に平和を身近な話題にしてもらうための手段を探るなかで、人を巻き込むには「伝える」ことよりも「伝わる」ことが大切なのだと気がついたそうです。現在もその軸は変わらず「それによって誰が喜ぶのか」を常に頭に置いているとのこと。ワークではその考え方を自身に置き換え、より伝わる表現を探ります。
ある古民家再生に取り組む参加者に対しては、ともに「強みのコア」を探りながら答えを導き出す場面も。「以前は空き家を改修すること自体が目標だったが、今は地域との繋がりを大切にしながら空き家改修を通じて人を呼び込み、還元することをゴールにしたい」と、彼が持つ「誰かが喜ぶ価値」を言語化していきました。
第4回(12/19):「伝えるから伝わるへ~魅力や個性の可視化~」未来に向けたアクション宣言

いよいよ最終回。この回では総括として「自身の一言キャッチコピー」を作成。セミナーを経て参加者たちが何を学び、考えたのかがここに集約されています。現状を見つめ直し、一年後、三年後に向けた行動を発表する参加者たちの目には、未来を自身で切り拓くという決意が見て取れました。
また、坂口さんから「互いの知見を環流させることで、新たな知見が生まれる」とのコメントが、加瀬さんからは「皆さんとの交流で刺激を受け、翌週には新たな営業を行い、イベント実現に向けて動いています」と激励の言葉が寄せられ、「勇気づけられました」と振り返る参加者たち。「キャッチフレーズの作り方などを通して、まさに今知りたいことを教えていただけました」「これからどうしていくか悩んでいたので、さまざまな考え方を知り参考になりました」と、意義のある時間を過ごすことができたようです。
岡山さんは「外と繋がることも大切ですが、まずは中にいる素敵な仲間と繋がることで、魅力が掛け算になる」と総括。最後に「今回は講師として知り合いましたが、今後は地域で事業を行う友人のひとりとして仲良くしていきましょう」とエールを送り、大きな拍手とともに今年度のセミナーが終了しました。
未来に向けたアクション宣言!
「地域の特性を活かした、目指せ!巻き込み型オールマイト農家」
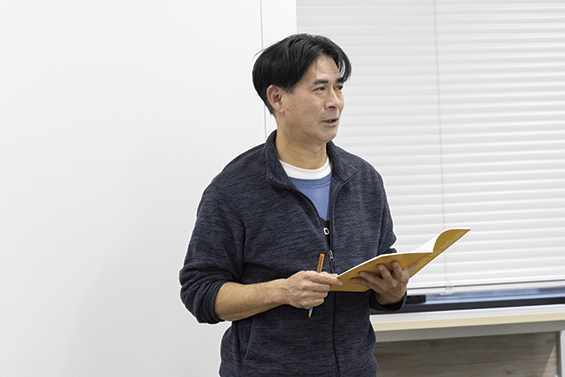
阿東という地域が持つ特性と、自分が持つ人を巻き込む力を活かし、多芸多彩な農家を目指します。そして、若い人に自分の経験を伝え、活躍できる場をつくっていきたいです。
「自然と遊び、心が踊る。歩幅に合わせたいい波を」
今後1年は「できることをやる」のではなく、自分の心が向いたことに対してチャレンジを重ね、3年後はそのチャレンジから見出したいくつかの柱ごとに仲間を募って夢のある楽しいことを実現させたいです。
「なんちゃって巻き込まれフィクサー」

何か事業を始めたいという人がいて、地域の中でうまく話がまとまらないときに、話を聞いたり第三者の意見を持ってきたりと、地域内での空気を醸成していくこと。そして、巻き込まれたことに対して、心の底から自分が楽しんでいくこと。その2つを意識していきたいです。
「普段は田舎の便利屋さん 任せて安心地域を笑顔にする古民家再生事業」

地域おこし協力隊の活動を経て、地域を笑顔にすることが1番やりたいことだと気づきました。1年後は会社を作って地域の信頼を獲得し、3年後には関係人口創出に繋がる事業を起こしたいです。
「自然とくつろげる場所づくり」

これまでがむしゃらにみかん観光農園の経営に取り組んできましたが、もっとお客様の満足度を高めたい。1年後、3年後には農園をもっとくつろげる場所にして、それを付加価値にしていきたいです。
「山口のおばちゃんになろう」

元保育園調理師の経歴を活かし、遊び場の提供や食育・木育など、山口市の親子のための活動をしたいです。また、まずは真似からでもいいんだと教えていただいたので、おにぎり屋さんに挑戦してみたいです。
地域の潜在的なヒーローを顕在化する」

地域のプレイヤー同士の繋がりを作り、インナーコミュニケーションの醸成に取り組んでいます。そして、1年後、3年後に人を呼び込めるような地域づくりに発展させていきたいです。