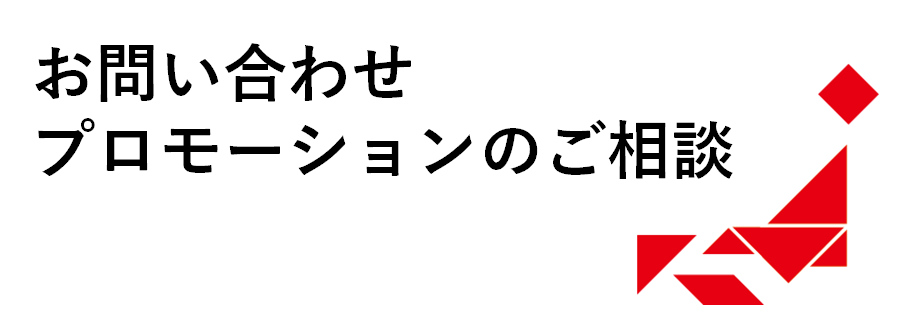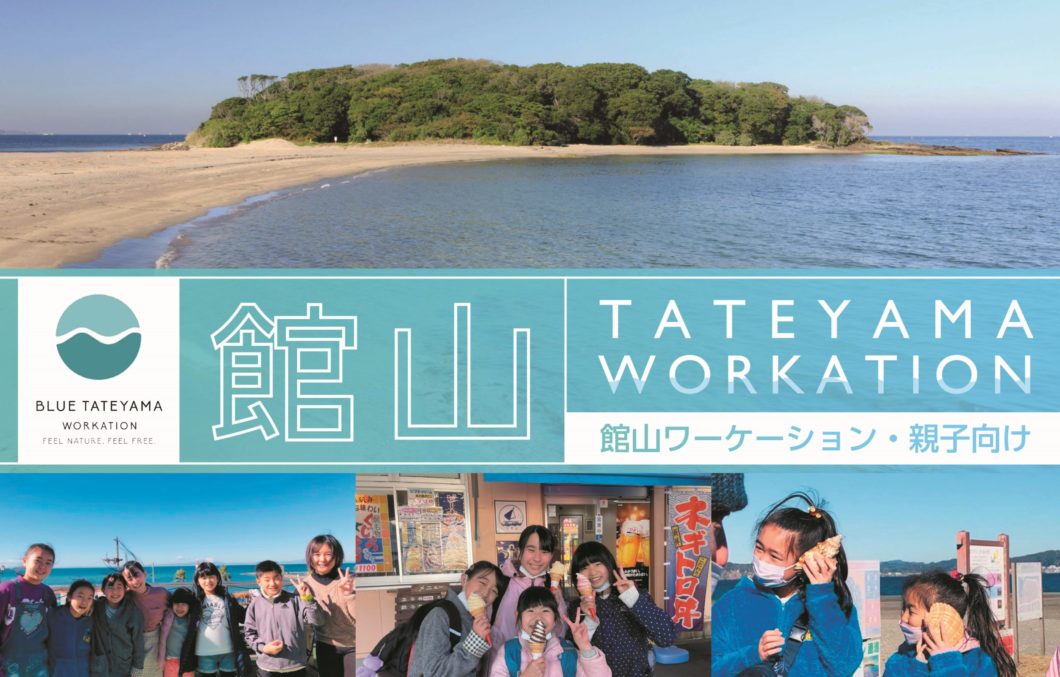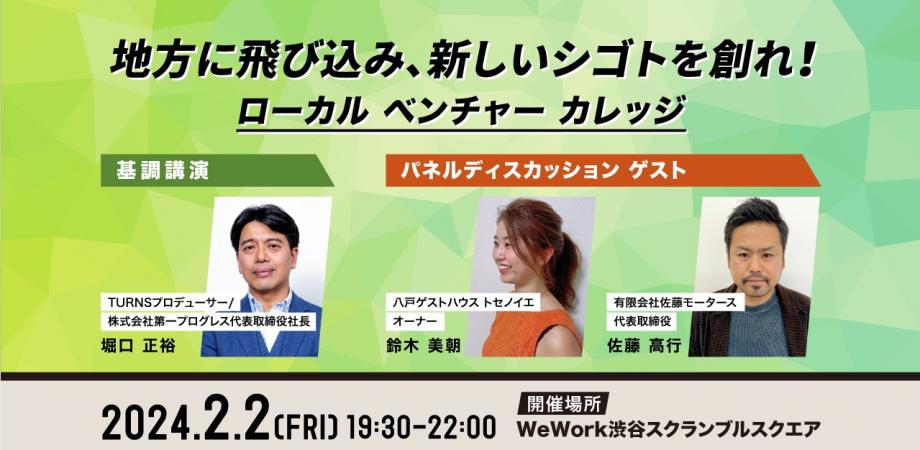日本全国どこの町にもあり、暮らしの一部に溶け込む公園。その多くが国や自治体が所有する公有地ですが、特に小さな公園においては、草刈りや落ち葉拾いといった維持管理は、一般市民による「公園ボランティア」によって支えられています。小さな公園にある市民協働の形とその可能性について、公園ボランティアのサポートを行う「一般社団法人みんなの公園愛護会」の椛田里佳さんに聞きました。

GUEST 椛田里佳( かばた りか)
一般社団法人 みんなの公園愛護会代表
愛知県出身。京都大学農学部卒業後、研究所向けのソフトウェアの営業を担当。2007年にデザイン事務所に転職し、上海へ。2009年に帰国し、自由大学の企画運営を担う。2016年に、家族とともに鎌倉へ移住。子育て中心にシフトチェンジした2年を過ごしたのち、夫と死別。2020年、一般社団法人みんなの公園愛護会を設立。2児の母。
脇 椛田さんの書籍『推しの公園を育てる!』でも、様々な公園ボランティアの活動について紹介されていて、興味深く拝見しました。まずは、みんなの公園愛護会の取り組みについて伺えますか。
椛田 みんなの公園愛護会は、公園ボランティアとして活動する方たちを応援する一般社団法人です。「公園愛護会」とか、「アダプト制度」とか、「里親制度」とか、公園で活動するボランティアのための制度は自治体ごとにいろんな名称がありますが、そういった制度のもとで地域の公園を良くしようとしている人が、ずっと昔から全国にいます。私たちは、そういう人たちをまとめて「公園ボランティア」と呼んでいます。公園ボランティアの人たちはもちろん、それをサポートする自治体の人も含めて、公園を良くしようと頑張る人を応援する団体です。具体的な活動のひとつは、公園ボランティアに関する情報共有です。例えば、この季節にこういう作業をするといいですよとか、こういう道具を使うと便利ですよとか、全国の公園ボランティアの人が持つノウハウを共有しています。公園ボランティアの方への取材や、全国の公園ボランティア活動実態調査も行っています。
脇 公園の管理は行政で行っているというイメージを持っている方も多いと思いますが、地域の方のボランティアに支えられているのですね。官民が連携するのが前提とも言えます。全国でどのくらいの方が、公園ボランティアとして活動しているのでしょうか。
椛田 「わからない」というのが正直な答えです。そもそも、公園の数も、正確には把握されていません。「都市公園」として定義される公園は、国土交通省のデータベースに載っていて、その数は全国で約11万4千です。ただし、そこには児童遊園やちびっこ広場といった子どもの遊び場は含まれていません。そういった遊園も地域の人がお世話をしています。所管する役所が違っても住民にとってはあまり関係ないですし、私たちも公園を幅広く捉えていて、暮らしている人が公園だと思ったら、そこは公園でいいのではないかと考えています。

自分たちで公園を良くするという選択肢
脇 公園が把握できないほどたくさんある中で、関わるボランティアも全国にたくさんいるのだろうと想像できます。椛田さんは、どうしてこの活動を始めようと思ったのでしょうか。
椛田 私自身、家の近くの公園でボランティア活動を始めたのですが、実際に動こうとすると分からないことだらけだったんです。私たちは公園を使っていた友人たちで活動を始めたので、町内会のような既存の団体ではありませんでした。掃除道具を置いておく場所もありません。どんな道具を使えばいいか、そもそもどの時期にどんなお手入れをすればいいのかなど、わからないことだらけでした。そこで、活動していくために、他の公園ではどうしているのか調べてみると、地域によって制度はそれぞれ違うことがわかりました。公園ボランティアは全国にたくさんいるけど、地域によってサポート体制はそれぞれ違う。一方で、やっていることは同じで、公園をきれいにすること。ほとんどが草刈りと落ち葉拾いです。花壇活動をしている人たちもいます。私たちのように知りたい人が他にもいると思いましたし、この活動を続ける人たちが全国にいるのであれば、その情報を繋いだらきっといいことがあると思って、いまの活動が生まれました。
脇 ご自身の経験、困りごとから活動が始まったのですね。そもそも、公園をきれいにしようと思ったのは、どんなきっかけがあったのでしょうか。
椛田 子どもが幼稚園に通っている頃からよく遊びに行っていた公園が荒れてしまったんです。ぱっと見た感じは普通の公園なんですけど、隣にレトロな建物の子ども会館があるいい場所でした。屋内でも屋外でも遊べるし、赤ちゃんから中学生くらいまでの子どもが集まって、みんなで子どもを見守り合うような環境がありました。少し大きな子どもは、小さな子のために遊ぶスピードを緩めて優しくしたり。いろんな子どもの様子を見て「こんな風に自分の子どもも大きくなっていくのか」と感じたりと、子育てに必死で狭くなっていた自分の視野を広げてもらったりしていました。ところが、その子ども会館が突然閉館になったのです。すると、公園も急に荒れ始めました。理由はいくつかあったと思います。それまでは、子ども会館の方が時々きれいにしてくれていたのと、子どもが多かったので草が踏まれて高く伸びなかったのだと思います。また、公園の草抜きを丁寧にやってくれていた人が、その時期に引っ越してしまったらしく、草は伸び放題で、鉄棒もベンチも草に埋もれてしまうような状況でした。そんな状況を見かねた友人が、草刈りを企画したんです。誰もやらないなら、自分たちでやればいい。たしかに、自分たちで公園をきれいにするという発想もいいなと思いましたね。
脇 自分たちでやってみようというのが、素敵なことですね。実際にやってみて反響はいかがでしたか。
椛田 公園を普段から使っている人に呼びかけたら、たくさんの人が集まってくれました。子どももお母さんもお父さんもいっぱいで、公園に人が溢れていましたね。草刈りは大変でしたが、いい運動になるし、みんなでおしゃべりして楽しい。公園がきれいになってスッキリした手応えがありました。さらに、継続するのであれば、行政の公園愛護会の制度に登録することでサポートが受けられこともわかりました。これは地域によっても違うのですが、私の住んでいた地域では単発の清掃に支援はないものの、継続するのであれば、ゴミの回収や活動費のサポートが受けられるのです。その後、市役所と相談をして、友人たちと公園愛護会を結成。月1回おしゃべりしながら公園をきれいにする活動をゆるく続けています。
脇 そこからさらに、全国をつなぐ活動に広がっていくんですね。
椛田 そうです。ちょうどその頃、難病で2年ほど闘病していた夫が亡くなりました。周りのお母さんたちや公園で子どもたちの育つ様子を見て助けられましたし、この場所にずっと関われたらいいなという思いもありました。また、夫はもともと公園の情報を共有するスマートフォンアプリを作っていたので、そのようなご縁もあり、公園に関わる仕事をすることになりました。公園のポテンシャルはすごいですよね。でも大きな公園は何かと話題になりますが、小さな公園は、大きな公園に比べて注目されにくい場所です。多くの人が日常的に利用するにもかかわらず、見過ごされがち。全国には街区公園と呼ばれる小さな公園が9万も存在しています。こうした公園を全体的に良くしていくことが、地域に大切ではないかと考えるようになりました。実際に、自転車で行ける範囲の様々な公園に足を運んでみると、使われていないように見える公園や、草が生い茂り、立ち入るのもためらってしまう公園もある一方で、草花が整えられ、ゴミ一つないきれいな公園もありました。一体なぜだろうと、興味が湧きましたね。また、小さな公園は、子どもたちの遊び場としてだけでなく、大人がリラックスしてお茶を飲んだり、昼食を取ったりする場所としても機能しています。こうした公園がたくさんあることは地域にとって大事なことだし、これらの公園を応援し、貢献したいと感じるようになりました。私自身が関われるのはせいぜいひとつの公園ですが、それぞれの公園にはすでに公園ボランティアとして活動している人たちがたくさんいます。だったら、そういった公園ボランティアを支援することで、大勢の力で公園全体を良くすることができるのではないかと考え、今の活動が始まりました。
行政、企業、住民が連携する仕組み
脇 活動している人を応援したいというのが、原点にあるのですね。実際の活動は、なにから始めたのでしょうか。
椛田 各地の活動を知らなければ、適切なサポートができないと思ったので、まずは公園ボランティアに関する行政制度を調査することから始めました。インターネットで調べてみると、制度は地域によってそれぞれ違うことがわかってきました。お金で支援しているところもあれば、掃除道具などのモノを支給しているところもあり、ばらばらです。さらに体系的に制度を知るために、2020年に神奈川の33市町村を対象にアンケート調査を行いました。公園ボランティアの制度があるか、ある場合はどんなサポートをしているか、現状困っていることや公園ボランティアの価値をどう感じているかなど、調査してウェブサイト上で公開しています。
脇 調査の結果、どのようなことが見えてきましたか。
椛田 結果として、困っていることのほとんどは、高齢化と担い手不足でした。ただ、こうした問題は何年も前から言われていることなので、実際に何歳くらいの人が多いのか、どうやって運営しているのかなど、もっと細かいことが知りたくなりました。そこで、市役所に聞いた調査と合わせて、公園ボランティア団体への調査も行いました。 市役所に協力してもらい、各ボランティア団体にアンケートを送りましたが、その返答がとても面白かったんです。記入欄にびっしりとコメントを書いてくれた方も多く、情熱を感じました。公園ボランティアのみなさんは、言いたいことがたくさんあるということがよくわかりましたね。みなさん、その地域が好きとか、子どもたちの遊び場を守りたいという思いで活動されていますが、その活動はなかなか注目されることがありません。話を聞いてもらえること自体にも、嬉しさを感じていただけているようでした。
脇 公園ボランティアの人たちは、批判ではなく自らの行動で地域を良くしようとしている人の集まりで、まさに地域の担い手としてポテンシャルが高いように感じます。地域にプレイヤーがいないという声を聞くこともありますが、実は公園に集まっているのかもしれないですね。
椛田 まさに、公園や緑に関わって地域を良くしようという人たちは素敵な人ばかりなんです。年齢は様々で、若い人たちもいれば、90歳くらいの高齢の人もいます。大人だけでなく、子どもたちも大活躍しています。「公園で子どもたちの声が聞こえるのは幸せなことだよ」というような人もいっぱいいて、 会うとすごく優しい気持ちになれます。話を聞いていくうちに、今度は全国での違いを聞いてみたいと思うようになりました。例えば、制度の多くは、毎月活動するとサポートが受けられることになっているのですが、北海道では冬の活動をどうしているんだろうか、どんな制度になっているんだろうか、と気になり始め、2021年と2022年とに全国での調査を進めました。調査や取材をしていくうちに、普通に公園をきれいにするだけでなく、池や樹林の保全などかなり本格的に環境を守る活動をしている人たちがいることや、音楽フェスや畑づくりなど公園という場所を最大限活用してより楽しいみんなの場所にしている人たちがたくさんいる、そんな事実や可能性を知ることができました。そのような各地の公園ボランティアの活動事例や楽しく活動するためのヒントとなるアイデアをまとめたのが『推しの公園を育てる!』です。
脇 様々な取り組みを取材する中で、特に素敵だと思った事例があればぜひ教えてください。
椛田 例えば、官民連携の視点でいえば、東京都・東村山市の稲荷公園は素敵な取り組みをしています。鬱蒼とした暗い森になっていた公園を、地域のお父さん仲間がボランティアで楽しい場所に再生し、毎月公園清掃+ロープアスレチックや落ち葉プール、ものづくりワークショップ、音楽フェスなどのイベントを行っています。地域の人がやりたいことをやれるように、一緒に伴走してきた行政のサポート体制も仕組み化されました。東村山市では全ての公園の運営を指定管理事業者に委託しているのですが、市民協働による公園づくりという項目もあり、行政、指定管理事業者、公園ボランティアが連携して公園づくりを行っています。
東京都・江戸川区の取り組みも画期的です。公園に「だれでもお掃除セット」が設置されていて、誰でも、いつでも公園の清掃に関わることができます。掃除道具が公園にあり、ゴミも回収してもらえるので、ラジオ体操に集まった人が帰りにぱぱっと掃除したり、子どもたちが遊びの延長で掃除をするといったことが起きています。公園利用者からすると画期的ですし、いろんな人が関われる余地があって、とてもいい取り組みだと思います。
公園の価値はいろいろな使い方ができること
脇 いろんな人に関わってもらうというのは、まさに大事なテーマかと思います。これまで公園に関わったことがない方は、どうすれば関われるのでしょうか。
椛田 その公園にすでに登録している団体があるなら、その団体に連絡してみるのがいいと思います。登録団体として多いのは町内会ですが、学校として関わっていたり、企業が会社近くの公園をお昼休みに手入れするような形で関わっていることもあります。公園の掲示板に活動情報が掲載されていることもあるので、それを見て、連絡してもらえるといいかもしれません。もしその公園で活動している団体がない場合は、その地域の役所に連絡をしてみるのがいいと思います。公園で面白いことをやってみたいと考えている人は、役所に相談に行く時に「前例あります!こんな風にやっている人たちがいます!」と、この書籍をアイデアブックとして見せてもらうと、話しやすいのではないかと思います。あとは、「話を聞くことでの貢献」もあると感じています。アンケートや取材に行くと、みなさん本当に色々話してくれますし、喜んでくれます。活動を取材をされることが、モチベーションアップにつながるんです。ですので、取材をするような形でも、公園ボランティアのみなさんに貢献できると感じています。実際に、みんなの公園愛護会でも各地で取材できる人を増やしたいと考えていて、大阪では公園の設計や利活用を勉強している学生さんが関わってくれています。
脇 話を聞くことが応援になる、というのはまた新しい役割が生まれていいですね。最後に、あらためて椛田さんが感じる公園の価値や、繋いでいきたい思いを聞かせてください。
椛田 公園は、みんなの庭というか、気持ちのいい地域の庭みたいな存在であればいいと思いますね。日常的に通ったり、癒やされたり、人と関わることができたり。気持ちのいい場所だと人が集まって、楽しいことが起きる。イベントの日は、日常が一瞬非日常になる。使う人や、時間帯によっても違う場所になることもある。そうやって変化できることが、公園の価値だと思います。誰でもいていい、ということにも公園の価値がありますし、そういった場所は他にあまりありません。アイデアと行動力で公園はもっともっと楽しい場所に育てていけると思います。各地で公園を楽しく育てている人たちの様々な情報も広く共有しながら、これまで続けてきた人も、これからやってみたい人も、役所の人も含めて、地域に面白い場所を育てていく仲間が増えたらいいですね。
脇 関わる人によってその場所の価値や意味が変わってくるというのは面白いですし、みんなに開かれている公園ならではの価値かもしれません。そして行政だけでなく、いろんな人が関われる仕組みを作ることが、公園の価値を高めていくように感じました。素敵なお話をありがとうございました。

行政と市民の連携で、公園との関わり方を広げる
自分の手で公園をきれいに
日常の中でボランティアに参加できる仕組みづくり
だれでもお掃除セット 江戸川区

ラジオ体操が行われている公園や、町会活動やボランティア活動が盛んな公園から始まり、現在は区内の31カ所の公園に設置されている「だれでもお掃除セット」。登録ボランティアはもちろん、近所の住民や遊びにきた親子、公園を利用する保育園の先生たちなど、多くの人に利用されている。行政の主導によって複数の公園に同じセットが設置される例はまだ少ないこともあり、「近所の公園にも」という要望も多く、徐々に設置箇所が増えているという。
ボランティアの活動報告を、スマホアプリで簡単に、わかりやすく
PARKFUL Watch 茅ヶ崎市

PARKFUL Watchは公園愛護会の活動充実化のために茅ヶ崎市が導入したアプリ。紙の報告書で行われていた活動報告が、写真付きで簡単に送信できる。外出の多い公園緑地課の職員は、アプリができたことでボランティアとスムーズに連絡が取れる上、ゴミ回収や剪定作業については、量や場所を画像で共有することで、口頭では説明しづらかった進捗の確認がスムーズにできるようになったという。講習会を開くことでスムーズな導入ができているが、「紙の報告の方が良い」という団体には無理強いせず、手を挙げた団体から導入する形をとっている。
昔遊んだ公園をなんとかしたい
そうじ+イベントで三世代交流を
大岱稲荷プロジェクト 東村山市

かつて遊んだ「稲荷公園」にもう一度活気をとりもどしたいとういうオヤジたちの思いから徐々に集まったメンバーが主体となり、大岱稲荷三世代交流、略して「おいなりさん」という名前をつけて活動がスタート。「まずは掃除から」と始まったプロジェクトにさまざまなプロを招いた企画を盛り込むうちに参加者も増え、500人規模の音楽イベント「おいなりサンデー」をはじめ、数々のイベントが開催されるまでに発展。毎月の活動やイベントにおいては、遊びとそうじをセットにすることで、子どもたちにも、〝公園を管理し、育てる〟マインドが根づくように運営している。
東村山市では、公園のハード整備や維持管理を行う公園係、緑化推進や啓発を行うみどりの係が協力して、継続的にサポートするための体制を整備。現在では、大きなイベントは市との「共催」として、資金や人員サポートを行うなど、〝市民がやりたいことを実現〟できる仕組みが整備されている。
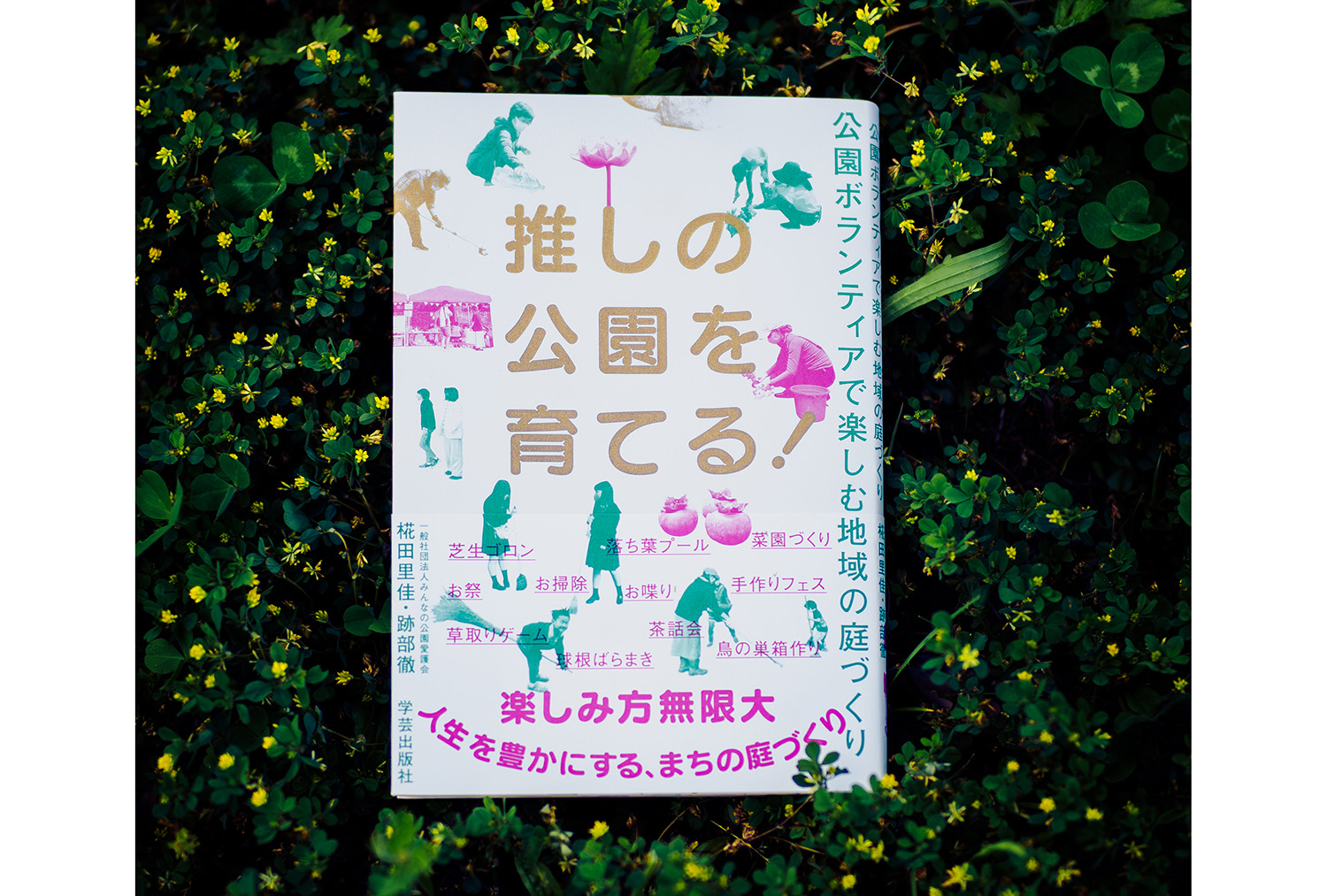
推しの公園を育てる! 公園ボランティアで楽しむ地域の庭づくり
一般社団法人 みんなの公園愛護会 ( 著 )
椛田里佳(著)
跡部徹(著)
学芸出版社 2,530円(税込)

Coordinator
脇 雅昭
よんなな会/オンライン市役所発起人
宮崎県出身。2008年総務省入省。神奈川県庁に出向し、官民連携等の取組を進めてきた。プライベートでは、全国の公務員がナレッジや想いを共有する「よんなな会」「オンライン市役所」を立ち上げ、地方創生のためのコミュニティ基盤づくりを進めている。
編集 文・島田龍男 撮影・荒井勇紀