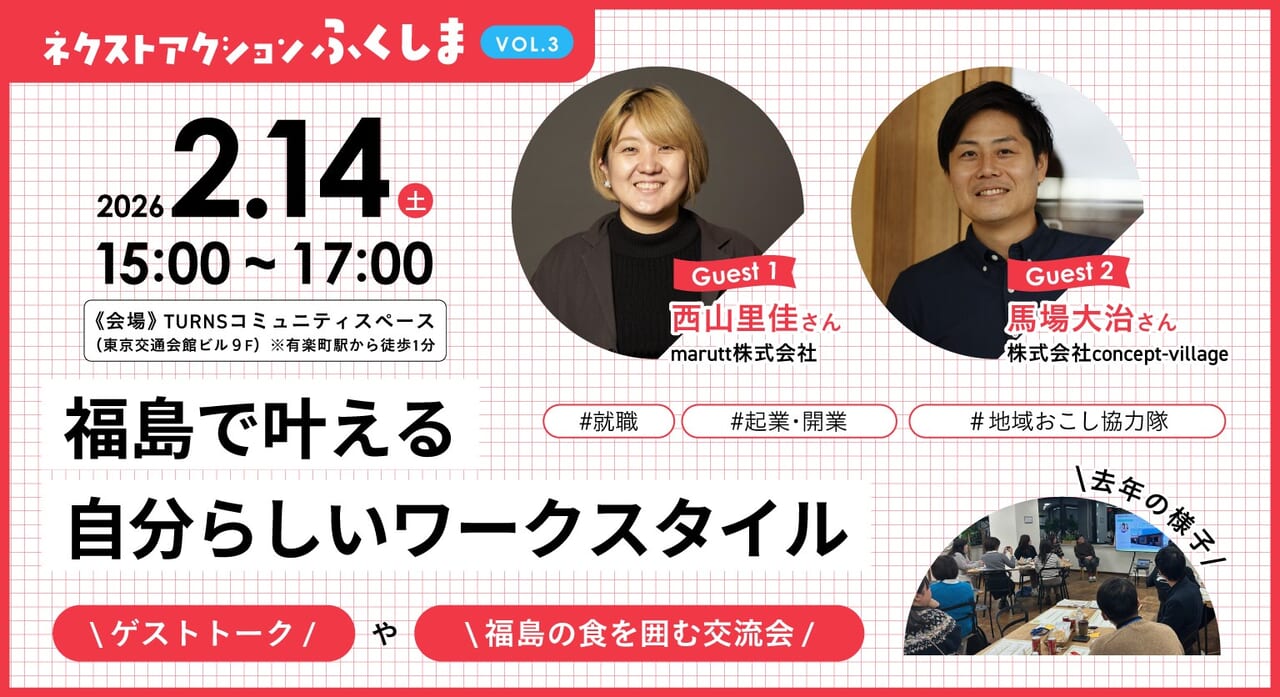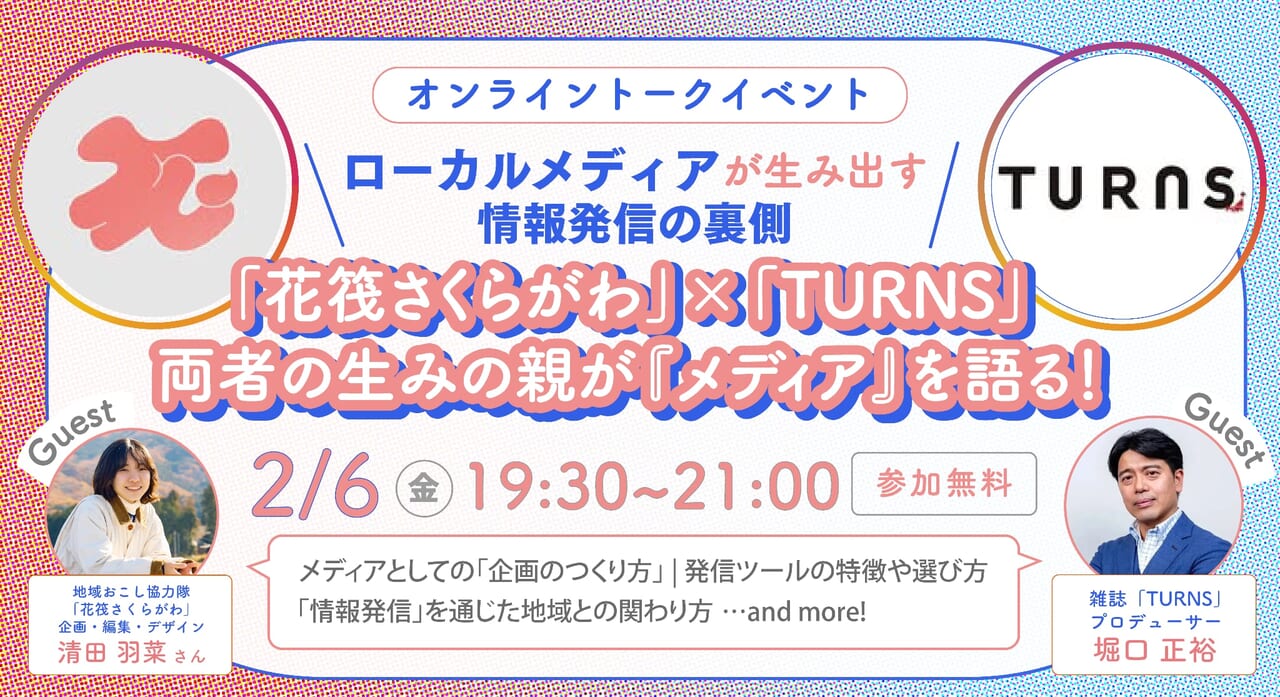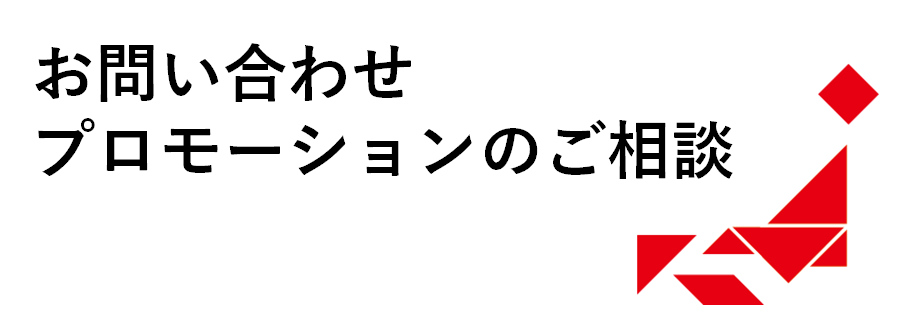高知県中西部に位置する中土佐町は、古くからカツオ漁で栄えた漁師町。潮の香りが漂う海辺の風景が印象的だが、山間部へ足を伸ばすと、日本最後の清流と呼ばれる四万十川の源流や緑豊かな農村が広がり、「海」「山」「川」三拍子そろった自然が、訪れる人をやさしく包み込んでくれる。
けれど、この町の魅力は風景だけでは語りきれない。土地に根ざした食文化や、そこに暮らす人々の営み――。その何気ない日常の中にこそ、この町の本当の姿があるように思う。
美しい風景の奥にある「暮らし」にふれたくて、人と出会い、時間をともにする旅に出ることにした。

旅の始まりは、“カツオの聖地”久礼から。
昭和の面影がただよう漁師町を歩く
旅の出発点には、やはりこの土地らしい「海の香り」を感じられる場所を選びたい。
そう思ってまず向かったのが、久礼漁港だ。

中土佐町の沿岸部にある久礼は、400年前からカツオの一本釣り漁が行われてきた漁師町。港と住宅街をつなぐ細い路地には、堤防に立て掛けられた物干し竿に洗濯物がふわりと揺れていたり、家々の軒先には魚を捌くための流し台があったりする。郷愁を誘う久礼のこの街並みは、国の重要文化的景観にも選定されていて、漁師町で暮らす人々の“生(なま)”の生活を感じることができる。

「おはよう」「おぉ、おはよう」
地元のおんちゃん(高知弁で、おじさんのこと)たちが、軽やかにあいさつを交わしながら商店街へ吸い込まれていく。その姿を追うように、私も中へ足を踏み入れた。
久礼漁港からほど近い「久礼大正町市場」は、全長わずか40メートルほどの小さな商店街。水揚げされたばかりの魚介が並ぶ鮮魚店はもちろん、青果店や惣菜店、呉服店などが連なり、レトロな景観の中にも活気が見られる。

大正時代から100年以上続く「田中鮮魚店」へ立ち寄った。ここでは、店頭に並ぶ魚をその場で選び、捌いてもらって白飯や味噌汁とともに店内で味わうことができる。
「持ち帰りますか? それとも食べて行きますか?」
店頭のお姉さんにそう声をかけられ、目の前の新鮮で立派なカツオの節を見て、迷わず即答した。
「食べていきます! ご飯大盛りで!」
すると、お姉さんはにっこりと笑いながら、 「それじゃあ、背と腹、両方食べてみて。せっかくだから」と、すすめてくれた。

ほどなくして運ばれてきたのは、カツオの刺身と藁焼きタタキ。どちらも見た目からして新鮮で、モチモチ、ぷりぷりの食感。背の部分は弾力があり、腹側は柔らかいという違いも、ここで初めて知った。食事の美味しさだけでなく、地域の暮らしに一歩踏み込んだような感覚を味わうことができた。

商店街の入り口では、一匹の野良猫がすっと近寄ってきて、私の足元へと落ち着く。漁師町に住む猫たちは、おおらかで人懐こい。そういえば、中土佐町の人々の印象にもどこか重なる。猫も人も、この土地の空気の中で育まれる性格というものが、きっとあるのだろう。

静かな山あいに響く音色。大野見で出会ったスティールパンバンド
海辺をあとにして向かったのは、山あいに広がる大野見地区。田畑が広がるこの地域では、里山の原風景が今も色濃く残っている。田んぼ道を歩けば、すれ違うのは農作業をする人か軽トラックのみ。人間よりもむしろ、鳥のさえずりや道端を行く虫たちの姿など、自然の世界に目が留まる。
そんな静かな風景の中で、どこか異国のような軽やかな音楽が聞こえてきた。スティールパンバンド「Oh!No!!Me!!!」の演奏だ。

スティールパンは、カリブ海の島国・トリニダード・トバゴ共和国発祥の打楽器。ドラム缶から作られ、澄んだ音階を奏でるユニークな楽器だ。この町でスティールパンが根付くきっかけとなったのは、かつて中土佐町で上映されたドキュメンタリー映画『スティールパンの惑星』だった。その上映をきっかけに地域内にスティールパンへの関心が広まり、町はトリニダード・トバゴ共和国とホストタウン協定を締結。その後、現地のバンドが中土佐を訪れたことで機運がさらに高まり、2019年に「Oh!No!!Me!!!」が結成されたという。今では、夏祭りなどの地域行事や、町外のイベントなどでも演奏を披露しているという。

「ホワン、ホワン、ホワン」と響き渡る彼らの音色に不思議と元気をもらい、癒され、また、実際に演奏の体験もさせてもらった。外から来た文化を受け入れ、自分たちのものとして育てていく姿に、この土地の懐の深さを感じた。
地域の人と助け合いながら生きていく。
移住者夫婦が語る中土佐で見つけた豊かな生き方
久礼にある「中里自然農園」を訪ね、有機栽培の農作業を体験させてもらった。園主は神奈川県出身の中里拓也さんと兵庫県出身の早紀子さん夫婦で、毎年50〜60品目の野菜を、農薬や化学肥料を使わずに育てている。
畑の一角では、ニンジンやそら豆、ズッキーニなど、色とりどりの野菜が元気に育っていた。
実際に収穫作業を体験してみると、スコップで根元を掘り起こしたり、コンテナを運んだりと、想像以上に体力を使う作業が続く。それでも、土の感触や風の匂い、鳥の鳴き声に囲まれながら体を動かす時間は、どこか心が落ち着いていくようだった。

農作業の合間には、二人の移住のきっかけや日々の暮らしについて、率直な話を聞かせてもらった。
拓也さんにとって中土佐町は、母親の故郷。幼いころ、母の実家を訪れては川や山を駆け回り、自然の中で過ごしたという。そんな思い出のある場所に、いわゆる“孫ターン”をした拓也さんと、海に惹かれて高知に移住していた早紀子さんが出会い、二人の中土佐町での生活が始まった。
「農業は天気に左右されるし、多品目を育てているから作業が複雑で、毎日のやりくりが大変。まるでパズルみたい」と拓也さん。
一方で、早紀子さんは明るく笑ってこう語る。
「でもね、好き放題やってる感じだから楽しいんです。ヤギや猫、鶏もいて、塩やサトウキビ、小麦も育てるし、養蜂に椎茸栽培も。やりたいことをやっているけど、サボらずきちんと手をかけるのはやっぱり大変。でも、毎日コツコツ続けていれば、ちゃんと形になる。それが面白いんですよ」

そんな中里さん夫婦のまわりには、地元の人たちや、同じように中土佐の自然や人の魅力に惹かれて移り住んできた仲間たちが、自然と集まってくる。田舎ならではの人づきあいや、この土地に根づく暮らしの知恵についても、二人は惜しみなく教えてくれた。
「全部ひとりでやろうとすると大変だけど、『人に助けてもらいながら生きていく』っていうスタンスが、この町では大事かな。中土佐の人たちって、困りごとがあるとすっと手を差し伸べてくれるんです。そこから関係が自然と広がって、深まっていく。そういうことが自然にできるのがいいですね」(拓也さん)
「何かやってみたいなと思ったら、すぐそばに“達人”がいるんですよ。『木を切りたい』『釣りに行きたい』『狩猟をしてみたい』って思ったとき、何でもできる人がいて、しかもみんな気さくに教えてくれる。それは中土佐町のすごいところだね」(早紀子さん)
自分にできないことは、素直に人に頼る。それがごく自然にできるこの町では、気づけば信頼できる人たちが増えていて、つながりが少しずつ暮らしの中に根を張っていく。二人の言葉の端々から、そんな日々のやりとりが、暮らしそのものを豊かにしている様子が伝わってきた。

おんちゃんたちと過ごす、ほろ酔いの時間
夜は中里さん夫婦に誘われ、地域のおんちゃんたちとの定例飲み会に参加させてもらった。場所はなんと、普段農作業に使っているという作業小屋。ローカルな居酒屋も味わい深いけれど、この“いつもの集いの場”には、それ以上のぬくもりと親密さがある。

ビールと手づくりのおつまみを囲んで、「昔はなあ〜」「これ見てみい」と、懐かしそうに写真を取り出すおんちゃんたち。50年前の話から、最近の畑のことまで、語り口は軽やかで、とにかく話が尽きない。
世代は大きく離れていても、「この町のことをもっと知りたい」と耳を傾ければ、おんちゃんたちも自然と心を開いてくれる。誰かの昔話にまた誰かが乗っかり、あちこちで笑いがこぼれる。そうやって繰り広げられる語らいの中に、この町を思い続けてきた人たちの誇りや、根っこにある中土佐らしさが滲んでいた。

中里さん夫婦が話していた「誰かを頼る」という感覚。こんなおんちゃんたちが近くにいてくれるなら、「困ったときには頼ってみようかな」と思えてくる。
いつかこの町に暮らす日が来るかどうかはわからない。でもきっとまたここに来て、この人たちに会いたくなる。通いたくなる。そんな気持ちが、心の奥に灯った夜だった。
また帰りたくなる場所と人に出会えた、中土佐の旅
中土佐町には、何十年、何百年も昔からこの土地に根差して暮らしてきた人やお店も多く、今もその文化が色濃く息づいている。
今回の旅で出会った人たちとの語らい、共に囲んだ食卓、山あいに響くスティールパンの音色、そして自然の中で汗を流した農作業。五感でこの土地を感じ、体を動かすことで、少しずつこの町との関係が育っていくのを感じた。ただ「見て帰る」だけではなく、「一緒に何かをやってみる」。そんな関わりの入口が、この町にはいくつもある。
住民票はなくても、「帰ってきたよ」と言いたくなるような場所が、自分の中にひとつできたような気がする。

中土佐町のご紹介
高知県中西部に位置し、高知市内から車で約45分。人口は約5,700人。古くからの漁業や農業に支えられた暮らしが今も息づき、町の空気にはゆったりとした時間が流れている。
町は4つのエリア〈久礼〉〈上ノ加江〉〈矢井賀〉〈大野見〉から成り、それぞれに異なる風景と暮らしがある。
・久礼(くれ)
カツオの一本釣りで知られる港町。大正時代から続く「久礼大正町市場」には、新鮮な魚介や惣菜、地元の味が並ぶ。創業300年以上の「西岡酒造」など、歴史を感じる店も点在し、歩くだけで土地の文化に触れられる。港の先に見える双名島(ふたなじま)は、並んで浮かぶ二つの岩が特徴的で、久礼の象徴ともいえる存在。
・上ノ加江(かみのかえ)
山と海に抱かれた小さな漁村。はえ縄や刺網漁でアマダイ、タイ、伊勢エビなどが水揚げされる。漁業体験施設「わかしや」では、漁師町ならではの食と体験を満喫できる。山あいに広がる山内ダムでは、四季折々に表情を変える湖の風景が広がり、春には湖面に浮かぶように咲く「浮島桜(うきしまざくら)」がひときわ美しい姿を見せる。
・矢井賀(やいか)
中土佐町の南の端に位置する小さな漁村。昭和の雰囲気が残る細い路地や、古い港周辺の風景が魅力。急峻な山と海に囲まれた地形に沿って集落が広がり、静かでゆったりとした時間が流れる。バイク旅に人気の「ライダーズイン中土佐」があり、宿泊+キャンプが海岸で楽しめる。
・大野見(おおのみ)
四万十川の源流点近くにあり、棚田や渓流が織りなす里山の風景が広がるエリア。川に架かる沈下橋は、欄干のない素朴な姿で、まるで風景の一部のように静かに佇む。増水時には水の流れを妨げずに沈む構造となっており、自然と共に生きるこの土地ならではの知恵が、景色にそっと溶け込んでいる。
町の詳しい情報は、中土佐町公式サイトへ。また、移住に興味のある方は、中土佐町移住ポータルサイト「なかとさLIFE」をぜひご覧ください。
文:岡本里咲
▼あわせて読みたい
▼「私が好きな、中土佐」動画公開中!