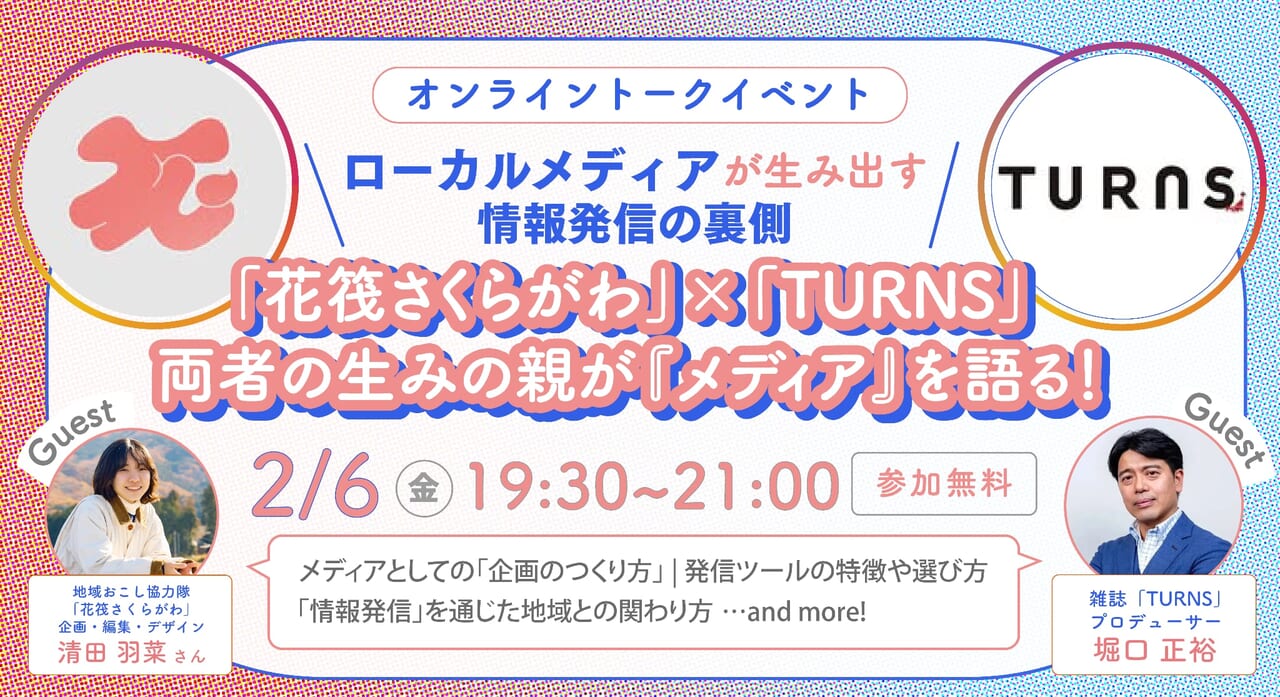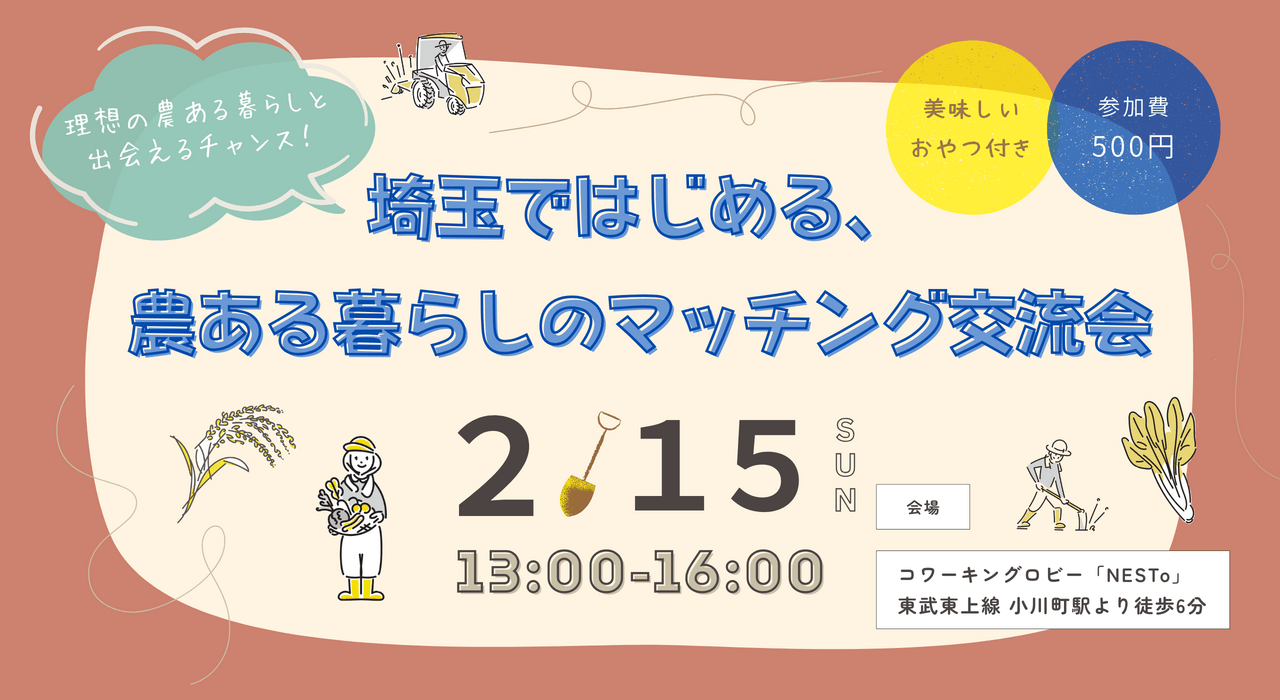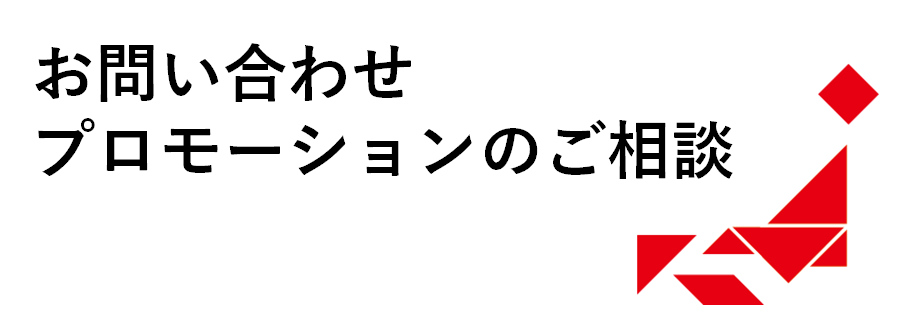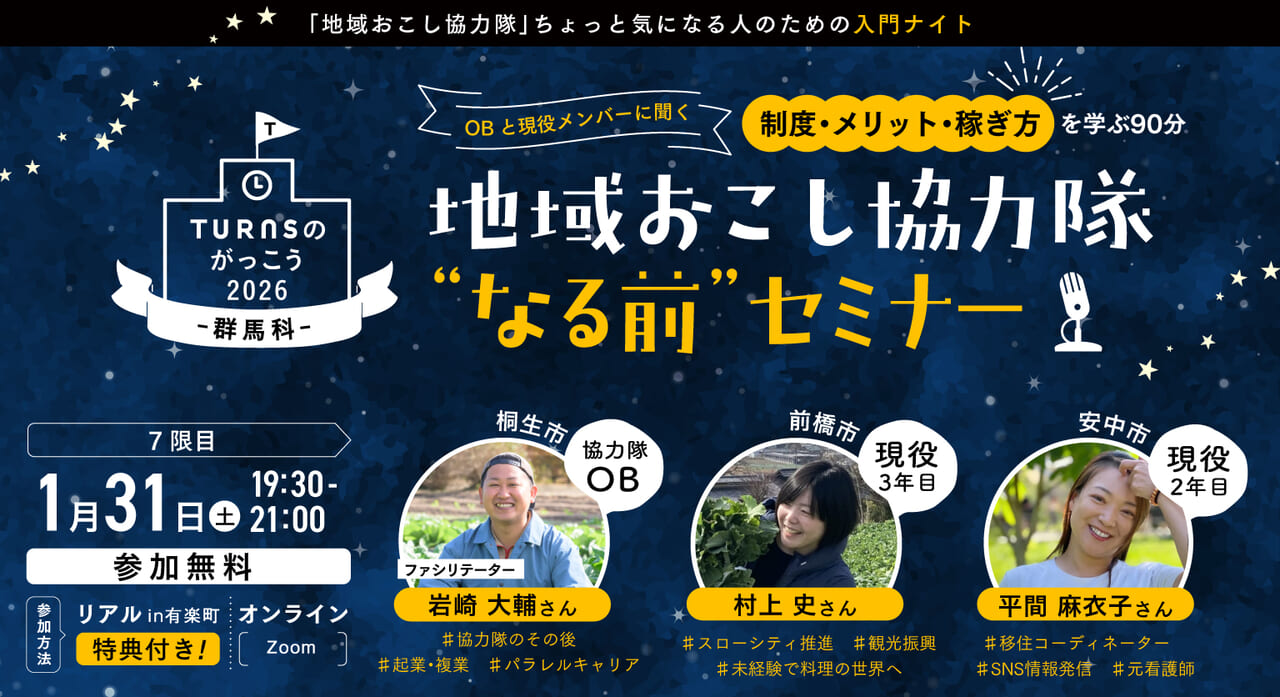カツオの一本釣りで有名な高知県中土佐町。
土佐湾に面した海の恵みと共に、四万十川源流域を擁する山側では米や野菜などの農業も盛んで、食と自然の豊かさは指折り。そんな環境と人のあたたかさに惹かれ、この地で暮らし始めた二人がいる。
一人は絶品の食材との出会いを求めて、もう一人は地場産業の七面鳥の生産に興味を持ち、地域おこし協力隊としてこの町にやってきた。違う入り口から中土佐町に辿り着いた二人は今、どのように暮らしているのか。
移住のきっかけから日々の過ごし方まで、お話を伺った。
| Part 1 山崎千絵さん|
“おいしい”を求めて中土佐町へ。その一歩から人生が回り出した!

【プロフィール】
大阪府出身。料理への情熱からフランスに留学し、現地で出会った高知出身のシェフのすすめで高知県を訪問。中土佐町の自然や人のあたたかさに惹かれ、町内の「田中鮮魚店」でお試し勤務を経験。2022年に中土佐町へ移住し、地元出身の男性と結婚、第一子を出産。海と山の恵みを食卓に取り入れながら、「みんなで楽しく食べる」暮らしを満喫している。
本物の食材を求めて。京都、フランス、そして高知県中土佐町へ
若くして料理の道を志した山崎さんが、生まれ育った大阪を離れたのは22歳のとき。「本物の食材と出会うなら地方だ」と考え、京都府福知山市のレストランで3年半修行を積んだ後、ワーキングホリデーを利用してフランスのバスク地方へと渡った。
「フランス料理って、高級なイメージがありますよね。でも、私が興味を持ったのは、その土地の家庭の味。地元の人が普段どんな料理を食べているのかを知りたかったんです」
フランス滞在中、農家やレストランの仕事を手伝う中で出会ったのが、高知県出身の女性シェフ。彼女から高知の自然や食文化の魅力を聞くうちに、山崎さんの探究心はどんどん高知に向かっていった。

帰国後、山崎さんはすぐに高知を巡る一人旅へ出発。数ある町を訪れるなかで、なぜか中土佐町だけは物事がとんとん拍子に進んだという。仕事、住まい、そして人との出会いまで、次々とご縁がつながっていった。
「最初は地域おこし協力隊として水産業に関わりたいと思っていたのですが、そのときはちょうど募集がなくて、諦めかけていたんです。そんなとき、『久礼大正町市場にある田中鮮魚店を紹介しようか』と声をかけていただいて。田中社長とお会いして話すうちに、『うちでちょっと働いてみる?』とお誘いいただき、一気に道が開けていきました。高知の人って、そこで終わりにせずに『じゃあ、こっちはどう?』って次につないでくれるんですよね」

田中鮮魚店での一週間の“お試し勤務”を終え、大阪に戻る頃には中土佐町への移住を決意していたという山崎さん。その決め手となったのは「人の魅力」と話す。
「高知県の中でも、中土佐町の人たちは特に人情味があって、あたたかいなと感じました。地元のおばちゃんたちに料理を教わるのもすごく楽しくて、みんなとてもフレンドリーなんです。人との距離感は近いけれど、性格はさっぱりしていて、その感じが私にはとても心地よかったです」
料理の腕を活かして食堂を切り盛り。
空き店舗を改装してデリもオープン
移住後、山崎さんは田中鮮魚店で半年間ほど働き、その後、料理の腕を買われて中土佐町の台所「久礼大正町市場」にある食堂「浜ちゃん」(現在休業中)を任されることになった。

食堂では、久礼漁港で水揚げされた新鮮なカツオや地魚を贅沢に使った定食や丼ものを提供。さらに、隣の空き店舗を助成金を活用して改装し、キッシュやサラダなど、手作りのお惣菜を販売するデリもオープンさせた。
「その土地の食材を使った料理で日常を豊かにする」。そんな山崎さんが掲げてきた料理のテーマが、中土佐の地で少しずつ形になっていった。

釣った魚、採れた野菜をおすそわけ。次々と生まれるあたたかい交流
長年、大阪の都市部で暮らしてきた山崎さんにとって、中土佐町の暮らしは新鮮な驚きが多かった。そのひとつが、地域の人たちの“おすそわけ文化”だ。
「近所に住む漁師のおんちゃん(中土佐の方言で“おじさん”)が、家の窓から野菜や魚やお手製のお寿司を差し入れしてくれるんです(笑)。他のご近所さんからもおすそわけをいただくことがあって、それがきっかけで自然と仲良くなったりもします。最初のころは、『何かお返ししなきゃ』と思っていたけれど、みなさん見返りを求めているわけではないんです。だから今は、素直に「ありがとう」と喜んで受け取るようにしています。その方が、自然といい関係が育っていく気がします」

海や畑で採れたものを当たり前のように分け合うのは、自然の恵みがふんだんにあるからこそ。「あげること」も「受け取ること」も、この町では愛情表現だ。
単身移住、結婚、そして母になる
中土佐町に移住して1年後、地元の男性と結婚し、2024年の冬には第一子を出産。夫は町内でコーヒー豆専門店を営んでおり、その近くの平屋を自宅兼焙煎所として使っている。さらに、別エリアにも古い平屋を所有し、町内で二拠点生活を実践中だ。
「街やお店に近くて便利な家と、静かな里山の中でのんびりできる家。どちらの暮らしも、それぞれの良さがあって気に入っています」

山崎さんは現在、育児休業中で二人目のお子さんを妊娠中。食堂の仕事はしばらく休み、家族と過ごす時間を大切にしながら、これからの働き方を見つめ直しているという。
「ずっと自分のやりたいことを追いかけてきたので、子どもを産んでからどうなるのか、正直わかりませんでした。今は子どもと過ごす時間がとても楽しくて、日に日に成長していく姿を見るのが面白いです。もちろん、また働きたいと思っていますが、以前と同じ形に戻るというより、これからの自分に合ったスタイルを探していきたいです」
結婚や出産を経て、これまで仕事に全力で取り組んできた価値観にも、少しずつ変化が現れているようだ。

「海のそば」で暮らす楽しさと、子育てにうれしい地域の支え
山崎さんが中土佐町での暮らしで特に魅力を感じているのは、「海がすぐそばにあること」だという。
「景色がきれいなのはもちろんですし、義父が漁師なので魚をもらえたり、家族でアサリを掘りに出かけたり。“海のある生活”って、やっぱり楽しいですね」
また、子育て環境についても中土佐町は心強いサポートがそろっており、山崎さんは大きな安心感を得ているという。
「児童手当のほかに、町内のドラッグストアで使えるオムツ券や、小児科・産婦人科に通院するための交通費補助もあって助かっています。子育て支援センターには遊び場のほか、洋服のシェアサービスや親子イベントもあって、気軽に利用しています。それに、近所の皆さんが、子どもを自分の家族のように見守ってくれるんです。そんなあたたかい雰囲気がとてもありがたいですね」

中土佐町で見つけた、理想の食と暮らし
料理の仕事から少し離れている今も、山崎さんが何より大切にしているのは、家族と囲む毎日の食卓だ。
「わが家にとって“食”は生活の中心。中土佐では新鮮な魚や野菜がすぐ手に入るので、料理するのも食べるのも自然と楽しくなるんです。その環境が、私たちの暮らしを支えてくれています」

料理への探求心から始まり、たどり着いた中土佐町での理想の暮らし。自分の直感と興味に素直に従って歩んできたその道のりは、思いがけない出会いや発見に満ちていた。
あふれんばかりの自然と人懐っこくもさっぱりとした人々の包容力の中で、山崎さんのこれからは、さらに伸びやかに、自分らしく花開いていくに違いない。
移住を考えている人へのメッセージ
山崎さんのように、自分の好奇心を信じて、あれこれ考えるよりもまずは現地に飛び込んでみることで、人生が思いがけず面白い方向へ動き出すことがある。
そんな実感をもとに、山崎さんは移住を考える人たちに、こんなアドバイスをくれた。
「いろいろな場所を見れば見るほど迷ってしまって、かえって決められなくなることもあると思います。だから、“ここかも”と感じるところが見つかったら、まずは思い切って住んでみることをお勧めします。もし合わなければ、戻ればいいだけのこと。大きな決断に感じるかもしれませんが、やってみないと分からないことってたくさんありますから。
実際に暮らしてみて初めてわかることもあります。たとえば、田舎の暮らしは手間がかかることも多いです。古い家だと虫が出ることもありますし、庭の草取りも一苦労だったり(笑)。でも、そうしたことも含めて、自分なりの楽しみ方を見つけていくことが大切だと思います」
| Part 2 松下昇平さん|
地域おこし協力隊から起業へ。
アスリートの経験を地域に活かす七面鳥と歩む挑戦の日々

【プロフィール】
大阪府出身。高校時代をアメリカで過ごし、帰国後は日本体育大学に進学。在学中にトライアスロン大会への参加をきっかけに中土佐町を訪れる。2017年、地域おこし協力隊として中土佐町へ移住し、七面鳥生産事業に従事。退任後の2020年、大野見地区で「松下商店」を起業。中土佐町を起点に多様な地域を行き来しながら、七面鳥の生産・加工・販売、スポーツ振興、テナガエビの養殖など多岐にわたる事業を展開している。
スポーツ脳が閃いた!
中土佐産の高タンパク・低カロリーな七面鳥との出会い
中土佐町の中でも、四万十川上流域の山深い場所に位置する大野見(おおのみ)地区。ここでは約60年前から、町が産業創出を目的に全国でも珍しい七面鳥の飼育に取り組み、「しまんとターキー」として現在まで生産が続けられてきた。
2017年、当時28歳の松下さんは、この七面鳥生産に惹かれて地域おこし協力隊として中土佐町へ移住した。

松下さんと中土佐町との出会いは、大学時代に遡る。2012年に中土佐町で開催されたトライアスロン大会に、競技者として出場したのが最初の接点だった。
「町の人たちはトライアスロンに詳しいわけではありませんでした。でも、終始声援を送り続けてくれて、あのときの応援のあたたかさは今でも心に残っています」
大学卒業後は、大阪の市役所でスポーツ振興課の臨時職員として勤務。将来の進路に悩んでいたある日、大阪で開催されていた高知県の移住相談会へ足を運んでみると、中土佐町との思わぬ再会が待っていた。
「中土佐町の方とトライアスロン大会の話をしていたときに、『七面鳥って知っていますか?』と聞かれたんです。高校時代にアメリカへ留学していたので、『よく食べていましたよ』と答えると、『実は中土佐町の山間部で、昔から七面鳥を育てているんですよ』と教えてくれました」
七面鳥は日本ではあまりなじみのない食材だが、高タンパク・低脂質で、世界的にはアスリート向けのヘルシー食材として知られている。その話を聞きながら、松下さんの中にひとつのアイデアが浮かんだ。
「この七面鳥を活かして、スポーツ選手や健康志向の人に向けた新しいビジネスができるのでは? と思いついたんです」

その日を境に、松下さんは中土佐町へ何度も足を運び、七面鳥の生産現場で話を聞いたり、町役場に相談したりしながら、少しずつ地域での足場を築いていった。
「畜産は自分にとってまったくの専門外。正直、自分に務まるのかという不安もありました。実際に話を聞いてみると、多くの生産者は七面鳥一本で生計を立てているわけではなく、農業や大工など別の仕事を本業としながら、副業的に関わっていることが分かりました。生産自体は60年以上続いているものの、販売は行政の支援に頼っている状態で、民間としての自立が求められていると感じたんです」
そこで松下さんは、七面鳥生産の自立運営を目指し、地域おこし協力隊の制度を活用してその一歩を踏み出した。
日本各地で「しまんとターキー」の販売・普及活動に尽力。
原動力は、地域の生産者の思い
地域おこし協力隊に着任した当初、松下さんは七面鳥を飼いながら、生産のすべてを覚えていくことを目標にしていた。しかし、実際に取り組むなかで、生産以上に販売の難しさに直面する。アメリカでは、コンビニでも手に入るほど一般的な七面鳥だが、日本にはその食文化はなく、認知度も低い。
「地域の生産者の方々とWin-Winの関係を築くためにも、飼育のお手伝いをしつつ、自分は販売を中心に取り組もうと考えました。日本では、七面鳥を食べたことがある人はごくわずか。まずは、そうした方々に『日本でも七面鳥が手に入るんだ!』と感動していただけるような活動に力を入れています」

四万十川の源流地域で育てられる七面鳥「しまんとターキー」。初めはオンラインストアでの販売をメインに考えていた松下さんだが、それだけでは新しい人に七面鳥のおいしさを届けられない。そこで、各地のイベントに屋台を出店し、七面鳥を串に刺して炭で焼く“焼き鳥スタイル”での販売を始め、地道な普及活動を続けた。
2020年、地域おこし協力隊の任期終了と同時に「松下商店」を起業。しかし、ちょうどコロナ禍に見舞われ、出店がままならなくなった3年間は大ピンチ。それでも松下さんは苦しい期間を耐え抜き、コロナ終息後に販売活動を再開。売り上げは徐々に伸び、ついに事業は独立採算で自走できるところまで成長した。

松下さんが七面鳥に携わり始めて足掛け9年。その原動力は何だろうか?
「いちばんは、大野見で七面鳥を生産している農家さんの思いです。初めて炭火で焼いた大野見産のしまんとターキーを食べた時、シンプルに『めちゃくちゃおいしい!』と感動しました。アメリカで食べていた七面鳥とはまるで違って、しっかりとした旨みがある。農家さん自身が『自分たちが食べたいと思えるおいしいものをつくる』という気持ちで生産を続けていることが伝わってきますし、だからこそ僕自身も、“ぜひ一口食べてみてほしい!”という思いが強いです」
町の産業として約60年前に始まった七面鳥の生産を民間の力で自立させ、マーケットを広げながら息の長い産業として育てていく。松下さんが受け継いだこの営みは、静かに、着実に前に進んでいる。
「田舎でのんびり」はまだ早い。
働くからこそ感じる自然のありがたさ
そんな思いを胸に、日々各地を奔走する松下さん。四万十源流の豊かな大自然に身を置きながら、「都会の忙しいビジネスパーソンと変わらないほど仕事している」と笑う。それでも出張先から戻り、車が大野見の山々へ差し掛かると「帰ってきた」とほっととするそうだ。熱い夏場は、四万十川の冷たい水流に足を浸しながら取引先と電話することも。
「自然環境に囲まれていることは、人間にとって大きなリフレッシュになります。でも、ずっとここにいるのではなく、外との行き来があるからこそバランスが取れる。僕はまだ田舎でのんびり暮らすには少し早い(笑)。仕事があるからこそ、こうした環境に身を置くことでプラスマイナスゼロになるのだと感じています」

運動と七面鳥で、地域に健康の習慣を根づかせる
松下商店では、七面鳥だけでなく、地域のスポーツ振興ももう一つの事業の柱に据えている。七面鳥一本槍では鳥インフルエンザなどで打撃を受けた場合にリスクが大きいと考えたからだ。
具体的には、体育教員のいない中学校で水泳の授業を請け負う他、アメリカ留学時代に触れた「シーズンスポーツ制度」(季節ごとに異なる種目に取り組む仕組み)をヒントに、過疎地の子どもたちに多様なスポーツ体験の機会を提供している。
「日本では部活動でも一つの競技を極める傾向がありますが、アメリカの中高生は、春は野球、秋はバスケットボールというふうに、季節ごとにさまざまな種目を経験しながら運動能力を伸ばしていきます。中土佐町は子どもの数が少ないので、野球やサッカーのようなチームスポーツがなかなかできません。そこで町内3つの小学校に、週1回・90分間のシーズンスポーツクラブをつくって、いろいろな種目で体を動かす場合を設けています」
この取り組みは現在6期目を迎え、初年度に小学生だった子どもが高校生となり、今はアルバイトとしてクラブ運営を支えてくれている。

一方で、中高年男性を主な対象者とした「体づくり計画」も展開。お酒が好きで運動機会が少ない年配男性が増えるなか、医療費の増加も懸念されている。そうした背景を受けて中土佐教育委員会と連携し、町内にプライベートジムのような場所を整備。誰でも気軽に、自発的に運動できる環境づくりを進めている。
「松下商店の背骨はあくまで七面鳥。でも、体を動かすことなしに食べることだけを推しても健康は得られません。両方をやることに意味があると思っています。最終的には、運動して高タンパクな食事を摂る意識が地域に根付いて、七面鳥の需要や生産にもプラスに働くといいなと思っています」
“地元で生きる”という選択肢を子どもたちに残したい
松下さんは、2020年からテナガエビの養殖事業にも取り組んでいる。もともと約10年前に役場主導で始まった事業を松下さんが引き継いだかたちだ。
遊休施設となっていた鮎の養殖施設を活用し、四万十川流域の食文化であるテナガエビの量産に挑戦。共食いの習性があるため、養殖は不可能とされてきたテナガエビだが、松下さんは研究を重ねた末に稚エビの量産に成功している。これは世界でも極めて珍しいケースだ。
「ある程度の広さのある水槽で飼育すれば、共食いしないことが分かりました。ただ、今は七面鳥の事業で手一杯で、テナガエビに十分な時間をかけられていません。七面鳥がもう少し安定してきたら、本格的に力を入れていきたいと思っています」

松下さんがこうして中土佐の資源を活かし、さまざまな事業に挑み続けているのは、ある思いが根底にあるからだ。
「小学校で子どもたちと接していると、『将来この町を出るかもしれないけど、いずれ中土佐町に帰ってきたい』という子が結構いるんです。僕が移住してきて強く感じているのは、地元で育った人が地元で働く姿が、いちばん自然で格好いいということ。中土佐町では外からの移住者の受け入れも進んでいるけれど、やっぱりこの土地で育った子どもたちが、大人になってこの町で仕事を持てることが大事だと思うんです。その環境をつくることが、地域の持続性にもつながるはずだと思って取り組んでいます」
移住当初はまだ20代。地域おこし協力隊として中土佐町に飛び込み、地域資源と向き合いながら手探りで道を切り拓いてきた松下さんの歩みは、約9年を経て、確かなかたちになりつつある。その歩みを支えてきたのは、地域に根ざした人々の思いと、豊かな自然、そして挑戦を受け止める町の風土があった。中土佐町だからこそ生まれた挑戦の連鎖は、これからも着実に町の未来を育てていくはずだ。
移住を考えている人へのメッセージ
外から来た人だからこそ持ち込めるアイデアやスキルは、地域にとって大きな力になります。でも、「やってあげている」というスタンスだと、自分も地域側もお互いに辛くなってしまうこともあります。大切なのは、地域の課題や目的と、自分自身の関心・得意なことがうまく重なるかどうか。その接点が見つかれば、無理なく、自分らしいかたちで地域と関わり続けることができると思います。
文:森田マイコ
▼あわせて読みたい
【関連サイト】
中土佐町 移住ポータルサイト「なかとさLIFE」
https://iju-nakatosa.jp/
中土佐町 公式サイト
https://www.town.nakatosa.lg.jp/