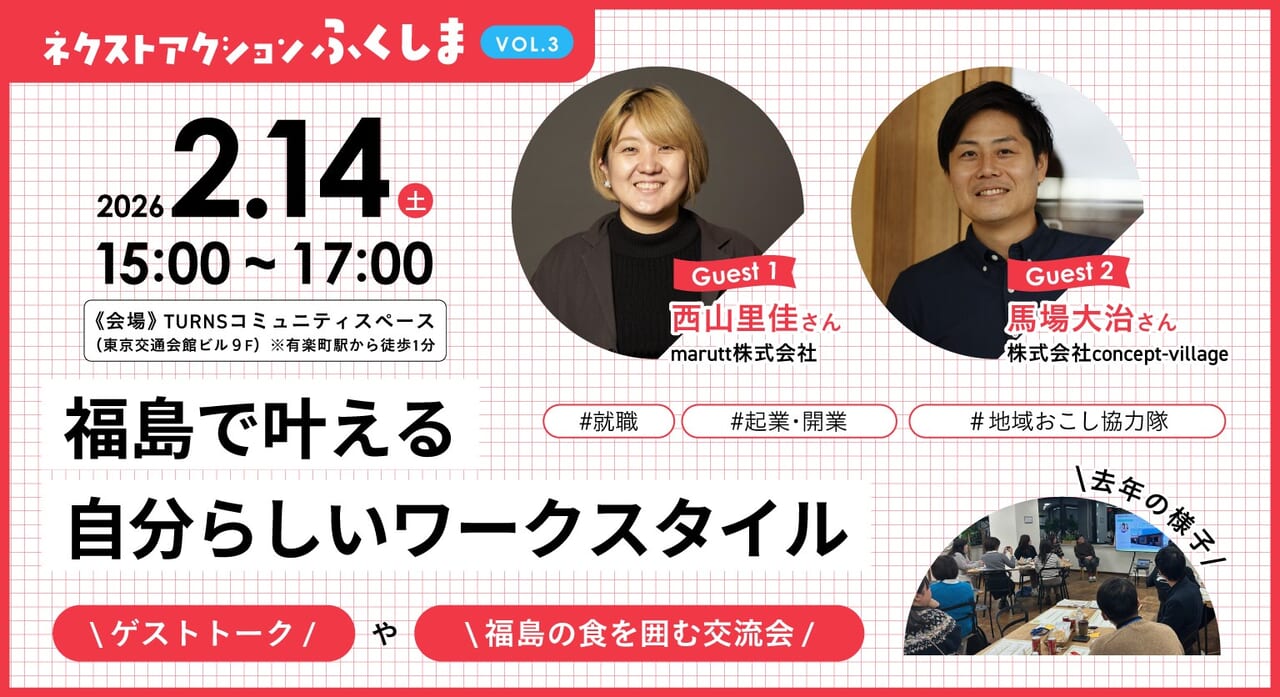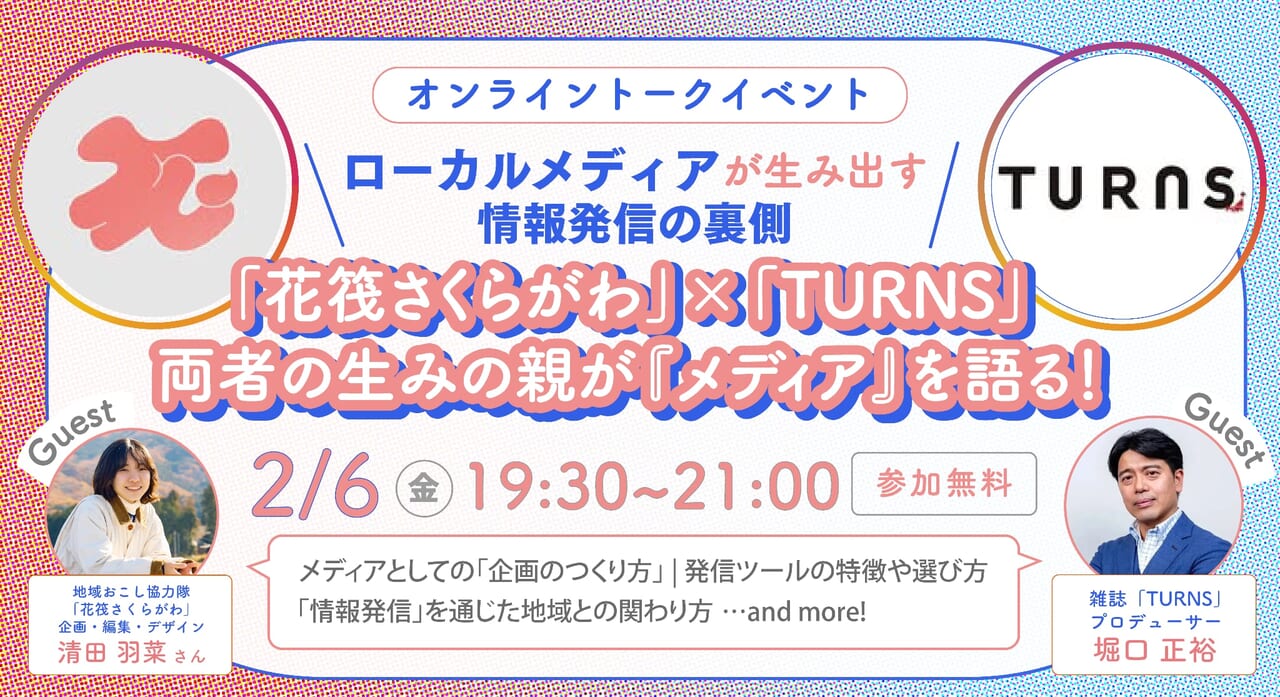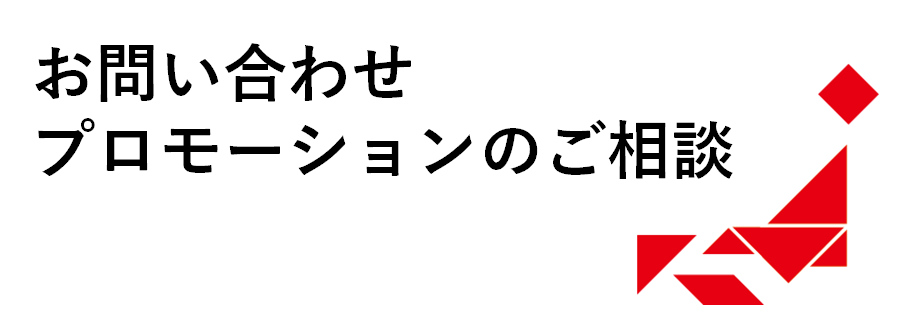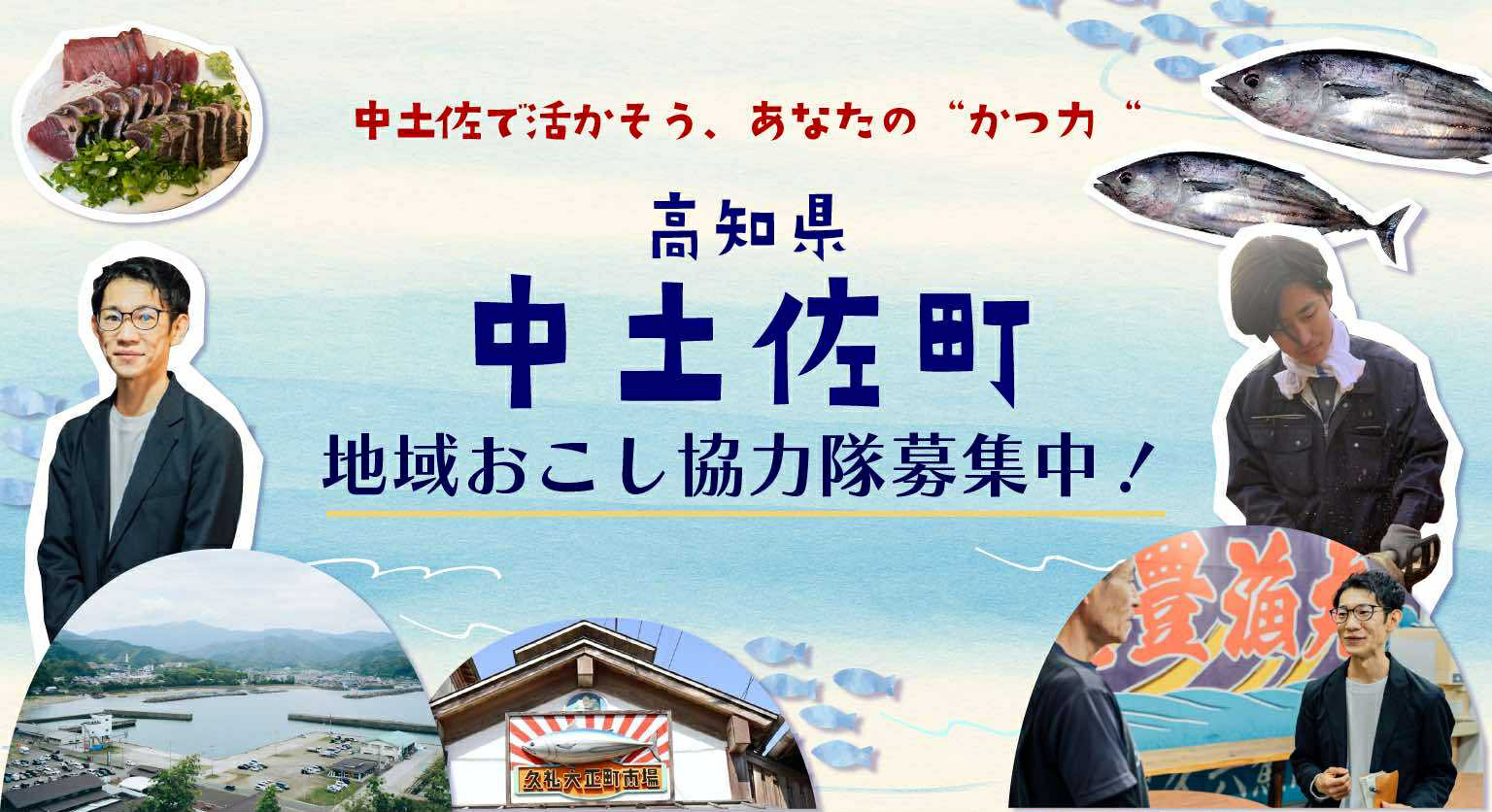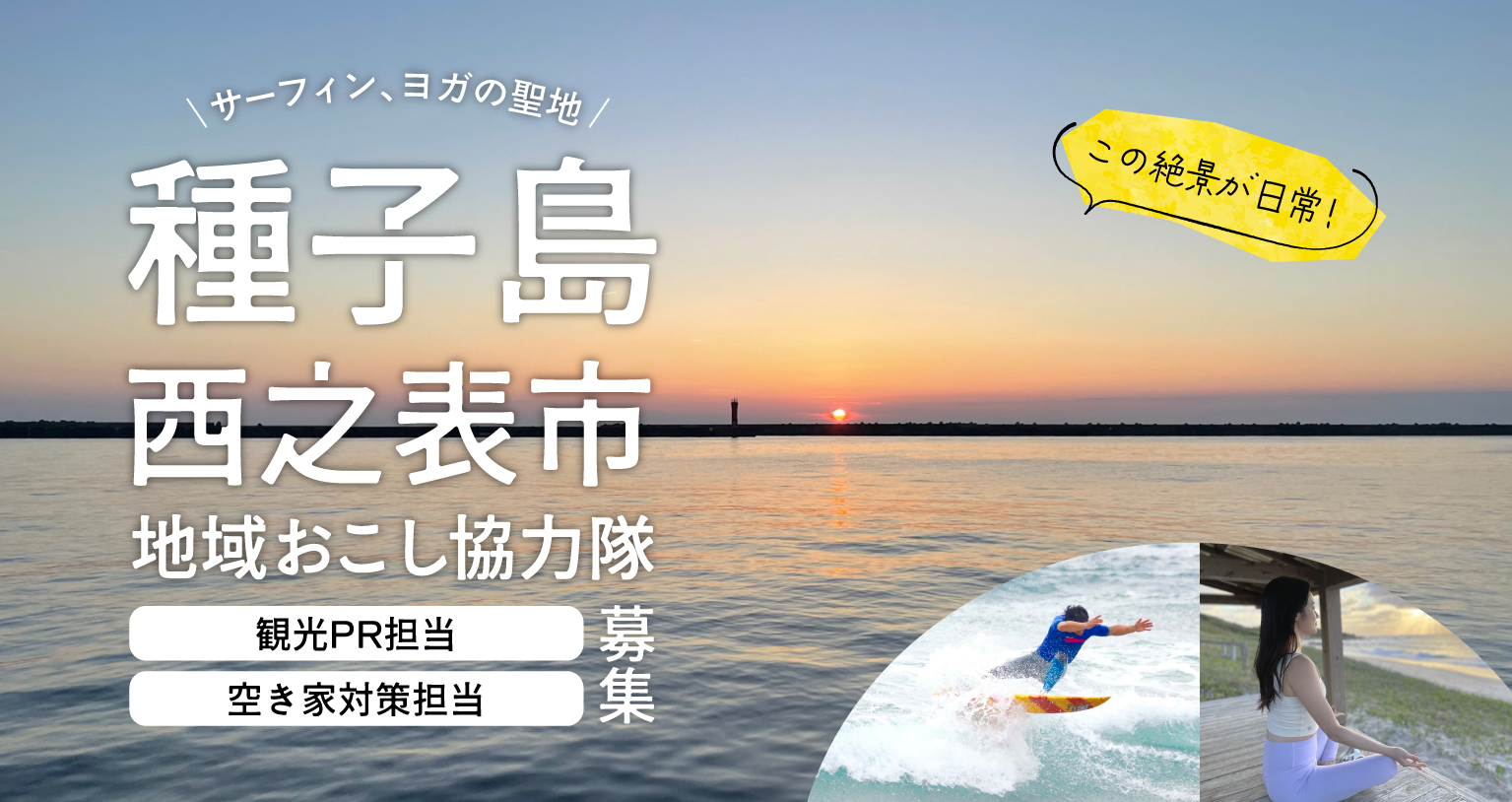秋田県の北西部に位置する八峰町は、八森町と峰浜村が合併して誕生した町です。
北は青森県に接し、東から北にかけて白神山地が連なり、西には日本海が広がります。町の面積234.19平方キロメートルのうち80%近くを森林が占める自然豊かな風土です。
 「鹿の浦展望台」から見渡す町の沿岸部。
「鹿の浦展望台」から見渡す町の沿岸部。
海と山に囲まれた八峰町。
白神山地は、人の影響をほとんど受けていない原生的なブナ林として世界最大級であり、貴重な生態系が保たれていることから1993年12月にユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録されました。八峰町の山間部は白神山地の裾野にあたり、町内のどこからでも白神山地を望むことができます。
町には八森と岩館(いわだて)、2つの漁港があります。秋田音頭の冒頭で「秋田名物八森ハタハタ♪」と唄われるように、ハタハタ漁をはじめとする漁業が盛んな町でもあります。
 海岸沿いに国道101号を北上すると、八森漁港、そして岩館漁港があります。
海岸沿いに国道101号を北上すると、八森漁港、そして岩館漁港があります。
JR五能線・八森駅から車で10分ほど山間部に向かうと「手這坂(てはいざか)」と呼ばれる茅葺き屋根の民家が残る集落があります。
江戸時代の紀行家・菅江真澄が秋田県を旅した際に手這坂に立ち寄り、集落に咲き乱れる桃の花を見て「まるで桃源郷のようだ」と感動して和歌を詠んだと言われています。
 集落の入り口に道標があります。花の見ごろは5月。
集落の入り口に道標があります。花の見ごろは5月。
里山を彩る桃の花の間にぽつぽつと建つ茅葺き民家。年月を経ても変わらず美しい風景に、春になると遠方から観光客が訪れていました。
しかし時代の流れで少しずつ住人が減っていき、2000年に最後の住人が町なかに引っ越してしまうと5軒の家だけが残る無人の集落となりました。
人が住まない家は荒廃していきます。特に茅葺き屋根は、手入れを続けていかなければ屋根に飛んできた草木の種子が根を張り、屋根が水分を含んで倒壊してしまいます。
そこで2001年、地元の有志による保存会が立ち上がり、茅葺き屋根の修繕や農地利用など集落の整備をしてきました。
無人になってから12年。
2012年7月、古民家のひとつに宮城県から移住してきたのが木村友治(ともはる)さんです。
茅葺き屋根の補修をしながら自給自足の生活を始めました。
 木村さんが住んでいる茅葺き古民家。
木村さんが住んでいる茅葺き古民家。
木村さんは、里山の自然環境・暮らし・文化を守り、次世代へ繋げていくために、昨年「NPO法人ミチのクニ手這坂」を発足しました。
活動の第一段階として、木村さんが住む古民家をリノベーションし、「里山暮らしが体験できる宿泊施設」を作ります。次にそこを基点として、茅葺き屋根の修復、古民家DIY、農業・林業体験、山・川・海での自然遊びを盛り込んだ宿泊体験イベントを開催します。
名付けて「みんなで創る古民家の宿プロジェクト」。
今回は、このプロジェクトを木村さんと共に進めていく人材を募集します。八峰町の大自然に包まれ、自分の手足と頭をフルに使って食べ物と暮らしを作っていくことに興味のある方。時に喜び、時に厳しさを感じながら、地域の人々やイベント参加者との交流を楽しめる方を求めています。
それでは、手這坂集落や八峰町での暮らしについて、詳しくご紹介していきます。
江戸時代から変わらない古民家で暮らす
移住して6年目となる木村さんの家にお邪魔しました。
自然厳しい里山の集落に住み、家の修繕も農業もこなしていると聞いて、ものすごく逞しい人物像を勝手に思い描いていたのですが、約束の時間に軽トラで現れた木村さんは、とても物腰が柔らかく笑顔の優しい方でした。
 笑顔の奥に見せる強い眼差しと、自然体で生きるしなやかさが魅力的な木村さん。
笑顔の奥に見せる強い眼差しと、自然体で生きるしなやかさが魅力的な木村さん。
「息子をこども園に送っていく間、少し家の周りを見て待っていていただけますか?」ということだったので、朝の忙しい時間に伺ったことをお詫びしつつ、さっそく家の周りを見せていただきました。
一番に目を引かれるのは、やはり存在感のある茅葺き屋根です。

移住後6年かけて修繕してきた屋根は、茅がびしっと揃っていてとても気持ちよく、見惚れてしまう美しさです。茅葺き職人さんの作業を木村さんが手伝い、少しずつ補修を進めてきました。修繕が終わっているのは全体の約半分。ブルーシートがかかっている部分はこれから直していきます。
木村さんはこの家で、2匹の犬と数羽の鶏、そして奥さんとお子さん2人と一緒に暮らしています。
 白い屋根の風除室はDIYワークショップで参加者と一緒に作ったトイレへのエントランス。床下は鶏の巣になっています。
白い屋根の風除室はDIYワークショップで参加者と一緒に作ったトイレへのエントランス。床下は鶏の巣になっています。
 木村家の鶏たち。写真には写っていませんが、比内地鶏のメスもいます。
木村家の鶏たち。写真には写っていませんが、比内地鶏のメスもいます。
木村さんは静岡で1年間、長野で6ヶ月間、パラグアイで2年10ヶ月間、有機農業を学んできました。2011年に研修が終了し、農家として独立する場所を探し始めました。20代のころに青年海外協力隊としてパラグアイで農業指導をした経験から、自然とともに生きる暮らしがしたいと思っていましたが、宮城県ではピンとくる場所が見つからなかったそうです。
「農業だけでなく家づくりもしたくて、手のかけ甲斐がある、遊び甲斐のある場所を探してヒットしたのが、古民家のあるこの集落でした。ここなら自由にやりたいことがやれて面白そうだな、と感じて決めました」
12年間無人だった集落に単身移住し、古民家を補修しながら農地を作っていきました。畑も田んぼも無農薬・無化学肥料で栽培しています。基本は自給自足。少量多品目の野菜を育てています。個人契約しているお客さんへの販売や、道の駅や県内のマルシェでの販売も行っています。
 木村さんの田んぼ。左奥にブルーシートがかかっているのが木村さんの家。正面にはビニールハウスがあります。
木村さんの田んぼ。左奥にブルーシートがかかっているのが木村さんの家。正面にはビニールハウスがあります。
移住してきた時は1人でしたが、古民家で一緒に暮らしたいという奥さんと出会って結婚し、2人のお子さんが生まれました。
耳に心地よいせせらぎをたどって、ビニールハウスの横の道なき道を分け入ると、きれいな川がありました。水が澄み、魚の影がちらちらと見えます。
「溜まりもあるので、夏にはよく子供を遊ばせています」
と、にっこり笑う木村さんは、まるでここで生まれ育った”手這坂の主”のように見えました。
 涼しい川風とマイナスイオンに、身も心も癒される空間です。
涼しい川風とマイナスイオンに、身も心も癒される空間です。
冬には積雪が1メートル近くなりますが、木村さん一家しか住んでいない集落なので除雪車は入りません。
「冬は大変ではないですか?」と聞くと、「自分たち家族しかいないので、かんじきで踏み固めて道を作っておしまいです。町に住んでいる人たちより除雪作業はしていないかもしれません(笑)。」と、やはり楽しげな表情。
大変なことも全て含めて、自分の生活にしている力強さを感じました。
古民家をゲストハウスに改造
家の間取りは4LDKと30坪の土間。この家をDIYで改造して、半分をゲストハウスにします。
改造前の状態ですが、家の中を見せていただきました。

ここはゲストも利用できる居間です。一度、家具を全部出してから床に断熱材を入れます。さらに天井を高くして囲炉裏を復活させ、団らんのできる空間にします。
囲炉裏で火をおこし内側から屋根を燻すことで、茅が丈夫になっていく効果もあるそうです。

こちらは客室です。電気の傘には、友人の職人さんの手による透かし彫りが施されています
「この透かし彫りは町内の製材屋さんで手工芸としてやっているものです。繊細できれいですよね」
廃材を使ったテーブルもあり、とてもいい味を出しています。
「断熱材を入れたり、水回りを新しくしたり、居心地よく使いやすい工夫をしつつ、余計なものを極力なくしてシンプルなゲストハウスにしたいと思っています。自然な暮らしと便利さの兼ね合いをいろいろ考えています」
土間には竈(かまど)やピザ窯も設置します。スイッチひとつで炊飯できる今の時代、竈でご飯を炊くだけでもひとつのイベントになるに違いありません。
 家の壁には、よく手入れされた農具が掛けられています。
家の壁には、よく手入れされた農具が掛けられています。
「茅葺き屋根の補修や家づくりのDIYなどは、未経験の方にとってものすごくワクワクする作業だと思います。都会の方には、農作業も新鮮な体験になることでしょう。ここだからこそできるコトをイベントとして開催しつつ、海や山での自然遊びなどを盛り込んで楽しい宿泊体験の企画を考えていきたいと思っています。イベントは今年3回、来年3回予定しています」
木村さんが移住してきてからも二軒、無人民家の屋根に積もった雪が春先に氷になり、重みで潰れたそうです。
古民家を維持していくためには、やらなければならないことがたくさんあります。1人ではやれることが限られていますが、イベントにして楽しく人の手を借りながら作業ができ、それを機に集落のファンが増えれば、みんなの手で集落を保存していくことができるのではないでしょうか。
それが「NPO法人ミチのクニ手這坂」の狙いです。
大自然に囲まれた八峰町での暮らし
NPO研修生として滞在する八峰町の暮らしについてご案内します。
住居は町内のアパートなどを用意する予定です。手這坂から車で約10分。爽やかな海風が吹く高台にあり、海岸までは徒歩3分という近さです。
内陸部と違い冬の積雪が20~30センチと少ないので、雪に慣れていない方でも比較的生活しやすいでしょう。
 写真のような一戸建てのほか、メゾネットタイプのアパートもあります。
写真のような一戸建てのほか、メゾネットタイプのアパートもあります。
JR八森駅周辺に図書館や公民館、文化ホールなどの複合施設「ファガス」、商店街、銀行や郵便局など生活に必要な機能がひととおりそろっています。さまざまなイベントや伝統芸能のお祭りなどもここで開催されます。
 JR八森駅の近くにある文化複合施設「ファガス」。図書館は夜9時まで開いています。
JR八森駅の近くにある文化複合施設「ファガス」。図書館は夜9時まで開いています。
町の大きな特徴として、ファミレスなどのチェーン店がほとんど無いことがあげられます。町内にコンビニが2軒あるほかは、個人経営の飲食店がちらほら点在しています。
どうしても必要なものがあるときには、車やJR五能線で能代市まで行くと大型店もあります。
木村さんによると、農家が多い旧峰浜村側の人は比較的物静かなタイプが多く、漁師町である旧八森町側の人は、大きな声で笑ったり話したりする元気なタイプが多いとか。地元の人たちと積極的に交流することで、八峰町の魅力をたくさん見つけることができるに違いありません。
ここにしかない風景、人、お店…地域の宝がぎっしり詰まった八峰町。
木村さんも移住してきた時は1人でしたが、集落を保存していくため、町に活気を取り戻すためのさまざまな活動を通じて、友達がたくさん増えました。今は、イベントの開催や家の改造を手伝ってくれる心強い仲間に囲まれています。
「NPO法人ミチのクニ手這坂」のプロジェクトは、いろんな人と関わり合いながら古民家のファン、手這坂のファンづくりをしていく仕事です。
未経験のことにも興味を持って積極的に取り組んで行ける方。
イベントの企画・PR・運営に関心がある方。
イベント参加者と地域の人々との架け橋として交流を楽しんでいける方。
ここ八峰町で手這坂集落の保存に取り組みつつ、あなたの暮らしを見つけてみませんか?
※後編では、この地に暮らす人々を通して八峰町の魅力をご紹介します!
https://turns.jp/24327
写真:コンドウ ダイスケ 文:島田 真紀子
東京で事前相談会も開催予定です!
開催日時:12月11日(火)13:00-17:00
場所:東京交通会館ビル B2F 第2会議室B
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目10−1
http://www.kotsukaikan.co.jp/meeting_room/