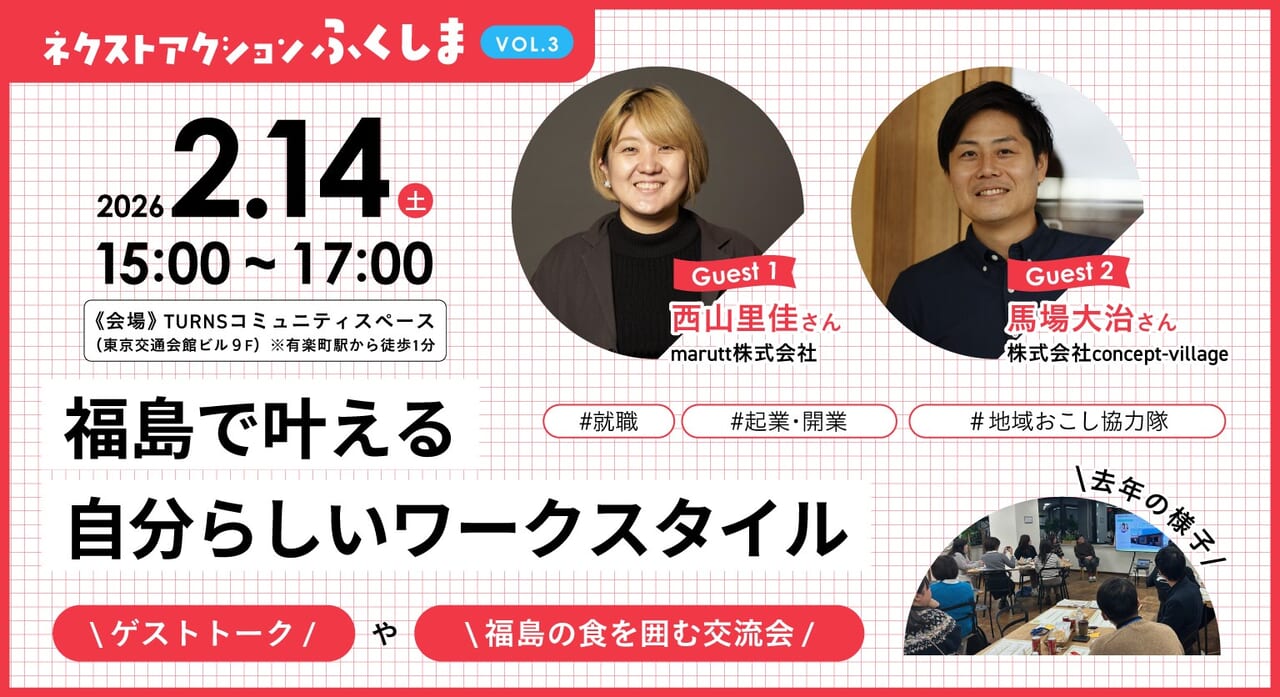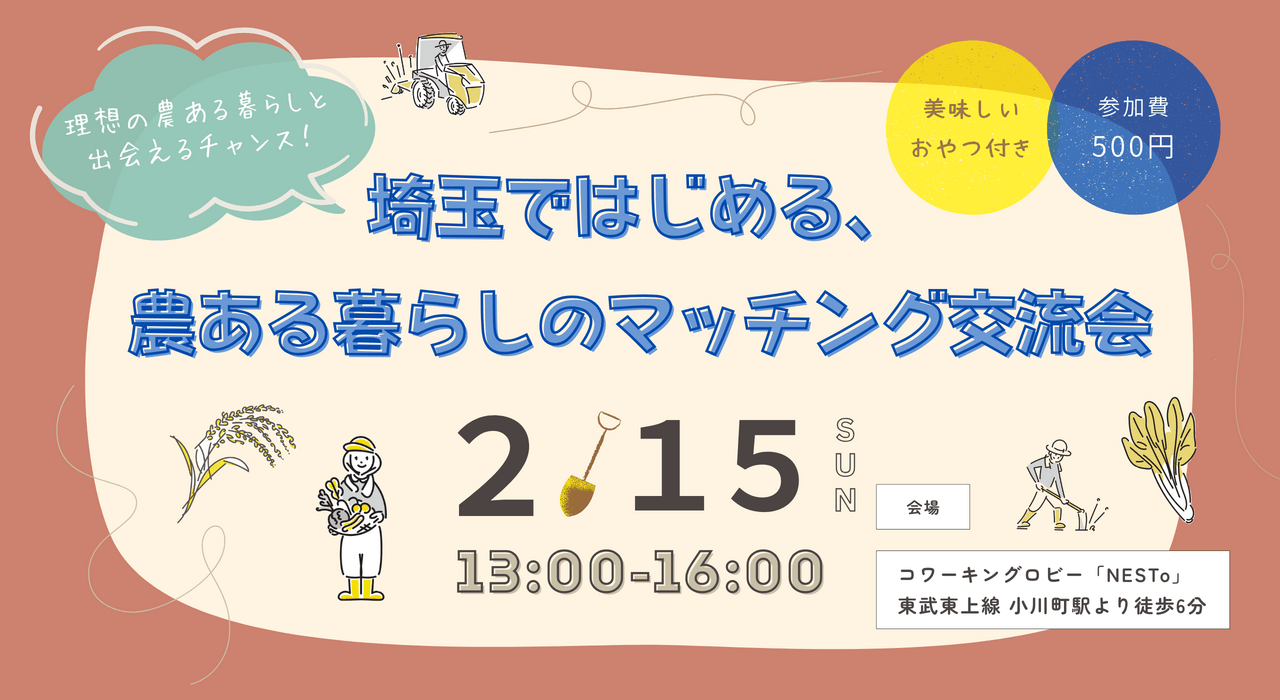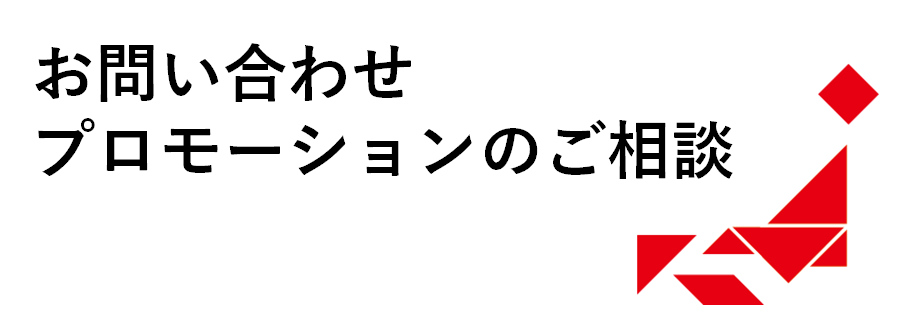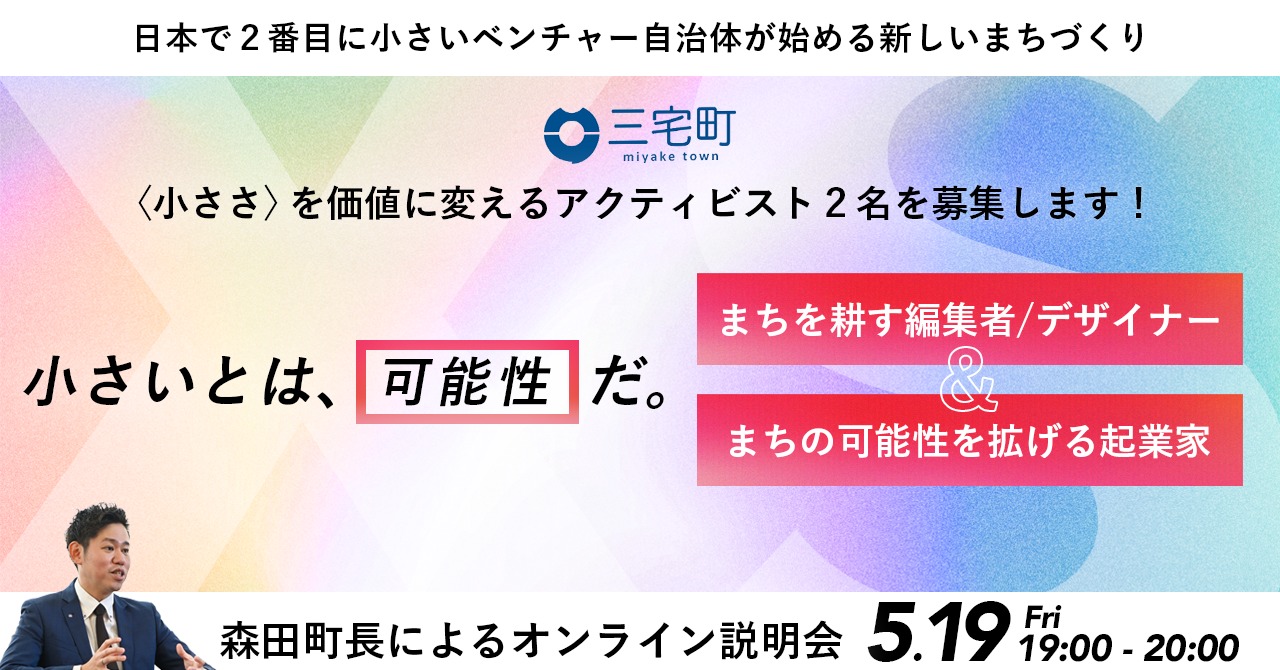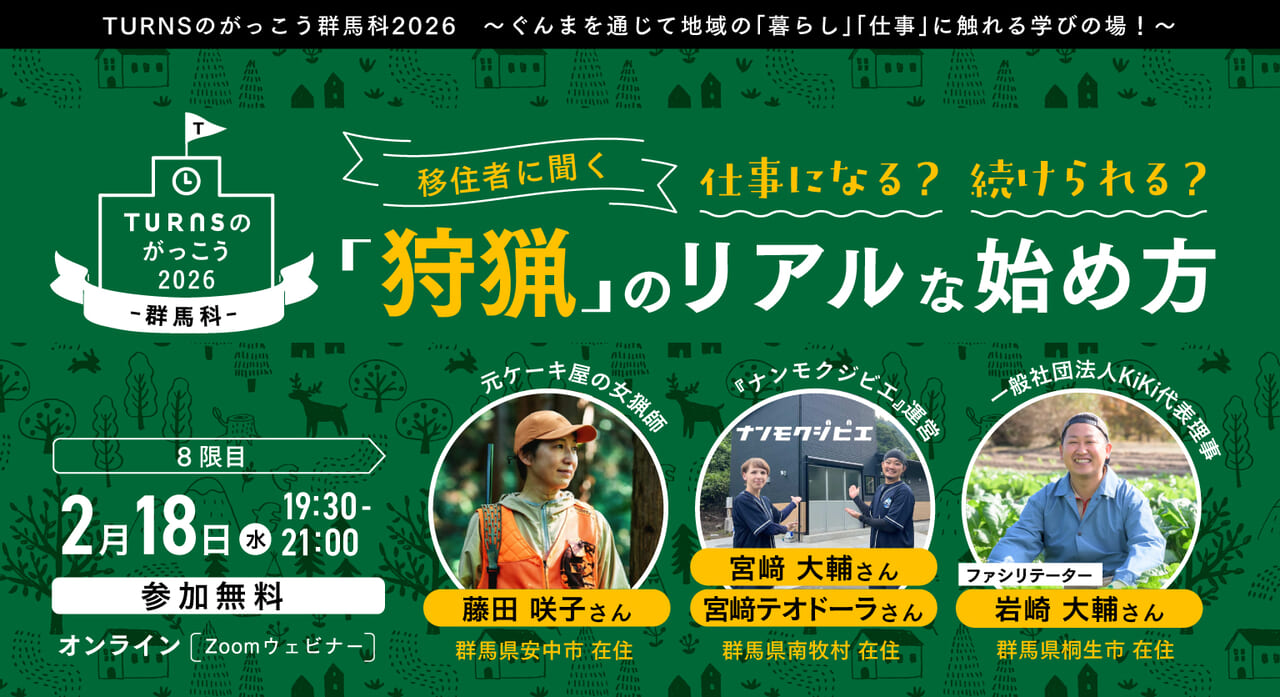東京・新宿から車で約2時間。山梨県南部に位置する身延町は富士山を始めとする山々に囲まれ、日本三大急流の一つである富士川が町の中心を流れる自然豊かな町です。
昼夜の寒暖差と霧が多い気候を活かして町内で栽培されているのが、“幻の大豆”と呼ばれるブランド特産品「あけぼの大豆」。身延町では、この伝統を受け継ぎながら地域を盛り上げる「地域おこし協力隊」を募集しています。
幻の大豆「あけぼの大豆」とは?

あけぼの大豆は明治時代に関西地方から伝わり、身延町曙地区を中心に150年以上栽培されてきた在来種の大豆です。手に取って驚くのは粒の大きさ。一般的な大豆の1.5倍、重さは約2倍にのぼります。「大味なのでは?」と思うかもしれませんが、一番の特徴は甘みの強さと食味の良さにあります。総糖量は一般的な大豆の約1.2倍で、特にショ糖(砂糖の主成分)の割合が高く、豊かな食味を誇ります。

左があけぼの大豆、右が一般的な大豆。豆粒を10粒並べると6寸になることから「十六寸」の別名がある
良質な味わいは、曙地区特有の風土によって育まれます。地質、朝霧の発生による適度な保水性と排水性、そして枝豆の成熟期(10月)から大豆の収穫期(12月)の昼夜の寒暖差。曙地区は標高300〜700mで傾斜地が多いなど農業に不向きとされますが、あけぼの大豆の栽培には非常に適しているのです。限られた気候条件のもと手作業で栽培されるため流通量が少ないのが、「幻の大豆」と呼ばれる理由です。
発祥の地である身延町では2016年から、あけぼの大豆を活用した6次産業化による町おこし事業をスタート。味噌、シュウマイ、スープ、コーヒーなど約15種類の加工品を開発・販売しています。2022年には農林水産省地理的表示(GI)保護制度の産品に登録されました。
唯一無二の味わいは県内外で人気が高く、枝豆収穫期の10月には多くの人が身延町を訪れます。さらに東京の有名百貨店でも人気を博し、販売価格も年々上昇しています。
地域おこし協力隊募集!ミッションは…
\どんな仕事をするの?/
町の6次産業化の拠点「身延町あけぼの大豆拠点施設」で、
・あけぼの大豆の栽培
・あけぼの大豆拠点施設における商品開発、販売促進
・あけぼの大豆振興協議会の事業補助
・イベントへの出店
・町内の生産者への農機具の貸し出しや栽培支援
など、多岐にわたる業務を担います。
\こんな方は大歓迎!/
・自分の力で何かを作りたい方
・地域を動かすことに情熱を持てる方
・自分の意思と行動で新しいことにチャレンジしたい方
・農業経験は問いません!
この取り組みに決められた正解やルートはありません。自分の意志と行動で道を切り拓いていくことになります。だからこそ多様なアプローチが可能で、無限の可能性が広がっています。むしろ“敷かれたレールが欲しい”という人には向いていないかもしれません。現役隊員やOBの中には、あけぼの大豆の栽培に加えて大豆を使ったお菓子を考案・販売する人、農業と保育士の二足のわらじで地域に根ざしている人などがいます。経験よりも大切なのは、地域と向き合う熱意です。その情熱があれば、きっと活躍できます!
\受け入れ体制も安心!/
・栽培技術はあけぼの大豆拠点施設で丁寧に指導
・隊員就任の2年目から最大100万円の「地域おこし協力隊起業支援事業費補助金」制度あり
・研修費や家賃の補助あり
あけぼの大豆の作付けは、6月の種まきから1月の収穫までの約半年間。それ以外の期間は、他作物を耕作したり、人脈づくりや販売活動をしたり、自分の自由な活動に力を入れることができます。活動に支障がない範囲で副業もOKです。
先輩隊員インタビュー
農と地域とコーヒーと。
加藤 新さんが身延町で実践する、新しい生き方
地域おこし協力隊員として、2023年に愛知県から身延町に移住した加藤 新さん。あけぼの大豆の栽培を中心に、出会った人たちとの縁を紡いで多彩な活動を始めています。移住前とは180度違う働き方、暮らしを始めた加藤さんに、就任のきっかけや地域への思い、これからのビジョンを聞きました。

身延町地域おこし協力隊 加藤 新さん
愛知県出身。国立高専を卒業後、喫茶店勤務を経て県内に自分の店をオープン。2023年、地域おこし協力隊着任を機に妻と山梨県身延町へ移住。現在、任期2年目。あけぼの大豆に加え、今年から米作りにも挑戦中。
「食を生み出す仕事をしたい」と、喫茶の世界から農業へ
前職は喫茶店経営。20代から喫茶店の聖地・名古屋で飲食業の経験を重ねてきた加藤新さんが地域おこし協力隊として農業の世界へ飛び込んだのは、38歳の時でした。
「長く食の仕事に携わる中で、しだいに“食材を作る側”として苦労や喜びを知りたいと考えるようになったんです。農業ができる移住先を探して休日に妻と各地を巡る中で、身延町の下部温泉と自然に惹かれて。最初は移住先というよりも好きな旅先だったのですが、何度か訪れた時に特産品のあけぼの大豆を知ったんです。地域おこし協力隊制度もその時に初めて知り、固定収入を得ながら農業に取り組めることに魅力を感じて、応募を決めました」
妻も「米と水、豆があれば人は生きていける」と大豆農家への転身に賛同。移住後に約3,000㎡の畑を借り、あけぼの大豆の栽培をスタートしました。初めての農業、どのように取り組んだのでしょうか?
「町のあけぼの大豆拠点施設で講習を受け、分からないことは地域の先輩農家の方に質問するとなんでも教えてくれました。初めての経験ですから、1年目は『失敗しても仕方がない』とあまり考えすぎず走り抜けましたが、2年目の今年からが勝負ですね」

取材に訪れたのは8月。ふかふかの土で整えられた畝にあけぼの大豆の葉がみずみずしく生い茂り、紫のかわいらしい花を咲かせていました。6〜7月に種をまくあけぼの大豆は、10月に枝豆収穫の最盛期を迎えます。枝豆はとにかく鮮度が命。この時期は集落一帯が忙しく、活気に満ちるのだそう。
「初めての枝豆収穫は嬉しかったですね。とはいえ、とにかくスピード勝負なので、自宅のリビングにシートを敷き詰めて夜まで選別作業。感慨にふける暇もなく、あっという間でした(笑)」
大粒で甘く食べごたえのある枝豆は県外にもファンが多数。10月には、枝豆の直売会や収穫体験といった町内各所で開かれる産地フェアなどのイベントに、多くの観光客が訪れます。さらに東京の有名百貨店でも高値で販売されるほど。12月になると大豆の収穫期を迎え、絶品の味噌や豆腐に加工されます。

一人の住民として、地域に根ざして暮らしたい
あけぼの大豆の栽培についていきいきと言葉を紡ぎ、「大豆や米の
「畑のことも町の暮らしのことも全部、昭男さんが教えてくれました。野菜が採れたら分けてくれたり、こんな農機具がほしいと相談すればエンジニア経験を活かして設計図を書いてくれたり。いつも笑顔で、自分より他人や地域を優先して、自分はこんな風には生きられないなと尊敬します」

昭男さんもまた、「畑作業で困ったことがあると、加藤さんがとんで来て手伝ってくれる。若いのに思いやりがあって気配りもすごくできるんだよ、憎らしいぐらい(笑)。若い人が来てくれるのは嬉しいし、移住者が地域に新しいアイデアをもたらしてくれるのがありがたい」と笑顔で話します。

加藤さん夫妻が暮らす西嶋地区は町内でも地域活動が盛んで、草刈りや獣害対策の電気柵設置といった自治活動に加え、月に一度は住民が公民館に集まり、食卓を囲みながら情報交換を行っています。結束の強さを物語るのが、年末恒例の「西嶋イルミネーション」です。2000年から住民主体で行うイベントで、500mの道沿いに10万個以上の電球が点灯する風景を見に、全国から観光客が訪れます。昭男さんが長年リーダーを務め、12月には毎週末、住民が集まって準備を行うのが恒例です。

こうした密な地域活動は地方ならではのもの。都会から移住した人の中には戸惑う人、面倒に感じる人がいるのも事実です。不安があれば住まいを決める前に町役場に様子を聞いたり、お試し移住を利用してから検討することも可能ですが、 加藤さん夫妻はどうだったのでしょうか?
「こうした地域活動があることは、住んでから初めて知りました。正直、合うかどうかは人によると思いますが、僕らとしては地域に早く溶け込むきっかけになって良かったと思います。参加は強制ではないですし、あまり参加しない人もいますが、さすがに昔話のように村八分にされることはありません(笑)。ただ僕らとしては、せっかく縁あってこの集落で暮らすことを選んだのだから、できる限り参加したい。協力隊員である前に、住民でありたいという思いがあるから」

農業+αの働き方を探して
加藤さんの仕事は農業だけにとどまりません。飲食業の経験を活かして、グルテンフリーのシフォンケーキやマフィンを妻と一緒に開発製造して道の駅で販売するほか、町内外のイベントにコーヒー店として出店することも。昭男さんの紹介で、菓子製造業の許可を取るための中古住宅も購入しました。

さらに畑の生育状況を調査するため、ドローン操縦資格を取得。加藤さんの資格取得をきっかけに、町ではスマート農業実証実験プロジェクトが立ち上がり、将来的にドローンを使った農薬散布や獣害対策、気温などのデータ管理を目指しています。
「近年の急激な気候変動の影響で、ベテラン農家でも予測がつかないことが増えつつあります。ドローンを活用して得た詳細なデータが役に立つ場面も多く、新人の僕が先輩農家から相談されることもあるんです」

こうして町全体の農業のために役立てるほか、将来は副業としてドローン操縦による収入も見込んでいる加藤さん。「協力隊の収入が安定しているからこそ色々な分野に挑戦できる」と話す一方で、背景には「あけぼの大豆の栽培だけでは食べていけない」という現実があります。あけぼの大豆は一品種のみで収穫期が集中するため、それだけで生計を立てることが厳しく、町に専業農家はいません。任期終了後も定住した協力隊OBはたくさんいますが、現在全員が農業に加えて別の仕事を持っています。
農業以外の仕事は、自分で探すしかありません。大変だと感じるかもしれませんが、見方を変えればあけぼの大豆を収入の柱に、複数のキャリアを広げられる可能性があるということ。加藤さんは、自分が持つ能力と地域のニーズが重なる部分を探して、複数の仕事を生み出しています。例えば、カフェが少ない身延町では加藤さんのような飲食のプロは歓迎され、高齢化が著しい地域では農業の機械化や若い力は何よりも求められます。
「よく『喫茶店やってよ』と町の人に言われるんです(笑)。でも愛知と身延町では人口がまったく違うから、喫茶店専業は成り立たない。けれど複数の仕事の一つとしてであれば可能ですよね。例えば、日蓮宗総本山やゆるキャン△の聖地など、実は身延町には観光客が多く訪れます。店舗を持たなくても、そのイベントに参加するだけで自分やあけぼの大豆を知ってもらう機会は豊富にあるんです。ドローンもそうです。昔ながらのやり方にこだわる先輩農家は多いものの、皆さん高齢になり、耕作放棄地や鳥獣被害が増えている。だからこそ実は心の底では効率化を望んでいるのです。地域の困りごと=仕事のチャンスになると、今では逆転の発想で捉えられるようになりました」

一つの仕事に100%つぎ込むのではなく、いくつかの軸を持つことで収入のリスクが分散し、コミュニティも経験の幅も広がります。複数の仕事をバランスを変えながら持つ自由な働き方を、加藤さんは身をもって示しています。副業があると忙しいのでは?と尋ねると、「一つに集中するより、いろいろなことをする方が僕には合っているみたいで、そこまで頑張っている感覚はないんです」と加藤さん。
農業中心の暮らしは朝から働き、日が暮れたら帰るという健康的なリズムが基本。昼夜問わず働き続けていた喫茶店時代よりも、メリハリをつけて休めているといいます。
「移住前は経営のことを四六時中考えていたし、『普通以上でいなければ』『ちゃんとしていなければ』と自分を追い込んでいました。でも身延町に暮らしてから、『穏やかでもいいんだな』と思えるようになったのは大きな変化です。例えば『今日何もしてないな』と感じても、それでいいと思える。ここではのんびりした人も受け入れてくれるし、普通でいい。そうした環境で無理しすぎずやりたいことに取り組めるから、心地よく日々を重ねていけるのだと思います」
地域おこし協力隊への応募を考えている方へ
\加藤さんからのメッセージ/
「農業プラスαの生き方を楽しめる人、いろいろなことをやってみたい人が、この町に向いていると思います。人によって違う生き方の可能性が、ここでは開けると思います。何をすればいいか分からない方もいるかもしれませんが、そんな時こそ役場に相談してみてください。身延町の役場はすごく協力的な人ばかりで、協力隊が暮らしやすいように、町を盛り上げるために、一緒に悩んでくれます」
\身延町からのメッセージ/
「身延町は人口が少ない町なので、役場と住民の距離が近いことが特徴です。協力隊の皆さんも大きな町や人気の移住地に比べて存在感が大きい。例えば、町のスマート農業実証実験プロジェクトも、加藤さんがいたからこそ企画が立ち上がりました。協力隊の皆さんが「こんなことを始めたい!」と相談してくれたら、それが農業でも他の分野であっても私たち役場も協力したいですし、悩みは一緒に解決したいと思います。当然のことですが、協力隊のミッションは町が抱えるミッションです。少しでも興味がわいたら、まずは“おためし地域おこし協力隊”として是非お越しください」
10/18(土)「みのぶフェス2025」開催のお知らせ
あけぼの大豆の枝豆を生産者から直接購入したり、その場で味わえる「みのぶフェス2025」 が、今年10月18日(土)から新たに開催されます。
地元事業者による特産品販売や、個性豊かな作家が集まる クリエイターズマルシェも同時開催。秋の身延を満喫できる1日を、ぜひお楽しみください。
イベントの詳細はこちら https://www.minolove.jp/soshiki/1/102578.html
山梨県身延町はこんなところ

身延町全景

下部温泉

本栖湖でのアクティビティ

身延山久遠寺 観桜期

本栖湖の紅葉と富士山
豊かな自然環境、歴史と文化が息づくまち
身延町は面積の8割を森林が占め、その豊かな自然環境から登山やキャンプ、富士山の絶景が望める本栖湖(もとすこ)でのSUPやカヌーなどアウトドアアクティビティも満載です。また最近では、アウトドア系漫画『ゆるキャン△』の聖地としても知られています。意外と海にも近く、駿河湾までは車で30分です。
歴史も古く、町の南部には1282年に日蓮聖人によって開山された日蓮宗の総本山「身延山久遠寺(くおんじ)」があります。富士川の流れに沿って旅館などが建ち並ぶ「下部(しもべ)温泉郷」は1300年の歴史があり、日本の名湯百選にも選ばれています。
子育てにちょうどいい生活環境
身延町は、自然の中でのびのびと子育てができる環境が整っています。豊かな森や川に囲まれ、四季折々の自然に触れながら、子どもたちは感性を育み、健やかに成長できます。若者や子育て世代へのサポートも手厚く、給食費・修学旅行費は町が全額負担。また、18歳まで医療費が無料など、町は「全国トップレベルの子育て・教育支援施策」を掲げています。すでにお子さんがいる方や、田舎暮らしでの子育てを考えている方には最適の環境です。
取材・文:石井妙子 写真:古末拓也
身延町地域おこし協力隊OGインタビュー
150年以上の歴史を持つ「幻の大豆」を次の世代に。
小林あゆみさんに聞く「あけぼの大豆」と身延町の魅力
地域に支えられながら、あけぼの大豆を次の世代へつなぐ
▼身延町公式サイト
https://www.town.minobu.lg.jp/
-
都道府県+市町村 山梨県身延町 募集状況 募集中 勤務地 身延町あけぼの大豆拠点施設 募集職種 あけぼの大豆推進担当【2名】 雇用形態 個人事業主として、身延町と委託契約を締結して活動します。 給与 年額350万円(消費税及び地方消費税を含む)
年間の委託料を12で除した金額を1月ごとに支払います。福利厚生 国民健康保険、国民年金などは、自身での加入が必要です。 勤務時間 週5日、1日 7時間30分勤務(1週間あたり37時間30分の中で、身延町及び身延町あけぼの大豆拠点施設の指定管理者と協議) 応募資格 (1)概ね年齢18歳以上40歳未満の方
(2)三大都市圏内の都市地域又は指定都市に現に住所を有し、採用後、身延町内に住民票を異動できる方(地域要件については総務省ホームページ参照)
(3)普通自動車免許を有し、実際に運転できる方
(4)地域の特性や風習を尊重し、異なる価値観を持つ人たちとも円滑なコミュニケーションを図りながら積極的に 企画・提案・実施ができ、求められた業務に対して誠実に取り組める方 、活動に取り組むことができる方
(5)パソコンの基本操作(ワード・エクセル・パワーポイント等)ができる方
(6)あけぼの大豆の栽培方法を柔軟に学び、組織や近隣住民と協同して農業に従事できる方
(7)心身が健康で、かつ地域おこし活動に意欲と情熱を持ち、地域を元気にするとともにと協働することができる方
(8)協力隊としての活動期間終了後も身延町に定住し、就業・起業しようとする意欲を持つ方
(9)地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない方募集期間 定員になり次第、締め切り 選考プロセス (1)書類選考後、面接審査を実施します。
(2)面接前後に活動拠点となる事業者との顔合わせ等を行います。
(3)面接審査日時は、後日応募者に連絡します。
(4)面接審査会場は、身延町役場となります。
(5)最終結果報告は文書で通知します。
(6)応募、面接審査等に係る経費(旅費等)は応募者の負担となります。
※応募前に、実際の活動内容や生活を2泊3日で体験ができる「おためし地域おこし協力隊」を活用することができます。詳細はお問い合わせください。交通費は自費負担になります。採用問い合わせ先 身延町役場産業課 磯野・渡辺
TEL:0556-42-4805 FAX:0556-42-2127
E-mail:sangyo@town.minobu.lg.jp備考・その他 委託料とは別に、下記の活動に要する経費を支給します(上限200万円)。
(1)住居の家賃(光熱水費は個人負担)
(2)車両の燃料費(活動使用分)
(3)研修費・出張などに係る旅費
(4)活動に要する消耗品
(5)その他活動に要する経費