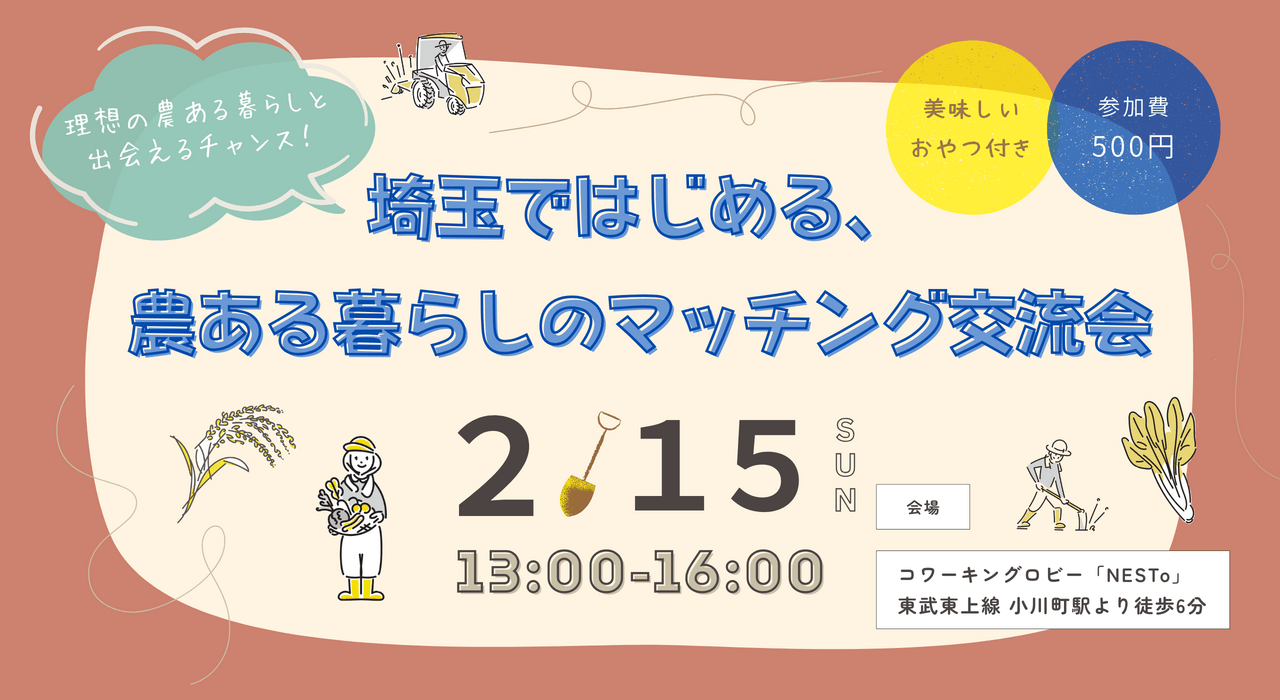妙高の山々が織りなす豊かな自然環境は多くの人々を惹きつけます。絶滅危惧種のニホンライチョウが生息する妙高戸隠連山国立公園や雄大な山々を擁し、多様な動物たちが生息する妙高市では「山との共存」は重要なテーマになるでしょう。
妙高市で鳥獣対策の専門員として働く福島脩太さんは東京都出身の移住者。妙高市内のアウトドア専門学校在学中に狩猟免許を取得して、卒業後も妙高に残り続けています。25歳の福島さんが猟師として山と向き合い続けることを決めたストーリーを聞きました。
※取材時は令和4年3月
高校卒業後は東京から単身妙高市へ進学
「小さい頃から父の影響で釣りが好きだったんです。自然の中にあるものを自分で採って食べるという子供の頃の体験が今に繋がっているのだと思います」
福島さんは生まれも育ちも東京。高校を卒業するまで都内で暮らしていました。高校を卒業した後の進路を探していたときに目に留まったのが妙高市にある「国際自然環境アウトドア専門学校(i-nac)」だったといいます。

福島脩太さん
1997年生まれ、東京都豊島区出身。2016年4月に妙高市の国際自然環境アウトドア専門学校へ進学するため単身移住。在学中に狩猟免許を取得。専門学校卒業後は妙高市に残り、アウトドアショップで働きながら、冬期の鳥獣対策専門員として猟師経験を積む。2020年4月に市役所内で2名しかいない通年の鳥獣対策専門員となり、猟友会などと連携をしながら鳥獣対策や害獣防除業務に従事する。
「高校も農業関連の高校で造園について学んでいました。卒業してからも自然と関わるようなことを学んでいきたいという思いがあったので、東京から妙高へ行くことには抵抗ありませんでしたね」
自然と関わる仕事をしたいという福島さんにとって、必要な知識と経験が得られるカリキュラムがあったのが進路選択の決め手になりました。登山やキャンプといったアウトドアが趣味であった福島さんにとって、妙高市は理想の環境だったといいます。

猟の装備に着替えて山に入る
「専門学校では子供向けの自然キャンプやトレイルランの企画をしたり、自然ガイドの資格を取ったりしていました。念願の狩猟免許を取得してからは、動物行動学や獣害についても学ぶようになって、その頃から猟師という仕事に対して深く興味を持つようになったんです」
専門学校を卒業した福島さんは、東京には帰らずに妙高市に留まり、アウトドアショップの店員として働きながら、猟師としての経験を積むことを決めました。
ショップ店員をしながら猟師の道を目指す

冬季はスノーシューを装着して道のない場所を進む
「最初は趣味のためだけに猟をしていました。自分が仕留めた獲物を捌いて食べるという生活が気に入っていたんです。その延長で鳥獣対策に協力することになってから、猟に対する考え方も変わっていったように思います」
妙高市の鳥獣対策は、市と鳥獣対策専門員と地元猟友会などが協力して行っています。社会人1年目の冬、福島さんは冬期の専門員として山に入り、実際に畑を荒らす『加害個体』と呼ばれる猪などの動物を捕獲・駆除したり、近隣地域への注意喚起や指導を行っていました。

この日は人家近くまで猪が近づいてきていた
「妙高市でお世話になっている方と一緒に、その人がサツマイモを育てている畑に行ったことがあったのですが、その時にイノシシ被害の現場に出くわしたんです。趣味で大事に育てていたサツマイモ畑でした。もうすぐ収穫というところで、イノシシに荒らされていたんです」
動物は一度、餌がある場所を覚えてしまうと何度も畑を荒らすようになります。一頭のイノシシがいれば、個人で育てているような広さの畑は一晩で掘り出され、群れであれば農家にとって生活に関わる深刻な被害に繋がります。

足跡を辿って山道を進む
「その人が『もうすぐ収穫する』と話していた直後に畑が荒らされていることに気づきました。『まぁ、仕方ないよねぇ』とは言っていたのですが、本当に悲しそうでした。そのときに、自分がなんとかしてあげたいという気持ちが強くなったんです」
猟師でもある自分なら、もっと出来ることがあったのではないだろうか。その出来事は、福島さんが鳥獣対策のスペシャリストを目指すきっかけとなりました。

猟師としての責任の象徴を手に
鳥獣対策の専門員として山と暮らしを守る
社会人2年目の春、妙高市の通年の鳥獣対策専門員として働くことが決まり、目標への一歩を踏み出しました。福島さんは、『加害個体予備軍』の調査と防除、実際に加害を行った『加害個体』の捕獲・駆除などを中心に、獣害対策の指導や注意喚起などを業務として行っています。

GPS等を活用して加害個体を追う
「同じ猟師という立場でも、趣味の猟で山に入るのと、仕事の猟で山に入るのとでは心持ちが大きく変わりました。仕事の時は『自分が取り逃がしてしまったら、その個体が誰かに被害を及ぼしてしまうかもしれない』と考えると、趣味の時とは違い、必ず駆除しなければならないという使命感が強くなります」
危険も伴う駆除・防除の仕事。福島さんは趣味であれば見逃すことやそもそも無理をしないこともありますが、仕事として山に入るときはいつも以上に緊張感を持って、見つけたら必ず仕留めるという気概で業務に取り組んでいます。

「猟をしていれば『この一発を外したら攻撃される』という緊迫した場面には何回か遭遇します。幸いにも、まだ怪我をしていませんが目の前の数メートルのところまで迫ったイノシシを撃つこともありました」
狩猟免許を持ち、銃を扱える人材というのはそう多くはありません。銃の管理にかかる時間とコストはかかり、心ない偏見にさらされることもあります。それでも信念を持って仕事に取り組むことができているのは、妙高市に住む人たちの人柄だといいます。

「私ほど若い猟師はおらず、移住者ということもあって、とても気にかけてもらってます。罠の設置場所には近づかないように周知と指導をするのですが、近隣住民の方々が自主的に周知に協力してくれるのです。本当に助かっています。夏の間は山の中で長時間、泥だらけになって作業をすることもあるのですが、差し入れをしてもらったり、声をかけていただけたり、人のあたたかさを感じますね」
単身であっても心細さは感じないという福島さん。鳥獣被害に対する理解を広げるために妙高市内を駆け回っています。
「鳥獣被害は畑を荒らされてしまうことだけではありません。イノシシが木の根を掘り起こすことで地盤が緩み、土砂災害の原因になります。イノシシが増え、環境収容量(キャパシティ)を越えれば、国立公園妙高の鳥に指定されているライチョウの住処が侵される可能性もあるのです」

山奥へと続く足跡と妙高市街

雪解けには山の根などが掘られ、土砂崩れの原因に
人口減少によって、山と街の緩衝地となっていた集落が消滅することで、猿や熊といった動物が山から人里へと降り、人への危害を加えることにもなるでしょう。暮らしの安心安全が脅かされる危険性もはらんでいるのです。
「動物たちも自分たちの住処である山で暮らしています。狩猟は動物愛護の観点から批判されることもありますが共存していかなければなりません。妙高市で暮らす安心を守るために人と山の境界をつくることが私たちの仕事でもあります」

動物が争った形跡を見つける
日々フィールドワーク、移住も同じ
近年では社会的な必要性が増し、狩猟に対する捉え方も変わり始めています。しかし、狩猟を取り巻く環境は決して楽なものではありません。その中でも、福島さんは真摯に信念を持って『自分に出来ること』を粛々と行っています。
「狩猟に対して鉛玉による環境汚染が懸念され規制がはいったり、コスト面やイメージによって若手猟師の数は減ってきています。その一方で獣害の原因となる個体は増えており、厳しい状況が続いています。その中で、社会的な意義だけではなく、やり甲斐や楽しさについても伝えていけたらと思っています」

同じ状況はない山での狩猟
そんな活動が認められ、福島さんは新潟県で実施されている『令和3年度農繁期イノシシ捕獲者表彰』において最高賞である『新潟県鳥獣被害対策支援センター所長賞※』を受賞しました。
※捕獲したイノシシの大きさや頭数、安全性、射撃の成功率、畑からの距離など獣害被害に対して効果的な狩猟を行っているか総合的に採点・評価し、最も優れた有害鳥獣捕獲の従事者に対して贈られる賞。

市役所庁舎にて
「やはり賞をいただけたのは嬉しかったですね。一つとして同じ状況はない猟の中で日々、フィールドワークを重ね、加害個体が発生する場所の把握や罠の設置場所の精度を上げていく。それによって今まで見えてなかったものや新しい学びが得られること、そして人の繋がりが広がっていくことが仕事のやり甲斐に繋がっています」
妙高市の安全・安心を守る使命を背負う福島さん。これから妙高市へ移住を考えている人に対してもフィールドワークが大事だと話します。
「妙高の冬は寒いですが、人はあたたかいです。四季がはっきりしていて、どの季節でも楽しさがあります。自分自身の足でフィールドワークをすることで、地域の良さを知れたり、人間関係を広げたり出来ると思うので、ぜひお越しください」
福島さんは現在、街中に降りてきた動物を捕獲するための麻酔銃の資格取得のため研修を行っているとのこと。鳥獣対策のスペシャリストへの道を一歩ずつ進みながら、充実した妙高暮らしをしています。あなたにもきっと、必要とされる場所があるはず。それを見つけるために妙高での暮らし方、働き方を考えてみませんか。

文/大塚眞
写真/ほんまさゆり