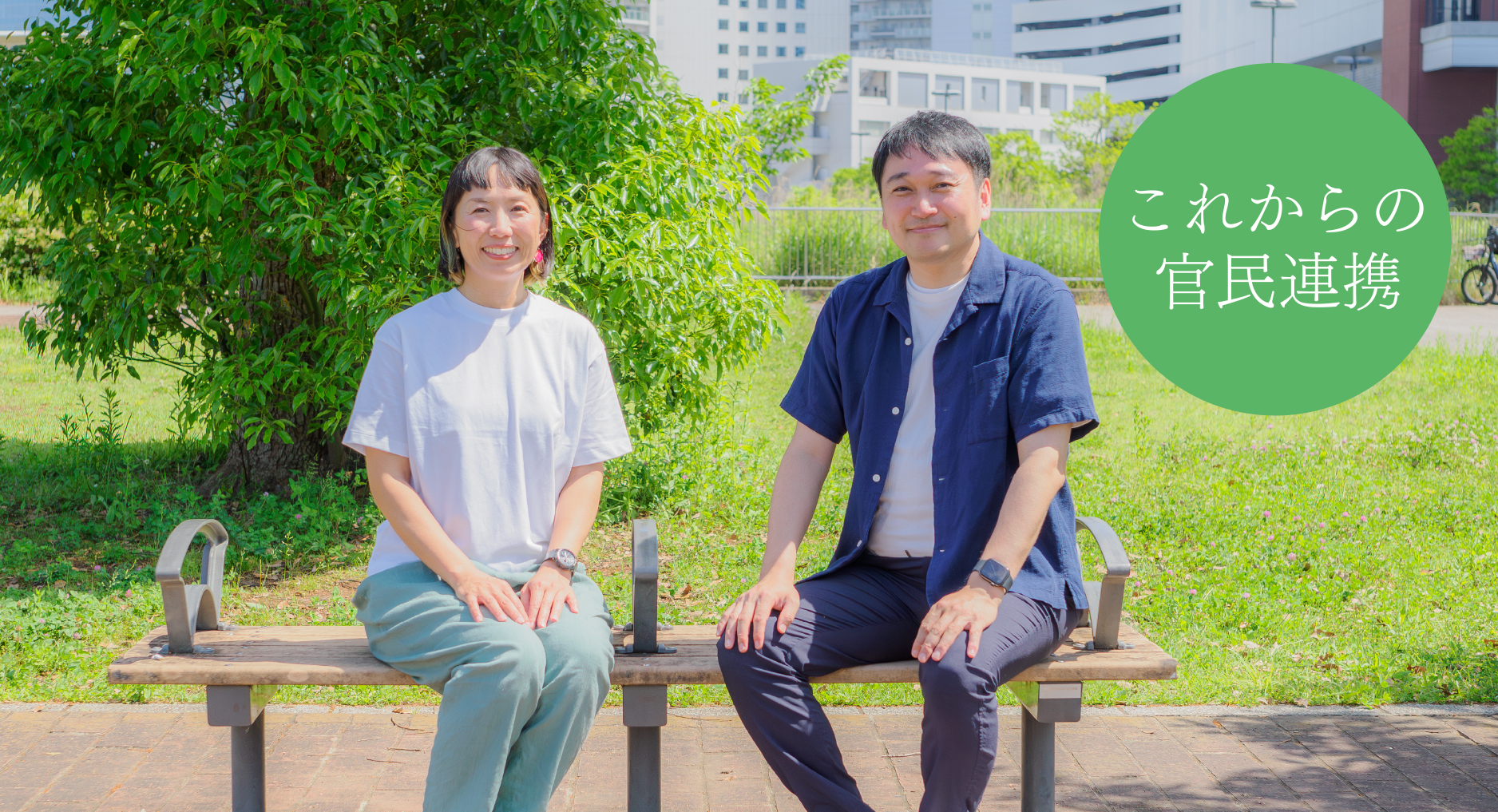ものを売るだけじゃない。
周辺のアクティビティも一緒に楽しめる総合的な施設として人気のユニークな道の駅が愛知にある。
副駅長の吉開仁紀さんに話を聞くうち、人がまちを好きになる理由が見えてきた。

開駅直後から大反響
成功の秘訣は何か?
「道の駅」と聞いて何を思い浮かべるだろうか。ツーリングやドライブの休憩所? 産直の野菜が売っているところ? どちらも正しいが、これだけでは、道の駅について半分しか知らないに等しい。本稿では、愛知県豊橋市にある「道の駅とよはし」の例を参照しながら、残りの半分について見ていく。
道の駅とよはしは、二〇一九年五月に開駅した比較的新しい道の駅だ。元々あった産直施設「あぐりパーク食彩村」の隣に、地元のこだわりの食材を使った飲食店や特産物を扱うショップなどが入居する「Tomate(トマッテ)」が新設され、道の駅とよはしとして開駅した。愛知県内で最大の規模であり、豊橋市内外から年間二百万人が訪れる。売り上げは約十六億円で、これは全国の道の駅のなかでもトップレベルの数字だ。すでに人気スポットになっている。なぜだろうか?
多くの道の駅と同じように、道の駅とよはしでも地元のおいしい農産物を幅広く取り揃えている。そのまま買うこともできるし、それらを使ったグルメを楽しむこともできる。オリジナル商品も開発しており、なかでもクラフトビールは品評会で金賞や銀賞を受賞するなど高い評価を受けている。さらには地元の特産品を購入することもできるし、単に憩いの場として楽しむこともできるし、あるいは多目的スペースで料理教室やセミナーを受講することもできるし、マルシェを開くこともできる。
ユニークなのは、周辺のアクティビティを楽しむことができること。近くの海ではサーフィンやサップ、パラグライダーのほか、ウミガメの産卵を観察することもでき、海までの道中はネクストクルーザーでドライブすることができる。また、畑ではさつまいもの収穫体験ができるし、この夏からはとうもろこし、秋からはうずらいもの収穫体験も始める。道の駅とよはしは、そうしたアクティビティの窓口になっている。ここに行けばいろんなことができる、そんな場所だ。

幅広い世代に愛される
みんなの場所になるために
この施設の特色は、売りをひとつに限定していないこと。ウェブサイトにはこんな言葉がある。「ぜんぶ名産」。多くの道の駅が産直モデル一辺倒に傾くのに対し、道の駅とよはしでは、ここで楽しむことのできるあらゆるモノやコトを名産とし、さまざまな客層に応えられるよう平等に提供している。
開駅から副駅長をつとめる吉開仁紀さんは、道の駅の存在を「地域のインフラ的な存在であり、たくさんのお客さんを呼べる場所」だと語る。
「でも、若い人に話を聞くと、道の駅に対して『高齢者が利用する場所』というイメージを抱いている人が多いんです。もちろん、高齢者のみなさんの場所でもあるけれど、もっと多くの人たち、たとえば子育て層の人たちや若者たちからも愛される存在にならないといけない。みんなが使いやすい、行きやすい場所にしなければいけない、そういう思いが前提にあるし、それに応えられるだけの可能性が道の駅にはあると思っています」
だから、さまざまなアクティビティー体験の窓口になり、多種多様なイベントを開催するわけだ。
売り場の小さなデザインや見せ方のひとつひとつ、ロゴやBGMにもこだわる。若者が「ダサい」と感じる施設にはできないからだ。実際に足を運んでみると、アウトレットモールにいるかのような快適さと洗練を感じさせられる。道の駅としてはかなり先進的だと言えるだろう。
しかし吉開さんは「特別なことはやっていない」と謙遜する。「他の業界や施設なら当たり前にやっていることをやっているだけなんです。しいて言えば、スタッフや地域の人の声を積極的に取り入れてはいますね。誰かが教えてくれたり提案してくれたりするから、じゃあやってみようと。その繰り返しです。マルシェも、商品開発も、サーフィンなどのアクティビティもそうでした」
そうして周囲の声を取り入れて、レゲエイベントを開催したこともあったという。
「そしたら、クレームが来ましたね。品が悪いって(笑)。まあ、レゲエをまったく知らない人からしたらそう見えるのかもしれない。でも主催者はちゃんとルールを守っていたし、誰にも迷惑をかけていません。だから僕らは、そういうクレームには負けません」
このエピソードは、スタッフやユーザーに自由な意見を求めながらも、最終的な責任は道の駅が負っていることを示す好例だろう。道の駅がケツを持ってくれるという安心感があるからこそ、人々は積極的にアイデアを出すことができる。

メディアとなり自ら発信することで
得られるふたつの効果
もうひとつ重要な特徴は、メディアとしての機能を果たしていること。
先にも触れたように、豊橋は農業が盛んな地域。市町村ごとの農業産出額を見ると、一九六七年から二〇〇四年まで、実に約四十年ものあいだ全国第一位の座についていたのは豊橋市なのだ。政府主導の市町村合併推進運動によってトップの座を譲り渡したものの、現在でも全国上位を維持し続けている。盛んどころか、日本有数の農業地域と言っても過言ではないわけだ。しかし、どれくらいの人がこの事実を知っているだろうか? 豊橋に特別な縁がない限り、ほとんどの人が知らないのではないか。これが問題だと吉開さんは考えている。
「なぜ問題かというと、次世代の担い手になる若い人たちが農業をやろうと思わなくなるんです。だから、今メインで働いている農家さんの下の世代やその下の世代の人にちゃんと農業をやってもらえる環境を、この道の駅でつくっていきたいんです」
こうした理由から、道の駅とよはしでは、洗練されたウェブサイトを構築し、SNSでの発信を強化。インスタグラムのフォロワーは七千人を超えており、これは道の駅としては異例の数字だ。さらには年に二回、タブロイド版「道の駅とよはし通信」を発行。一号につき一万部以上印刷し、道の駅や市役所などに配布している。地元のライターやカメラマン、デザイナーらと組んで編集された誌面はおしゃれで読み応えがある。
道の駅とよはしとはどんなところで、何を伝えたいのか。豊橋とはどんなところなのか。そうしたことを積極的に発信し、それを受け取った外部の人が興味を持って足を運ぶ、そんなサイクルが生まれている。
メディアになる効果はもうひとつある。それは、地域の人たちが地元を再発見する助けになるということだ。
本誌を読むような人ならば、まわりにひとりくらい、「うちの地元には何もない」と言う人がいないだろうか。もしかしたらその人は、自分の地元に何があり、そこで何が起きているのか知らないだけなのかもしれない。それも無理もない。だって、発信しなければ知られることもないのだから。しかし、地元にある魅力的なメディアが地元の魅力を深堀りして発信してくれれば、人々は自分のまちを客観的に見ることができる。そこで初めて知ることができる。それがきっかけで地元をもっと知ろうと思ったり、好きになるかもしれない。
「お客さんがたくさん来ることはひとつのKPIではあるけれど、それ以上に、ここに住んでいる人たちが、豊橋っていいよね、と思うようになることが大事だと思うんです。だから豊橋の人には、うちの地元には何もないとか言わないでほしい。豊橋はいいところです。でもそれはちゃんと伝えないとわからないから、伝えられるように空気をつくっていきたいんです」

誰かの「やりたい」を
応援できる場所にしたい
道の駅とよはしが開駅して二年。業績が順調に伸びていくにつれて、吉開さん自身もこの施設の広告塔となって奔走し、ちょっとした有名人になりつつある。なぜそれほど豊橋に情熱を注げるのだろうか。もちろん、このまちが好きだからだ。吉開さんによれば、人がそのまちを好きになるかどうかは、その一員になれた実感があるかどうかで決まるという。
「僕は幼少期から高校まで、豊橋ではなく岡崎で過ごしました。岡崎も大好きだけれど、あの頃は、住んでいるというより住まわされている感覚の方が強かった。でも豊橋は僕にとって、自分の意志で選んで住んだまちです。自分の意志でいろんなことを選んで、人生をつくってきたんです」
なるほど非常にシンプルな理由だが、案外、この言葉には重要なヒントが隠されているかもしれない。というのも、吉開さんにとって豊橋が「自分の意志で選ぶ」ことのできる環境だったことを示唆しているからだ。「レゲエのイベントをやりたいと言われたら、やってみなよと言えなければいけない。それが言えないまちであれば、好きにはなってもらえない。実際にやってみたら失敗するかもしれないけれど、それでもいいんです。こんな人が来てくれたとか、こんな知り合いができたとか、そういうことが積み重なって、その結果、このまちに住んでよかったとか、このまちはいろんなことをやらせてくれるんだなと思うようになる。そうやって人はまちを好きになる。これって、きれいごとではないと思うんです」
逆に言えば、やりたいと思っても言えない、言ってもやらせてもらえない、そんな環境であれば、人はまちを好きにならないだろう。自分がまちから切断されたと感じた経験が、「うちの地元には何もない」と思わせるのだ。そのまちにはその人が求めるものがないという意味においては、「うちの地元には何もない」にも半分は真実があるわけだ。
「そういうつまらん社会にしてはいけないと思うんです。少なくともこの道の駅は、誰かが何かをやりたいと思ったら、それを応援できる場所にしたい」
そう語る吉開さんの思いは、少なくない人々の心に届いているはずだ。
取材・文…山田 宗太朗 写真…福村 暁