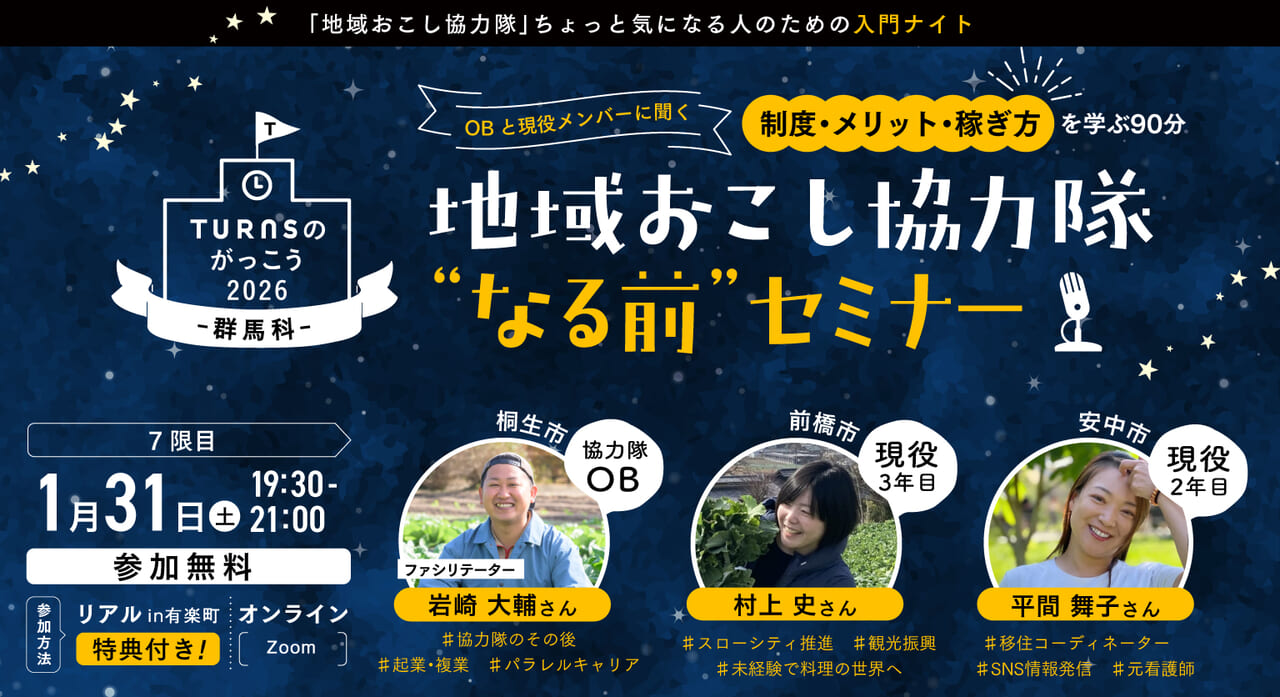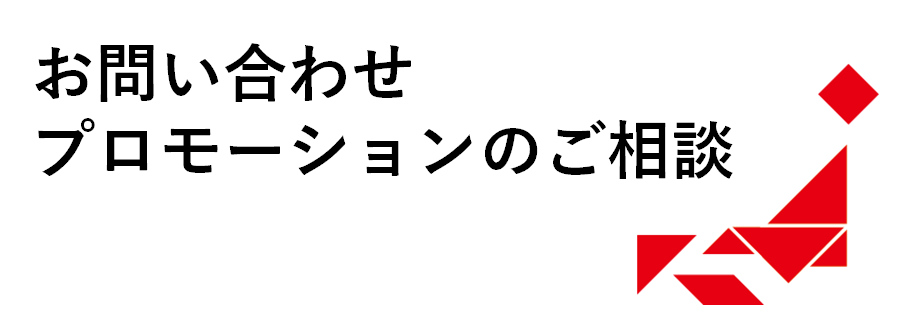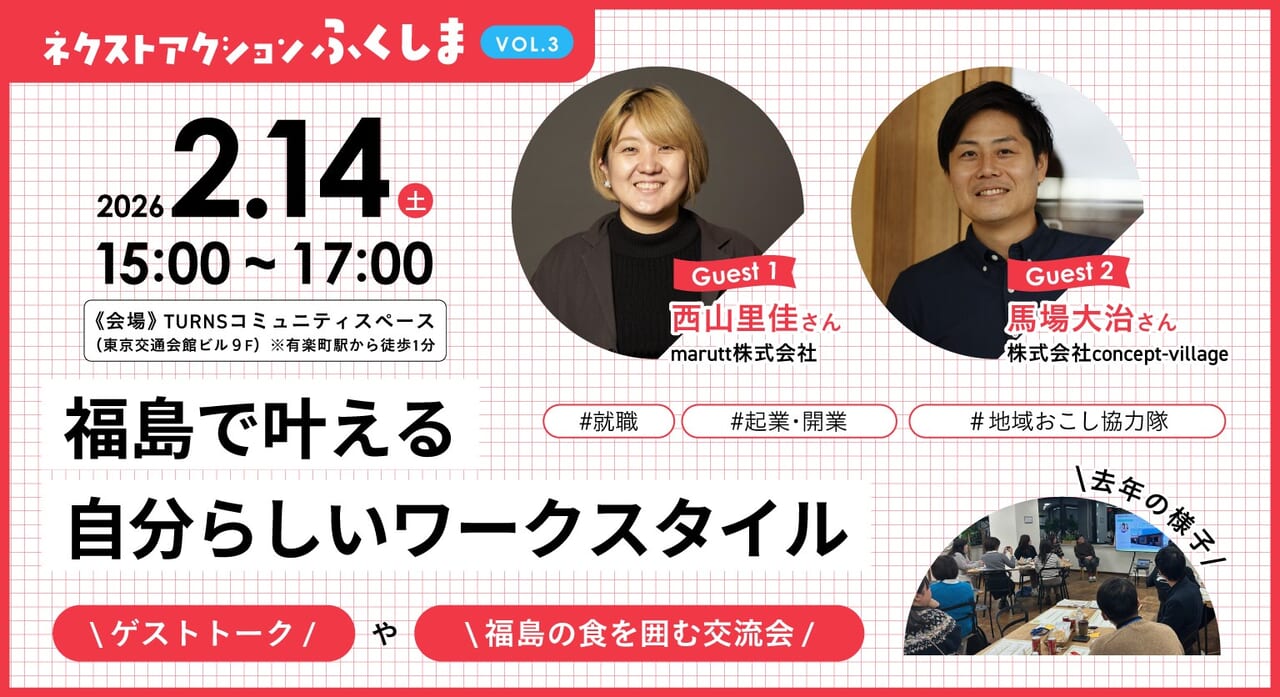福島県の広野町は、「東北に春を告げるまち」とも呼ばれる冬でも温暖な気候と、海と山に囲まれた自然が魅力のまち。サッカーの聖地「Jヴィレッジスタジアム」があるほか、こども園から高校までをひとつのエリアに集約し、地域一帯で教育に力を入れています。
そんな広野町を訪れる移住体験ツアーが、3/15・16に開催され、8組の親子が参加しました。子育て世代におすすめのスポットや先進的な教育で知られる「福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校」を見学したり、先輩移住者と交流したり。また、実際に町内を歩き、町で暮らすイメージが持てるようなフットパス体験も行われました。コンパクトで利便性の高い広野町の魅力がつまったツアーの模様をレポートします。

ツアー1日目
バナナを育てる温暖な町
午前11時。東京駅から約2時間半の電車旅を経て、参加者を乗せた特急ひたちが広野駅に到着。さっそくバスに乗り込み、ツアーの開始です。
まず向かったのは「二ツ沼総合公園」。広大な敷地の中に遊具やパークゴルフのコースがあり、休日に家族で過ごすにはもってこいの場所。公園に併設されている「トロピカルフルーツミュージアム」では、広野町の温暖な気候を生かしさまざまなフルーツが栽培されています。なかでも注目がバナナ。震災で傷ついた町を盛り上げたいと栽培がはじまったそうで、収穫したバナナは「綺麗(正式名称は「朝陽に輝く水平線がとても綺麗なみかんの丘のある町のバナナ」)と名付けられ販売されています。

バナナが栽培されている温室の中は、まるでジャングル。子どもたちは大きな葉っぱをかきわけながら、「迷路みたい!」と大はしゃぎ。大人たちも茎に成ったバナナの房を興味津々に眺めていました。

バナナ園を見学後は公園内のレストランに移動し、ランチタイム。「綺麗」から作ったバナナパウダー入りのカツカレーとバナナシェイクを味わいました。
全国屈指の先進的な学校が立地する「教育の丘」
続いて向かったのは「教育の丘」。広野町では「地域が人を育み、人が地域をつくる」という理念のもとさまざまな教育施策に取り組んでおり、そのひとつが半径1㎞以内のエリアに町立のこども園、小学校、中学校、県立の中高一貫校を配した「教育の丘」の整備でした。
教育施設を一ヶ所に集約したことで多世代の交流が活発になったほか、保護者の送迎の負担も軽減されるなどのメリットもあるそう。その中心となっているのが、「福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校」で、参加者の中には「この学校が気になって来ました」と話す人もいるほど、全国的に注目度の高い学校です。地域に開放された学校であるために門を設けていないのも特徴で、校内にはカフェもあり誰でも自由に立ち入ることができます。

「本校は原発事故で休校となった双葉郡内の5つの高校の伝統や想いを継承すべく設立されました。「変革者たれ」を理念に掲げ、主体性、協働性、 創造性をもった人材の育成を目指しています。たとえば、「未来創造学(中学)」、「未来創造探究(高校)」という総合的な学習の時間では、子供たちが実際に地域に出かけて課題を見つけ、地域の方々に協力してもらいながら解決方法を考える等の実践的な学びも行います。
上を目指すための勉強だけでなく、それぞれがやりたいことに全力で向き合える環境づくりを大切にしています」


そう語るのは、案内してくださった「福島県立ふたば未来学園高等学校」の佐藤教頭。先進的な教育の取り組みはほかにもあり、毎年著名人を招いて子供たちとディスカッションを行う「リーダー学」や、海外研修も行うグローバルスタディ、近年話題の哲学対話や演劇教育もいち早く授業に取り入れているそう。参加者は充実した教育環境についての話に、熱心に聞き入っていました。
その後は佐藤教頭の案内で、学校内をめぐります。
開校して10年とまだ新しい校舎はとてもきれい。食品加工が行える実習室や、3Dプリンタの設置された教室、本格的な音響や照明を備えたシアターなど、充実した設備を見るたび驚きの声があがります。



途中、立ち寄ったバドミントン部の専用コートでは部活の真っ最中。さすがは全国大会常連の強豪校、気合の入った練習風景は大人だけでなく子どもたちの目も釘付けにしていました。
地元のリアルを知るフットパス&交流会
学校見学を終えた参加者は、広野町公民館へ移動。待ち受けていた町民の青木裕介さん、村上千種さん、石田祥子さんを案内人に、町内を歩いてめぐるフットパスへ出発です。

「この道は桜が咲くといいお花見スポットになるんですよ」「このお肉屋さんのコロッケが絶品なんです!」と、住民目線で町の情報を教えてくれる3人の話を聞きながら、散策を楽しんだ参加者たち。実際に歩いてめぐると、行政機関やスーパー、駅などが町の中心に集まっているコンパクトタウンぶりも実感できた様子。
30分ほどゆっくり歩いて、次なる目的地の「多世代交流スペースぷらっとあっと」に到着です。
「多世代交流スペースぷらっとあっと」は、青木さんが運営する多世代交流スペース。休憩やコワーキングスペースとしてはもちろん、時にはイベント会場にもなる広野町の拠点のひとつです。高校生が電車の待ち時間に利用したり、子どもたち向けのプログラミングや教室も行われているそう。
ここではフットパスに参加した3人に、移住者の池谷昭男さん、広野暮らし相談窓口「りんくひろの」相談員の大森博隆さんを交えて交流会が行われました。

交流会は「親子で遊びに行くなら」「買い物はどこでする?」「働き口は?」など、移住する前に知っておきたいポイントについて、それぞれが答えるかたちで進行。住民は車で20分程度のいわき市や楢葉町にある大きなスーパーで買い物している人が多いこと、休日のお出かけ先は「二ツ沼総合公園」はもちろん、茨城県や宮城県まで足を伸ばすこともあることなどが語られました。
大森さん「小さな町なので町内で生活のすべてを完結するのは難しい。いわき市を含め広いエリアを生活圏として考えていただければ」
また、移住者の石田さん、池谷さんに対しては「移住して良かった点は?」といった質問も。

石田さん「住民の方が気さくで、コミュニケーションしやすいところです。いつも人のあたたかさに癒されています」
池谷さん「環境が良く、ストレスを感じることがなくなりました。夏もそれほど暑くないので暮らしやすいです」
「広野町はどんな人におすすめ?」という質問には、地元出身のふたりが答えます。

村上さん「何もないように見えて、実は見どころがたくさん。不便の中にも楽しみができると思うので、どうか皆さんも楽しんでみて」
青木さん「自分のペースで暮らせるので、子どもたちものびのびしています。普段の生活でモヤッとしてる人、心豊かになりたい人にはおすすめの場所です」
一通り話を聞いたツアー参加者からは、「子どもたちの習い事はどうしてる?」「子どもたちの放課後の過ごし方は?」など、子育て世代ならではの質問が飛び出し、移住に向けて真剣に検討している姿が伝わってきました。
住民を囲んで和気あいあいと懇親会

実際に町を訪れ、さまざまな施設をめぐり、町民の方の話を聞いてと、やや駆け足で進んだツアー1日目。しかしその分、広野町への理解も深まった様子。参加者からは「充実した1日でした」「メリットとデメリットの両方が見えて検討しやすくなった」といった感想が聞かれました。
この日の最後は「お昼ごはん柏屋」で、交流会に登場したメンバーと懇親会。広野町の食材を使った料理や、地元産のみかんで作った「みかんサイダー」を楽しみながら、町に関する話題に花が咲き、賑やかな時間を過ごしました。
ツアー2日目
役場やJヴィレッジなど町のランドマークを見学
翌日は朝からあいにくの雨模様で、予定していた日の出鑑賞はできず。
ツアーに同行している広野町復興企画課の横田侑哉さんからは「その代わりと言ってはなんですが」と、現在テレビ東京系で放映中の福島沿岸地域を舞台にしたドラマ「風のふく島」で広野町の美しい海や朝日の映像が見られることを教えていただきました。

2日目の最初の目的地は広野町役場。実はこちらには町内で出土したという化石の同種「チンタオサウルス」の化石の骨格標本が展示されています。全長約7メートルの迫力ある姿を前に、太古の広野町に思いを馳せる参加者たち。ガイドブックには乗らない町の魅力を知ることができるのもツアーの醍醐味かもしれません。

その後は、お隣の楢葉町へ移動し、「道の駅ならは」でしばしの自由時間。
地場野菜のコーナーの安さに驚く人、おみやげ選びに夢中な人と、思い思いに買い物を楽しんだ後は、サッカーの聖地「Jヴィレッジ」へ。この日はちょうどU-18日本代表やU-17日本高校選抜ら、国内最高峰のU18プレミアリーグ2025に所属する7チームが参加して行われる「第7回J-VILLAGE CUP U-18」が開催中。今まさに試合が行われているピッチに後髪をひかれつつ、施設内を見学します。

Jヴィレッジは日本初のサッカーナショナルトレーニングセンターとして1997年にオープン。震災後は福島第一原子力発電所の廃炉作業の拠点となっていましたが、2019年4月に全面営業を再開。スポーツ施設としてだけでなく、ホテルやレストラン、フィットネスジムもあり一般の方にも気軽に使用できます。


施設内にはプールやジムやヨガスタジオなどがあり、さまざまな運動に対応。水泳教室やサッカー教室も行われており、広野町の利用者も多いそう。また併設の「JFAメディカルセンター」は整形外科やリハビリ専門のクリニックで、一般利用が可能です。これほど本格的なスポーツ施設があるなら、親子で体を動かす機会も増えそうです。
移住にまつわる疑問や不安を洗い出し
町内視察を終え、最後の目的地「広野町文化交流施設 ひろの未来館」へ向かいます。
「ひろの未来館」は、歴史文化の継承と世代や地域を越えて相互交流が生まれる拠点としてオープンした施設。
文化財の展示が常設でなされているほか、キッズスペースやセミナールームもあり住民がさまざまな活動で使うことができます。ここでは先輩移住者を招き、参加者に近い目線で広野町への移住にまつわるあれこれを直接聞いていきます。

宮城県石巻市出身の都築ほのかさんは、子ども2人を育てるシングルマザー。
「教育の丘」の利便性の高さ、大森さんらが移住へ向けて親身に話を聞いてくれたことで広野町を気に入り、2年前に移住してきました。

都築さん「移住して子どもとの時間が増えました。休日はふらっと海に遊びに行ったり、のんびり過ごせるのが広野町の魅力。ご近所さんもとても良くしてくれて、毎日楽しく過ごせています」
また、昨日に引き続いて登場の池谷昭男さんは、町内で「騎西のパイラ整体院」を営む整体師。実は昨年の同じ時期に開催された移住ツアーの参加者でした。

池谷さん「もともと東北沿岸の被災地に思い入れがあり、いつかは移住したいと思っていました。ツアーで広野町を訪れ、実際に住民の方の話を聞く中で魅力を感じて移住しました。虫が多いなどの困った点はありますが(笑)、自然豊かな環境が気に入っています」
参加者からの質問タイムでは、都築さんには子育て支援制度や、子育て世代同士の交流の有無など、池谷さんには移住者の新規開業や集客にまつわる質問が相次ぎました。見知らぬ土地で起業するのは困難にも思われますが、広野町は開業支援制度体制が整っているのもメリットだそう。
都市部と違い、小さな町に新しいお店ができると必ず注目されるばかりか、移住者の起業には地元メディアの注目が集まりやすいのも地方ならでは。これまで起業を考えたことのなかったという参加者のひとりは「目からウロコでした」と新たな可能性を考えるきっかけになったようです。

移住者が開業した「惣菜弁当 KIYA 広野町」のお昼ごはんをはさんで、午後からは広野町を含む福島県沿岸地域への移住促進を行う「ふくしま12市町村移住支援センター」の担当者による移住支援制度の説明や、町内にある住宅造成に関して一条工務店からの耐震住宅の取り組みの紹介があり、お金や住まいなどにも言及した内容の濃いセミナーに。
それぞれが移住に向けた課題を整理し、より具体的に考えるためのヒントを得ることができました。
ツアーを終え、“ひろの暮らし”がより身近に
ここで2日間にわたってたっぷり広野町を満喫したツアーは終了。
最後に参加者の方に感想をお聞きしました。
中島さんご家族

「町の機能が集約されていて、コンパクトなところが移住者にも優しい町だなと感じました。また、子どもを大事にしてくれる環境が整い、支援制度もしっかりしていて、子育てしやすい雰囲気を感じました」
中村さんご家族

「出会った町の皆さんが優しくて、ここでなら楽しく暮らせそうだなと感じることができました。「福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校」の設備や教育方針が素晴らしく子どもも興味を持っていたので、いろいろと相談しながら次の動きを考えていきたいと思います」
中村さんご家族

「実際に来る前と後では町に対するイメージが変わり、より関心を持てるようになりました。こういった機会はとても大事ですね。メリットが感じられた反面、不便に感じる部分もあったのでそれにどう対処したら心地よく暮らせるのか、自分でもじっくり考えてみます」
ツアーを終えた参加者の方の晴れ晴れとした表情からは、理想の移住に向けてビジョンが明確になったような充実感も見えました。最後に大森さんが伝えたのは、「一度だけでなく、ぜひ何度も訪れて決めてほしい」という言葉。繰り返し来てみることで町の解像度が高まるだけでなく、“縁”も深まっていくのかもしれません。今回のツアーが、移住に向けた大きな一歩となることを願っています。
文・渡部あきこ 写真・渡部聡
\広野町の詳しい記事はこちら/
広野町ってどんなどころ?気候や立地、生活環境など5つのポイントでご紹介!
https://www.arukunet.jp/213966/
広野町に住んで、実際どう?移住した2組の方にインタビュー!