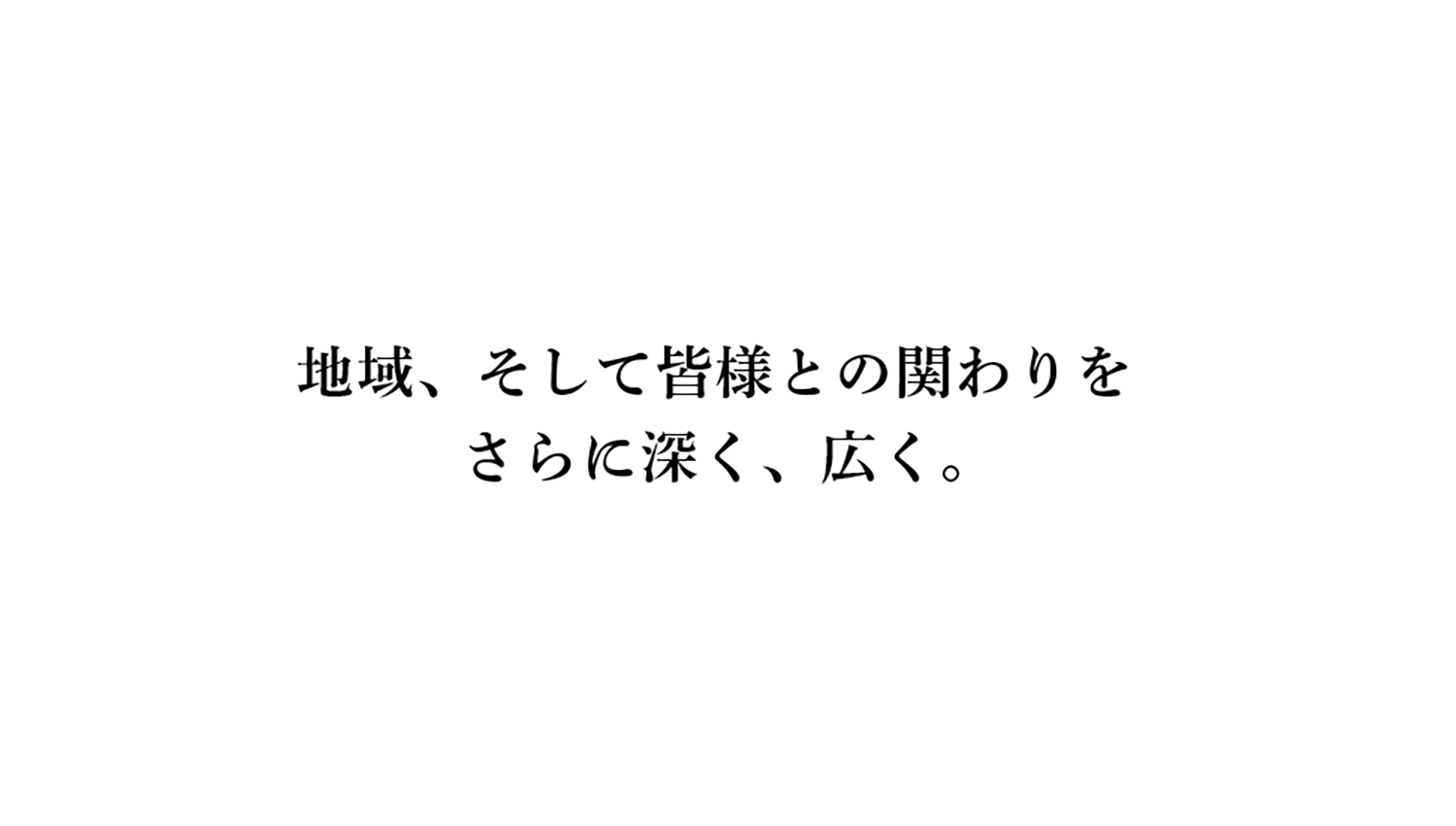日本人にとって「祭り」ってなんだろう?
各地で行われる祭りは大小合わせて何十万ともいわれている。地域が一体となって、歌い、踊り、楽しみ、そして祈る。
そして最近は音楽フェスなど趣味嗜好から人々が集う祭りも増えてきた。地方にある「祭り」に注目して、地域で生きること、地域とひとのつながりかたを紐解きたい。
さあ、お囃子が聞こえてきたらまちに飛び出そう移住したなら踊らにゃ損!
文・編集:アサイアサミ 写真:TAKAMURADAISUKE
まちには祭りが必要だ!|特集1
祭りの美学1【北海道札幌市】さっぽろ八月祭
作る人 大友良英さんと札幌駅前通まちづくり株式会社のみなさん

バットしいたときに
世界が変わる

「盆踊りは踊ってる人が主役。誰もステージなんて見てない」
そう苦笑する大友良英さんは、バンドを率いる祭りの中心人物の1人。ノイズミュージシャンであり、ドラマの伴奏音楽をつくるなど幅広く活躍しながら、最近では音頭を多数手がけ、また祭りのディレクターもつとめる。自称「祭りが何なのか日本で1番考えているギタリスト」なのである。

「日本の庶民の祭りって、伝統といわれるものでも、実はいろいろな理由で一旦途切れてつくり直したものが多いんです。それはコミュニティの再生と関係があって。戦後の復興期をはじめ、震災後にすごい勢いで東北の祭りの復興が望まれたのも、祭りをフックにコミュニティの危機を乗りこえたいという願いから。だから祭りの成り立ちを見れば、そのまちのコミュニティの成り立ちも見えてきます」
大友さんが祭りを意識するようになったのは、2011年8月、福島市で開催した「フェスティバルFUKUSHIMA! 」以降。東日本大震災直後にパンクロッカーの遠藤ミチロウさん、詩人の和合亮一さんとともに立ちあげた祭りだ。
「震災後の福島を訪れたとき、ここに祭りが必要だと思った。福島が自信を失っているいま、自分たちの手でなにかを生みだす経験が必要で、それには祭りだと、理屈じゃなく直感が走った」

除染か移住か、推進か反対か、
さまざまな分断に晒された福島の現実と向きあいながら毎年フェスを続け、2013年からは、土地に縛られない、誰でも参加できる盆踊りに形を変えた。
それが福島以外の都市で行われるようになり、札幌の八月祭の前身もこの盆踊りだ。札幌国際芸術祭2014の関連企画として行われた盆踊りが、翌年「さっぽろ八月祭(以下、八月祭)」として地域の新しい祭りになった。
八月祭の企画運営を行う「札幌駅前通まちづくり株式会社」の白鳥健志社長は、この新しい祭りにシンパシーを感じた1人。

「北3条広場は、全国の企業の支社があり、サラリーマンが集まるビジネス街にあって、単身赴任や転勤族が多い場所。地域を限定しない新しい盆踊りなら、この地区の新しい祭りとして育てていけるだろうと思いました」
普段は人同士の関わりが少ない都市部だが一緒に踊ることでみんなの笑顔を交換できる。祭りの主役はあくまでも市民。そして支えるプロや関係者をつなぐ調整役がまちづくり会社のスタッフだ。白鳥社長はこう語る。
「いろんな関係者に平等に接することができるのは、まちをつくる会社だからかもしれません。まちづくりは非常に多岐に渡ります。そのなかで、祭りも大風呂敷づくりもすべて我々のストライクゾーンに入ってるんです。広告代理店だったらたぶんストライクゾーンは違ってくるでしょうね」

写真:TAKAMURADAISUKE(P16 〜17 下、P20 上) 写真提供: ハレバレシャシン 文:坂口千秋 編集:來嶋路子
祭りの美学2【宮城県石巻市】花火づくりを学び、人生を楽しむ美学
東日本大震災をきっかけに、暮らしと仕事を見つめなおした人は少なくない。宮城県石巻市に移り、花火づくりや猟師に深く向き合いはじめた大島公司さんは、心のままに行動したことがまた次のなにかにつながっていくことを繰りかえすうちに、やがて海の向こう、フランスでお祭りをおこなうまでになった。人を喜ばせ、自分も楽しむ大島さんの大切にしていることとはなんだろう?

異色の花火師
この日は「知人にお孫さんが生まれたので、〝そのおめでとう花火”を打ち上げる」という。
宵闇の海岸に集まっていたのは仲間たち十数人。街灯は皆無で、お互いの顔はほとんど見えない。「キューン…、キューン…」と鹿の鳴き声が、湾の向かい側の小山に跳ねかえって響く。
「ごお、よんー、さんー、にいー、いーち!…」
漆黒の空に瞬く大輪が、みんなの顔をその間だけわずかに照らしだした。ここまでプライベートな花火はなかなか味わえない。花火は、直後の静けさを際立たせた。

「大切な人に喜んでもらえるとすごくうれしいし、そんなとき、花火を打ち上げる術を持っていてよかったなって思います」
大島さんは、演出と玉の構成を考え、現場での打ち上げまでおこなう花火師。多くの花火師は花火屋の社員として働き、消費のピークを迎える夏場を目指して年中汗を流すが、大島さんは常勤の社員ではない。個人として依頼を受け、その都度、打ち上げをおこなう。また、打ち上げ花火以外にも、原料から自分で採掘する線香花火づくりツアーや教室なども開催してきた。
身につけたかった

「炭も原料のひとつですが、これが固いと飛びだす火花が繊細になります。つくるのは面白いですよ。その気になれば庭木とか、死んだクワガタだって炭化させると花火の原料になりますしね」
いたずらっぽく笑う大島さんは2011年、震災をきっかけに石巻へやって来た。沢の瓦礫の撤去をして、集落の集会所をつくることにも精を出した。そして、被災した地元の人たちのたくましさに触れたことで、心の中にある思いが芽生えていった。
「軽々とロープワークする漁師のおっちゃんとか、自分の体を使って生きる人たちを目のあたりにして、無力さを感じたんですよね。ぼくも自分自身の手でなにかつくれる人間になりたいと思った」

そんなときに着目したのが、大島さん自身も企画した夏祭りでの打ち上げ花火。周りにいる人たちみんなを喜ばせる、手仕事による芸術に大島さんは嫉妬に近い感情を憶えたという。すぐさま花火屋に「つくらせてほしい」と直談判しに行ったときから、大島さんの花火師としての歩みが始まったのだった。
海岸では2発目の準備が整っていた。
「ごお、よんー、さんー、キューン!いーち!」
カウントダウンするかけ声に、鹿の声が重なった。夜空に美しい花が咲き、水面に吸いこまれるように落ちた花びらのカケラが、そこかしこで「ジッ……」と小さな音を立てた。

文:磯木淳寛 写真:寺島由里佳 編集:古瀬絵里
祭りの美学3【京都府京都市】バチ・ホリック
日本の楽器で世界を踊らせろ!

いまを生きる
ぼくらの音楽と
結成より以前、そのはじまりの場に関わったキーパーソンが、黒坂周吾さんだ。

「ぼくは、東京に生まれ育ったんですが、中・高と埼玉県の自由の森学園に通っていて。そこで、和太鼓の教育を受けたんです。卒業後、京都の大学に進学して出会った仲間が偶然、『和太鼓がやりたい』といったので、サークルをつくったのがはじまりです」
その「仲間」とは、ナホトカ号重油流出事故のボランティア仲間だった。
「大学から、重油回収のためのボランティアバスが出ていて、現地を往復するそのバスの中で和太鼓やろうぜって盛りあがったんです」
自主性と社会性が高く、行動力のある大学生たちが、そんないきさつで立ちあげた立命館大学の「和太鼓ドン」というサークルは、1997年から20年以上経ったいまも約50名が在籍し、活動を続ける、名物サークル。その初回の自主公演を見て入部したのが、平浩之さん。「夜な夜なクラブ通いをしていた学生だったんですけどね(笑)。公演を見て、純粋にめちゃくちゃ感動したんです。なにこれ?踊れるじゃん、オレもやりたい!って。心が震えた」
後年になってバチ・ホリックに合流する最年少の松上祐来さんは現在31歳。彼は、「鼓童」に憧れ、小学生から和太鼓を習った世代。

「それまで触れていた創作太鼓と、地域の郷土芸能を訪ねて学ぶ『和太鼓ドン』のサークル活動は、まったくの別ものだったから衝撃を受けました。いろんな地域で、祭りがつくられていく過程を間近に見るのもたのしくて。バチ・ホリックの公演に、企画段階から初めて関わったときも、はっきりと「これは祭りだ!」と確信しましたよね」
永田充さんは、茨城県水戸市出身で、高校時代からプロドラマーを志望。在学中のバンド「くるり」がメジャーデビューするなど、軽音サークルに勢いがあった立命館大学に憧れて入学。
「大学4年間は軽音サークルと和太鼓ドンをかけもちで。海外のドラマーが「日本のドラマーは、なぜ和太鼓を勉強しないんだ?」といっていたのを音楽雑誌で読んで、感化されたところもあった。実際、日本だけでなく、他の国の民族音楽にも触れる機会が多くなったことで、音楽家としての人生が豊かになりました。プリミティブな太鼓のリズムは、人種を超えて、世界の共通言語のようなところがある。その、“ホモサピエンスの高ぶり”みたいなものを表現したいと思うようになったんです」
今では、日本では珍しい、中東の打楽器「ダラブッカ」という太鼓の奏者としても知られ、プロパーカッショニストとして幅ひろく活躍する。そして、和太鼓から郷土芸能に惹かれた4人とは異なり、きっぱりと「はじめは和太鼓にまったく興味がなかった」といい切るのが、中島弘如さん。

「中学からエレキギターを手にしていたので、三味線めあての入部でした。はじめのころは、ぼくも同じように地域の祭りに参加してましたが、性格としてそもそも「お祭り騒ぎ」が苦手で、地元コミュニティにはなかなかなじめないタイプです」
全員がそろって“お祭り男”じゃないというのも、そんな中島さんが演出を手がけるというのも、意外と、まちの構造の縮図のようでリアリティがある。
「メンバーそれぞれの背景には郷土芸能や、日本文化がある。でも、ぼくらは、小学校の音楽教育からはじまり、幼いころからあたり前に洋楽器になじんで生きてきた世代。だから、むかしの日本をなぞるのではなく、いまのぼくたちにしかできないハイブリッドなものを創造していきたい。数ある和太鼓団体のどれでもない、海外のロックバンドでもない、日本でしか生まれ得ないロックをやろうよって。そう思うんです」(中島さん)
伝統音楽も、かつて「いつかの新作」だった。できることなら、次のシーンの「はじまり」になりたいのだ。
文・編集:高橋マキ 写真:石川奈都子
※各記事全文は、本誌(vol.31 2018年10月号)に掲載