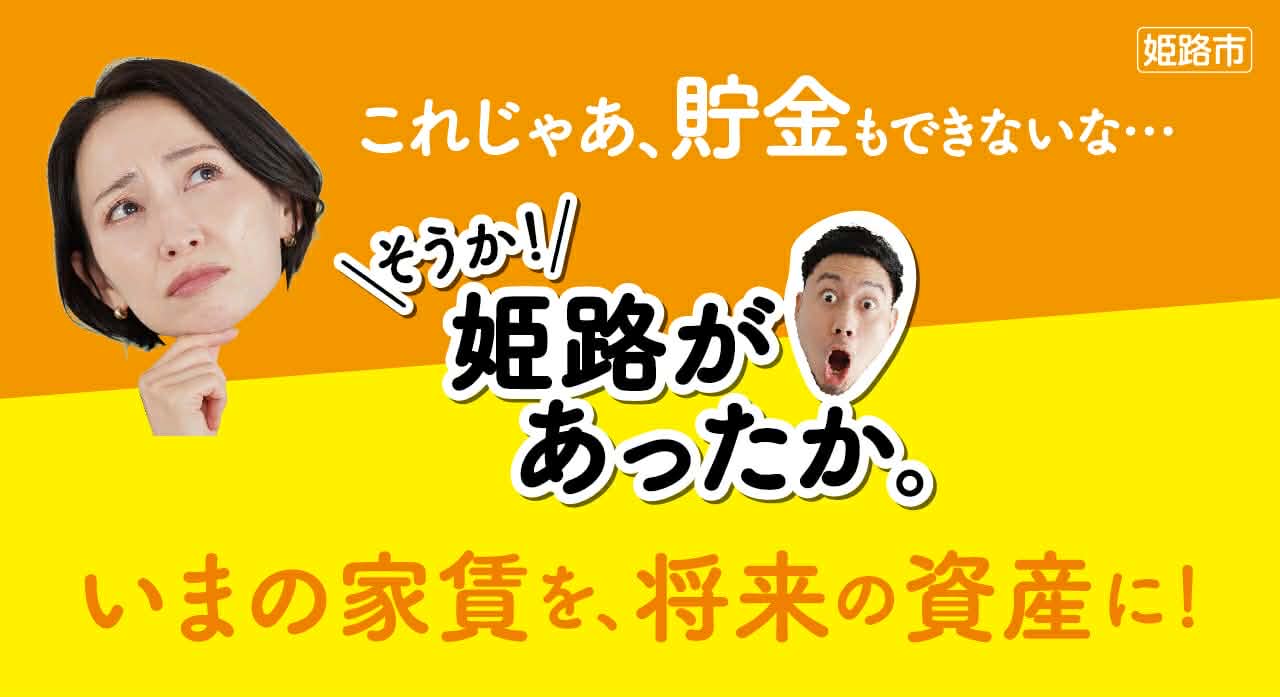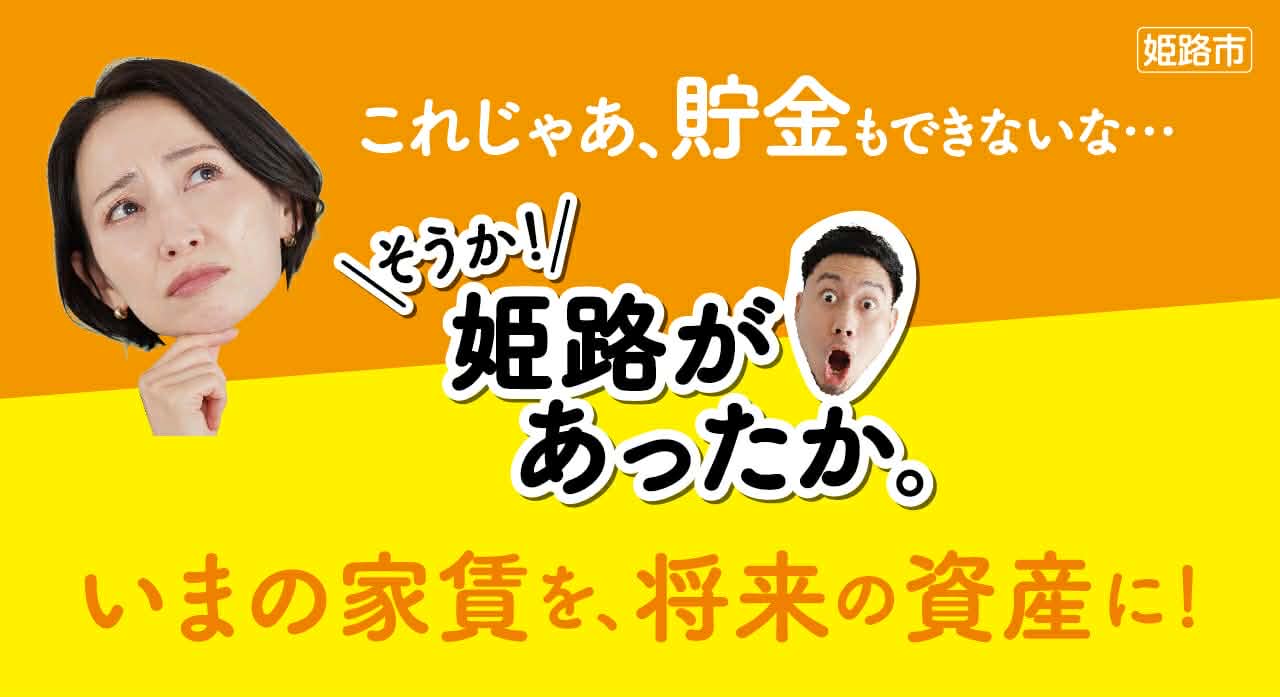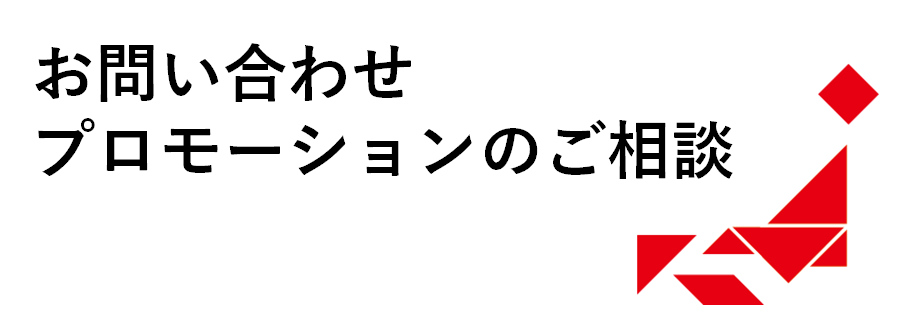日本の国土の7割の面積を占める森林。森と聞くと、誰にも手をつけられていない原生林を思い浮かべる人も多いかもしれないが、日本の森の大部分は、人の手を入れながら受け継がれてきたものだという。この森を次世代に残していくためにも、人と森の共生が不可欠だ。しかし、森の維持には費用がかかり、森を手放したいといった声も多く聞こえてくる。今回はそんな森に新しい価値を吹き込み、森に関わる人をつなぐ活動をする、株式会社モリアゲの長野麻子さんに「森と地域の可能性」について聞いた。

GUEST 長野麻子
株式会社モリアゲ 代表
愛知県生まれ。東京大学文学部フランス文学科卒、1994年に農林水産省に入省。2018年から3年間、林野庁木材利用課長として「ウッド・チェンジ」を各地で叫び続ける。豊かな森を次代につなぐことをに天命と感じ、2022年6月に早期退職。同年8月に日本の森を盛り上げる株式会社モリアゲを設立。
森の維持に不可欠な「人の手」と「光」
脇 長野さんは、日本の森の可能性を感じて活動をされていらっしゃいますが、まずは日本の森の現状について、簡単に教えていただけますか。
長野 日本の森の多くは、先人が植えてくれたものが育ってきているので、木材を積極的に活用して手入れを進めていかなければならない状況です。我々日本人の中で森というと、木々が生い茂り青々とした状態を思い浮かべる方が多いと思いますが、こんなふさふさの状態になるのは400年ぶりの快挙なのです。日本では江戸時代あたりから、木を伐採しすぎて荒れた山が広がっていたのですが、人工林の植林などを通じて、木々が生い茂る森へと育ってきました。一方で、人工林は人の手を入れ続ける必要がありますが、いまは林業に関わる人材が不足したり、丸太が安くて再造林できなくなったりしており、このままでは豊かな森を残せません。森が大事なことは、みなさん分かっていらっしゃいます。ただ、何をしたらよいかわからない方が多い。より多くの方に、森の価値を知ってもらい、森に関わる人を増やしながら、一緒に森を〝モリアゲる〟ことが大事だと考えています。
脇 森をモリアゲる、素敵なコンセプトですね。私たちが目にする森の多くが人工林ということですか、どれくらいの規模でしょうか。
長野日本の森の面積は約2500万ヘクタールで、その中でおよそ4割の1000万ヘクタールほどが人工林です。多くは戦後に森を復興させるために植林されたもので、天皇陛下の植樹祭もその中心的な活動の一つです。他の6割は天然林ですが、人の手が全く入っていないわけではありません。里山など、そのほとんどで何かしら人の手が入っています。人の手が全く入っていない原生林は、屋久島や知床半島、白神山地などが有名ですが、日本では数パーセントほどです。
脇 人の手を入れるというのは、森にとってなぜ大事なのでしょうか。
長野 一言でいえば「光」が行き届くようにするためです。森の中では、木の根っこが網の目のようにはりめぐらされ、土をつかんでいます。間伐などがされない状態が続くと、光が届かず、木の根が張らず、下草もなくなります。そのような状況で大雨や台風が発生すると、雨水が一気に流れ、土砂崩れが起きやすくなります。林業とは、〝光をコントロールする営み〟なんです。たくさん植えたものを間伐しながら、地面に光が届くようにして、少しずつ育てる。時間を味方にしながら、自然のエネルギーを活用して私たちがほしいと思えるものが育つのに手を貸す。その営みのかっこよさに惚れてしまった部分はありますね。

正解がないからこそ、ロマンがある
脇 長野さんご自身が森というテーマに惹かれたきっかけはあったのでしょうか。
長野 私は大学を卒業してから農林水産省で働いてきましたが、2018年に林野庁に出向になり、木材利用課長を3年間務めました。その時、実際に様々な森に行く中で、森って農林水産業にとって、とても重要な存在だと気づいたのです。たとえば、日本は水資源が豊富ですが、雨を涵養して、土の中に溜めておける森の存在が重要です。農林水産省では、農業、漁業といった一次産業の支援を行ってきましたが、農業で利用している水はどこから出てきているのか、魚が育つための栄養豊富な水はどこから生まれるのかを考えると、原点は全て森にあったのです。森という存在の重要性を、その時改めて強く認識しました。それから森に関する仕事を続けたいと思ったのですが、何年間も林野庁に残るのは組織として難しい部分がありました。兼業ができないか、プライベートで活動を続けられないか等、様々な手段を模索しましたが、時間的な制約など、どれも自分の思いを体現するには難しいと感じ、起業するという決断に至りました。
脇 長野さん自身も、実際に森に行って、体感したからこそ森の価値に気づけたのですね。
長野 そうですね。それに、森ってロマンがあるんです。一本の木が育つまでには、長い年月がかかります。人工林でよく植えられるスギやヒノキの場合、概ね50~60年で成長します。ですので、他の部局や省庁が通常は5年や10年先を目標に計画を策定している所、林野庁では森林・林業基本計画という100年先も見据えた計画を策定しています。だけど、森づくりに正解はありません。例えば、大きな柱となる木を育てるためには100年単位の長い年月がかかりますが、100年後にその木が必要とされるのかわかりませんし、災害などで育ちきる前に倒れてしまうかもしれません。だから、必ずしも100年育てることだけが正解とも限りません。長い年月の中で、色々な要素が組み合わさることで森は作られる。教科書のような正解はなく、各々が信じる道を突き進んだ先に、森が形作られていく。そこにロマンを感じます。しかも、一口に森と言っても、森ごとに全然違います。地域ごとに味があり、その森に携わっている方々も、多種多様で魅力的なのです。この人たちがあきらめないで森を繋いできてくれたからこそ、今の豊かな森の姿を私たちは見ることができる。私たち世代が諦めてしまったら次世代に繋げられないのです。
森づくりは地域づくり
長野 森づくりを進めていく上では、官民を越え、業界を越えて様々な立場の人が連携することが不可欠です。先ほど森は多種多様といいましたが、森の所有者も多様です。国が保有する国有林は全体の3割程度で、自治体などが持つ公有林が1割、残りの6割は企業や個人が持つ民有林。一つの森に見えても、所有者は複雑なんです。
脇 日本全体の森を守り、受け継いでいくために、企業と行政が連携して、6割の民有林を一緒にモリアゲることが大事ということですね。
長野 かつての林野庁は国有林から伐った木材を売却することで、収益を得ることができていましたが、森を育てている期間は売ることができないので赤字状態でした。また、民有林についても、木材を販売しても収益が上がることは少なく、補助金頼みなのが実情です。その結果、人工林の再造林率も3割程度。もっと森にお金が戻っていく仕組みや森の応援団が必要なのです。
木材流通の仕組みをつなぎ直し、森にお金を戻す
脇 森にお金が戻る仕組みとはどういったものなのでしょう。
長野 ひとつは、再造林可能なサプライチェーンをつなぎ、適正な価格で木材を買ってもらうことです。現在、日本で使われている木材の6割は外国産になります。木材を建築資材として利用するためには、安定供給が前提ですが、、戦後森を育てている間は木を伐りだせず外国産で需要をまかなってもらったため、国産材のサプライチェーンが構築されていない状況です。実際、安定供給の観点から、日本の林業にはいくつかの課題があります。まず、木はただ切り出した状態では、水分を含んでいるため、製材した上で乾燥をさせなければならず、発注から調達までに時間がかかります。さらに切り出した木を、納品で求められる品質にするために製材所が必要ですが、国産材を生産しなかった期間に廃業してしまった所も多く、担い手が非常に少ないのです。森の所有者が複数にまたがることで、意見をまとめづらい実情もあります。それに比べて、外国産のものは商社が間に入ることで、安定供給が可能で、外国産木材が選ばれやすい状況になっています。
脇 外国産木材が多い今、国産材の活用はどう増やせるでしょうか。
長野 「地域にある裏山の木は活用できない」と思われている現状を変えることが大切だと考えています。都市部のように、より迅速により多くの建築物を建てるためには、大きな製材所で作った規格の整った木材を使うのがいいかもしれませんが、地方では小さな林業、「小商い」があってもいいのではないでしょうか。大きな林業に乗れる森や地域ばかりではないですし、様々なパターンのサプライチェーンや林業を作ることが大事だと考えています。そのためにはまずは「この山の木を使いたい」という需要を作ることが先です。例えば、家を建てたりリフォームするときに、地域の木を使ってもらう。住宅のほとんどは木造ですが、国産材の利用率は5割。ここに国産材を活用する余地があります。住宅に限らず、商店街のお店や事務所などで、地域の木材を利用することも大切と思います。
脇 点在するプレイヤーをつなぎ直し、小規模でも流通する林業を実現することで、地域の木材が活用されるのですね。そのためには「地域の木を使いたい」という需要を喚起することも重要そうですね。
長野 そうなんです。国産材は高いと言われますが、木材の価格で見ても、日本の杉が一番安いとも言われています。ただ、そもそも、家を建てる時に木の産地までこだわっている方はあまり多くありません。システムキッチンのようなオプションは選ぶかもしれないけど、建築材料まで選んでいることは少ない。そういった方に興味を持ってもらうには、とにかく森に足を運んでもらうことが大事だと思います。気持ちのいい森を体験してもらう。その中で、この気持ちいい環境を維持するためには、人の手を入れ、手間をかけていることを知ってもらうんです。
脇 家族で一緒に森に行って、子供から「この木で家を建てたい」と言われたら、半年待ってでもその木を使いたいと感じられそうですね。
長野 地域の木を使うことを決めたら、その半年間はその森と触れ合って、できあがるのが楽しみな時間にすればいいんです。昔は娘が生まれたタイミングでキリを植え、結婚するタイミングでキリ箪笥にして贈るという習慣もありましたよね。最近だと、6歳になったら自分で机を作るプロジェクトも広がっています。そういった生活の中で、木・森との接点も増やしたいです。
「一社一山」であらゆる企業が森と関わる社会
脇 森との接点を増やすということですが、長野さんは「一社一山」と掲げて、一般の企業も森を持ったり、森と関わることを提唱されていますよね。企業にとって、森の価値ってどういったものがあるのでしょうか。
長野 わかりやすいのは、脱炭素の文脈でのカーボンオフセットのために森を所有してもらうことですね。森は二酸化炭素を吸収しますし、木は炭素を固定します。吸収・固定した分をクレジットとして売買することも可能です。他にも、半導体メーカーのように水をたくさん利用する企業にとっては、森は重要で守るべきものです。森の中で雨水が涵養されることで水が豊かに綺麗になっているわけですから。さらにいえば、おいしい空気や生き物を育んでいるのが森で、森の恵みを受けていない企業なんてないと思いますので、あらゆる会社が山と関わる「一社一山」を実現してもらいたい。最近では、ウェルビーイングに森林浴が効果があるという研究も進められているので、従業員の福利厚生にもいいと思います。ドイツでは、医師が森に行くことを処方し、それが保険適用されたりもします。日本でも、長野県・信濃町が大手企業の健康保険組合と組んでいます。健康保険組合は、病気になる人が減ると財源も安定するので、森に行って健康な人を増やそう、という取り組みです。
ちなみに、「森林浴」は、日本発祥の言葉で、海外でも「shinrinyoku」で伝わると言われていますし、外国の森の写真ばかりなのが残念ですがSNSでもたくさん投稿されています。社員のウェルビーイングのためにも、森を所有するのはいいですね。会社で森を持っていれば、休日に友人を連れてレジャー感覚でも行けます。企業と森の取り組みを広げていき、ビジネスの場で「おたくの森最近どう?」みたいな会話が出てくると嬉しいですね。
脇 会社所有の森があれば、週末に遊びに行くこともできますね。森を所有することが、会社の良さを広報することにもつながりそうです。
長野 広報体制が整っていないような中小企業でも、自治体の公有林と組めば情報発信になりますしね。実際に、企業と共同で森を保全するような制度もあります。例えば愛知県・岡崎市と三菱自動車は森林保全活動連携協定を結び、「岡崎アウトランダーの森」という森で活動しています。社員が個人で森に行ってもいいし、研修で使おうという計画もあります。私のように、仕事で森と関わる中で、森に感化される方も出てくることを期待しています。
森側の受け皿になる人を育てる
脇 森に関わりたいけれど何をやればいいかわからないといった方は、何から始めればいいのでしょうか。
長野 「森に行きたい!」という需要は高まっていますが、実は自由に入れる森はあまり多くありません。それは、受け手側の森に人手が足りず、受け入れ態勢ができていないからです。ですので、山村側で受け入れをコーディネートするような仕事も需要があります。森には仕事があるし、自然と触れる仕事ができる、というのをみなさんに知っていただきたいですね。実際、森は盛り上がりつつあり、稼げる仕事にもなっています。私一人で全ての森を活性化させることは難しいですし、地域で森に携わってくれる「モリアゲ団」を増やしていきたいですね。森に関わる様々なプレイヤーが点在しているので、その人たちをつなぐことが今は大事だと思っています。
脇 稼げる状況を実現していくことは、担い手を増やす上で大事ですよね。
長野 株式会社モリアゲは黒字です(笑)大事なのは、木を売るだけでない「森林業」の可能性を広げ、小さい商いをたくさんつくり、つなげることです。小さい商いがたくさんあれば、一つのことで無理をして森を貪るようなことは避けられます。「マイクロ六次産業化」として、いろんなことをやることが大切だと考えています。
MORI-AGE 森の時代
脇 「森は人の手を入れ続けることで受け継がれている」「地域の裏山の木を使う」「企業が森を持つ」など、たくさんの示唆をいただきました。あらためて最後にメッセージをいただけますか。
長野 とにかく「森が森であること」の価値をあげることがとても大事だと考えています。私有林が6割ということで、手入れにコストだけがかかり、森の価値が見直されなければ、森を切り崩して他のことに使われてしまう可能性だってあります。現に太陽光発電などで森を切り拓かれています。国や自治体で法令や条例などを創ることができるかもしれませんが、それでも限界はあり、お金の流れを変える必要があります。脱炭素だったり、観光だったり、企業の福利厚生だったり、お金が森に還る仕組み作りをして、森を森として残すことが重要です。世界では2030年までに、人と自然が共生する社会に向けて、生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ」が注目されています。陸域生物の8割は森に暮らしているので、森への注目はますます高まります。国土面積の7割に森が広がり、かつ島国で生態系としても独立している日本は、世界から注目されるホットスポットです。森にとってはチャンスでしかありません。まさに森の時代です。先祖から受け取ったこの豊かな森を、価値に転換して、次世代につなげていけたらと思います。

暮らしと森を結ぶ。多様化する森林資源の活用例
森林セラピーの利用に補助金支給
森林を活用して加入者のウェルネスを向上
TOPPANグループ健康保険組合

「森林セラピー」は科学的な証拠に裏付けされた森林浴のことで、近年のストレス社会に効果的であると注目されている。TOPPANグループ健康保険組合ではこの「森林セラピー」を積極的に自然から活力を受けることができる健康増進活動として推奨し、利用の際に補助金を支給している。より気軽に体験できるよう、森林セラピー基地周辺の宿泊施設と契約し、宿泊費用も補助。そのほか、健保の加入事業所が実施する社員研修や健康づくり活動での利用においてもサポートや補助金の支給を実施し、組織の活力アップにも効果を発揮しているという。
https://www.toppankenpo.or.jp/foresttherapy/
「森をつくる暮らしをつくる」
アカマツを使った包装材
やまとわ「信州経木Shiki」

かつては生活と密着していた森林資源の活用。やまとわは、現在では循環の糸が切れてしまっている森と暮らしを再びつなげ、「森をつくる暮らし」をつくることを理念にしている企業だ。プロダクト開発や空間設計、イベントや体験の場の提供、情報発信まで、さまざまな形で木を身近に感じ、使う暮らしをプロデュースしている。
「やまとわ」の代表的なプロダクトである「信州経木Shiki」は木を紙のように薄く削った日本伝統の包装材。原材料は信州伊那谷のアカマツ100%で素材から生産まで全て信州伊那谷産で、添加物一切無し。かつての生産者から経木をスライスする機械を譲り受け、試行錯誤しながら職人芸とも言える薄削りを再現させたという。「敷く、包む、飾る」。現代の包装材にはない上品さ、そして新鮮さを感じさせてくれる経木。やまとわでは、五感に訴えるさまざまな手法を用いながら、暮らしのなかに森の息吹を吹き込んでいく。
活用されていない広葉樹を木育に
木と触れ合う機会をトラックで全国に運ぶ
一場木工所の木育トラック「manaviba」

日本には広葉樹が多く生えているにもかかわらず、その9割は木材チップになっている。また、木製の家具やおもちゃの国内需要が高いのに対し、その材料はほとんど自給されていない。こうした現状に対し、森林との親しみを深めるために、国産の広葉樹を活用する取り組みが始まっている。 令和6年6月から首都圏を中心に利用を開始する木育トラック「manaviba」では、活用されていなかった広葉樹で家具やおもちゃをつくり、トラックに搭載することで、全国各地で木と触れ合える機会をつくり上げていく。内装費用や広報、営業に株式会社モリアゲも協力し、森林への理解促進を強化。子育てや地域、企業のイベントをはじめ、災害時における支援車両としての活用も期待されている。

Coordinator
脇 雅昭
よんなな会/オンライン市役所発起人
宮崎県出身。2008年総務省入省。神奈川県庁に出向し、官民連携等の取組を進めてきた。プライベートでは、全国の公務員がナレッジや想いを共有する「よんなな会」「オンライン市役所」を立ち上げ、地方創生のためのコミュニティ基盤づくりを進めている。
編集・島田龍男 文・鈴木亮人 撮影・荒井勇紀