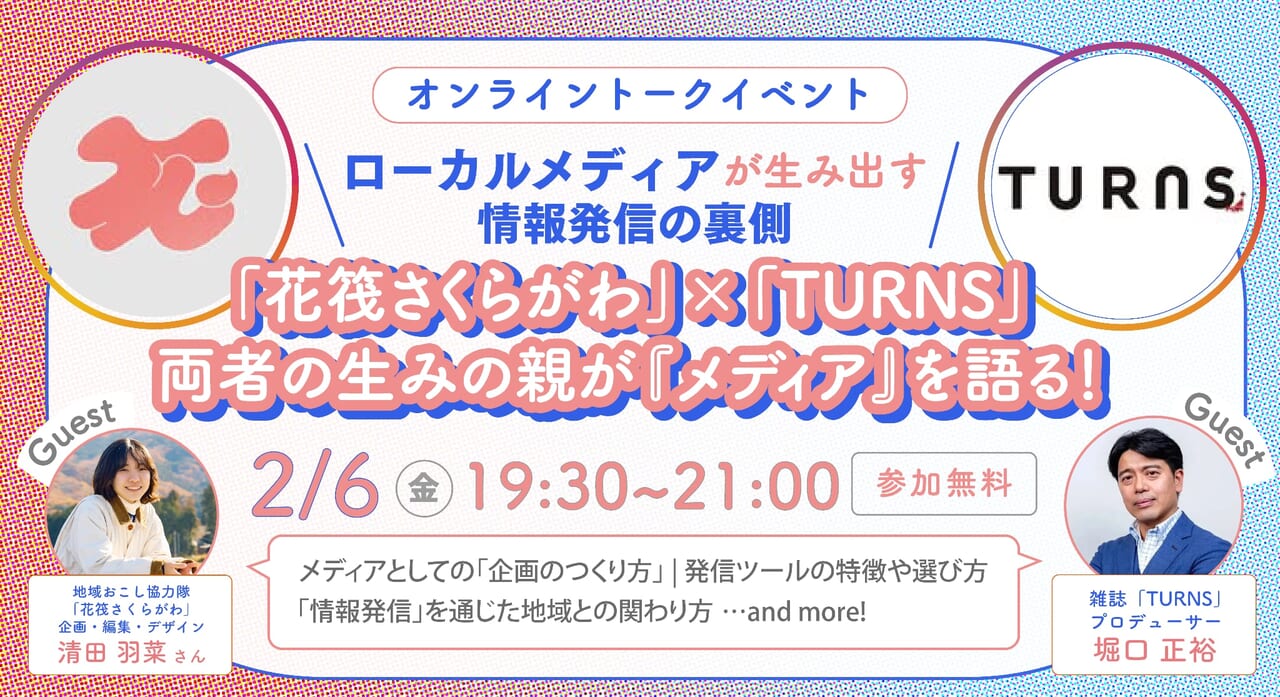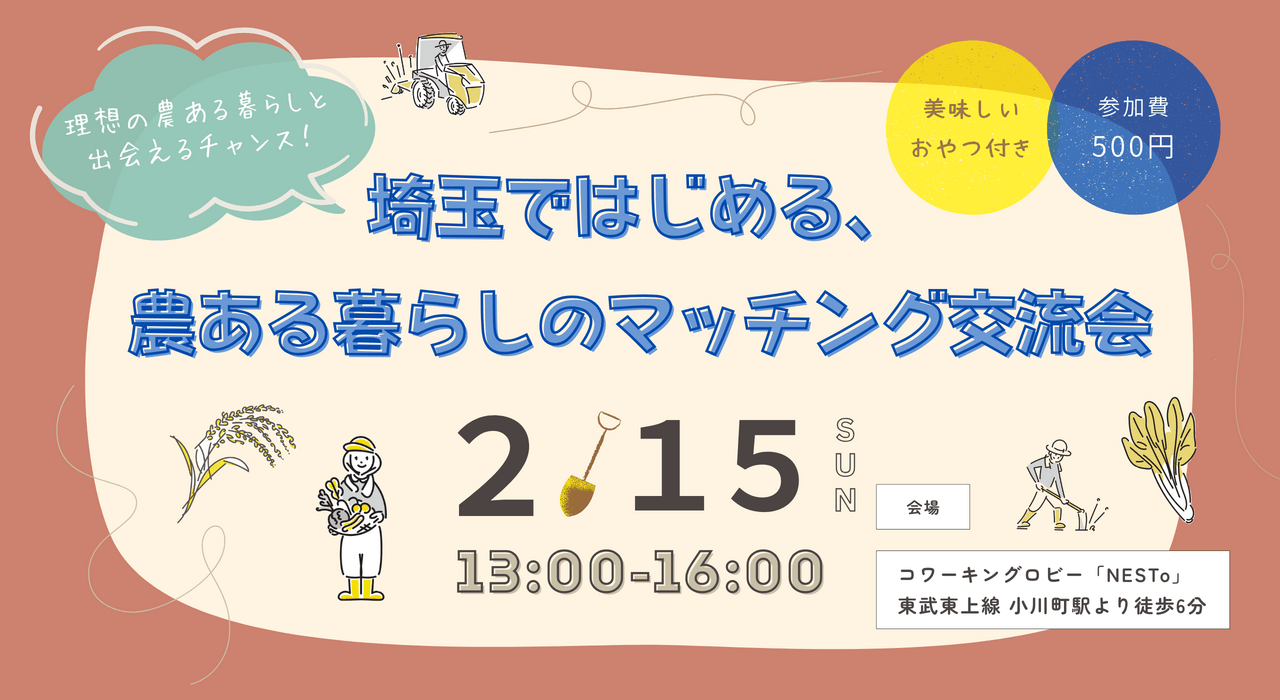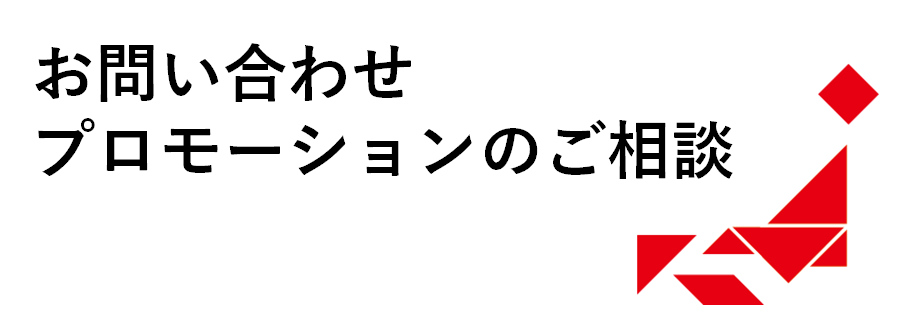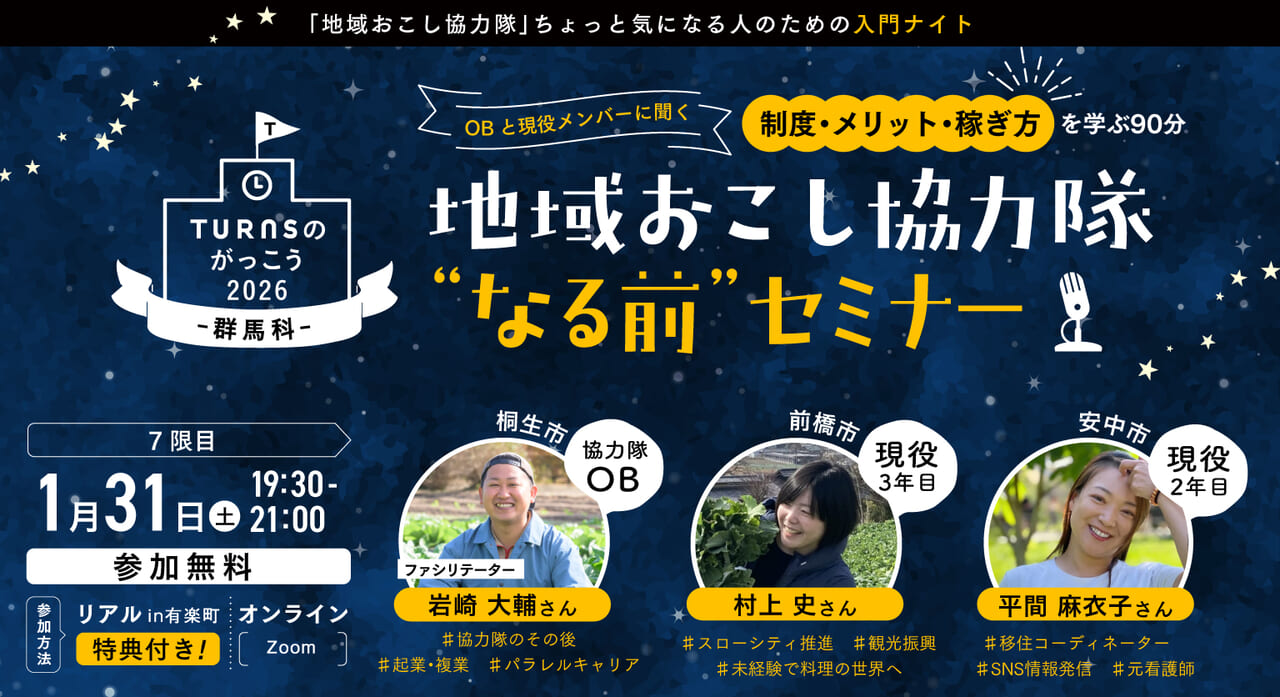古代から人が住まう土地、奈良県・奥大和。ときに厳しい表情を見せる大自然のなかで、地に足のついた暮らしを営み、外の人々からさまざまな技術を吸収しながら、独自の歴史を紡いできた場所だ。
古いものと新しいものが心地よく共存する奥大和では、いつも新しいコトが起こる。今回は、奥大和で今、「面白い!」と注目を集める活動を行っている団体に取材。地域ならではの楽しみ方を通じ、奥大和を存分に満喫している人々の姿に、奥大和の懐の深さが感じられるだろう。
奥大和とは?-What is OKUYAMATO-

奥大和地域とは、山々が入り組む奈良県南部と、高原地帯が広がる奈良県東部からなるエリア。世界遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」の主要な構成地であるほか、古くから人の往来が盛んな宿場町、日本の原風景を残す里山や棚田など、地域ごとに独自の歴史文化を形成してきた。
「なんか面白そう」がすべての原点
遊びから始まる里山への関心
【全日本棍棒協会】-From 宇陀市-
 全日本棍棒協会の皆さん(左から上村櫟さん、間宮桐さん、東樫さん、西田合歓さん)
全日本棍棒協会の皆さん(左から上村櫟さん、間宮桐さん、東樫さん、西田合歓さん)
誰しも子ども時代、お気に入りの棒を集めたり、手頃な大きさの棒を振り回して遊んだりした経験があるのではなかろうか。そんなワクワクを大人だからこそ叶うスケールで、全力で楽しんでいる人々がいる。奈良県宇陀市に拠点を置く「全日本棍棒協会」だ。
会長を務める東さんは、山の木の伐採を生業にしている。たくさんの木と触れ合い、作業場に持ち帰る日々のなかで、あるとき、ふと閃いたという。「この木で棍棒を作ったら面白そうやな」。それまでは伐採した木のほとんどを薪として活用していた。しかし、燃やすだけの薪よりも“棍棒”にしてみたほうがずっと面白いじゃないか、と。
さっそく形にしやすそうな木をナタで削り、棍棒を製作。仲の良い友人たちに配ってみたところ、予想以上に皆が喜び、面白がってくれた。そして、同じように棍棒を作って遊び始めた仲間たちと「全日本棍棒協会」を結成。身内同士の悪ノリに近い形で、おそらく世界初となる「大棍棒展」の開催を決めた。
メンバーのひとり、間宮さんが所有する大阪市内のギャラリーを会場に、素材や形の異なる棍棒を200本以上も展示。「棍棒は殴ってこそ」と試し殴りコーナーも設置した。その様子をSNSに投稿したところ、斬新かつユニークな視点がうけて大バズり。身内だけの小規模な展示会だったはずが、来場者は一日100人を超え、用意した棍棒は100本近くも売れたという。
さらに、棍棒遊びを続けるうちに「棍棒飛ばし」という新たなスポーツも考案。「これは面白い」と普及活動に取り組むこととなり、ルールを整備して全国大会も開催している。2025年現在、東さんたちの「大宇陀」チームをはじめ、愛媛や名古屋など西日本を中心に8チームほどが棍棒飛ばしを楽しんでいるそうだ。
 左:全日本棍棒協会・会長の東樫さん/右:「大棍棒展」の展示風景。形も大きさもさまざまな棍棒が並ぶさまは壮観
左:全日本棍棒協会・会長の東樫さん/右:「大棍棒展」の展示風景。形も大きさもさまざまな棍棒が並ぶさまは壮観
 「棍棒飛ばし」はチーム対戦と、純粋に飛距離を競 う個人戦があるそう。チーム対戦では、攻撃側が台 にセットした「被打棒」を「殴打棒」で殴って飛ばし、 守備側は飛んできた「被打棒」を撃ち返すなどして 落下点を調整、高得点を防ぐ。落下地点が遠いほ ど高得点となるが、場外に落下すると0点に。より 面白くするために、ルールも日々進化しているそうだ
「棍棒飛ばし」はチーム対戦と、純粋に飛距離を競 う個人戦があるそう。チーム対戦では、攻撃側が台 にセットした「被打棒」を「殴打棒」で殴って飛ばし、 守備側は飛んできた「被打棒」を撃ち返すなどして 落下点を調整、高得点を防ぐ。落下地点が遠いほ ど高得点となるが、場外に落下すると0点に。より 面白くするために、ルールも日々進化しているそうだ
と、ここまでの経緯を聞くだけでは、ただ遊んでいるだけのように聞こえてしまうかもしれない。しかし「全日本棍棒協会」の活動は、それ自体が地域課題の解決にひと役買っているという事実を忘れてはいけない。
「棍棒を作るには、木が必要です。より良い棍棒を作るにはより良い木が必要となる。そのためには里山の整備が重要となってくる。自分たちで道具を調達する必要のある棍棒遊びは、そこに参加すること自体が里山保全の活動に参加しているようなものなんです」と、東さん。
棍棒活動を始める以前から里山の保全活動に携わってきたこともあり、活動に人を集める難しさを肌で感じてきた。しかし「棍棒」という「遊び」を始めたことで、図らずも里山に目を向ける仲間が増えた。
「みんながみんな里山のことを考えるというのは現実的ではない。それよりも棍棒遊びを楽しんでいるうちに、結果的に里山もよくなっているほうが流れとしてはいいし、長く続いていくと思います」
棍棒づくりの魅力は、作る前から始まっていると語る東さん。
「山の木を見て、あの木ならこんな棍棒が作れそうだな、とイメージするんです。あの木はめっちゃ硬いからスポーツ用やな、とか、あの木は色や形がかっこいいから観賞用やな、とか。切った後も、曲がり具合を見てどのあたりを使おうかと考えたり、ナタで削りながら木の硬さの違いを味わったり。そういうものを味わいながらできたものが棍棒っていう、そういうアホっぽいところもまたいいでしょ?
こういうのが作りたいと思っててもそれが叶う木に出会えなければ意味がない。棍棒が木との出会いを演出してくれるんですよ。木の種類にも詳しくなりましたし、山を見る目も変わりました」
 大学在学中から田舎暮らしを希望していた東さんは、ほどよ く山の近くで田畑があり、地元の大阪に出やすい場所を探 して宇陀市に辿り着いた。現在は、大宇陀に来てから知り 合った人の縁で、築250年の古民家を借りて暮らしている。
大学在学中から田舎暮らしを希望していた東さんは、ほどよ く山の近くで田畑があり、地元の大阪に出やすい場所を探 して宇陀市に辿り着いた。現在は、大宇陀に来てから知り 合った人の縁で、築250年の古民家を借りて暮らしている。
今年は2回目の「大棍棒展」と、「棍棒飛ばし」全国大会を開催するスペシャルイヤーになるのだとか。すでに隔週で棍棒づくりのスキルを鍛える「棍棒ジム」を実施し、展示会に向けて準備を進めている。また、棍棒普及のための刊行物を制作したり、昨年から募集を始めた協会員に向けてワークショプも計画するなど、勢いは止まらない。
「大宇陀をローマ字にしたら『OUDA』= 殴打なんですよ。それに気づいたときは、なんて運命的なんだ!と感動しましたね」。
そんな巡り合わせにも強い縁を感じているという大宇陀の地。ここで生まれた「棍棒」遊びがどのように全国に広まっていくのか。想像するだけでも楽しみだ。

奈良県東部の大和高原に位置し、奈良盆地に比べて冷涼な気候が特徴。里山の景観が残るのどかな場所で、農業や林業に携わる人が多い。市内には「女人高野」と呼ばれる室生寺をはじめ、国宝や重要文化財も多く見られ、古きよきものを大切に守ってきたことが感じられる。
先人が守ってきた「西熊野街道」を
未来の子どもに受け継ぐために
【西熊野街道再生プロジェクト】-From 十津川村-
 左から西熊野街道再生プロジェクト代表の南さん親子、松田規孝さん
左から西熊野街道再生プロジェクト代表の南さん親子、松田規孝さん
広大な紀伊半島の大半を占める紀伊山地。世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の中心地となる奈良県南部から和歌山県にかけては特に深く山が入り組み、簡単には人を寄せ付けない雰囲気を持っている。十津川村は、その奈良県南部に位置する日本最大の面積を誇る村だ。
高野山から村を通って熊野本宮大社へと続く世界遺産熊野参詣道「小辺路」、天空の郷として知られる「果無集落」、日本有数の長さを誇る「谷瀬の吊り橋」、源泉掛け流しにこだわった「十津川温泉郷」など、多くの魅力あるコンテンツを持つ十津川村。
ここで今、新たなコンテンツの再生と復活が進んでいる。それは、昔から生活道路として受け継がれてきた「西熊野街道」。プロジェクトの代表を務めるのは、大阪からUターンした南さんだ。
「この山のもと、大好きな十津川の自然環境のなかで子育てがしたいと思い、戻ってきました」。
 西熊野街道再生プロジェクト代表の南さん
西熊野街道再生プロジェクト代表の南さん
しかし、戻ってきてからあることに気づく。
「山に入る手が減り、その様子は私が子どものころと比べて大きく変わっていたんです」
それでも子どもに山の楽しさを伝えたい。知ってほしい。そう考え、集落の名士に案内を頼み、山を歩いてみることにしたそうだ。
「集落の長老に案内していただくなかで『西熊野街道』を教えてもらいました。もともとは集落と集落を繋ぎながら五條市まで続いており、昭和初期頃まで使われていたそうです。しかし、国道が通ったことをきっかけに使う人がいなくなり、今は荒廃が進んでいる。
それを見たとき『今はまだ集落の先輩たちもご健在だからこうして伝えていくことができるけれど、世代交代が進めばこのまま山に返ってしまうんだろう』と思ったら、すごく勿体無いなと感じてしまって。それで仲間を集め始めました」
 生活のツールとして親しまれてきた道ゆえに、使う人の都合によってルート変更なども柔軟に行われてきた西熊野街道。都度、丁寧に手入れされてきた。「先人たちが組んだ石垣は、今の僕たちの技術では再現できない。とても貴重です」と松田さん。
生活のツールとして親しまれてきた道ゆえに、使う人の都合によってルート変更なども柔軟に行われてきた西熊野街道。都度、丁寧に手入れされてきた。「先人たちが組んだ石垣は、今の僕たちの技術では再現できない。とても貴重です」と松田さん。
まずは十津川村で以前からトレイルランニングなどの活動に取り組んできた松田さんに話をもちかけ、そこから山好きな知人に声をかけてもらった。また、村の資料館に情報が少ないことに気づき、インターネット上でも情報収集を開始。奈良南部から和歌山にかけての山に精通し、大手出版社の地図制作にも関わっている児嶋さんのブログを見つけてコンタクトを取った。
そこから人の輪が広がり、2020年、正式に「西熊野街道再生プロジェクト」がスタート。現在は月1回を目処に集まっている。南さんは息子さんとともに活動に参加。生き物が好きな彼にとっては文字通り「宝の山」のようで、目をキラキラさせながら山を楽しんでいるそうだ。

そんな楽しみがありながらも、実際、荒れた山の整備は体力を消耗する。誰も入らない道はあっという間に荒れてしまうため、月1回の活動では維持しきれないと感じるときもある、と南さん。
「この間も凍った雪がちらついてきて、だんだんと指の先に感覚がなくなっていくのを感じながら、『誰も見ていないのになんでこんなことをやってるんだろう』『誰かに頼まれたわけでもないのに!』と思ったり。なくても誰も困らない道を整備しているので、めげそうになることはたくさんあります。
でも、自分たちが整備した場所を振り返って見たときに、きれいで歩きやすい状況になっていると、やっててよかったなと思いますね」

五條市から十津川温泉郷のあたりまでを結んでいた西熊野街道。ルートの一部は国道168号線の下に埋もれたり、ダムに沈んだりしたためすべてを再生することは不可能だが、風屋から那智合集落までの状態は比較的よく、もっとも再生が進んでいる。
現在、整備可能なルートのうち、60%ほどの整備が済んだ。次に発行される地図には西熊野街道が掲載される可能性も出てきた。そんな、先が見えてきた今だからこそ、将来的な活用方法について考える機会も増えている。
「トレイルランニングなどのイベントで外から人を呼び込む必要性はもちろん感じています。取り組みを知ってもらうことが、道の保全に繋がっていきますから。
一方で、私はこの道を昔そうであったように、「私たちのそばにある道」にしたいと思っています。さすがに生活で使ってもらう、というのは難しいかもしれませんが、ハイキングコースや郷土学習として利用したりなど、観光や教育のコンテンツとして、身近な存在になってくれたらいいですね」
「自分たちが子どもの頃に山を駆け回ったように、未来の子どもたちにもこの道を通じて山を身近に感じてほしい」。そんな思いのもとで、プロジェクトは進んでいる。西熊野街道が再び人々の目に触れるようになるまで、もうすぐだ。

奈良県南部、もっとも山深い地域に位置し、日本最大の面積を誇る村。主要な産業は農林業と観光業で、ジビエやきのこを使った土地の料理も人気だ。高野山と熊野本宮大社を結ぶ世界遺産熊野参詣道「小辺路」が通るほか、温泉地やここでしか見られない自然の景観など、見どころも多い。
「まちおこし」のバトンは今
外から来た若者たちへ
【NPO法人 大和社中&株式会社 GOJOチャレンジ】-From 五條市-

5つの街道が交差する交通の要衝として栄えてきた五條市。なかでも「五條新町」エリアは江戸時代の町家が多く残り、往時の姿を伝えている。
全国でまちおこしの機運が高まる以前から、ここでは住民による地域活性化の取り組みが行われてきた。その中心として活動してきたのが、NPO法人 大和社中だ。設備屋や建具屋、酒屋など地元のメンバーが集う任意団体から始まり、平成17年に現在の形となった。
現代表の中さん曰く「このまちに3人のアホがおってな。その人らが集まって『なんか面白いことやろう』って言い始めた」。
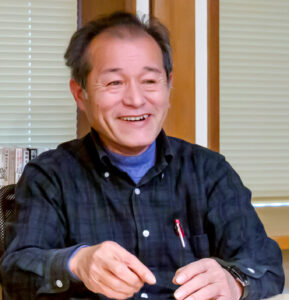
NPO法人大和社中 理事長 中純宏さん
そこで最初にあがった企画が、まち全体を使うフリーマーケットの開催だったそうだ。「かげろう座」と名付けられたそのイベントは、最盛期には約7万人が訪れ、通りは動けないほどの人で溢れたという。
「最初は各地のフリーマーケットに行って出展者に直接声をかけて、そこから広がっていった。まわりに同年代が多くいたから、たくさんの人を巻き込んで半年がかりで準備をして。本当に楽しかったね」と懐かしそうに目を細める。
 最盛期には7 万人以上が訪れたという「かげろう座」。関西最大級のフリーマーケットとして名を馳せた
最盛期には7 万人以上が訪れたという「かげろう座」。関西最大級のフリーマーケットとして名を馳せた
惜しくも20周年を機にその歴史に幕を下ろしたが、大和社中のメンバーによるまちづくりはそのほかにもさまざまな形で行われており、五條新町の「重要伝統的建造物群保存地区」選定にも貢献した。
そんなまちおこしの下地を持つ五條市と、外の若者を繋ぐ会社がある。北海道出身の木村さんが代表を務める株式会社GOJOチャレンジだ。
「東京の会社が地方創生事業を行うことになり、最初に繋がったのが五條市。そこで大和社中の方々と話すなかで、若い経営者を集めて何かできないかという案が出たそうです。そしてツアーを組んで人を呼んだのですが、次第に参加者から『どうせなら五條市に会社を作ろう』という話が出るようになり、立ち上がったのがGOJOチャレンジです」

株式会社GOJOチャレンジ 代表 木村 航さん
「僕は当時大学生で、他の会社で内定も出ていたんですけどね(笑)」という木村さんがここに飛び込んだのは、将来的な起業を視野に入れていたからだそうだ。
すでに東京のチームが新町通の空き家を取得しており、あとは木村さんが入って活動を始めるだけ。
その際、中さんはまず「お前はここ“で”いいんか?それともここ“が”いいんか?」と質問したという。その問いに木村さんは「ここ“が”いいです」と答えた。
「それなら全面協力しよう」と大和社中からも2人ほどが役員として入り、まずは事務所が入る空き家にコワーキングスペースをオープンすることに。それに加え、中さんたちからはもう一つ提案があったそうだ。
「とにかく実業を持て、と。きちんと地に足をつけられる実業を持つことが、地域で何かをするには大切やから」
そこで改めて五條の課題を話し合った。五條市でも他の地域同様、子どもたちが進学などで出ていったあと、戻ってこないという課題がある。「子どもの頃に地域のことに触れる機会があれば、戻ってくる人が増えるのでは」。そう考えた木村さんは、若者が戻ってくる仕組みづくりとして、地域のことを学ぶ学習塾を開くことに決めた。
「最初は『よそ者に地域のことなんか教えられるんか?』という声もありました。でも、大和社中さんが協力してくれているというだけで受け入れてもらえましたね」
 みよし邸に開塾した「五條しんまち塾」。2016 年のスタート時からeラーニングを取り入れ、 地域文化を先進的なスタイルで学ぶことができる
みよし邸に開塾した「五條しんまち塾」。2016 年のスタート時からeラーニングを取り入れ、 地域文化を先進的なスタイルで学ぶことができる
ビジネスの視点を持つGOJOチャレンジと、地域の事情や信頼に強く手に職を持つメンバーが集まる大和社中。この役割の違いは自然な形で作用しており、外から来た若者はまず発信力の高いGOJOチャレンジを通してまちと繋がり、実際に物件を探して事業を始める際には大和社中が面倒を見るという流れが生まれている。これまでに三人ほどがこの仕組みのもとで起業したそうだ。

GOJOチャレンジの事務所が入る「みよし邸」は、中さんがリフォームを担当。(左)/五條市を拠点に店舗を拡大している「株式会社イトバナシ」と同社が経営する「chocobanashi」も、GOJOチャレンジをきっかけに、中さんが物件を紹介した(右)
そんな理想的な関係を築いている2組だが、中さんは「大和社中はみんな高齢になり、後継者もいない。あとは自然に消えていくだけ」と今後を冷静に見ている。
「GOJOチャレンジに引き継げるものは少しずつ渡していっているけれど、彼らにあとを継げとは言わない。僕らは本業を持ちながら遊びでやっていたけど、彼らはビジネスでやっているからね。僕らがやっていた行政との連携とは違う形での連携も積極的にしていくべき」と、中さん。
「こういう場所で何かをするには、ゆとりや遊び心が大切。焦らんとゆっくりやっていってほしいね」

市内を吉野川が流れ、5つの街道が交差する五條市は、奥大和の玄関口。奈良中心部や和歌山、大阪を結ぶ交通の要衝として発展し、現在も奈良県南部の中心地に位置づけられている。江戸時代の面影を残す「五條新町通り」は、古民家再生の先進地域としても注目されている。
奥大和への移住に関する相談はこちらへ
奥大和移住定住交流センター「engawa」
奈良県橿原市に位置する、情報発信と繋がりづくりの拠点。移住相談窓口にはコンシェルジュが常駐し「奥大和をもっと知りたい」「奥大和に住んでみたい」という人のさまざまな相談に対応している。
TEL:0744-48-3019
奈良県 総務部知事公室 奥大和地域活力推進課
TEL:0744-48-3016
奥大和を知るWeb Site「Local Life in Nara Okuyamato」