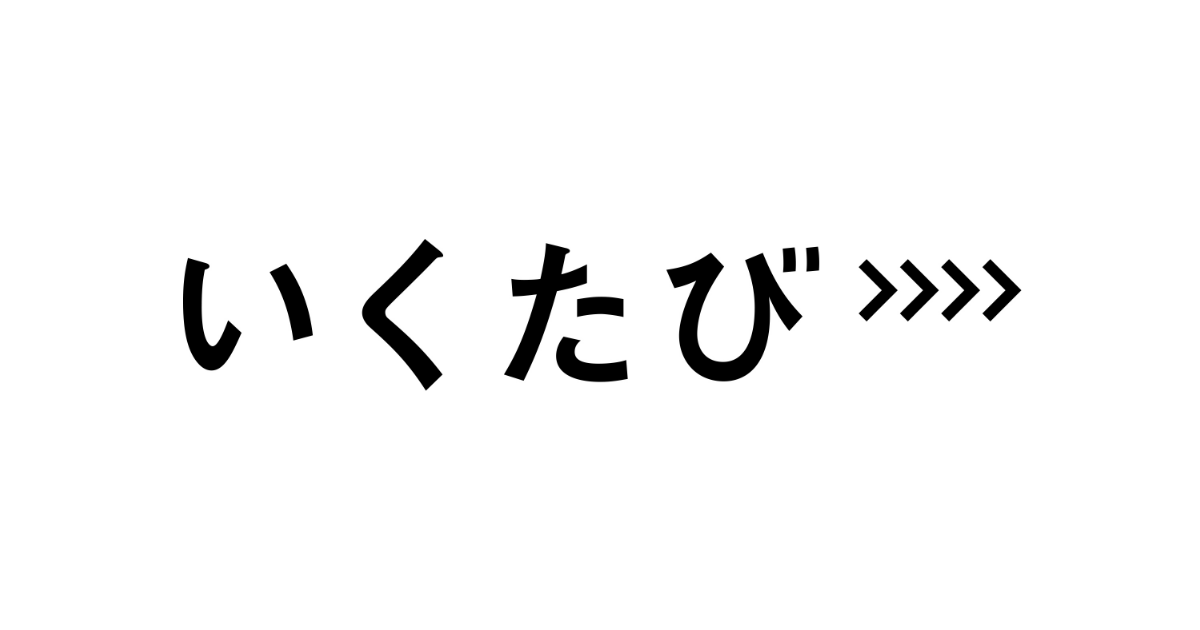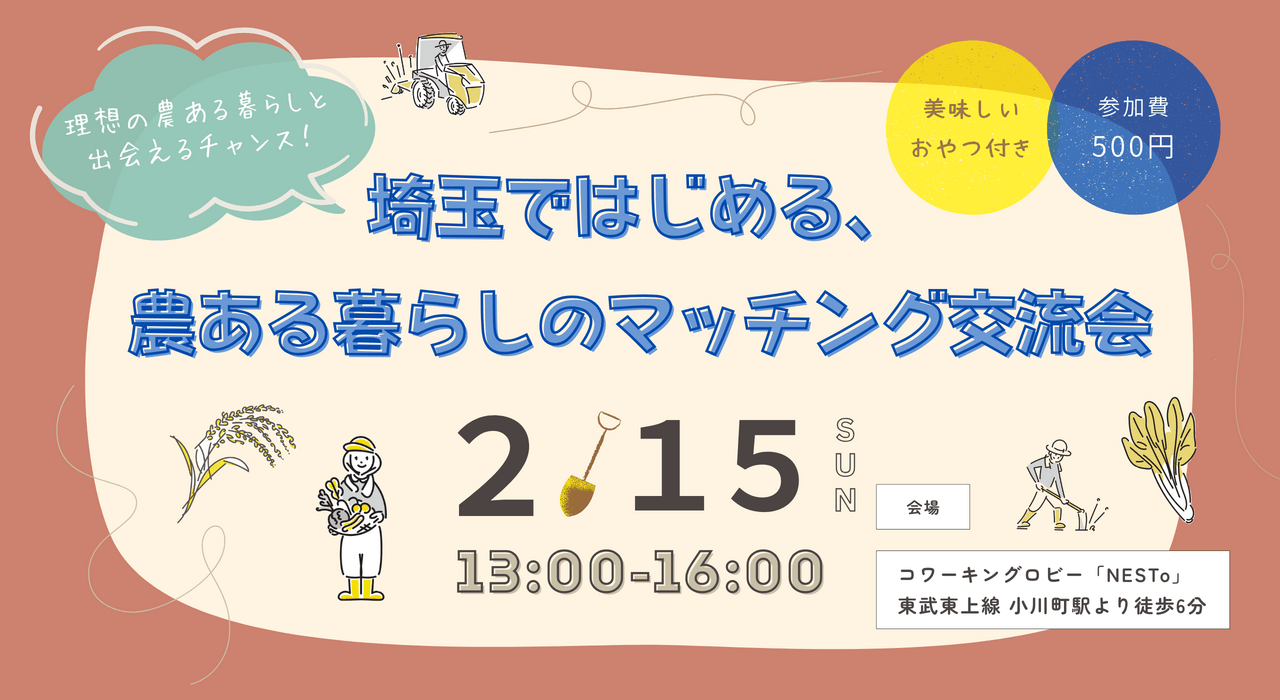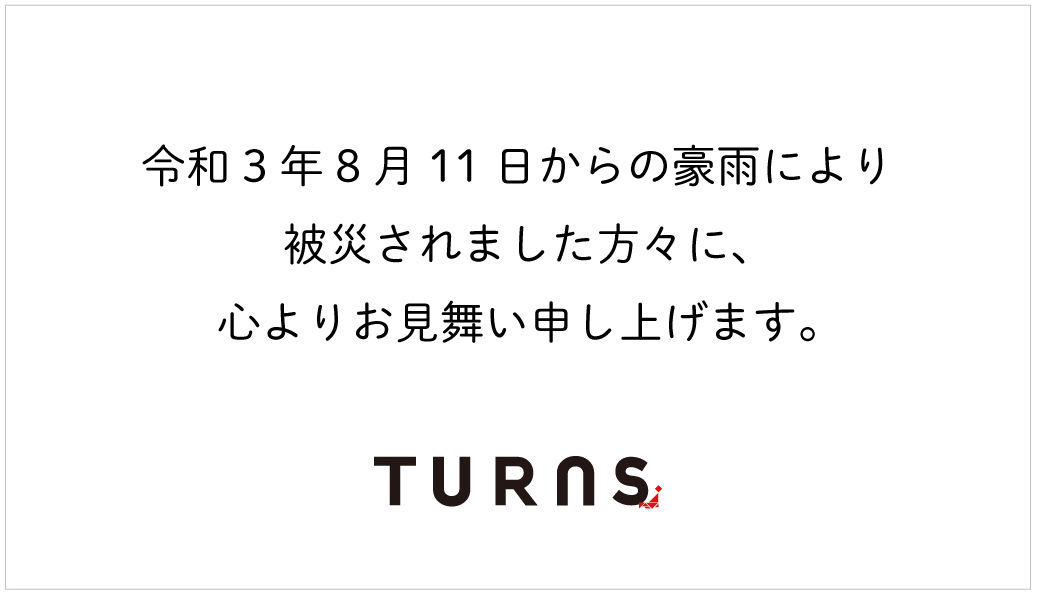日本のどこかで心惹かれるまちに出会い、幾度となく足を運ぶうちに、一度では知り得なかった地域の魅力が明らかになり、出会った人との絆が深まっていく。やがてそのまちが心の拠り所となり、帰りたくなる「第2のふるさと」へと変わっていく。
そんな “旅”と“移住”の間の新しいライフスタイルを提案する、観光庁が立ち上げた「第2のふるさとづくり」プロジェクト。令和6年度は「まちが わたしが 育つ旅。いくたび」をテーマに、各地で魅力的な旅のプログラムが展開されています。
ひとつの地域で新たな出会いや学びを重ねながら、自分自身も成長するこの豊かな旅の体験を、TURNSライターがお届けします。
いくたびREPORT_01 新潟県南魚沼市
家業のお手伝いから芽生える郷土愛
旅のはじまりは「おかえり、ただいま」の笑顔から

初めてなのに懐かしい、八海山の麓に広がるまちへ
JR越後湯沢駅からほくほく線に乗り換え、魚野川に沿って下るように六日町駅へと向かう車窓から見えるのは、八海山を筆頭に連なる深い緑の山々と、山頂にかかるむくむくとした白い夏雲、そして一面に広がる水田。子どもの頃に母の田舎へ里帰りした夏休みを思い出し、初めての景色のはずなのに、なぜだか懐かしい気持ちになる風景です。
南魚沼市は指折りの豪雪地帯。かつては商店街のアーケードが埋まるほど降ったという大量の雪が、春になると一気に解け出し、豊かな雪解け水が田を潤して日本一の南魚沼産コシヒカリを育てます。私が訪れた8月の終わりは、見渡す限り広がる田んぼに、ようやく粒の張ってきた青い稲穂が揺れていました。

鮎釣りのメッカでもある清流 魚野川を渡り、今回の「いくたび」体験の舞台となる「さかとケ」がある古民家ホテル「ryugon」へ。
「ryugon」は、かつてお城のあった坂戸山の懐に、この地域に残存していた複数の古民家を集めて再生させた温泉宿です。“雪を回生するホテル”と謳うこのホテルは、日本一雪深いこの地域で、人々が雪と共に循環しながら生きてきた知恵や文化を体感するための場所。
その一角に併設されている建物が「さかとケ」で、「ryugon」でのお手伝いと引き換えに無料で「さかとケ」に泊まり、観光やワーケーションができるのです。この素晴らしい宿でどんなお手伝いができるのか、はたして私に務まるのだろうかとドキドキしながら「ryugon」に到着しました。

雪国文化を体験する宿「ryugon」と、“帰る旅”の拠点「さかとケ」
待っていてくださったのは、「ryugon」の経営者である井口智裕さん(株式会社いせん代表取締役)。井口さんが思いを持って取り組んでいる「雪国観光圏」や、「さかとケ」を始めた経緯についてお話しいただきました。

「私は湯沢の『いせん』という旅館の4代目に生まれました。時代が大きく変わる中で、世界にも目を向けつつ観光業の今後の可能性を考えた時、これまでのスキーリゾート一辺倒ではなく、例えば『フランスのワイナリーに一週間泊まりたい』というような旅のリテラシーを持ったお客さまに来ていただける観光にしていくことが必要だと考えました。この地域には、長い時間の中で培われた分厚い雪国文化があります。“非日常”を消費しに行く旅ではなく、雪国の暮らしに入り込むような“異日常”を体験する旅を提供したい。世界にも十分通用するこの価値ある文化を、雪国が広域で連携して提案していこうと、雪国観光圏の取り組みを始めました。これを場として表現したのが『ryugon』です」

さらに井口さんの視座を大きく変えたのがコロナ禍。これをきっかけに、何度も通ってくれる、「ただいま、おかえり」の関係でつながる仲間を増やしたいと感じたそうです。
「あの時、お客さまが一人もいない宿を見ながら、私はなぜかワクワクしたんです。観光業が大きく変わる予感がしてね。豪華さを競い合うようなラグジュアリーな旅の一方で、これからはもっとフラットに地域やそこにいる人と関わり合える旅を求める人が、きっと増える。何かしら地域に貢献しながら、地域を楽しみ、大変な時には駆けつけてくれるコミュニティのようなファンを増やしたいと思って立ち上げたのが『さかとケ』なんです」
「さかとケ」の「さかと」は坂戸山、「ケ」は「家」。坂戸山の懐にある、もうひとつの帰る「家」。ハウスワーク(家業)を手伝うことで宿泊料が免除になるワークインレジデンスという、地域と旅人との関係づくりのための井口さんの新しい試みなのです。
宿の仲間になってお手伝い
お話の後は、早速エプロンを着けてハウスワークを実践。今回は「ryugon」の客室清掃をお手伝いすることに。お客さまがチェックウトした後の客室に入り、まずはベッドシーツを剥がす作業。

「ひとつのベッドの上に全部のシーツ類を集めて、最後は1枚のシーツでくるんでクリーニングの袋に入れます」
と、スタッフの方が優しく要領を教えてくれました。15時頃には今夜宿泊するお客さまがチェックインし始めるので、時間との勝負。
ソファなどのファブリック類は、粘着クリーナーをくまなくかけます。手際よく進めながらも、髪の毛1本見逃さないように注意が必要とのこと。

大きなガラス窓の拭き掃除もお手伝い。
「光の加減で汚れが見えたり見えなかったりするので、いろいろな角度から見て、汚れている所を中心に磨きます。部屋がたくさんあるから、全面を全力で拭いていると時間もかかるし、体力も持たないのよ」
と、コツを教えていただきました。スプレーを掛けながら、汚れを見つけては拭き取ります。

ピカピカに整えられた客室の裏側に、人の思いやりがこもった一つひとつの仕事があるんだなぁと、泊まるだけでは見えてこない気づきがありました。
落ち着く個室と整った共用スペースで充実の滞在
お手伝いの後は、宿泊する「さかとケ」の部屋を案内していただきました。「ryugon」の敷地の一角にある古い蔵を改装した建物が「さかとケ」。2階建ての内部には4つのシングルルームと共用のキッチン、洗濯機、ワークスペースが。お風呂は贅沢にも「ryugon」の大浴場を利用できます。
お部屋は一般的なビジネスホテルのシングルルームほどの大きさで、ベッドとデスク、一人掛けのソファもあり、落ち着いた雰囲気で安心して眠れそう。

キッチンはコンパクトながら調理器具、食器、炊飯器や電子レンジも完備。近隣の地元スーパーなどで新鮮な食材を買って来て自炊することができます。

キッチンスペースの壁には、これまで「さかとケ」を利用した皆さんが書き加えていった地域の地図も。発見した穴場や情報を教え合う仲間同士のコミュニケーションボードから、人とつながっていくあたたかさを感じました。

お手伝い以外の時間は自由に地域を探究
1日5時間のお手伝い以外の時間は、「ryugon」内のワーキングスペースで仕事をしたり、ライブラリーで読書したり、eバイクを借りて散策に出かけたりと思い思いに過ごすことができます。

歴史とお寺が好きな私は、ryugonから自転車などで行ける「雲洞庵」を拝観。苔むす境内の美しさに癒やされました。

水芭蕉や桜、夏は蛍の名所でもある銭渕公園でフォトウォークも楽しみました。

お手伝いをしながら関わることで、地域がいっそう近くなる
今回、初めて体験した宿のお手伝いでしたが、井口さんをはじめスタッフのみなさんが壁をつくらず本当に仲間のように受け入れてくださったことで、リラックスして臨むことができました。「ryugon」の舞台裏にほんの少し関わることができたおかげで、今までの「お客さま感覚」とは違う、働く方々への親近感やこの場所への愛着の兆しのようなものが芽生えたように感じました。

聞けば、ほぼ毎月1回「さかとケ」を利用して六日町に通っている方や、「さかとケ」でのインターンをきっかけにこのまちを気に入り、その後「ryugon」に就職して移住した学生さんもいるそうです。このワークインレジデンスの仕組みは、「帰る旅」のプログラムとして雪国文化圏の他のまちにも波及し、福祉施設で障害者の方々と働く体験ができる「いなりケ」や、秘境・秋山郷での古民家再生プロジェクトなど、広がりを見せています。
井口さんの「さかとケ」での次なる目標は、ハウスワークを地域の仕事にも拡大していくこと。例えば高齢化するまちの冬場の雪かきや、美しい水の源流を生み出す森林の保全活動など、地域により近づき、地域を一緒につくる仕事の創出を目指しているそうです。

エピローグ
雪国に雪のない季節に行って、楽しめるのだろうか? そんな私の無知な疑問は、今回の「さかとケ」での体験や井口さんとの出会いで見事に払拭されました。井口さんの言葉を借りれば「ミルフィーユ状に積層した」奥深い雪国文化が南魚沼にはあり、今回は探究できなかった織物や郷土料理などを、次回はぜひ知りたいと思います。そして何より、あの一面の水田で実った南魚沼の新米を現地で食べたい。次回はいつ頃行こうかと考え始めています。
取材・文:森田マイコ 撮影:宮崎純一
いくたびREPORT_02 富山県南砺市
250年の歴史を刻む木彫刻のまちへ
つくる人と出会い、学び、深く味わう旅

一人の彫刻師を源泉に、時代をこえて受け継がれてきた「井波彫刻」
日本一の木彫りのまちとして知られる富山県南砺市井波。井波の人口は約8,000人。その内のおよそ200人が彫刻産業に携わる「彫刻師のまち」です。まちのシンボル「瑞泉寺」に至る八日町通りには、さまざまな工房が軒を連ねています。

1390年に建てられた古刹は、これまでに3度の火災に見舞われながらも、その度に職人たちの手で再建されてきました。1879年の大火災で消失すると、京都の東本願寺から御用彫刻師・前川三四郎が招かれました。地元の大工がこれに参加し、前川氏から彫刻の技法を習ったのが井波彫刻の始まりです。その伝統が受け継がれて、全国から彫刻の技法を学びに職人たちが井波を訪れるようになりました。
井波の伝統にふれる「井波彫刻塾」
まず訪ねたのは、「井波木彫工芸館」を営む彫刻師の前川大地さん。本業の傍ら、地域の課題解決とまちづくりに取り組む一般社団法人ジソウラボの理事も務めており、芸術と地域振興の両面で活躍しています。

井波の工房には、全国各地から神社仏閣や祭りの山車などの彫刻の依頼があり、制作が追い付かないほどだそうです。これまで彫刻師の養成を担ってきたのは、井波彫刻協同組合が運営する職業訓練校。彫刻師を目指す全国の若者たちが、5年間かけて木彫りの技術を学んでいましたが、生徒数の減少で現在は休校中。彫刻師を目指す人の入口を広げることを目的に、2023年に始まったのが「井波彫刻塾」です。8ヶ月間(4月〜12月)、毎月井波を訪れて、熟練の彫刻師から技術を学びます。

昨年は県内や隣県からの参加のみでしたが、2期目となる今年は、ジソウラボが彫刻組合の協力のもと特別コースを設置し、日本全国に情報を発信。美術大学にも発信したところ、若者からシニア世代まで約20人が参加。7月に行われた第1回目の活動では、参加者からさまざまな反響があったそうです。
「美術大学ではあまり教えてもらえない実践的な技術を学べて良かったという声がありました。また、彫刻の技法を包み隠さず教えてもらえたことに驚いていた参加者も。井波彫刻の技法は門外不出というわけではなく、この場所に残るか残らないかにかかわらず昔から伝承してきたものです。井波彫刻塾でも、ここでの定着をゴールとはせずに、参加を通して井波のファンになってもらえたらうれしいです」
井波彫刻を体験。匠の技の奥深さに魅せられる
筆者も前川さんの工房で井波彫刻を体験させてもらうことに。四角いヒノキの器の周りの部分を、のみとげんのうで削ぎ落として筒状に仕上げる作業です。師匠から簡単な手ほどきを受けて、いざ実践。やってみると刃の当て方や力加減が難しく、木がささくれ立ったり、ざっくりと削げてしまったりして、なかなか思い通りにいきません。「こういう時はこうして……」と、師匠はトントンと小気味よい音を立てながら、ささくれ立った部分を修復してくれます。師匠のアドバイスを聞きながら彫り進めていくと、少しずつコツがわかってきました。

ヒノキの香りが心地良く、無心になって彫っていると不思議と癒やされてきます。30分ほど彫ると、なんとか筒状に。完成品はややいびつな形になりましたが、それも私の個性ということにしておきましょう。
あらためて工房内の作品を見渡すと、匠の技のすごさがよく分かります。短い時間でしたが、井波彫刻の奥深さを身にしみて感じることができました。

つくる人をつくる。新しい才能と文化が生まれる匠のまち井波
前川さんが理事を務めるジソウラボは「人材輩出のまち、井波をつくること」をビジョンに2020年6月に設立した団体です。メンバーのほとんどがUターン者で、建築家やエンジニア、石屋、IT起業家など、異業種のメンバーで運営しています。立ち上げのきっかけは、2018年に井波が木彫刻のまちとして文化庁の日本遺産に認定されたこと。若い世代が中心になって地域のことに責任をもって取り組んでいこうと、前川さんの同級生で林業家の島田優平さんが仲間に声を掛けてジソウラボは始まりました。
「まちの運営に関わる組織はいろいろありますが、役員が交代すると終わってしまう事業が多く、継続性のある自発的な取り組みが必要だと考えました。ジソウラボの主な事業は、『つくる人』の育成です。ものに限らず、何かを生み出す人に伴走して支援を行っています」と前川さん。

「オール井波」でつくる、ここにしかないクラフトビール
工房を後にして向かった先は、そこから歩いて5分ほどの距離にある「NAT.BREW(ナットブリュー)」。ジソウラボのサポートを受けて、2023年2月に開業したブルワリー(ビール醸造所)です。150年前に前川三四郎氏が源泉になって800人の彫刻師が育ったように、地域の源泉になる人を呼び込みたい。そんな思いから始まったのが「BE THE (MASTER) PIECE プロジェクト」、略して(MA)Pです。ジソウラボが県外から起業家を募って支援する事業で、他にもコーヒースタンドやベーカリーなどが続々と開店しています。

「NAT.BREW」を運営するのは醸造家の望月俊祐さん。山梨県出身で、20歳の時から大手ワイナリーでワイン醸造の仕事をしてきました。その後、妻の実家がある南砺市に移住して、市内のワイナリーの立ち上げに参画。転機は、知り合いからジソウラボのビール醸造家募集の話を聞いたことでした。
いつか自分の醸造所を持ちたいと考えていた望月さんは、ワイン醸造の技術を活かせると思い応募。面接ではブルワリーのオーナーで、ジソウラボ理事の藤井公嗣さんと意気投合。打ち合わせを重ねながら、3年の準備期間を経て開業しました。
「ブルワリーという大枠は決まっていましたが、自分で考えてやっていいよと言ってくれたので、とてもやりやすかったです。商品開発の際などは藤井さんに相談しますが、『いいね、やろうよ!』という感じで。オーナーと醸造家がこんなに仲がいいのは珍しいかもしれません」(笑)。
「みんなで一緒にやろう」という雰囲気が井波の魅力
「NAT.BREW」は、ジソウラボ代表の島田さんの旧家。内装には島田さんが営む木材会社の木を使い、改修の設計や施工もジソウラボのメンバーが手掛けたそうです。

「NAT.BREW」では「土着(Native)醸造」をコンセプトに、自由な発想で井波の風土を活かした醸造酒をつくっています。例えば、クロモジで香り付けしたものや地元の果物農家とコラボレーションしたものなど、どれもユニーク。地元の特産品である干し柿を使った醸造酒は、「ジャパン・グレートビア・アワーズ2024」で金賞を受賞しています。
「販路の9割が地元なんです。それまでなじみのなかったクラフトビールが地域で受け入れられたのは、ジソウラボが地元の人との橋渡しをしてくれたおかげです」

最後に、望月さんに井波の魅力を尋ねました。
「みんなで一緒にやろうという雰囲気が井波の魅力です。ここでは地元の人も移住者も関係なく、外から来た人でもすっと入り込んでいけます。昔から全国の彫刻師を迎え入れてきた歴史が、その温かい受け入れの基盤をつくり上げているのかもしれません。だんだんお店も増えてきて、まちに良い流れができているのを感じます」
ジソウラボのメンバーや望月さんをはじめ、そこに住む人たちの思いが魅力ある人々を呼び寄せ、まちに新しい風を吹き込んでいるようです。次に井波を訪れた時に、どんな変化が起きているのか楽しみです。

エピローグ
井波彫刻や望月さんとの出会いは、私の中に眠っていたものづくりへの興味を静かに呼び覚ましてくれた、意義深い経験となりました。彫刻の匠たちが紡いできた伝統と、現代の創造力が融合するこの井波は、まさに「つくる人」を育てる場所であり、新たな文化が息吹く土壌を感じさせてくれます。そんな井波の地へ、また足を運ばずにはいられません。
取材:文・鈴木俊輔 写真・中西優
いくたびREPORT_03 福島県福島市
真綿の手ざわりと人とのふれあいに癒やされて
養蚕のまちで紡ぐ地域とのあたたかな縁

絹の里、信達地方へ
旅の舞台は、福島県北部に広がる信達地方。阿武隈川のほとりに広がる自然豊かなこのエリアは、かつては「信達蚕糸業地帯」として日本全国にその名を知られ、江戸時代から養種・養蚕・生糸・絹織物の名産地として栄えてきました。
ここで訪れたのは、福島市飯坂町の古民家を改装した「染織工房おりをり」。迎えてくれたのは、工房を主宰する染め織り作家の鈴木美佐子さんと、シルク文化の継承に力を注ぐ福島市フルーツラインエリア観光推進協議会の中山高行さん。まずはお二人に、信達地方の養蚕業の歩みと現状についてお話を伺いました。

最盛期は、大正から昭和初期にかけてで、現在、果樹園となっている大部分は、かつて蚕のエサとなる桑畑であったそうです。しかし、桑の病気が蔓延したり、化学繊維が主流になるにつれ、養蚕業は徐々に衰退。現在、福島県内の養蚕農家は12軒を残すのみとなり、他地域も含めた純国産生糸の生産量は国内消費量の1%にも満たないと言います。
「このままでは福島から養蚕の文化がなくなってしまう」
中山さんはそんな危機感を抱き、観光からの切り口で養蚕について知ってもらう機会をつくれないかと模索していました。そんな時に出会ったのが鈴木さんでした。

鈴木さんによれば、福島では養蚕だけでなく、製糸や真綿生産、機織も一貫して地域内で行われていた全国でも珍しい地域で、昔ながらの手仕事を体験したい人からの問い合わせが年々増えてきていると言います。鈴木さんの存在を知り、中山さんは「養蚕や織物の体験は、地域に何度も足を運んでもらうきっかけになると感じました」と振り返ります。
現在、中山さんは鈴木さんの活動をサポートしながら、都心タワーマンション在住者向けの出張ワークショップを企画したり、地元の大学生を巻き込んで養蚕をテーマにしたカルタや絵本を制作したりするなど、信達地方が旅の選択肢のひとつとなるような仕掛けづくりを進めているそうです。
繭パフ作り体験と、鈴木さんとの心あたたまる時間
お話の後は、「染織工房おりをり」で人気のワークショップ、繭パフ作りを体験。繭から取り出した真綿(繭から蛹を取り出した後で糸にする前の状態を真綿と呼ぶそうです)を撚り合わせて糸にし、パフのかたちに織り上げていきます。初めてふれる真綿はふわふわと柔かく、心なしかしっとり水分を含んでいるかのよう。そう伝えると鈴木さんは「真綿は人間の肌と同じアミノ酸でできているからとっても肌に優しいの。これで洗顔すると肌がスベスベになるわよ」と、にこやかに教えてくれました。

パフを織るのに使ったのは手織り機の一種である高機。あらかじめセットされた経糸の間に左右交互に横糸をくぐらせて平面状に織り上げていきます。左から入れた横糸を右から出し、筬を引いて打ち込み、足元のペダルを踏んで経糸の開口部を変え、次は横糸を右から左へ。順番を間違えないように気をつけながら作業していきます。慣れてくると、ペダルを踏んだ際に綜絖が開くガチャンという音、筬を整える際のトンという音がなんとも心地よく、夢中で右から左、左から右へを繰り返していました。きれいな織り目を作るためのコツは、糸を引っ張りすぎないこと。繊細な加減が仕上がりの美しさに影響します。

途中、「手を動かすだけじゃもったいないから、おしゃべりしましょ」と鈴木さん。
震災後に「福島のために何かしたい」と染織工房に養蚕を加えたこと、建物を10年かけて改装し、宿泊もできるように整えたこと、養蚕を始めたばかりの頃は「うまくいくわけがない」と言われ、悔しくて本気で取り組んできたこと。そうして出来上がった繭を素晴らしいと褒めてもらえたこと。お茶目な話しぶりを聞いていると、工房を訪れる人たちはワークショップ体験だけではなく、鈴木さんとの交流を楽しみに来ているんだなぁと感じました。

10センチほどに織り上がったパフを、鈴木さんがミシンでしつけしてくれました。絹の自然な色合いが美しく、つやつやと光る繭パフの完成です。やや不揃いな目も、自分で織ったことを思えば愛おしく感じられるから不思議。これからパフを使うたびに、工房で聞いた鈴木さんの話や機織りの音を思い出すことでしょう。


養蚕文化を次の世代へ
「歴史を大切にしないと未来はないと思うの。昔ながらを守りつつ、新しいものを生み出していかないとね」と鈴木さん。そのために今後は、体験にも商品自体にもさまざまな付加価値をつけて養蚕の素晴らしさを伝えていきたいと意気込んでいます。なんと、「食べる繭」にも挑戦するのだとか!
「蚕は捨てるところがないの。繭は生糸になるし、美容成分をたっぷり含んでいるから化粧品にも使える。糸を取り出したあとの蛹を食べる地域もあるし、フンは漢方薬や肥やしになるのよ」

織物以外の活用法で新たな収入源ができれば、再び養蚕が見直されることもあるかもしれません。実際にそんな動きも生まれつつあり、「ツアーに参加し、工房で養蚕体験をした人たちで商品開発のアイデアが生まれたりもしているんですよ」と中山さん。出かけた先で思いがけず新たな友人ができるのは旅の醍醐味のひとつ。まるで細い糸がより合わさって強くしなやかな生糸になるように、養蚕や鈴木さんを中心に人と人の縁が紡がれています。

「養蚕のすべてにワクワクしているの。このワクワクを来てくれた人に伝えるのが私の役目ね」
そう言ってにっこりと笑う鈴木さんと、その様子を穏やかな眼差しで見つめる中山さん。福島の養蚕文化を残したいという共通の想いをもつ方々との交流を通して、一緒にワクワクしてみませんか?

エピローグ
卵から孵った蚕が繭になるまで約1ヶ月。「染織工房おりをり」では、年に4回程度養蚕を行っており、タイミングによって異なる工程を体験することができます。糸にするまでにもさまざまな工程があるため、たとえば初めは蚕のお世話、次は繭から糸を取り出す作業と、何度も足を運ぶ楽しみがあります。
私はといえば、持ち帰った繭パフを実際に使って洗顔してみたところ、びっくりするほどしっとりツヤツヤ肌になり、改めて“お蚕さま”(養蚕農家では家族の暮らしを支えてくれる蚕をこのように呼んで大切にしていました)のパワーを実感することができました。
信達地方に根付いた養蚕の奥深い世界を、ぜひ皆さん自身の目で確かめてみてください。
取材・文:渡部あきこ 撮影:柳沼 亘
地域と旅人が分かち合い、深く関わり合いながら共に未来へ向かって成長していけるこの新しい旅に、あなたも出かけてみませんか? 全国で展開中の「まちが わたしが 育つ旅。いくたび」の詳細は、以下のリンク先からご覧いただけます。