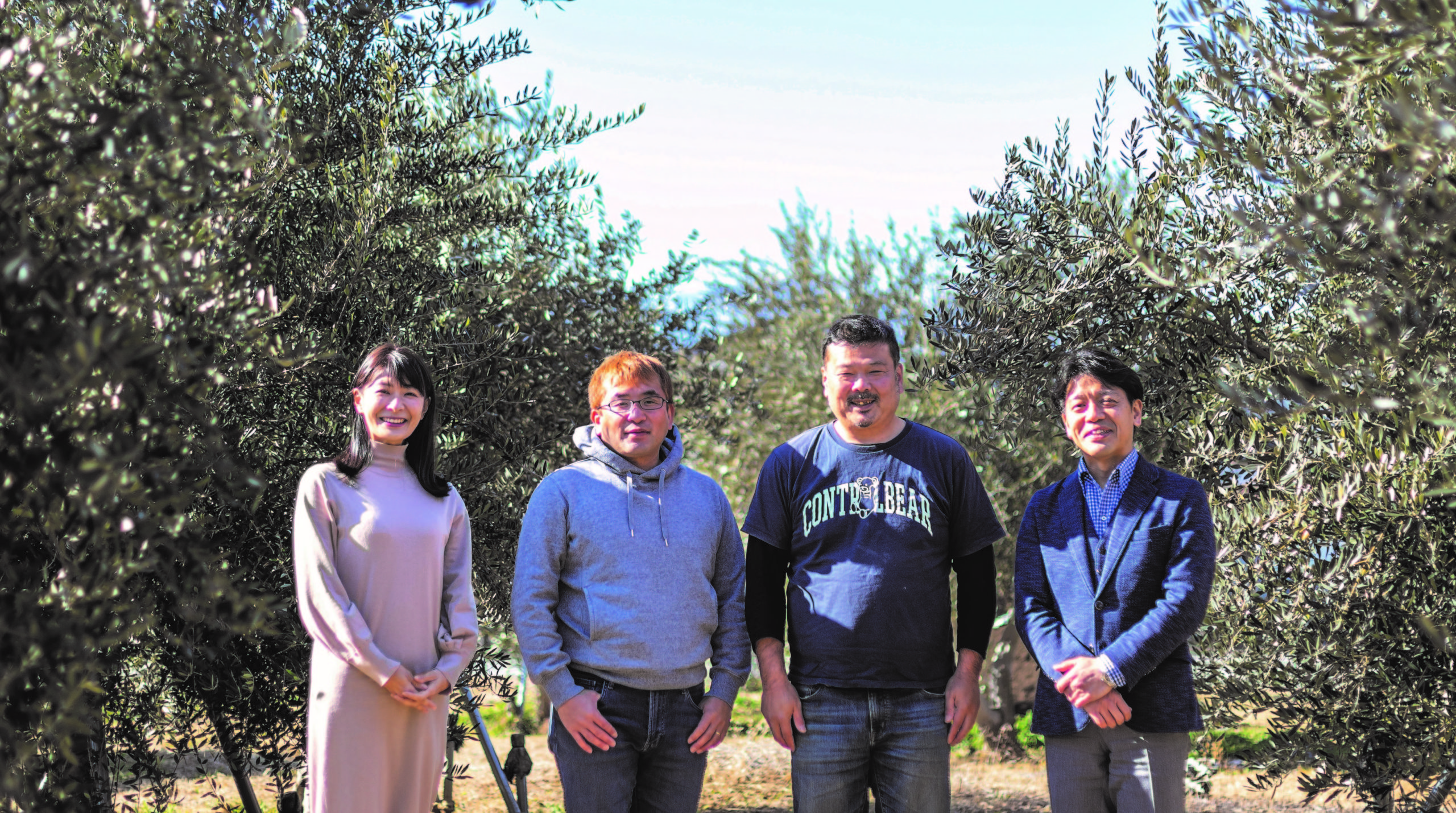
国際品評会で入賞した山梨県産オリーブオイルの生産者は、あの人気ロックバンドのメンバーだった。その情報を確かめに、TURNSプロデューサー・堀口正裕、「デュアルでルルル♪」パーソナリティー・八田亜矢子さんが山梨を訪れた。
バンド休止を機にゼロから始めたオリーブづくり
笛吹市御坂町は、甲府盆地や南アルプスを一望できる標高300~400mほどの街だ。中央道を下りて、柔らかな陽射しに包まれながらクルマを走らせた堀口と八田さん。やがて、青々とした葉がまぶしいオリーブ畑にたどり着いた。
「ここはもともと、僕の祖父のぶどう畑。今は採れたオリーブを搾ってオリーブオイルを製造しています。昨シーズンは収穫直前の雨が少なかったことで、とてもいい出来になりました」
 対談では、2人ともオリーブへの熱い思いを語ってくれた
対談では、2人ともオリーブへの熱い思いを語ってくれた
そう言って微笑むのは、ロックバンド「レミオロメン」のベーシスト・前田啓介さん。山梨でオリーブオイルづくりをスタートさせたのは、2012年のバンド活動休止後のことだった。そのときの前田さんは、音楽シーンの第一線で走り続けていたが、自分がやれることはやり尽くしたと感じていたそうだ。
「音楽が嫌いになったわけじゃないんです。バンドが一つの区切りを迎えたので、自分でゼロから何かをつくって、若い人たちにおもしろがってもらいたいという思いが芽生えました」
頻繁に足を運んでいたふるさと・山梨で、地元の仲間たちと話す中で生まれたのが、オリーブ栽培のアイデアだったという。
「素材の味を引き出せるオリーブオイルは名脇役。山梨が誇るワインとおいしい食材をつなぐオリーブを自分の手で育てたいと思ったんです」ところが「フルーツ王国」と称される山梨でも、オリーブの栽培実績はほとんどなかった。
 畑の隣にある工場で前田さん自ら搾油を行う
畑の隣にある工場で前田さん自ら搾油を行う
「困難なのはわかっていましたが、僕は思うがままに生きることしかできない。自分が一番自然でいられる山梨で、チャレンジしたかったんです」
約100本のオリーブの苗木を植え付けることから始め、さまざまな苦難に直面しながらも地道に栽培に取り組み、2016年に初めての搾油に成功。「笛吹オリーブオイル前田屋」のブランドで販売に乗り出した。
そして翌年には、心強い仲間が加わることになる。日本におけるオリーブの「本場」香川県・小豆島でオリーブオイルを製造する企業の栽培・採油責任者だった内海淳彦さん。前田さんとは、ある食品イベントで知り合ったという。
「私は東京出身で、親も歳を重ねたので、少しでも東京に近いところに移住して自分でオリーブづくりをしたいと考え、会社を退職。そこで頭に浮かんだのが、前田さんのいる山梨でした」
 右側が内海さんの「maruu」、左側が「前田屋」のオリーブオイル。
右側が内海さんの「maruu」、左側が「前田屋」のオリーブオイル。
前田屋のオイルは国際品評会「OLIVE JAPAN」で2年連続銀賞に輝いた
本当に山梨でオリーブが育つのか――。若干の不安を持って前田さんの畑を訪れた内海さんは、栽培されていたオリーブの木を見るなり移住を決心した。
「他の地域には、前田さんの木ほど立派に育っているものはありませんでした。自分も頑張れば、きっと高い品質のオリーブを育てられる。そうイメージできたんです」
内海さんは山梨の気候にも惚れ込んだ。降水量が少なく日照時間が長いうえ、山々が育んだ豊富な水資源があるなど、オリーブ栽培にとっての好条件が揃っているのだ。
「オリーブも人間も、過ごしやすい環境が一番。夏でも湿度が低くて病害も発生しにくいですし、オリーブの栽培条件としては、山梨は国内最高レベルと言ってもいいと思います」
栽培に成功した内海さんは、「maruu」の名でオリーブオイルを発売。前田さんとともに、より良い品質のオリーブオイルづくりに汗を流す。
山梨で気づいたやりたいことを追求する幸せ
前田さんは山梨に戻ってきて、それまで自分が「余分なもの」を抱えて生きていたことに気づいたという。
「今思えば、東京では常に自分を飾っていないと怖かった。でも、本当はそんなことしなくていいんですよね」内海さんが続ける。
「僕も以前は、見栄でいろんなものを周囲に合わせすぎていた。山梨では、そういう人付き合いをする必要がないので、それがとても心地良いんです」ありのままの自分で、シンプルに生きること。それがつくり手として重要な姿勢だと、前田さんは言う。
「とにかく、自分がやりたいことを追求して、幸せでいること。それでたまたま誰かを幸せにできたら素晴らしい。音楽もオリーブも人の感性に訴えるものだから、そういう気持ちが一番大切だと思います」
恵まれた気候風土、そして自然体で生きる生産者が織りなす、香り豊かなオリーブオイル。それを目当てに、世界の美食家たちがこぞって山梨を訪れる日も、遠い未来ではないかもしれない――。対談を終えた堀口と八田さんは、そんな期待を胸に抱きながら山梨を後にした。
移住者それぞれの新しい「挑戦」が生まれる山梨県。あなたも実際に訪れて、その魅力を体感してみてはいかがだろうか。
文・佐藤 史親 写真・小俣礼





















