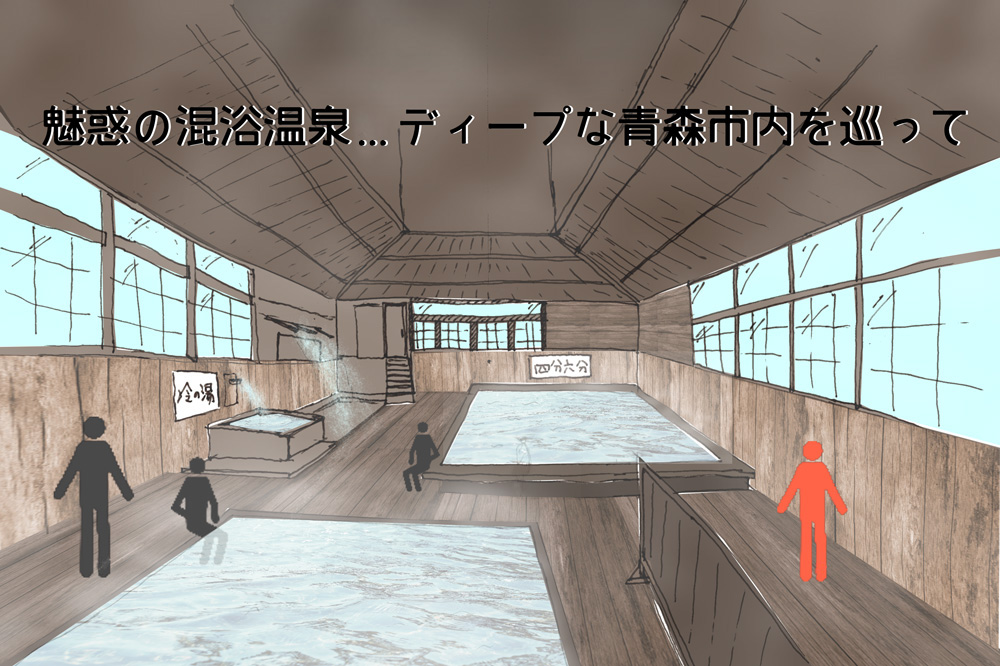新潟県三条市の農家で生まれた幼馴染3人で結成された農業ユニット「農業Crew(クルー)」。平日は会社員として働き兼業として畑を耕す彼女たちは、インターネット世代ならではの新しい価値観で「自分たちにしかできない農業」をまっすぐに見つめていた。
SNSのつぶやきから農業ユニットを結成
日本一の米どころ、新潟県。そのほぼ中央に位置する三条市は、隣の燕市と合わせて「燕三条」と呼ばれている。
「農業Crew」のリーダー・長野美鳳さんは三条市の兼業農家に生まれた歳。金属加工業が盛んな燕三条の包丁メーカーに勤め、プロダクトでザイナーとして商品企画からでザイン、マーケティングまで幅広く業務をこなす。日々忙しく働く彼女がなぜ兼業として農業を始めようと思ったのか?
「社会人として働き始めて年が経った頃、仕事以外の場所で何かやりたいと悶々と考えていました」。社会人年目といえば長野さんに限らず、きっと多くの若者がこの〝何か〟を求めてぼんやりと考えることがあるだろう。彼女はその正体を見つけるため、自分の好きなことを振り返ってみることに。するとその全てに共通して「食」があったのだという。「趣味が旅行なんですけど、旅先でおもしろい素材の味がする野菜に出会って感動したり、生で食べられるカボチャがあることに驚いたり。どこへ行っても食で、その中でも素材そのものに感動することが多かったんです。ビールが好きなあまり、ビールについて勉強した時は原材料のホップや作り方にばかり関心が向いて…。自分の感動の先にはいつも『農』があったことにそのとき初めて気づきました」。

実家は兼業で米農家を営む長野さん。幼い頃から農に囲まれて育ってきた彼女は自分のアイデンティティの中心にまさか農業があったなんてこれまで思いもしなかったのだそう。「自分の興味が農業に繋がっていることは、自然な流れだったのかもしれないけど、遠回りしてやっとストンと腑に落ちた。それで『農業やりたい』ってツイッターにつぶやきました」
その投稿に反応したのが農業Crewのメンバーで幼馴染の金子理紗さんと小川沙織さんだった。長野さんと同じく、農家に生まれ、地元企業に就職した二人。全く同じ環境にいた彼女たちにも「何かやりたい」という漠然とした思いがあったらしく、三人での結成は必然的なものだった。

なに作る? どう売る? 試行錯誤の農業がスタート
ツイッターの投稿をきっかけに結成された農業Crew。メンバー全員が会社員として働く中で、休日やそれ以外の時間を使って兼業として畑を耕すことに。農業を始めると決めたものの、時間も作れる農作物の量も限られていた。「兼業農家の大変さは両親を見てきたのでわかっていました。だから私たちは『自分たちにしかできない農業とは何か』を考えたんです」。
そう話す長野さんを筆頭に、三人はまず地元の朝市へ行って市場調査をすることに。しかし、そこで販売されている新鮮な野菜を見て圧倒されたという。「長年野菜を作っている地元農家さんたちの野菜を改めて手にすると、丸々と大きくて、瑞々しくて。私たちが同じものを作っても勝てないと思いました。だから、ここでは供給の少ない珍しい野菜に挑戦しようと決めました」
やるからには求めてもらえる野菜を作りたい。そんな思いから地元のベテラン農家との差別化をはかり、初年度(昨年)はビーツ、コリンキー、サラダごぼうなど地元朝市ではあまり並ばない種類の野菜作りに挑戦。その中で種類・白トウモロコシだけはタヌキに食べられて全滅したものの、そのほかの野菜はしっかりと実をつけることに成功した。実家が農家ということもあり、整備された土壌、そして農業の先輩である両親の存在。農業をゼロから始めるのとは段違いな好環境が彼女たちの追い風となった。

作って終わりじゃない届け方へのこだわり
収穫した野菜を消費者に届ける方法こそ、農業Crewならではの発想が光る。昨年収穫した野菜は、まず念願だった地元の朝市で手売りすることに。あまり目にしない珍しい野菜に足を止めるお客さんも多く、食べ方のわからない人にはおいしい調理法を説明するなど、彼女たちの接客も相まって用意した野菜はあっという間に売り切れに。自分たちの手で育てた野菜を誰かが買ってくれる喜びを感じ、次への自信がついたと三人は話してくれた。
そのほかの販売ルートとして、農業Crewの野菜は市内の一部飲食店にも卸されている。電話やDMを活用して、メンバー直々に飲食店へ営業をかけているのだ。最近では店の方から売って欲しいと声がかかることも増えたのだそう。「朝市に何度か出店してみて、飲食店の方に買っていただいておいしく調理した状態で消費者に味わってもらうことの方が、ファンになってもらう近道だとわかったんです」長野さんたちがこだわるのは〝おいしく食べてもらうまでの導線〟。珍しい野菜だからこそ、作って終わり、売って終わりではなく、おいしい料理になって消費者の口に入るまでをきちんと考えた販売方法を優先している。
そんな彼女たちは地元のレストランとコラボしたケータリングイベントも活発に行う。農業Crewの野菜と長野さんの実家で収穫されたコシヒカリをアレンジした「野菜おにぎり」を手作りして提供したり、節分には参加者と一緒に恵方巻きを作るワークショップを行った。これらもファンになってもらうための大切な〝導線づくり〟だ。「実際に食べて、おいしいと思ってもらえないと買ってもらえない。珍しい野菜もそうですが、お米もそうです。お米って〝炊く〟というひと手間なしには食べてもらえない、口に入るまでの導線がとても長い農作物なんです。その工程をお客さんに任せるのではなく、自分たちがお米を炊いて提供することで、すぐに味わってもらえるケータリングは長い目で見てもとても大切な活動の一つですね」
さらに、地元クリエイターとコラボした商品パッケージ作りにも挑戦している。昨年制作したのはオリジナルの「米袋」。お洒落なパッケージに入れて販売するお米は長野さんの実家で穫れた特Aランクの新潟県産コシヒカリだ。「米袋って、重たくて米びつに移すだけでも大変。それなら可愛らしいでザインでキッチンにそのまま置きたくなるようなサイズの袋があれば良いのにと思って」。アイでアの発端は自分自身が感じる米袋への使いづらさから。また、お米の売り方についてもずっと考えていたことがあったのだそう。

「うちのお米の大半は農協で出荷してもらっています。でも、特に出来の良いお米が穫れた年も組合の農家さんたちのお米と混ぜて『新潟県産コシヒカリ』のパッケージで売られるのはなんだかもったいないような気がして。家族でもいつか直売できるといいねと話していたところでした」。そういった家族の思いもあり、長野家のコシヒカリの一部は新しいパッケージに包み、農業Crewのお米として販売されることに。すると、このパッケージがきっかけで県外からの問い合わせがあったのだそう。また、アパレルのショップとのコラボで普段とは違うターゲットに向けて行った店頭販売では用意したお米のすべてが完売。想像以上にお客さんの反応は上々だった。
「農業をもっとコンテンツとして届けたいと思っています。自信を持って作っているものなので、きちんと良く見せて適正価格で買ってもらいたい。そして、どうやったら食べてもらえるのかは常に考えています」。本業でブランでィングやデザイン担当する長野さんにとって、売り方もおいしく届けるための導線だ。
自分たちにしかできない農業のこれから
2年目に突入した「農業Crew」。今年は新しいことにどんどん挑戦したいという。
「思いついたアイでアをツイッターに書くのが好きなんです。そうすると一緒にやろうよって手を挙げてくれる人もいるし、アドバイスをくれる人もいる。みんなからのいいね数がやるかどうかの指標になるので、それってマーケティングにもなっているのかなと思うんです」。SNSやネット、デザインを駆使した、今の時代を生きる女の子ならではの新しい農業のかたち。

柔軟な発想と若い感性、そして「とにかくやってみる」と軽快なフットワークを持つ彼女たち。「10年後どうしていたい?」という問いに「三人の未来の旦那さんや子どもたちも巻き込んで、みんなで楽しく農業をしていたい」と答えてくれた、まっすぐな瞳が印象的だった。
(文・編集:本郷結花 写真:斎藤恵)
=全文は、本誌にてご覧ください=