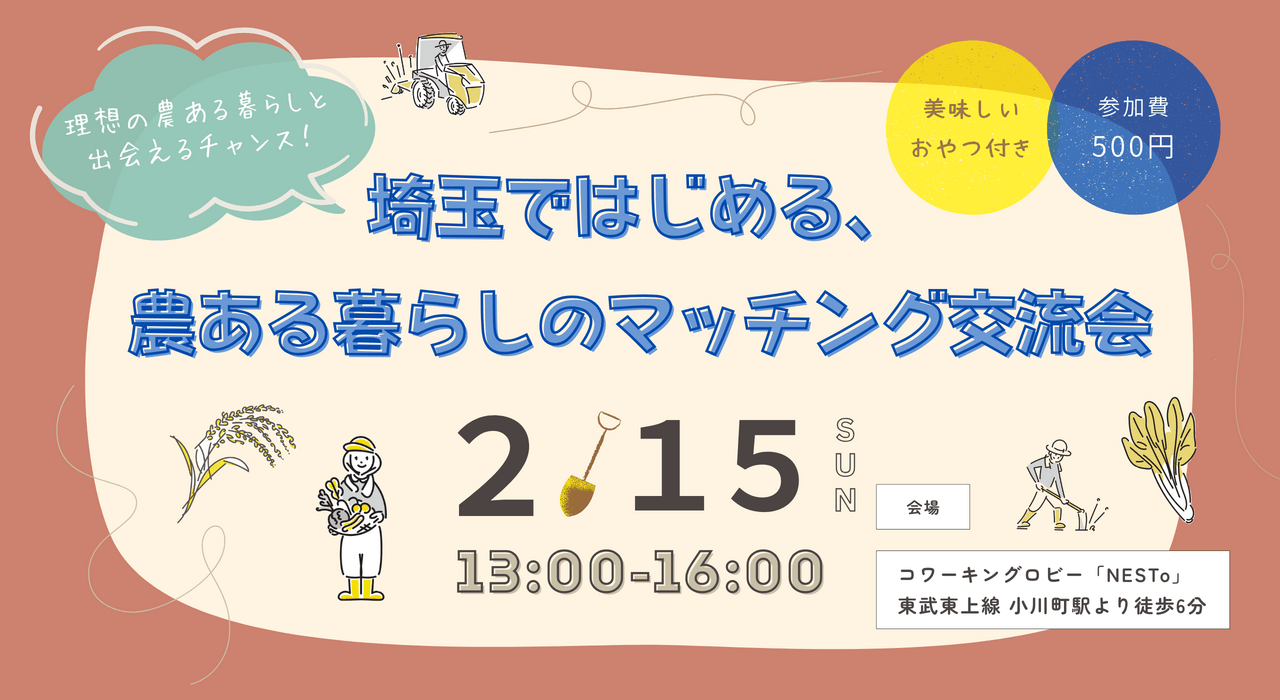まちの経済を循環させる、地域商社
宮崎県のとある町に、何やら勢いのあるまちづくりのチームがあるらしい。その魅力に引き寄せられ、多くの若い人たちが集まってきている。そんな噂を聞いた。チームの名は「一般財団法人こゆ地域づくり推進機構(略称・こゆ財団)」。この組織から仕事がどんどん生まれ、県内外から多くの人が訪れている。いったい現場では何が起こっているのだろう? その謎を探るべく、宮崎県新富町を訪れた。
こゆ財団(以下、財団)のオフィスは町の中心部にあった。十五年もシャッターが下りたままだった元空き店舗で、中へ入るとかなり広い。半分はコワーキングスペースになっており、研修中の団体が会議中。その横では若い人たちが楽しげに打ち合わせしていた。
現在、財団のスタッフは十四名。加えて十名の地域おこし協力隊がここで働いている。彼らはこの組織を「地域商社」と呼ぶ。
財団は新富町が出資してできた組織で、大きくいうと二つの動きをしている。一つは外からお金を稼ぐこと。そのために、町に埋もれている地域資源を探し出し、新しい商品や仕事をつくる。そしてもうひとつ、これがとても重要なのだけれど、稼いだお金をしっかり町に還元すること。主にこれから事業を始めようとする人や地元事業者の人材育成、空き家を宿にするなどの利活用、さらには町をスマート農業の研究拠点にする構想など、町の未来に寄与する動きが活発に行われている。
稼いでその一部を人材育成と新しいビジネスに投資し、さらなる仕事を生み出す。町の経済をぐるぐる循環させるエンジンのような組織なのである。

地域は、新しいビジネスフィールド
目下、財団の稼ぎ頭はふるさと納税だ。運営を町から委託されているほか、自社の商品開発を行い、その売上の一部が財団の収益となる。当初役場で扱っていた頃は年に二〇〇〇万円ほどだったふるさと納税の寄付額は、二〇一八年度には十九億円にまで伸びた。
たとえば地元の農家が品質向上に取り組んでいたライチを一粒一〇〇〇円で売り出したところ、ふるさと納税での申込数は二年間で四倍に。生産量はまだ一〇トン程度と少ないが、あっという間に売り切れる人気商品になった。さらには農業の盛んなこの町の野菜を発信したいと財団スタッフの提案から生まれたのが、新富野菜の定期便サービス。こちらも返礼品として提供し、今では月に約一四〇〇軒に送付している。そのほかまだ粒は小さいが、そばフロランタンというお菓子の開発や、パパイヤをメディカルフルーツとして売り出す試みなど事業のタネが次々に生まれている。その機動力はどこから生まれるのだろう?
一つのヒントは、これら事業の多くは発案者が進めていること。起業家精神をもつ若手と出会う場として、東京で起業家育成塾「宮崎ローカルベンチャースクール」を行っている。
参加者はプログラムの中で新富町をフィールドにした事業計画を練り、一〜二度は町を訪れて最終プレゼンに臨む。プログラムが終了する頃にはその企画を実践してみたいという気持ちになるのも当然だろう。「都会で培ったキャリアを活かして新しいことを始めたい」「地域課題の解決につながるようなことを」「起業するなら求められる場所で」と考えている若手からするともってこいのフィールドに違いない。実際、東京や千葉、埼玉などの関東圏、福岡などから移住してくる。
財団の代表理事、齋藤潤一さんはこう話す。
「今や都会より田舎の方がビジネスチャンスにあふれていることの表れだと思うんです。地域には眠っている資源が無限にある。農業も漁業も、手つかずのことだらけですから。たとえば新富町には、スマート農業の実証実験に使える圃場がたくさんある。その利点を活かしてスマート農業のベンチャーが集まる拠点づくりを考えています。地域の側も早く地方創生という言葉を忘れて目の前にあるビジネスチャンスを活かしていく方がいい。僕らはそのためのフィールドを提供しているということなんです」

ボトムアップでできた組織
ただし地域では人と人のつながりがモノを言う。ぽんと現れたよそ者が地元の協力抜きに事業を軌道に乗せるのは至難の業。財団の事務局長、高橋邦男さんは話す。
「その点うちは、よそから来た人たちがわっとつくった組織とは違って、地元のメンバーやUターン組が大半を占めているのが強みでもあります。農家や役場など地元とのつながりが濃い分、実現しやすいことも多いんです」
というのもこの組織自体、二十年間役場で働いてきた職員、岡本啓二さんの発案から生まれたものだ。岡本さんは町の財政状況の厳しさを肌身に染みて感じていた。
「役場で新しいことをしようとしても、計画して予算化して実現するまでに一年はかかります。世の中いろんなことがこれだけスピーディーに進んでいる時代に、それではついていけない。そこで実働部隊を外へ出しましょうと」。観光協会を発展的に解体し、元のメンバーに新メンバーが加わって今のこゆ財団ができた。財団という形を取ったのはなぜなのか。小嶋崇嗣町長はこう話す。
「民間に委託してしまうと外から稼いだお金がその先どう使われるかが見えません。外車を買って終わり、でもおかしくない。稼いだお金をきちんと町に還元できる経済の循環をつくるために今の形になったんです」
まちにどう還元しているか?
財団でお金を投資する先として、今もっとも力を入れているのは〝人〟。人材育成だ。起業家候補の若手だけでなく、これまで地元を支えてきた中堅どころの経営者にも〝学びの場〟を提供している。
二〇年近く養鰻業を営む「中村養鰻場」の中村哲郎さんはこう話していた。
「長く経営をやっていると、何度も壁にぶつかるんです。ちゃんと学びたいと思っても仕事もあるし遠くへ行くのは難しい。それが町内で行われるのは貴重なチャンスです」
知識や新しい視座を得ることは、短期的な成果が見えにくい。でも一人ひとりがスキルアップし、やる気が増すことは、町に活気をもたらすもっとも効果的な方法かもしれない。次頁から紹介する個々の動きを見てもわかるように、町の中でこれだけ新しいことが起き始めている現象は、わずか二年半の成果としてはとてつもなく大きなものだ。しかし町民全員が、財団が何をしているか理解できているわけではない。小嶋町長はその融合がこれからの役場の役割でもあると話す。
「こゆ財団の魅力は横に広がる力です。県内外の人たちとのつながりですね。それを地元に深化させるところは僕らがやること」
たとえば財団を通してつながりができたユニリーバは町に新設されるサッカースタジアムのネーミングライツを取得することになった。今さらに町とどんなコラボレーションができるかを検討しているという。
齋藤代表理事は、新富町や財団がいま若い人たちを惹きつけている理由をこう話す。
「今、地域に入って何かしたいという人たちは自分を活かせる場所を探しているんだと思います。みんな、自分のウェルビーインを実現できるような自由な風土とチャレンジできる環境を求めている。彼らの求める成功は従来の成功と違っていて、人の数だけあります。その多様性を許容できる土壌が必要なんじゃないかと思うんです」
一社が十億円稼ぐより、一千万円稼ぐ事業が百ある方が町は豊かになる。そんな多様な姿がここでは見えるようだった。

新富町の野菜を届けたい
新富町出身の黒木さゆみさんは、財団の設立時から携わってきたメンバーの一人。宮崎市内で野菜の物流に関わる仕事をしていたが、地元の野菜を発信したいと考え、ここなら実現できるのではと財団に参加した。
「新富町の野菜って味が濃くてとってもみずみずしいんです。それを外の人たちにもっと知ってもらいたいと思っていました」
財団の設立からほどなくして、ふるさと納税向けの野菜セットの販売を開始した。現在このセットを含むオリジナル商品全般の売上は八〇〇〇万円近く。財団の収益の大きな柱になっている。作業所を訪れるとスタッフ五〜六名が出荷準備の最中だった。黒木さん自らが農家の元へ通い、農作業を手伝いながら、美味しいと思った作物を選ぶ。
「行政では取捨選択ができないので、やはり財団でやる意味があると思っています。農家さんにもどういうものが欲しいか、要望を正直にお伝えするようにしています」
町の食材をアピールできる場にも
その美味しい町の野菜を食べられるカフェもできた。店長の永住美香さんも新富町の出身。ご主人の仕事で町を離れていたが、三年前に戻り、役場の臨時職員に。財団の設立時にスターティングメンバーとして加わった。
商店街に人が集まれる場所がほしいという町の人たちの要望もあり、カフェをつくることに。二〇一九年八月に一周年を迎えた。
「ランチを目的に来られる方が多いんです」
それもそのはず。地元の旬の野菜をたっぷり使ったランチはじつに魅力的。サラダにはパパイヤ、キュウリ、パプリカ、カレーにも種つきピーマンやかぼちゃなどのロースト野菜がどんとのる。
「こうしてお店をやっていると、うちのレタスも使ってもらえないか、この牛乳は美味しいのでぜひに、と持ってきてくださる農家さんが現れて。そうした町の食材を紹介して、応援できる場になれるといいなと思っています」

同年代のプレイヤーがつながるきっかけに
一方で、家業を継ぎ、町を支える中堅どころの事業主にとって、こゆ財団はどう見えているのだろう。キュウリの施設栽培を行う猪俣太一さんは、財団の主催する起業家育成塾「シータートル大学」に参加した一人。
実家で修行した後、キュウリ農家として独立。農業を始めて十年目。塾に参加したところ同世代のキュウリ農家二人と出会い、希少価値の高い在来キュウリの栽培をやってみようとクラウドファンディングに挑戦した。
「同じ農家でも知り合う機会ってないんです。在来種は日持ちがせず、その後にはつながらなかったんですが、PRなど初めて知ることの連続で。今後すごく役に立つと思います」
猪俣さんの呼びかけで農家が集まる勉強会も始まった。それが今、町で進むスマート農業の拠点づくりのコアメンバーにもなっている。
欲しいのは刺激し合える出会い
伊藤酒屋の伊藤寛人さんもシータートル大学の一期生。十六年前に東京から戻ってきた後、店を銘酒を扱う本格派の酒屋に転向した。
各地の酒蔵を巡り、蔵と密な関係を築いて希少価値の高いお酒を扱う。今では宮城の銘酒『伯楽星』や、ここでしか買えない地元の焼酎などを置いており、地元の飲食店とのつながりも深い。
「町に長く住んでいると刺激が少ないんですよね。やる気が出るような志ある人との出会いも限られていて。でも塾に参加して、同年代の刺激し合える仲間に出会えた。交流が続いていて、得るものは大きいなと思っています」
この塾で伊藤さんは前々から考えていた町の天然記念物である梅から梅酒をつくるプロジェクトをプレゼンし、実現させた。
「つくる側を体験できたのも大きな財産。これからも続けていきたいと思います」
文/甲斐 かおり 写真/藤本 幸一郎