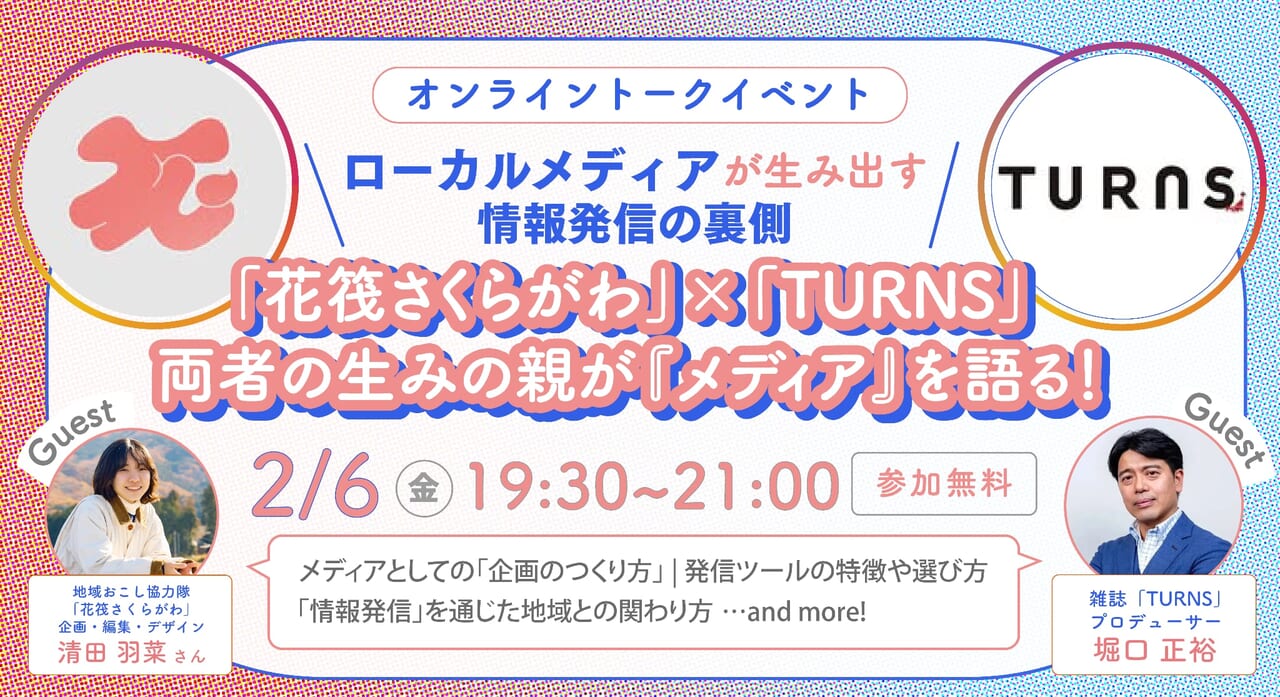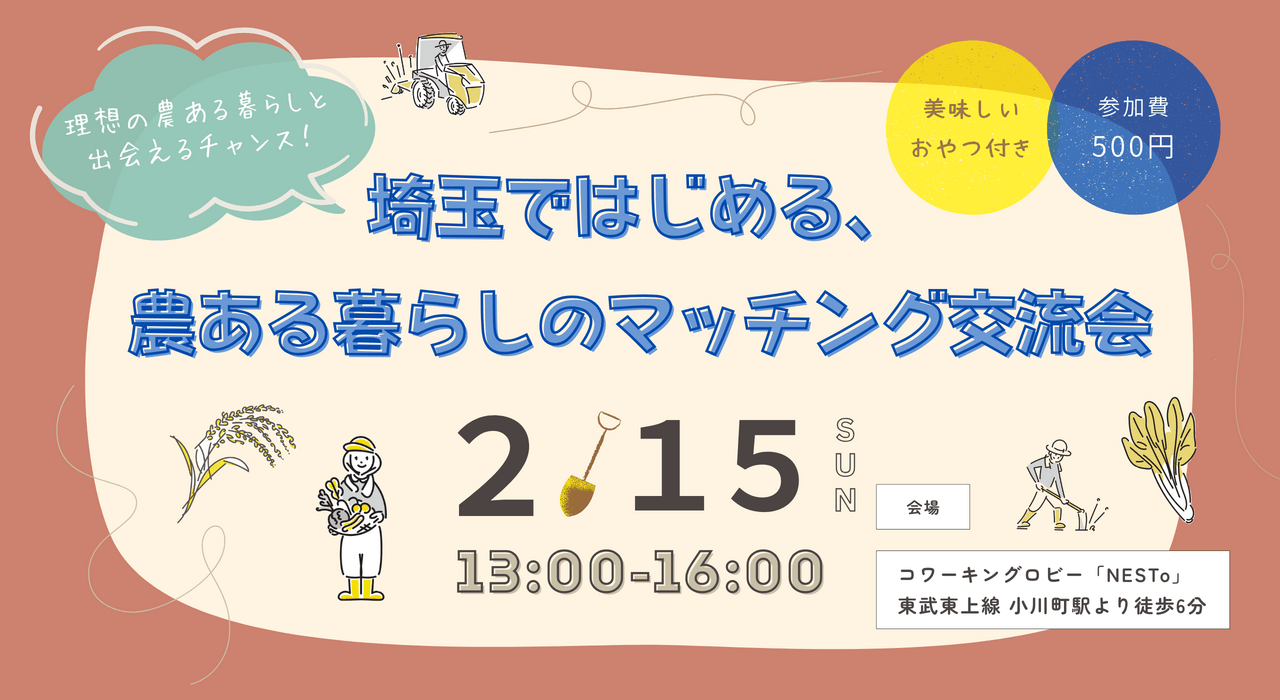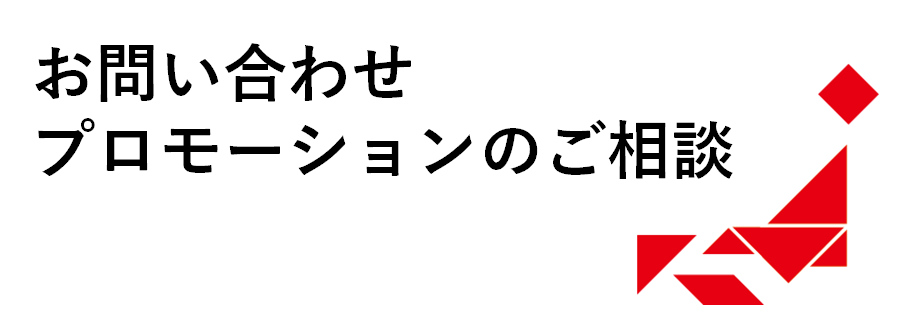全国で年間大量に排出されるコーヒー粕。その多くは焼却処分される有機廃棄物となりますが、堆肥化することで、土壌の肥沃度向上や温室効果ガスの削減といった効果が期待されます。
今回紹介する「堆肥化を通じた循環型プロジェクト」は、“茶業と挑戦に、火入れする。”をモットーにする鹿児島県志布志市の「鹿児島堀口製茶有限会社」が中心となり、コーヒー粕を堆肥化して農地に施用し、生産された食材を地域や店舗に供給するという地域循環共生圏のフードチェーンの構築を目的としています。
プロジェクトに参加する関係者と役割は以下のとおり。
・東京農業大学
コーヒー粕堆肥の適用条件についてアドバイス。今後の展開に向けたデータを提供します。
・冨澤ファーム
コーヒー粕を原料とする堆肥を製造し、野菜等の栽培に活用。また、収穫された食材を通じて循環型フードチェーンの構築を目指す。
・株式会社堀口珈琲
コーヒー粕の排出元として、堆肥化に活用する原材料を提供。併せて堆肥を利用して生産された食材の活用を検討。
・ローカルフードサイクリング
コーヒー粕の発酵条件や試験方法についてのアドバイスを実施。また、堆肥化に利用する家庭用LFCコンポストの調達をコーディネート。
・鹿児島堀口製茶有限会社
プロジェクト全体の進行や関係者間の調整、課題解決に向けたコーディネートを実施。
これらのメンバーがコーヒー粕の焼却処分を減らしつつ、地域社会における資源循環のモデルケースを目指していきます。
プロジェクトのキックオフとなるコンポスター製作ワークショップを実施
去る2月23日(日)、東京都三鷹市の「冨澤ファーム」で、「コーヒー粕資源化プロジェクト」の一環となる「木枠コンポスター製作ワークショップ」が行われました。コーヒー粕の堆肥化には欠かせない木製コンポスターをDIYでつくるワークショップ。今後コーヒー粕の堆肥化を行っていく「冨澤ファーム」には、関係者をはじめ学生や、循環型社会への取り組みをしている方々など20名以上が集まりました。
 冨澤ファーム代表の冨澤剛さん
冨澤ファーム代表の冨澤剛さん
冨澤さんの指導のもと、初めて使う電動工具に苦戦していた参加者も、作業を重ねるほどにスムーズに作業できるようになっていきました。


 参加者は冨澤ファームで生ゴミからつくられた堆肥も見学。さまざまな質問も飛び交いました
参加者は冨澤ファームで生ゴミからつくられた堆肥も見学。さまざまな質問も飛び交いました
1時間半ほどでコーヒー粕のためのコンポスターが完成。今後もプロジェクトを見守っていくという思いを込め、参加者の皆さんの所属する校名や団体名を記入しました。
 完成したコンポスターに店名を書き込む堀口珈琲の伊藤亮太さん
完成したコンポスターに店名を書き込む堀口珈琲の伊藤亮太さん
作業終了後は、堀口珈琲さんの極上ドリップコーヒーと、堀口製茶の和紅茶「カクホリ紅茶べにふうき」を飲みながらの懇親会。それぞれが普段行っているコンポストに関する活動の意見交流などが行われました。

冨澤さんからは「今後、どのように飲食店からこちらのファームまでコーヒー粕を運ぶか、プロジェクトを継続していくための伴走者やアイデアを求めています。皆さんもどんどん出してください」というお話しも。
コーヒー粕の堆肥化には発芽障害などのリスクが伴うことが知られています。本プロジェクトでは、こうしたリスクを低減するため、家庭から排出されるコンポストを混合するなどの工夫を行う予定です。今後は、実証を通じて、栽培に適したコーヒー粕とその他のコンポストの割合などを検証し、より安全かつ効果的な堆肥化の方法を探っていきます。
コーヒー粕よる堆肥を循環させ、いかに地域の持続的な仕組みにしていくか。こうした課題をそれぞれの胸に、ワークショップは終了しました。

連絡先
(プロジェクトについて)
鹿児島堀口製茶有限会社 葛井陽介